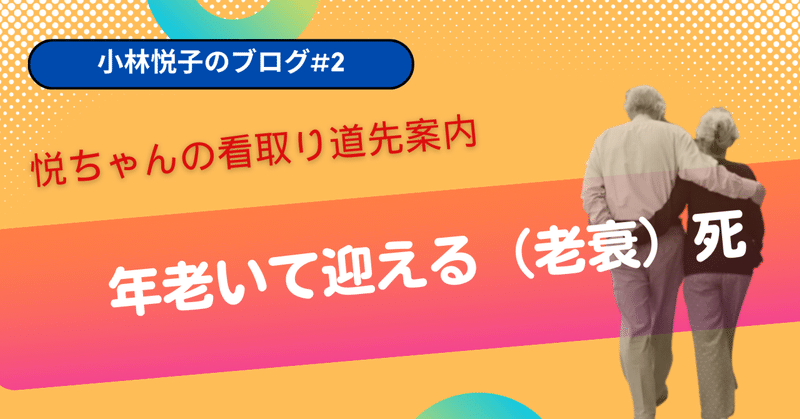
年老いて迎える(老衰)死_#02
看取り道先案内人の小林悦子さんの 「悦ちゃんの看取り道先案内」ブログ 看取りをもっとたくさんの方に知ってもたらいたくて 小林悦子さんのご了解を得て 私のnoteへマガジンを作って看取り情報をお届けします。 末尾に小川のコメントを加筆します。
看取り道先案内人の小林悦子です。
大切な人生の最終章を豊かにするために
看取り道先案内ブログをお届けいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
私の周りでは
がんに罹患した方は
死を迎えることを受け止め易いようです。
「がんは仕方ない」と受容するのでしょう。
しかし、高齢期の最期に訪れる
「年老いて迎える(老衰)死」を
受容することの方が難しい方が多いのです。
最期の時期の日常生活を2年前、5年前と比べることもせず、
昨日、先週、先月くらいの情報で「変わりない」と評価しがちなのです。
しかし、実は、私たちに気遣い、
随分頑張って生きているお年寄りたちです。
決して「もう死んで良い」ということでは在りません。
しかし、
「もう、頑張らなくても良い」
「年老いた、そのままの貴方で良い」
と、肩の荷を下ろすお手伝いも必要な時期ではないでしょうか。
その上で、
死を迎える時まで生ききっていただく。
望みを叶えて人生を楽しんでいただく。
できなくなったことを数えるのではなく、
まだできることを楽しみ、尽くしてもらえませんか?
それが高齢者の周りにいる者の役目だと考えます。
人生の最終段階を生きる利用者が多い
特別養護老人ホーム(以下、特養)の話です。
看護職員さんが30年前のことを話してくれました。
「以前は、秋になると運動会をしていた」そうです。
大玉転がし、パン食い競争、二人三脚までやっていたというのです。
2006年から特養を知った(勤務した)私には驚きでした。
賑やかに運動会が開催できた頃は、
介護度は1、2、3くらいだったのでしょう。
いえ、要支援くらいかもしれません。
それを聞いた2010年、
私の特養でもなんとか運動会ができそうな方は3割くらいいらっしゃいました。
しかし、とても二人三脚は難しそうです。
企画するなら車イス競争として、
職員が介助する「二輪さんきゅう(さんきゃく)」が良いね、と話しました。
2022年、特養の入所にあたり、介護度は3、4、5へと上がっています。
病院での治療ではなく、介護を必要とするお年寄りたちが暮らす特養です。
その意味と、この現実を丁寧に受け止めませんか。
終の住処の役割が求められていることが腑に落ちると思います。
このようにあらためて考えると、
貴方の役割もみえてくるのではないでしょうか。
【小川利久のコメント】
特養ホームは病院ではない
病院は生活を犠牲にして治療するところ
治療が叶わなくなった人へ、私たちができることがあります。
特別養護老人ホームは生活の場です。 その役割は人生最後までの生活を支え、 そのいのちをつなぐことです。
それが小林悦子さんをはじめ、介護職員たちとたどり着いた境地でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
