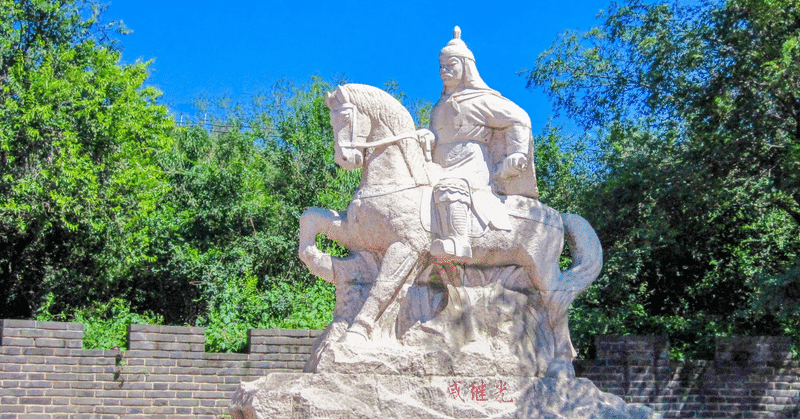
墨家が廃れた歴史に学ぶ
今日も結構暑くなりました。「うららかな春の日差し」という表現が似合う日数が、すごく少ないように感じます。
さて、……
墨家をご存知だろうか。スミヤではない。ボクカ(あるいはボッカ)と読む。なお、書道とは無関係である。
墨家は中国の戦国時代、平和主義・博愛主義を説いて一時は儒家に匹敵する勢力となった。しかし、内部分裂等もあって秦が国を統一する頃に廃れた思想的集団である。
彼らは戦いが起ころうとすると、仕掛ける国に向かって戦いは無益であることを説き、それを止めさせようとした。それでも戦う意思を捨てない場合は、相手国に防御方法を伝え、伝えた事実を仕掛ける国に伝えて諦めさせたりもした。
単純に戦争反対を主張しただけでなく、具体的な行動も取る者達だったのである。
しかし、悲しいかな人間は実際に被害が起こって初めて「このような悲劇を起こしてはならない」と気付く生き物である。彼らが事前に戦闘を食い止めたのに、その価値を正しく評価されないことがあった。
実際、戦を止めた帰路に立ち寄った助けた国で、邪険な扱いを受けたという話もある。
彼らは高い理想(非戦)と理想を実現する実務能力(兵法・ロジ対応等)を兼ね備えていた。このような素晴らしい集団が、紀元前に存在していたことは、もう少し着目されても良いこと。
ただ、あまりにもストイックであったがゆえに、広がって根を下ろすことがなかった。返す返すも残念なことである。
今、ロシアとウクライナの間で戦闘が継続している。世界中で戦闘の即時中止を訴える声が満ちているのだけど、収まる見込みは未だ立たない。
こう言うと私自身が非情な人間であるかのように受け取られるかも知れないのだけど、ただ戦争反対というだけでは、欲深い為政者を止めることは難しい。我々も、歴史から学ばなければならない。
墨家の歴史における興亡は、改めて人間という生き物の性を浮き彫りにする事実として、認識する必要がある。
ただ、その頃とは違い、物理的な力の行使により決着を図るのは時代遅れであることも確か。そうであれば、この一点において話し合いを放棄してはならない。
そして、今風の実務能力として経済制裁がある。武力ほどの即効性はないが、世界で一致して対応していくことで確実に効果を現すものと確信している。
お読み頂き、ありがとうございました。
読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。
