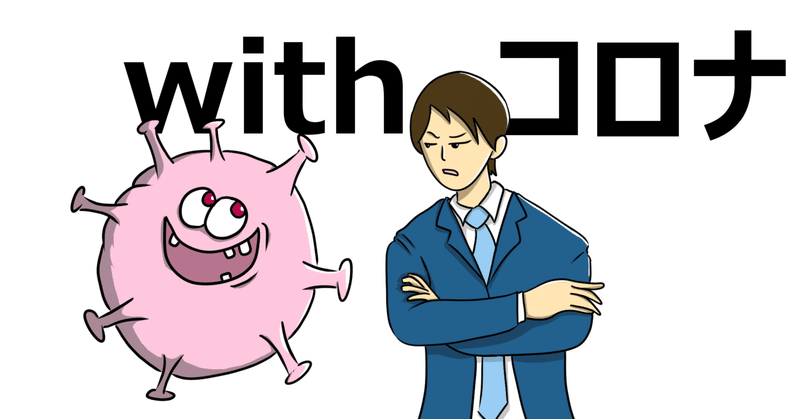
新型コロナウイルスの無意識的な生存戦略を考えてみる
月曜日からハードワークでした。早く楽になりたいですが、なったらなったでいろいろ思うことが出てくるだろうと思います。
さて、……
私たちの新型コロナウイルスとのおつき合いも長くなった。2019年の第Ⅲ四半期後半から話が出始め、2020年1月のダイヤモンド・プリンセス号での感染者多発により、一気に認知されるようになったと記憶している。
当時の新型コロナウイルスはかなり強毒性を持っており、志村けんさんや岡江久美子さんが罹患して亡くなったことで、その威力が世に知らしめられた。
その後、ウイルスは変異を繰り返して現在までコロナ禍が続いてきている。でも、当初のインパクトに比べると、毒性がそれほど強くない印象がある。
ウイルスは宿主あっての存在という一面がある。だから、宿主がバタバタ死んでしまうようになると、今度は自ら存在できる場所が減ってしまう。端的には、居場所がなくなってしまう可能性すらある。
そうなると、結果的にウイルス自体にとっても存亡の危機を招くこととなる。だから、ウイルスの毒性は段々下がっていくという説があるそうだ。
もっとも、ウイルスは単体で存在しているので、思考を巡らす部分などありはしない。従って自分で生存戦略を描くことはできない。
だからウイルス自体は、まさに変幻自在に変異してはいるのだろう。そして、生き残りに適した変異をしたものだけが残ってゆく。そういう偶然に作用される存在だと理解している。
ウイルスがオミクロン株に置き換わったというのも、従来株よりも生き残りやすいからではないのか。体内に入っても免疫細胞にやられにくいとか、数を増やしやすいといった特性があるのだろう。
このように考えると、ウイルス同士でも無意識ではあるのだろうけれど生存競争(ウイルスが生物かについては争いがあるため、厳密には生存とは言えない可能性がある)が行われて、敗れたタイプが消えていく。
人間とウイルスというのは、このような意思疎通のない営みの中で、落とし所が見つかっていく関係にあるのかも知れない。
初期のウイルス感染に世界が恐れおののいていた頃、既に「コロナとの共生」「ウイズコロナ」という言葉はあった。ぶっちゃけ当時は「ウイルスとの共生なんて、あり得ないだろう」と思っていた。
でも、今のような状況に至ると、完全には賛成しかねるもののその言いたいことの主旨は分かったような気がする。それをあの頃から見通していた人の慧眼には深く敬意を表する次第。
ただ、今でも重症者・死者が出ているのも事実。この点はキチンと意識し、感染予防は従来通り行いながら、この厄介な存在と付き合い続けることになるのだろう。
お読み頂き、ありがとうございました。
読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。
