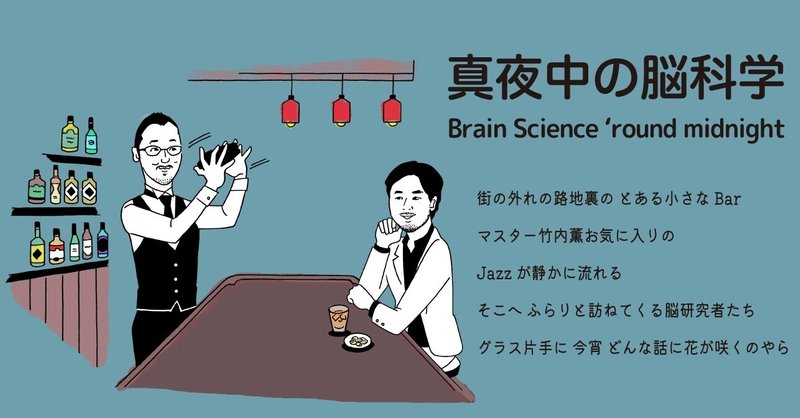
第二回 My Favorite Things♪-脳の可能性を見いだし次世代の人間観をつくる -研究者・柴田和久
Podcast版もお楽しみください🎵
意識と無意識の境界線
竹内 柴田さんは理研CBSで認知に関して研究していると聞きました。具体的にはどんな研究なんですか?
柴田 分野としてはヒトを対象にした認知神経科学です。ヒトが行動、思考、意思決定するときに脳がどのように情報処理しているのかを知りたい。特に潜在過程*1に興味があります。例えば新しいアイデアを思いつくとか、学習、思考、判断などを伴う高次的で意識的と思えるような脳の機能も、その前段階として無意識な過程、心理学の言葉でいうと潜在過程があって、それが実はすごく大事なんじゃないかと考えています。僕らの意識には上らない潜在的な認知過程が、意識や思考に先立ち多くを決定づけている、その脳メカニズムを示したい。「自分のあずかり知らないところで何かが変わっていく」という潜在過程のコンセプト、それが研究の中心です。
竹内 意識や無意識ってよく使う言葉だけれども、それぞれの定義って実はよくわからないというか。それぞれの専門や立場で、定義はいくつもあるのかなって思うんですが、柴田さんの考える、意識、無意識の定義って何でしょうか?
柴田 僕の立場でのもっとも直感的な意識と無意識とは、実験の参加者に直接報告してもらうことです。たとえば、見えるか見えないか微妙でかすかな模様をコンピュータ画面に提示して、それを被験者が「見える」と報告すれば意識的に「見えている」状態ということになる。でも、「見えない」という報告になることもあって、その場合は物理的に同じ模様が提示されているにも関わらず被験者の意識に上っていないということになります。いろいろ端折って説明しましたが、僕がよく使う意識と無意識の定義は、「被験者の報告に基づくもの」ということです。
竹内 なるほど。主体的な感覚か。実験中での意識・無意識の脳活動に違いはあるのですか?
柴田 脳の活動だけから「今は模様が意識的に見えている」「あ、この模様に対しては無意識だね」と言い切るのは現時点では難しいですね。実は意識と無意識に対応する脳活動がどんなものか、まだよくわかっていないのです。あと、今のは「見えるor見えない」の話でしたが、目が冴えているとき、ボーっとしているとき、寝ているときという意識のレベルという分け方もありますよね。このような意識レベルに関わる脳活動は、見えるor見えないの意識とはまた別だと考えられています。意識や無意識に関しては抽象的でややこしい議論が多く、研究者によって、または個々の研究によって、微妙に定義が違ってきます。
竹内 そういう何となく抽象的なことを、実験などで実際にデータを取ったりできるんですか?
柴田 できます。ヒトの脳機能の研究では、被験者に課題を行ってもらいながら、MRI(磁気共鳴画像法)や脳波測定などのシステムを用いて脳活動のデータを計測します。その課題を工夫することで、意識的に作業しているとき、無意識で作業しているときの脳活動を測れるのです。 また、僕が開発に関わった「ニューロフィードバック」という特殊な技術では、被験者が自分自身の脳活動パターンを変化させることができます。自ら変化させた脳活動が被験者自身の無自覚な行動や認知にどう影響を及ぼすかを調べることができる。
竹内 えっ、被験者が自分の脳活動を制御できる⁉

ニューロフィードバック実験中に測定された被験者のMRI画像
柴田 ニューロフィードバックではそれが可能です。まず被験者に脳活動を測るMRIに入ってもらいます。視覚野でも運動野でも、もっと抽象的な情報を扱う前頭前野でも良いのですが、ある脳領域をターゲットに設定し、その脳領域の活動を反映した信号をMRIで測定する。そうすると、安静時のベースラインよりも今は脳活動が上がったとか、下がったというデータを数秒ごとに計測できる。そのデータをリアルタイムで被験者に見せて報告する、つまりフィードバックします。例えば「あなたの脳の後ろの方にある視覚野の活動は、何もしてないときよりも、今はこのぐらい高いですよ」とか「ちょっと下がりました」とか、その場で被験者に情報をフィードバックしていく。そうすると被験者は、「上げてください」と言われたら上げられたりと、自分で自分の脳活動パターンを変化させられるようになるんです。
竹内 ある意味いつも脳の活動は変化しているからそれを自覚してみる、というトレーニングですか。
柴田 そうですね。この技術で我々が何をするのかというと、ある脳領域の活動パターンを変えたときに、被験者の知覚や認知、行動にどのような変化が出るのかを調べる。例えば、被験者が何かを好きだと感じるときの脳活動、嫌いだと感じるときの脳活動を事前に計測しておきます。次に、被験者の脳活動が「好き」活動の方に変化したときに特定の写真を見せる、ということを繰り返す。そうすると、被験者はなんとなくその写真が好きになる。逆に「嫌い」活動の方へ脳活動が変化したときに見せた写真は嫌いになるというように、自覚なく認知に変化が起こる。
竹内 方法としてはシンプルだけれども、好き嫌いをある程度外部からコントロールできちゃうのか。すごい技術ですね。
柴田 脳活動の変化とヒトの認知や行動の変化の対応を実験的に調べるツールとして、高いポテンシャルがあると考えています。
科学者は「変わり続ける」役割を担っている
竹内 今科学者・研究者として新しい技術開発までされているとなると、やっぱり小さいころから科学少年、メカ好き少年だったんですか?
柴田 サッカー少年でした! あとはゲームばかりやっていました。それに読書にピアノ。
竹内 サッカーにゲーム、読書にピアノですか。基本的にいろいろな好きなことをやって遊んでいた感じですね(笑)。いつ頃から科学者になろうと考えていたのですか?
柴田 好きなことをたくさんやって遊んでばかりいたので、そんなに成績も良くなくて。実ははっきりと「科学者になろう」と思ったことは一度もないんです。好きなこと、楽しいことを続けていて気がついたら研究畑にいて、そこそこうまく進んでいるし、いいかな、みたいな感じです。途中で失敗したらまた別のことをやろうと思っていましたが、今のところは大丈夫そう。
竹内 人間っていろんなことをやっているうちに、これ好きだな、これも楽しい、でもこれが一番いいかな、なんて選んでいって、何となくそちらに人生が流れていくっていうのはありますよね。
柴田 あると思います。人生の中で、その都度はっきりした未来予測なんてほとんどできない。現在から過去を眺めて、きっとこういうことなんだろうなって後付け的に物語を作ることでしか僕らは語れないですよね。今まで選択してきた数々を後付け的に考えてみると、未知のものとか成長できる場所に身を置くことが自分はすごく好きなんだ、ということなんだと思います。そしてサイエンスは常に新しくないといけないから、サイエンティストは変わり続けなきゃ存在価値がない。揺るぎなき個があるというよりは、自分の価値を示しながら常に自分を更新し続ける、それが面白い。そういう意味で研究者はサッカー選手、それもフォワードに似ている気がする。常に成長しないといけないし、所属が変わるたびに適応して、その中でゴールを決めないと次はない、というところがすごく似ている。
竹内 一方で新しいものに常に挑戦する刺激やリスクよりも、安心できるパターン化された仕事をして、ある程度の収入があれば良いっていう考え方も実は多い。その選択の差ってなんでしょうね。
柴田 うーん、どちらが大事だとかの優劣は全くなくて、両方の考え方、生き方がないと人類全体として生き残れないっていう感じだと思います。科学者みたいに興味のあることだけ追いかける人ばかりだったらすごく困るわけで(笑)。現在の環境を維持しながら少しずつローカルに改善していくタイプの人間がいなきゃ世の中は成り立たない。でも全体の1割ぐらいはちゃらんぽらんで遊んでいるように見えつつ残りの8~9割の人間がやらないことに手をつける人がいて、たまにその1~2割の人が大きな発見をして、全く違う価値や技術が生まれて新しい世界がやってくる、というのがないと上手く発展しない気がします。これは自己弁護でもあるんですけどね(笑)。10割がルーティンをやっていたら、発展どころか少しずつ後退していってしまうだろうし、反対に全員がちゃらんぽらんだったら、人類滅亡しちゃう。
竹内 ある意味、人類が自然に選択してきている生存戦略みたいな。
柴田 投資ですよね、人間が生物として生き残るための。リスクヘッジにもなっているというか。ナシーム・ニコラス・タレブ*2が言う反脆弱性(または抗脆弱性)や黒鳥理論みたいに、本当に想定外のことが起きたときに、人類が生き残るためには、多様性が鍵だと思います。8割ぐらいはそのときの価値観ですでに大切だとわかっていることをやる、残りの2割ぐらいが未知のことを含めいろんなことをやる。そういう状態だと、たとえどちらかの集団が滅亡したとしても、あとからなんとか盛り返せる。しかも盛り返した後は、お互いの弱いポイントを克服した後なので反脆弱性が働いて、種としてより強くなっている。
限界突破! 人間が人間の枠を超えるとき
竹内 「限界突破」というゲームにもよく出てくるワードが、柴田さんの研究テーマの一つにありますが、この限界突破っていったい何ですか?
柴田 直感的には、自分が思う「限界」と自分の筋肉や体、脳などのいわゆるハードウエアの「限界」は一致しているように感じられます。でも実際には、例えば筋肉が繊維として物理的に出せる筋力よりも、われわれが普段出力している仕事量って明らかに小さいんです。エネルギー消費を考えても、もっと脳は働けるような気がするけれど、ある時点でやる気がなくなっちゃったり気力が続かなかったりする。反対に、火事などの緊急時に普段は絶対運べないような重たい物を運べるとか、ピンチのときの集中力とかあるじゃないですか。
竹内 あるある。
柴田 外部からのトリガー(きっかけ・要因)と脳の認知次第で出力の限界は変わる、つまり限界って状況依存的なんです。状況をちょっと変えただけで簡単にその人の出力、パフォーマンスの限界は変わる。だけれど、意識的・主体的に自分がいくら頑張ってみてもなかなか変えられるものではない。これはまだ仮説の段階ですが、示唆的なデータはたくさんあります。だとすれば、その限界を決めている脳部位はどこなのか、例えばその部位を抑制したら限界突破がいつも起きるのか。どういう状況で抑えられているのか、逆にどういうきっかけで限界突破が可能になるのか。そういうことを考えたい。学術変革領域という他分野も含めた複数の研究者でつくるグループで「心脳限界のメカニズム解明とその突破」というテーマのもとこの課題に取り組んでいます。
竹内 経験的に思うのですが、誰かと一緒だったら限界突破できちゃうっていうのもありますよね。

柴田 そうですね。他者の存在とか、他者のアチーブメントが自分に関係するという例として、象徴的な話がスポーツでよくあります。誰かが一回記録を破ると、突然まわりのアスリートたちも次々と記録を破り始める。フィギュアスケートの4回転ジャンプもそうだし、陸上の100メートル走の「10秒の壁」もそう。10秒の壁に関しては、たまたま採用している10進法で10.00がすごく切りの良い数字というだけで、例えば12進法とか2進法を使っていたら、10.00は全く切りがよくないわけですよね。でも10進法だからだんだん記録が伸びていっても10に無意識に縛られて、10秒あたりで一回頭打ちになる。ところがその壁を誰かが一度破ると、ほかのアスリートを含め、ぐわってまた記録が伸びはじめる。
竹内 スポーツと似ているかもしれませんが、最近真剣に練習しているルービックキューブを夜中にカチャカチャやっているときに本当に何も考えてない瞬間があって。考えていないにもかかわらず、うまくそろっていた! 多分、無意識のうちに何かをやっていた、ということがありました。
柴田 ルービックキューブの上達につながるような運動学習や視覚運動の学習に関しては、脳の中にいくつかパスウェイがあるといわれています。もちろん、最終的な学習の結果は手の動きとか、目の動きなのですが、その動きを作り出しているシステムは何層にもわたっている。一番上の層は意識的に考えながら動かしているような層。動作に習熟していくと、例えば小脳などにその動作に特化した神経回路が作られていく。たとえ複雑な動作だとしても習熟するにつれどんどん無意識化されていく、という現象は昔からたくさんの知見があり、ゴーストパスウェイとか、脳の中のゾンビなどと呼ばれています。
竹内 こういう理由や仕組みは知らないけれど、何となく感覚ではわかっているってこと、ありますよね。
柴田 そうそう。例えば野球のバッティングにおいて、直感的にはボールを意識的に知覚して、それから体が動くという順序だけれど、その順序では到底間に合わない。プロレベルのピッチャーの手から150キロで放たれたボールがキャッチャーミットに収まるまで、0.2秒〜0.3秒くらいしかありません。しかしプロ選手はそのボールを打ててしまう。直球なのかカーブなのかという球種やコースを判断しつつ、すごく複雑な腕の動きのコーディネーションができる。ルービックキューブもバッティングも訓練により身体に教え込むことでそれに特化したゴーストパスウェイがプログラムされると考えられています。
竹内 超人的なパフォーマンス、そんなこと人間ができるはずないと思うことが、意外とできちゃうわけかぁ。
柴田 非常に高度だけれど、たくさん訓練することでプログラム化されたパスウェイがいったんできあがれば、それを発動させるのはかなり素早くできてしまう。
竹内 限界突破の話に戻りますが、その能力を抑えているリミッターってなんなんですかね? いつも高いパフォーマンスが発揮できればそれも良いわけだけれども、生物学的に脳がわざわざリミッターを掛けている理由は何だろうと。
柴田 ベストパフォーマンスを出し続けると、ハードウエアが壊れてしまうからだと思うんです。後々来るかもしれない大事なときに最大限の能力を発揮できないと困るので余力を残している。お給料だって全部使っちゃうと、急に入り用なときに出せなくなっちゃうので貯金するのと同じで、本当に重要だという外部トリガーが入るまでは、セーブしとかなきゃいけない。そういうエネルギー消費の観点からも、リミッターを最初から掛けておくというのは効率的な方法だと思います。
竹内 まだもちろん研究段階だと思いますが、柴田さんの中ではそのリミッターは脳のどこら辺にあるのか、リミッターを平時には作動させている仕組みってなんとなく目星がついていたりしますか?
柴田 いやー、これがまだ目星もついていないのです。今のところこれまでの神経科学の知見をもとにあれこれ推測する段階ですね。ただどうやって調べればいいかの道筋は見えているので、まずは実験して手がかりを得るのが大事かなあと思います。
脳の「余力」にはロマンが詰まっている
竹内 例えば、これまであまり開拓されていなかった自分の脳の領域を活性化するみたいな、そういうこともこれから現実化していくんですかね。
柴田 自分があまり使っていない脳領域を人為的に活性化させるというのは理論的には可能ですが、まだきちんと整理された研究はないと思います。実は、さまざまな行動や思考をしているときの脳の活動を可視化する研究を横断的に調べてみると、「ここの脳領域の活動増加はあまり報告されていないぞ」というサイレントエリアがあります。こういう脳領域をターゲットにして活動させるとどうなるか、という研究は面白いかもしれないですね。または普通の生活のなかでは起こり得ない脳活動パターンに変化させるとどうなるかとか。
竹内 それをなにか人や社会が良い方へ向かうように使う、または何かの治療に使うというような将来的な可能性はありますか?
柴田 ニューロフィードバックを応用することで、脳の疾患などにより変化しづらくなっている脳領域をターゲットとして活性化することで治療に生かせるかもしれない。実はすでに始まっていて、僕らの共同研究者は、恐怖心を克服するトレーニングにニューロフィードバックを使用していて、その一部は臨床試験の段階に入りつつあります。例えばクモがとても嫌いな人やヘビがすごく苦手な人は、それらの写真を見るだけで手に汗をかくような反応が起きる。その反応を軽減するようにニューロフィードバックでトレーニングをするような方法です。これはPTSD*3の治療に応用できる可能性があります。またはスポーツ選手の過緊張をコントロールできるようにするとか。
竹内 スポーツ選手の中には緊張や集中力を自分でコントロールできる人もいますね。
柴田 脳活動をわざわざ測らずとも、自分が最大限のパフォーマンスをできるように、限界突破を可能にする心的状態に持っていく方法もありますよね。ラグビーの五郎丸選手がキック前に行うルーティン動作などが良く知られています。どういう方法であれ、人間がリミッターを外して限界突破できるということは多くの人が経験的に理解できるものだけれども、その科学的裏付けはまだ示されていない状態なんです。その意味で、僕らの研究テーマは全く突拍子もないというわけではないと思っています。

竹内 ポピュラーサイエンス、アニメやSFで、「人間は脳の潜在的な能力のうち、数パーセントしか使ってない」といった都市伝説みたいな話がありますが、科学的にはどうなんですか?
柴田 限界突破はまだ仮説の段階ですが、もし科学的知見が集まりこの仮説が正しいとなれば、数パーセントは言い過ぎですが、使い切っていない余力、マージンみたいなものがあるということになり、一部は正しいという気はします。ただし、この類の脳科学にまつわる都市伝説にはいろいろ語弊があるんです。僕らの脳は実は、寝ていても、意識的に何かしていない状態でも常時活動している。つまり脳はいつも全体的に使われているともいえるわけで、こういう意味ではこの「数パーセントしか使われていない」という見方は正しくない。しかし脳の「能力」を、外から見たときのパフォーマンスと定義すれば、少なくとも一部においては間違ってはいないのかもしれない。こういう話っていろんな解釈ができて、ドキドキわくわくする話だからみんな好きですけれど、どういう意味での何パーセントなのかをちゃんと定義しないと、大きな誤解を生む話ですよね。
竹内 数字そのものが完全に独り歩きしているというか、特に根拠はないわけかぁ。
柴田 はっきりした根拠はありません。ロマンはあっていいですけどね(笑)。
子どもの限界、大人の限界
竹内 年齢も学習の速度や限界突破に関係していませんか? 例えば、子どもたちが何かを完成させるまでの時間は、ものすごい勢いでぐいぐい縮んでいく。でも僕ら大人は子どもの数倍の時間がかかる感じですが、それは脳の劣化というか、年齢的な影響があるんですか?
柴田 経験や環境に応じて脳が神経回路の処理効率を変えていき、より効率的なシステムを作り上げる能力を可塑性といいますが、この能力が年齢とともに下がっていくのは事実だと思います。可塑性による脳の変わり方も、高齢者と若者では違うことも分かっています。ただ、われわれの学習速度が脳の可塑性の限界を常に反映しているのか、疑問に思うところもあります。むしろ大人は、これまでの経験をもとにして、本来脳の可塑性で決まっている限界よりも自分の限界のハードルをさらに上げてしまっていることもあるかなと。これは全然、神経学的な根拠とか、データとかはないんですけどね。長く生きているうちに、「自分の能力はこんなもんだ」みたいなのがどんどん蓄積されていって、それが実際のパフォーマンスを押し下げたり、学習で本来向上していく成長具合にも歯止めをかけたりしているような気もしなくはないですね。
竹内 私、ブラジリアン格闘技のカポエイラを55歳からはじめたんです。
柴田 ええっ、すごいですね!

竹内 妻と娘がはじめたのを見学しているうちに自分もやりたくなっちゃって。今年で5年目です。そこでアクロバットな動きがたくさん出てくる。最初はもう、そんな動き絶対できないだろうっていうのに挑戦するわけですね。例えば、座った状態から後ろにふっと宙返りで跳ぶみたいな。それを小学生の娘は、意外と早くできちゃうんですよ。ところが大人にはそれが結構大変で。なぜかというと恐怖心がある。つまり、後ろに跳んでみたは良いが本当にそこにちゃんと地面があるんだろうかとか、ちゃんと着地できるのかとか、いろんなことを考えて跳ぶ前から恐くて。恐怖心の克服っていうのも限界突破のカギなのかなと。
柴田 恐怖心か。たしかに。
竹内 私にとっての限界突破をするにあたって、一番の障害が筋力とか柔軟性だったら練習を重ねて十分できるはずなのに、恐怖心を克服するのには時間かかった。そこで、まずは落ちてもケガをしない様に砂の上で練習をして、そのあとマットでできるようになって、やっと最後に固い床でもできるようになった。でも子どもは最初からマットでやってみて、失敗しても全然平気な感じで。これって、経験が邪魔するんですかね?
柴田 高さや落ちることに対しての恐怖は生まれつきではない、という研究があるんです。赤ちゃんは、結構高い所で透明のガラスの上をハイハイさせても怖がらない。大人だとはじめからうわぁってなっちゃう高所でも、赤ちゃんは全く平気。でも何回か落ちる経験をすると赤ちゃんも怖がるようになる。高い所から落ちたら危ないという感覚でさえも学習の結果かもしれない。だとしたら、さっきおっしゃったように、砂の上でまずやってみるというような条件付きで一つひとつ制限を外していくのはとてもスマートな方法だと思います。
竹内 一度学んでしまった恐怖心を段階的に取り除いていく。
柴田 あとは普段から、ちょいちょい羽目を外す練習をしておく、とかですかね(笑)。大人になると予測が先立ってしまい、この先、やらなきゃいけないこともいろいろあるから今はエネルギーをセーブしておこうとか、リソースの配分みたいなことを考え始めることも、限界突破しにくいことと関係しているのかなとも思います。そういう意味で大人では、意識的にも無意識的にも限界のハードルが上がっていて、なかなか突破しにくいみたいなこともあるのかなと。こういう大人のこじらせ的限界を突破する方法を見つけるのも面白いかもしれません。
限界突破と社会的意味を考える“超人間学”
竹内 限界突破のリミッターの脳内メカニズムが解明されて、たとえば個人個人がリミッターを自由自在にON/OFFできるようになったとしたら、人間や社会って変化していくんですかね?
柴田 先ほど出てきた学術変革領域の研究グループには哲学・倫理の先生が一名参画していて、その点も織り込んで議論し研究を進めています。いわゆるエンハンスメント論*4は昔から哲学や倫理の延長線上にあります。例えばドーピング問題。なんらかの形で人間の能力を想定されている以上のものにできた場合、社会はどう変わるのか、その行為を罰するべきなのか。その資源にアクセスできる人、できない人と分かれてしまう場合、格差をどうしていくのか、などなど議論すべき点はこれからどんどん膨らんでいく。脳刺激とか、ニューロフィードバックでも人間の能力を操作できるとしたら、薬などの化学的な方法を想定している今のドーピングの定義自体を変えないといけない。さらには自分が能力開発を受けられる立場であれば受けたいと思うけれど、同じことを他人がすることに対してはどう思うかと問われるとちょっと違う見解になる。
竹内 人の心理としては、大いにありますよね。
柴田 それに限界突破がいつも人を幸せにするかと問われれば、そうとも言えなかったりする。幸せは他者との比較として感じられる部分もありますし、自分が自分の限界を突破したところで、その能力をほかの人と比べて感じる劣等感というものは、いつまでもなくならないかもしれない。
竹内 自分と他人の比較だけではなく、もう一人の自分、つまりテレワークでも利用されるようになってきているアバターの自分と本当の自分の仕事量や能力差みたいのも議論になるかもですよね。
柴田 そうそう。難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)によって身体を自由に動かせなくなった方が遠隔地にあるロボットに入って労働を行うといった例がすでにありますし、時間や空間を超越して仕事ができたり、自分というものが同時に複数の場所で存在できたりが、技術によって可能になってきている。そうすると、自分以外にロボットやアバターが2体、同時期に仕事をしていたらサラリーは3人分に増やしてもらえるのかとか、アバターが問題を起こした場合にそれは本人の責任なのか、アバターを作った会社の責任なのか、という話が当然出てくる。自動運転技術開発でも同じ議論がありますよね。もし事故に対して開発者が責任を負うことになったら、開発は進まない。自分の意志や判断の外にあるアルゴリズムがやったことまでも自分の責任にされてしまうのは釈然としないとか、社会心理学的にも興味深いトピックであり、同時に今の社会が想定している倫理観や責任論では明確な答えを提示できないような、まさに今から深く広い議論が必要なテーマが百出している感じで、とてもエキサイティングです。
竹内 未来を先取りして議論する。これは科学的根拠の積み重ねだけではなく、想像、予測する力をもって挑まないといけない。面白いですね! そういう議論や活動を定義する新しいワードみたいなものは、ありますか?
柴田 すごく大上段かもしれないですけど、僕らはこのような議論を扱う分野を「超人間学」と呼んでいます。
竹内 超人間学!
柴田 優越という意味の「超」ではなく、現在の人間の枠をいろいろな意味で「超えた」ときに、個人とか社会がどのように変わらなきゃいけないか、というのを考え議論しています。
竹内 こういった先見的なディスカッションが研究グルーブで活発にされているんですね。
柴田 そうなんです。僕らは研究者という立場から、時代の価値観・人間観を先回りして考えたいと思っています。今のところは具体的なソリューションを提案できているわけではないですが、少なくとも、この議論の一部がどこかの誰かを刺激して、より大勢を巻き込んだ議論に発展していく可能性もある。 「こういう技術や研究方法、結果がありますよ」と僕ら研究者が示し、そこから想定される課題を広く様々な分野の方々と議論して、次の時代の人間観を作り出すような仕事ができたらすごくいいなと思います。
おしまい
本シリーズへのご意見・ご感想・今後への期待を是非お寄せください。
お礼としてCBSノベルティを送付させていただきます。
__________________________________________________________________________________
*1 潜在過程:心理学で使われる用語で、「素早く、自動的で、無意識的な心理過程」のこと。対義語は顕在過程。
*2 ナシーム・ニコラス・タレブ:レバノン出身の学者、随筆家、金融トレーダー。予想もつかないような事象が起きたときこそ破壊的なインパクトを残す黒鳥理論(ブラック・スワン)、脆弱なものと反脆弱なものが共存することで衝撃を受けた際に不確実性を生き延び、衝撃を糧に発展できるという反脆弱性によって成り立つシステムを提唱している。
*3 PTSD:心的外傷後ストレス障害(Post-Traumatic Stress Disorder)。戦争、災害、犯罪被害などをきっかけとして生じる精神障害。体験がトラウマとなり、長期にわたりその記憶がフラッシュバックしたりすることで日常生活に支障をきたす。
*4 エンハンスメント論:本来医療目的で開発された技術や方法を、健康促進や身体・精神機能を増進するために使用することについての議論

今夜の研究者 柴田和久
ボストン大学研究員、ブラウン大学リサーチアシスタントプロフェッサー、名古屋大学准教授、量子科学技術研究開発機構主幹研究員を経たのち、理化学研究所 脳神経科学研究センターにて人間認知・学習研究チームを率いる。学術変革領域「心脳限界のメカニズム解明とその突破」研究グループ代表
Twitter:@kazuhi_s_

Barのマスター 竹内 薫
猫好きサイエンス作家。理学博士。科学評論、エッセイ、書評、テレビ・ラジオ出演、講演などを精力的にこなす。AI時代を生き抜くための教育を実践する、YESインターナショナルスクール校長。
Twitter: @7takeuchi7
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

