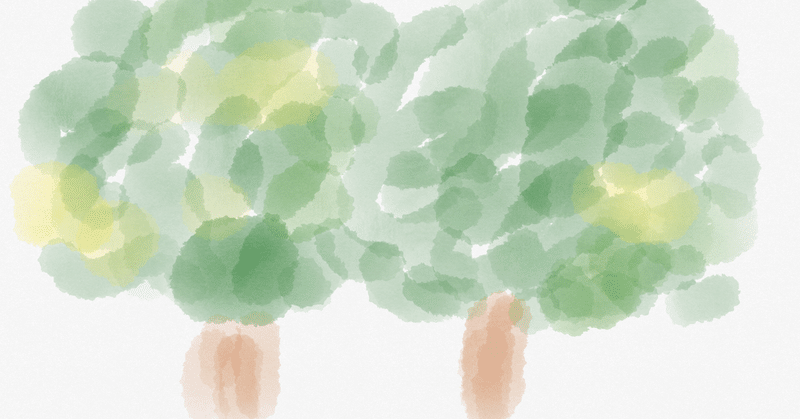
どうにも忘れられない、小学生時代の失敗「モチモチの木」
突然ですが、それは私が小学3年生の頃のこと。教科書にあった「モチモチの木」というお話について、感想文ではなく「感想を絵にする」、という授業があったんです。
正直、ストーリーの詳細はちょっとおぼろげなのですが、私が強烈に覚えているのが「どうしても上手に色が塗れなかった」という最悪な思い出。机に向かって、泣きそうなのを必死にこらえていました。
最初に鉛筆で下書きをして、黒いペンでそれをなぞり、最後に絵の具で色を塗る、というごく普通の作業。自分でも気に入った下絵が描けたつもりだったのに、色塗り段階ですべてがおかしくなってしまいました。
筆が紙に乗った瞬間、ペンの黒い部分が滲んでしまうんですよ。それも私だけ。周りの友達もみんな同じ様にやってるのに、ぜんぜん滲んでない。ボワボワしちゃった線をティッシュで押さえたり何度も絵の具を塗り重ねたりするんだけど、どんどん被害がひどくなるばかり。もう、ぐっちゃぐちゃになってしまいました。
悪い夢でも見ているような、長い長い授業時間。本当に悲しかったことを今でも忘れられません。
原因は簡単なこと。“水性ペン”のせいだった。
後でわかったんですが、それはつまり私だけが「水性ペン」で輪郭を描いていたからという単純な話でした。みんなは油性ペンを使ってた。だから滲まない。ただ、それだけ。本当に、ペンの種類のせいだけだったんですよね。
未だに、どうして自分はあの水性ペンを使ったのか、その経緯がまったく思い出せないのだけど、私の絵だけがボワボワのぐちゃぐちゃなのに先生も何も言ってくれないし。もう本当に悪夢としか言いようのない経験でした。
たぶん、当時の同級生も先生も、このことを覚えてる人なんて誰もいないと思います。でも、その最悪の絵が教室の後ろの壁に貼られている間(たしか全員の作品が貼られてた)、学校に行くのも嫌だった。恥ずかしいし情けないし、できれば破り捨ててしまいたかった。でも、壁の上の方に貼られた私の絵には手が届かなかったんだよなあ。
というか、あんな絵を描いたのに、怒られることも同情されることもなかったのか?うーん、なんだったんだろうなあ、あれ。

小学校の時のことなんて、もうあんまり覚えてないんだけど、ぐちゃぐちゃになった「モチモチの木」の絵のことだけは鮮明に覚えています。黄色くて3つに仕切られた「筆洗いバケツ」や、いろんな色が混ざってる絵の具パレットや、机が汚れないように敷いていた古新聞のしわくちゃな感じも。
胸の奥のほうが、きゅーってなりながら思うこと
そして今でも、なんだかうまくいかないことがあると、ふとあの光景が頭をよぎることがあります。胸の奥のほうが、きゅーっと痛くなる。でも、その度に「うまくいかないのは、そこでの私の努力や頑張りが足りないからだけじゃないかも。準備段階や装備など、なにか外的で圧倒的な要因があるっていう可能性もある。そっちを見直してみよう」って思えるんですよね。
何が言いたいかっていうと。どうしてもうまくいかない時って、その瞬間の自分だけを責めても仕方ないんだなという再確認。思い通りにいかないと、ついパニクってしまいがちだけど、そんな時こそ息を整えて冷静に、俯瞰して考えるべしってことです。そう思うと、あの苦い思い出も「悲しい」だけじゃなく、ちゃんと意味があった……ということなのですかね。ある意味、大切な学びなのか?
でも、もしもタイムマシンが完成して、10歳くらいだったあの日の自分に会えるんなら。「絵の具を塗る前に使うペンは、絶対“油性のマジック”を使うんだよ!」と教えてあげたいです。ほんとに。ぜひとも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
