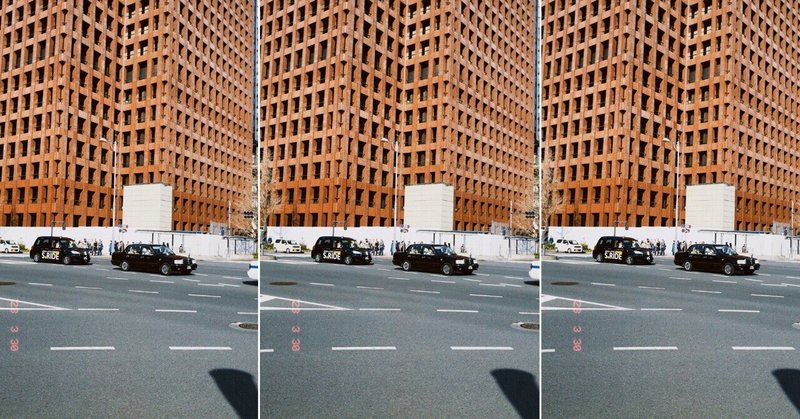
建築写真の生きる道
近頃はあまり聞かなくなったが、かつて建築写真はしばしば(揶揄や自嘲を含みながら)お見合い写真になぞらえられた(たとえば本誌1979年10月号「建築写真とは何か」特集参照)。どちらも客あっての商売であることを前提とし、一定のかしこまった形式性の上で、被写体の真の姿を写すリアリズムよりも実物の表面的な美化を厭わない功利主義が優先される、といったあたりに共通性が見られたのだろう。その比喩がこの頃聞かれなくなったのは、お見合いというものが世間で昔ほど一般的でなくなった影響が大きいかもしれない。代わりに出てきたのはマッチングアプリだが、建築写真をマッチングアプリのプロフィール写真になぞらえるのは、今のところなにがしか躊躇われるものがある。お見合い写真が備えていた文化的な様式性が瓦解し、なんでもありの功利主義があからさまになっているからだろうか。修整の度合いが増すことで被写体の個性が失われている? 写真の重要度が上がる一方で写真の信頼度が落ちている? しかし現代のマッチングアプリ事情に明るくない筆者は、ここでこれ以上この問題には立ち入らない。
建築の表現手段として20世紀のあいだ安定した地位を占めてきた建築写真の存在が揺らいでいる。情報技術・情報環境の進化や社会における建築の在り方の変化は、CGやムービーなど新たな表現手段の可能性を提示するが、発展著しいそれら他ジャンルに対し、旧来からの建築写真がジャンル総体として展開すべき目新しいテーマは、現時点で特にないような気がする。建築写真はすでに大まかに認知されている建築写真の領分で、各々が良い仕事を心掛けるほかないのではないか。
してみれば良い建築写真とは一体どんなものだろう。その判断は意外と難しい。一度でもその建築を訪れていれば、それを写した写真の良し悪しはおおよそ判断できる。しかし訪れたことがない多くの建築の場合、それがいくら魅力のある写真であっても、建築写真としての良し悪しは保留にせざるをえないことが少なくない。待庵を写した写真が見せる「狭さ」をどこまで信じていいのか。天壇を写した写真が見せる「広さ」をどこまで信じていいのか。建築写真のこうした根本的な信じられなさは、訪れたことがない建築を伝えるものとして建築写真が発展してきたことを考えたとき、奇妙なねじれを感じさせる。
写真は決して真を写すものではない、日本でphoto-graph(光で描かれたもの)に写真という訳語が充てられたことが多くの誤解を生んでいる、といった指摘はすでに至るところでされている。たしかに現代社会に生きる者として、写真が見せる「たしからしさ」には十分に疑い深くあるべきだろう。しかしもちろん写真のすべてを虚構と割り切ってしまうわけにはいかない。お見合い写真ならばいくら虚構だろうが、実際相手に会ってしまえば事前の写真がどうであったかはどうでもよくなるが、建築写真はそこに写る建築とほとんどイコールのものとして、そのイメージを社会に定着させる。そのことに対する責任は、今ではプロアマ関係なく、建築写真が不特定多数に発信された時点で発生する。
なにより図面やCGにはない建築写真の特性とは、撮影者としての主体(多くの場合、設計者とは異なる他者)が個々に実在する建築を経験しないことには成立しないという点にこそ見いだせるはずである。どんな建築であれ等しく見映えがするように写す技術や、どんな建築であれ一定の形式で客観的に記録する技術は、建築写真にとって今も変わらず有用だが、それらの技術はいずれ写真以外の何かによって、写真以上に効率よく担われるようになるだろう。写真がいくら真を写すものではないと言っても、一人の人間が一個の建築と向かい合い、その写らない真を写そうとするところに建築写真の生きる道があるのではないかと思う。
真を写すと言っても、「カメラとモチーフの直結」「絶対非演出」(土門拳)といった自然主義的なリアリズムでなければならないことはない(建築の真実は一つではない)。様々な道具や技術を用い、演出をして、写真にポエジーやファンタジーを生み出すのもよいと思う。しかしそれはあくまでその建築の固有性に立つ限りにおいてであり、そこから離れるなら、その写真は本文で問題にしている建築写真(ある建築を表現するものとしての写真)とは区別される。他方、もともと建築は必ずしもその個々が個性的なものではないし、個性的でなければならないものでもない。だからそれを写した建築写真も個性的な写真でなければならないことはなく、むしろ建築写真は時に個性的であることを諦めることも必要になってくる。
待庵と天壇の例はあまりに極端だが、建築写真においては、たとえばある部屋の一つの平凡な窓を写すことさえなかなか難しい。異なる領域を繋ぐ/隔てるものとしての窓という存在は、ただ漫然とシャッターを切っただけでは、写真の平面には十分に写らない。そしてそれをどうにか工夫して写したとしても、今度は全体のなかでその窓の存在がことさら強調され、一個の建築としての有り様を捉え損ねることにもなりかねない(一つの建築のすべてを写そうとすると却って見えなくなるものがある)。
あらためて、良い建築写真とは一体どんなものだろうか。その手がかりになりそうな言葉として、民藝運動の柳宗悦は「ものへの理解がなければ駄目」と書いている。「「美しき写真」はいい器械と上手な写真師とだけでは駄目である。ものへの理解がなければ駄目である。ものの美しさへの見方が悪ければ、写したとて、ものは死んでいる。大事なのは見方である。理解である。美への直観である。私は器械三分、見方七分と云いたい。」(柳宗悦「美しい写真とは何か」『光畫』創刊号、1932年5月)。
ここで柳が被写体として想定しているのは自然の景色だが、様々な部位による立体的な構成と内外多数の視点、社会的に複雑な意味や機能をもつ建築の撮影もまた、「ものへの理解」がとりわけ重要になるに違いない。加えて柳がこの文を書いた100年近く前のカメラと比べ、現代のカメラは誰にでも格段に容易に写真が撮れるようになっている。とすれば現代の建築写真においては、器械一分の見方九分ぐらいに言ってみることもできるかもしれない。事実、インターネット上で日々目にする建築写真には、若い建築学生によるセンスはあるが雰囲気だけで建築が撮れていないと感じさせる写真もあれば、一見平凡でも建築の有り様をよく捉えていると感じさせる熟年の建築家による写真もある。建築を理解すればするほど良い建築写真が撮れる。この単純な原則こそ建築写真の希望ではないか。
▼図版とキャプション

頂部から解体が始められた旧東京海上ビルディング(設計=前川國男建築設計事務所、1974年竣工)を筆者がiPhone 8で撮影した写真。建設以前から周辺環境との関係が問題視された超高層だが、その都市的な有り様を捉えるには今ならばドローンを飛ばすのがよいだろう。あるいはそんな手間をかけずとも、Googleマップの3D表示で、視点を自在に変えながら俯瞰で見たほうが得られるものは大きいかもしれない。マップ上の多様な文字情報も空間の把握に極めて有効だと思う。しかしいずれにせよそれらはあくまで超越的・仮想的な視点であり、人間の日常の経験からは切り離されている。そもそも超高層ビルなど地上から眺めるようなものではないだろうか。半世紀前、丸の内界隈の「巨大なビルの谷間を歩き廻っていた」写真家・中平卓馬はこう記している。「ちょうど日曜日であったが、宮城前には多くのアベックが散さくしていた。だがだれもこれら巨大なビルに眼を向ける者はいなかった。たったひとつ前川国男設計によるビルをのぞいては。」(「アナーキストは建築家になり得るか?」『近代建築』1974年6月号)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
