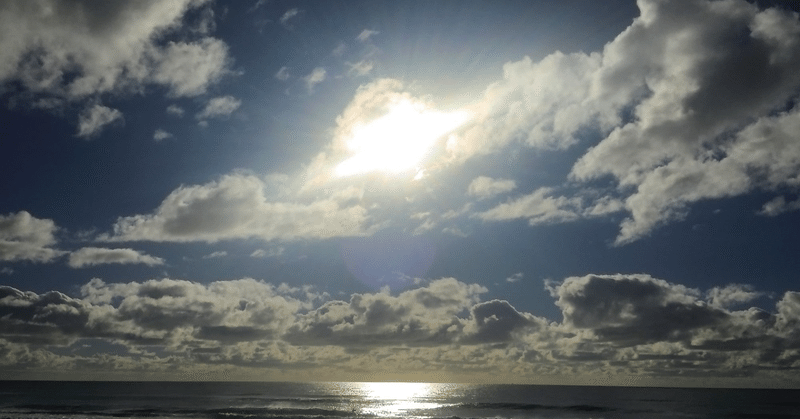
【読書メモ】ビジネスシーンを生き抜くための仏教思考 松波龍源著
〇仏教とはなにか?
宗教ではなく、哲学。
言い換えると、
超越的な何かにすがるのではなく、自分でよく考えること。
付け足すと、
今この瞬間を豊かに安楽に生きるための哲学。
〇不確実な未来に対してどう向き合えばいいのか?
未来の予測の当たり外れをどうしても重視してしまうので苦しみが生まれる。過去を振り返る、未来を予測する、今を生きる、この3つのバランスを取り、特に、今なすべきことをなしていく。
〇仏教の善悪の基準は何か?
苦しみが発生するかどうか。
〇輪廻転生は宗教的。仏教は哲学的とするなら、なぜ概念として必要なのか?
輪廻転生があるかどうかは分からないが、あると信じて生きる方が良い結果につながるから。
〇資本主義は仏教でアップデートできるのか?
資本主義には①唯物史観、②弁証法と進歩史観、③心の問題の軽視、という特徴から短期的、個別的な利害に集中しがち、という問題があるところ。
仏教の中観と唯識に基けば、私が他者との相互関係の中でしか存在できず、他者の利益を考えることは自分の利益を考えることに繋がる、と気づくことができ、長期的かつ全体的な利益を重視することができる。
〇仏教のさとりはどのような状態か?
時間や空間の認知スケールを自在にコントロールできる。
言い換えると、因果関係を認識し、苦の成就をいつでもシャットアウトし、楽を享受できる心の使いができる状態。
具体的には、目の前の物事について、直観的に空性を理解できる状態。
メタバースで言いかえると、物事の本質はあらゆる可能性を秘める空性であり、この空から生まれたこの世がメタバースであり、自身はこの世のアメタバースのアバターと言え、本来の世界である空を直覚できることがさとり。
〇どうすれば悟りに至れるのか?
聞思修
→仏教の論理を学び、考え、修行を通じて、空性を身体で納得する経験を繰り返す。
〇曼荼羅とは何か?
自分を中心としたネットワークの集合のありよう。一方で全体から見れば絶対的な中心はなく、web3的。
社会自体が中央集権的なweb2から自立分散的なweb3に移行する中で親和性がある考え方。
〇仏陀とは何か?
他者の苦しみを滅して悟りに導くことができる人。
〇唯心論とは何か?
自分の認識の中にしか喜びや悲しみは存在しない。
〇仏教では欲望はどのように位置づけられるのか?
すべては認識で決まるのであり、苦しみが回避できるなら欲望はあってもよい。苦しみにつながるなら欲望はない方がよい。
〇つらい過去は変えられるのか?
今という認識を変えられるなら、その原因である過去の認識を変えることができる。
〇ブルシットジョブはどう捉えられるのか?
ブルシットジョブを作る側に回ることはなるべく避けるべき。
一方で、ブルシットジョブをさせられる側については、意味のないことだ、と意味を求めるのは自分の心であり、自分次第。自身にとってより良い生に向かっていけるなら取り組めば良い。限界を越えれば無の境地に達する機会になる可能性がある。
〇人間の意識は変えられるのか?
顕在意識では変えられたようでいても、自分で直接体験したものでないと、潜在意識の執着やエゴ、末那識は変えることができない。
〇湧き上がる承認欲求はどのように対処すれば良いのか?
@ロジック
承認欲求は潜在意識から湧き出る人間の根源的な欲求。
そもそも、人間が自分を認識するためには、自分以外の他者に囲まれて、他者からの認知を教えてもらわなければいけない。
問題は、他者からの認知を受けて、自分をどう評価して、確立するかは自分次第である、ということ。これが、他者基準の評価で自身で評価することを放棄することで、苦しみにつながる。
@自分の価値は自分で決める
他者からの受け取るものはあくまで他者の認知であり、それをふまえて自分をどう認識するか、というのは自分の問題である。ゆえに、他者の意見や批判は真摯に受け止め、一方で自身の価値は自身で決める強さを持つ。
@利他的な振る舞いを心がける
湧き上がる承認欲求に対しては、直接的に欲求に基づく利己的なふるまいをするのではなく、結局、自分は他者の認知で認識できるのであるから、他者の利益につながる、利他を心がけた振る舞いをすれば良い。それが回り回って自身の利益になる。
〇どうすれば豊かに安楽に生きられるのか?
一切のものに苦の可能性があることを認識する。
対象、例えば自分の身体に執着するのではなく、関係性を認識する。関係性は身体がなくなっても続いていく。
〇苦の可能性について直面したとき、どう振る舞えばよいか?
回避可能か考える。
回避できない場合、そもそも苦と考える理由としての自身の評価基準が正しいのか考える。
それでも苦しい場合、その苦しみを受け入れ、関係性に目を向ける。→最大の苦しみである死も。
〇因果とは何か?
物事には結果と対応する原因がある。
〇縁起とは何か?
原因に働きかける作用が縁。原因に縁が加わり、結果が生じる。
〇因果縁起をふまえて、どう振る舞えばよきのか?
無限の因果関係をふまえて、自分に苦しみを生む縁を避け、喜びをもたらす縁を選ぶよう心掛ける。
〇空とはなにか?
全ての物事は因縁によって生じ、固定的な実体がないこと。あるいはそのありよう。
〇空をふまえると、どのように振る舞えばよいのか?
①この世の物事は空から因果縁起で生み出されたものであり、物事が何であるかには無限の可能性がある。ゆえに、苦しいというのであれば、その因果縁起を調整すれば苦しみも調整できる。
②物事に絶対性を認めることは誤りであるし、そのように認識することは諦める。
③因果縁起を調整するうえで主体的にコントロールできる自分の認識を、苦しみが少ないように変化させる。
〇唯識とは何か?
全て物事は自分の認識によって成り立っている。
言い換えると、全ては空に対して、認識力を持った存在がその力を向けたから、実存として存在が確定する。
それゆえ、認識力を持った存在の数だけ宇宙は存在する。
認識されていないものは、可能性として存在する。
〇人間の認識とはどのようなものか?
8種類、4つの識に分けられる。
思考や行動を通じて何かを認識し、蓄積される。何らかのきっかけで阿頼耶識から種が芽吹き、因果縁起で末那識から意識、5識にフィードバックされ、次の行動が起こる。
このように、認識は次の行動を作る。
5識→
目、耳、鼻、舌、身。感覚ではなく、その感覚に対する認識。
6識→
意識。ここまでが、顕在意識。
7識→
末那識。これまでに思考した、感じた、体験したことが一つも失われることなく蓄積されている領域。言語や理性では制御できない衝動と情動で表れる。
8識→
阿頼耶識。宇宙が経験したことが全て蓄積された海のようなもの。
〇唯識をふまえると、どのように振る舞えば良いのか?
意識的にこれまでと異なる行動を取ることで、これまでにない性質の種が芽吹き、心の方向性を変えることができる。
それゆえ、自分の体験がポジティブになるよう、認識をコントロールする。
潜在意識に働きかけるには、顕在意識では限界ぎあるので、身体性を持った体験が重要。
〇諸行無常をふまえると、どのように振る舞えば良いのか?
苦楽を普遍のものとする考えに陥らないように気をつける。そこに苦が生まれる。
〇利他とはどのような考えなのか?
以下の理由から、私と私以外の利益のどちらも大切にする。自分が犠牲になる、というものではない。
①私は私以外のものとの因果関係から特定される。ゆえに、私とは私以外のすべてのものである。
②形而下の世界では別のように見えても、形而上の空では区別ができるものではない。ゆえに、私と私以外に価値の優劣はない。
〇ギリシャ哲学と仏教は何が異なるのか?
ギリシャ哲学は不動の真理(プラトンのイデア、アリストテレスの最高善)、仏教は可変の真理を主張する。
ギリシャ哲学は弁証法により不動の真理に辿り着こうとする。仏教にとって真理は状況によって変わるもの。
ギリシャ哲学の問いは世界とは何か?であるが、仏教の問いは私とは何か?というもの。
〇その違いはどのような影響をもたらすのか?
不動の真理に向かい思考を進めるギリシャ哲学は社会の発展に向かう力が強く、結果として現代の科学の元となり社会は物質的により豊かになった。
一方で、精神的な一人一人の心の問題に向き合うものではなく、生きづらさに対して答えを与えてくれるものではない。
〇キリスト教と仏教の違いは?
キリスト教は神という絶対的な存在を信じる。
聖書は物語、仏教の経典はロジックと言える。
〇ルネッサンス以降の哲学と仏教の違いは?
哲学が徐々に仏教に近づいてきた。
デカルト→
神を含めた全てを疑うと、自分という確実な存在に気づく。
ジョンロック→
ある人の理性や感性は個人が経験したものに由来する、という経験主義を主張した。
ニーチェ→
神や聖書の絶対性を否定した。
サルトル→
実存(認識による作為)は本質に先立つ。
メルロポンティ→
頭で考えるだけでなく、身体を通じた認識、身体知を主張した。
〇こうした仏教と西洋哲学の比較をふまえて、どのように考えれば良いのか?
今の社会を規定しているものの、実在論と弁証法をベースとした思考、社会の改良には限界がある。仏教をベースとした思考にシフトするべき。
〇仏教が生まれたのはなぜか?なぜ普及したのか?
バラモン教の物事の絶対的な本質、アートマンを前提とすると、身分階級もまたアートマンに基づく絶対的なものになり、救いがないから。
バラモン教の後継であるヒンドゥー教は、コントロールできない天候に成果を左右されるため土着の神に祈らざるを得ない農民に普及し、仏教は変わる状況の中で普遍の真理を必要とし命の危機を抱えながら旅をする必要がある商人に受け入れられた。
〇宗教が流行るのはどのような時期か?
世の中が不安定になる時
@鎌倉新仏教→貴族から武士の世に
@諸子百家→春秋戦国時代
@宗教改革→ペストの流行
@仏教→バラモンの地位低下
〇中国で仏教はどのように変容したのか?
インドはものごとの順序や整合性を意識しない精神文化。そこから更にランダムに仏教が伝来ふることでより一層整合性が取れない状況になった。
①天台智顗により、法華経を最高の教えとする整理を自己の解釈で行なった。
②禅宗が伝来した際は、自由な思索に基づく真理へのアクセス、というのではなく、警策をもちいた厳しい修行に基づくものに変質した。
③出家者の在り方は本来人里から少し離れた場所で托鉢しながら修行するところ、百丈懐海により、人里から完全に離れた場所で生産活動に従事しながら修行するまのに変質した。
④阿弥陀信仰により、有神論に変質した。
⑤僧侶の衣服が三衣の質素なものから、華美なものになった。
〇日本で仏教はどのように取り入れられたのか?
苦しみから解脱する哲学ではなく、国家の統治ツールとして取り入れられた。
聖武天皇は神仏習合を行い、既存の土着で信仰される神道に中央集権的な仏教を融合することで、中央集権国家体制を強めた。
具体的には、仏教は華厳教に基づき盧舎那仏を擁する東大寺を頂点とした国分寺、国分尼寺のネットワーク、神道は伊勢神宮を頂点とした一宮、二宮、三宮を全国各地に近接して配置し運用した。
その後も仏教が国家統治ツールである性格は変わることがなかった。
江戸時代になり、寺は戸籍を管理し地域を監視する役所的な役割を果たすようになり、僧侶自身にとっての食べていくための職業になり、より本来の仏教から変質した。言い換えると、仏教が土着信仰化し、インドでは対抗概念として生まれたはずのヒンドゥー教と同じ位置付けになった。
〇鎌倉新仏教は新しいのか?
中国と同じく、本来天台宗、真言宗は新しい仏教にも関わらず、古いはずの浄土宗と禅宗が新しい仏教として取り入れられた。
〇以上をふまえて、何が言いたいのか?
資本主義、共産主義、ティール組織、DAOなど社会や組織のあるべき論をどれだけ優れたものを生み出したところで、それを運営する人々に利他ではなく利己の心の働きがあれば、利権を有する人々の言いように運営され、結局は崩壊してしまうかうまく行かない。
そうした心の働きを身につける1つの方法論が仏教である。
さとりまで行かずとも、仏教の教えを正しく身につければ一人一人は良く生きれるようになり、またその社会も良くなる。
その社会で起こるあらゆることは、その社会をつくる人々の心の表れなのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
