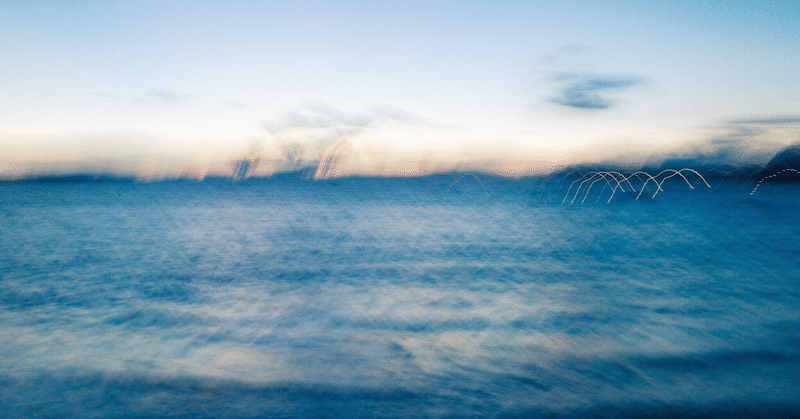
【読書メモ】「地図感覚」から都市を読み解く 今和泉隆行著
○まち分析で使える地図
分析:マピオン地図
https://www.mapion.co.jp/
加工:openstreetmap
https://www.openstreetmap.org/
比較:くらべ地図
https://kurabe-chizu.info/
距離測定・面積計算:地図蔵
https://japonyol.net/
○サイズの感覚を持つ方法
大都市の小学校:一辺60~80m
平均的な小学校:一辺100~150m
総合スーパー:一辺80~120m
広めのスーパー:一辺40~60m
小型スーパー:一辺15~30m
○道路模様でまちの特徴を分析する方法
・傾斜地:道路が曲線的
・明治以前からの市街地:道路が直線的・不規則・行き止まりが多い
・古くからの農地:不規則な曲線
・高度成長期の大規模開発宅地:道路が直線的
・近年の大規模開発宅地:道路はなだらかな曲線、建物は大型化
・小規模な開発宅地:道路は複雑
○日本のまちの変化の背景
・1950~1990にかけて日本のまちは大きく変わり、農村から都市部への人口移動、核家族化とそれに伴う住宅需要、自動車保有率の上昇を背景として、都市部の人口増加、都市周辺の農村の都市化(郊外化)が進んだ。その後の30年のまちのかたちはそんなに変わらない。
・高度成長以前に都市化が進んだまち:自動車移動を前提とせず、個人商店が連なる商店街が形成されている
・高度成長以後に都市化が進んだまち:自動車移動を前提とした道路網や大規模量販店が形成されている。商店街は形成されない
○まちの新旧を見分ける方法
・自動車が普及し始めた1920~30までに発達した古いまち:
寺院・神社、地元金融、郵便局、JA、米屋、燃料屋、中小企業、個人病院が多い
住所が大字・小字表記
道路の網目が細かくなる
・1967年(住宅表示法施行)以前に発達したまち:街境が道路や川に沿っていない
・2000年以降に発達したまち:
大規模な商業施設が立地
○まちの中心を見極める方法
・主要拠点と立地を確認する:
商業施設:最も人が集まるのは大規模商業施設
商店街:古くから人通りが多い場所
公益施設(博物館、図書館、病院など
ビジネス街:平日だけ賑わう
官庁街
公園・史跡
宿泊施設:ビジネス・観光の目的地付近、交通アクセスが良い立地
交通拠点:多くの人を集める
○まちの発展を見極める方法
・一般法則:
明治以前から発達した旧市街のまちはずれに鉄道の駅が設置される。
鉄道の駅周辺に新市街が発達する。
旧市街の周辺に市街地・住宅地が広がっていき、その外周部に高速道路のICが設置される。
・旧市街・新市街の具体事例:旧市街が発達しているほど、新市街との距離は遠くなる
旧市街・新市街が統合:青森、福島、郡山、高崎、福井、静岡、浜松、豊橋、姫路、倉敷、小倉、大分
旧市街と新市街が徒歩圏内(1km):盛岡、秋田、山形、仙台、永野、松本、甲府、富山、岐阜、岡山、鳥取、米子、徳島、高知、山口、佐賀、佐世保、宮崎
旧市街と新市街が1km以上離れる:札幌、水戸、名古屋、金沢、京都、広島、福岡、長崎、熊本
○まちの賑わいを見極める方法
都市人口100万人以上:中心市街地は県内だけでなく周辺県からも人を集める。郊外大型モールと共存。
都市人口40~100万人:中心市街地の集客力は依然強く、郊外大型モールと共存。
都市人口20~40万人:中心市街地と郊外大型モールは接戦
都市人口20万人未満:中心市街地はわずかに個人商店が残るのみ。中心市街地であっても車が必須。郊外大型モールの周辺に市街地が形成される
例外①:都市人口の割に中心市街地が賑わう
市域が狭く周辺市町村から人が流入:立川市
周辺により大きな都市がない:高知市
県庁など中心性が高い拠点が多い
例外②:都市人口の割に中心市街地が閑散
市域が広い:いわき市
小都市が複数合併:倉敷市
近隣により大きな都市がある:相模原市
○市街地の拡大を見極める方法
佐世保市(傾斜地が多く市街地に拠点が集中)vs佐賀市(平地で拠点が分散)
静岡市(新市街と旧市街が近接し賑わいが集中)vs新潟市(新市街と旧市街が分散し賑わいも分散)
熊本市:標高の高い平地に市街地が発達
○旧市街と新市街の強さを見極める方法
旧市街が強く鉄道駅は素通り:八戸、山口、高知、熊本、宮崎
旧市街が強く駅周辺は開発するも旧市街には負ける:盛岡、京都、広島、福岡、佐世保
新市街が旧市街の脅威になりはじめる:札幌、名古屋、鹿児島
旧市街と新市街が対等:弘前、仙台、山形、水戸、甲府、岐阜、富山、岡山、米子
新市街が中心、旧市街は観光・歴史施設で棲み分け:長野、松本、松江
新市街が強く旧市街の中心性はない:秋田、鳥取、徳島
○市街地の立地傾向を掴む方法
一等地:ファッション店(百貨店、ブランド路面店、宝飾品店等)
一等地の周辺部:専門店(書店、電気店、家具店、スポーツ店、雑貨店)
周辺(表側):オフィス街・官庁街
周辺(裏側):歓楽街・娯楽施設
まちの新たな動き(コワーキングスペース、カフェなど):市街地の少し外側、人通りが少なくなったかつてのまちの中心地
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
