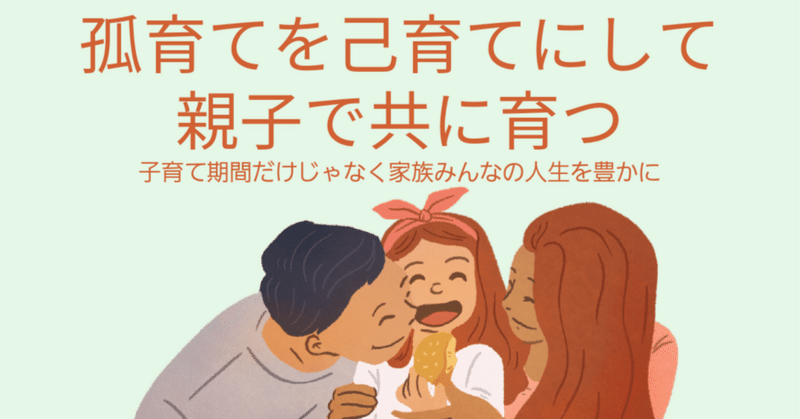
【サステナブル育児】目指して
孤育てを手放して己育てを楽しむためのマインドセット
【お母さんはみんな偉い】
独身子なしアラフォー女性とアラフォー専業主婦では
なんとなく専業主婦の方が自己肯定感低い気がする。
だからあえて言いたい。
「お母さんはみんな偉い」
子供がいる/いないだけで「偉い」「楽」って言えないけど
仕事を持っている人の方がやりがいを感じたり自分の好きな時間があったり
自分を癒したり認めたりするチャンスが多い気がする。
でも、育児中ってそもそも自分を振り返る余裕が少ない。
だからあえて言いたい。「頑張ってるね」「偉いよね」と。
仕事している人だってもちろん忙しいし疲れたり悩んでいたりもする。
でも収入として目に見える対価があったりするじゃない?
専業主婦を「旦那に養ってもらってお気楽にダラダラしているだけの人」「自分で戦わずして夫に守ってもらってる人」と思っているなら専業主婦本人が言っているとしてもそれは昭和マインドだと思う。
実はこれ、私が義実家に言われたこと。
妊娠中にパートナーが無職を選び(曰く「妊娠中のお前が心配で」年子で妊娠してるのにほぼ丸二年一緒にいた)預貯金食いつぶしてた時。
義実家に「息子が働けないのならあなたが働けばいい」って言われた。
妊婦が働けないとは言わないけど、悪阻や体調不良ひどくて、それを心配してパートナーは仕事辞めたんだよ…。
お宅の息子は働けないんじゃなくて働かないんだよ。
私に働けという前にお宅の息子を働かせてくれませんか…と心底思ったね、あの時は。
昔はある程度「女性はこうあるべき」が決まっていたからそこに合わせようとしてればよかったし、「女性の幸せは結婚して子供を産むこと」が主流だったんだと思うから「こんなはずじゃなかったな」と思っても「これが幸せに違いない」とか思いこもうともできたんじゃないかと思う。
…窮屈だったとは思うけど、余計なこと考えずに済んだというか諦める理由にはなっていたというか。
今は「子供たちの個性を認めましょう。伸ばしましょう」「多様性を受け入れましょう」だし、どこまでが躾・育児として必要なのか、どこからが親のエゴなのか皆目見当もつかない人も多いと思う。
そんな中、どこから文句言われるかビクビクしながら、無償奉仕して己を削ってるんだとしたらすごくない?
そしてそこまでして育てた子に「親ガチャ外れた」とか言われちゃう切なさ。
そして「子供の為の収入UPにパートでも…」と仕事を探すようになって「あぁ…私には何のスキルもない」とか「出産&育児でブランク空いちゃったし、今さら仕事も選べない…」とかさらに落ち込むママさんはたくさんいる。
確かにお金は稼いでなかったかもしれないけど。
家族が快適に過ごせるようにあちこちに目を配りつつ、子供が小さいうちは子供の世話やスケジュール管理しながら自分のタスクもこなす。
昔みたいに「義父母と同居」なら色々とストレスを感じながらも孫を任せちゃったりする時間もあったかもしれない。
でも核家族化が進んだ今、「育児方針に口出されない自由」と引き換えに「自分一人で育児の責任すべて背負ってます」状態のママたち…まさしく「孤育て」。
私自身は親兄弟どころか親戚まで地元に住んでいるので、何かあれば助けてくれる人はいた。想像以上のハードモードな育児経験だったけどうまく「己育て」に繋げることができ、子供も成人を迎えられた。
育児中に出会ってきた「戦うかーちゃん」たちが「燃え尽き症候群」にならずに育児を楽しむ方法や、これからパパ・ママになる世代が「人生の波乗り楽しみながら育児を楽しむぜ」って前向きになれるようなマインドをお伝えしたいな…と思って書いておこうと思う。
<戦うかーちゃんに伝えたい。あなたが日々積み重ねているスキル>
自分の意思とは関係なく家族のタスクを管理して効率よく進めるマルチタスク進行スキル
一緒に育児するはずが「ごみ捨ても仕事もする俺、偉い」とか平気で言っちゃう大きな子供への仏のような対応による堪忍袋の強化
自分の価値観に合わないのに「子供の同級生だから」「子供が仲良くしたい子だから」と共通点のないママ友とのお付き合いによるコミュニケーション能力向上
「今日はこの服を着たい」「今日はこれを食べたい」なんて小さな望みすら叶わない日もあるけれど、それでも小さなご褒美を見つけて自分を鼓舞する能力UP
今まで自分最優先で生きてきたような人ですら「我が子が得(楽)するために」と子供の為に考える利他思考
「愛する人の嫁になっただけであなたたちの娘になったわけではない」という声もよく聞く義実家との関係。心では泣いても怒っても笑ってお付き合いしちゃう腹芸スキル
一人暮らしなら絶対お付き合いしない近所の人。子供に挨拶を教えた手前…と知らない人にも挨拶する社交性
【大人の多様性】
【大人】にも色々いる
昭和の…と言っても60年以上もあったから昭和初期と昭和後期でも違うけど。
私が生きてきた昭和後期も田舎だったせいか「女性は家で子供を育てる」みたいなのが強かった気がする。
うちの母はフルタイム看護師して働きながら育児してた人。
母は「えー、子供苦手なのよね…」とか言いながら、子供が欲しかった父のご希望叶えて子供を産み、「やっぱ無理ぃ…仕事してる方が楽」と妹を産んでフルタイムの仕事に戻った。
ちなみに妹が幼稚園に入るころまでは祖母を呼び寄せて同居していたけど
私が2年生の時かな?「自分の家で最期を迎えたい」と祖母が叔父の家に戻ってしまって。
タクチケ使って幼稚園から体調不良の妹を引き取ってくる役目を私がこなしていた。
父は母をフルタイムで働かせつつ戦時中思想の残る人と言うギャップの激しい家庭だったので当時のスタンダードともちょっと違ったと思う。
ただ、当時の同級生の家庭は(外から見る限り)「趣味の時間を持つ」とか「子供の為に」みたいに優雅に時間を使っているママもまだ多かった気がする。
学校のPTA活動とかも「仕事あるから無理です」とか「下の子小さいから無理です」とかが免除理由になったりもしてた。
「母親とは」みたいな像に対して「こういうのが基本よね」が何となく共有されている感じ。サザエさん・ドラえもん・ちびまる子ちゃんの世界。
そうなるとその型にはまらない人を除外する動きも強いというデメリットもあるわけだけど、ハブられたくなければ「こうしてればいい」が結構明確だったのかな。
平成
平成になるとクレヨンしんちゃん的になって親子とも多少個性が強くてもちょっと許されるようになってきた気がする。
昭和の時代にはしんちゃんが主人公ってあんまり受け入れられなかった気がしない?
なんかそんな感じの違いが昭和と平成にはある気がする。
平成になるとだんだん「みんな自由にいこうぜ」「枠を壊そうよ」みたいな感じが強まって受け入れられやすくなってきたのかな。
働く女性も増え、働くママも増えてきて。
「その常識、間違ってない?」とかって考えながら、でも何となくは「これがフツーかな」みたいなものもあるから共通認識のベースはそんなに変わってない。
ただ、その「フツー」にはまらない人は相変わらずきつかったと思う。
例えば「毎日登園/登校する」ができなかった私は病院たらい回された上に「自立神経の問題」と診断されると「母原病(要は愛着障害)」とか「気合がたりん」とか責められた。
私の母は私が自律神経やられた(生まれつきという話もある)ことで散々責められたらしい。
私が成長してから聞いた話だけど私を連れて死のうかと思ったこともあるらしいし。
その時死んでいたら残された妹の立場は…というのが姉妹の共通認識だけど。
結果、妹を不幸にしなくてよかった。
「楽しく学校に行く」のが苦手な私だけでなく、当時家族ぐるみで仲の良かった「かわいらしいものが好き」な男の子や、かわいらしく振舞うのが嫌な「男前女子」とかも浮いてたな。
最近の「LGBTQ認めようぜ」っていう活動見るといつも彼らを思い出す。
あの子たち、今の方が生きやすかったのかな…とか。
実際の分類がどこになるタイプだったのかは知らないけど韓流アイドルもメイクする時代、うちに遊びに来てコンパクトを覗いていた彼は少なくとも当時より生きやすいんじゃないかなと思う。
当事者には当事者しかわからない部分もあると思うから想像でしかないけどそう感じる。今現在も「生きづらい」って感じるてる人はいる思う。でもきっと30年前よりは進歩してると思う。
私は昭和の終りの方と平成、そしてそれに続く令和を生きているわけだけど一人の人間が考察してもこれだけの価値観の波がある。
これに各自の性質や性格、習慣や思想・国籍・宗教的なものなど加わったらそりゃぁカオスだよね。
私の親はガッチガチの「こういう常識」にとらわれた人で、「常識的に考えて」「普通は」が口癖の人たち。だけどそもそもその価値観が同年代のご家族とズレていたので「どれが本当の常識?」と染まりきることなく育てたのが幸いしてその時々で比較的柔軟に対応できている…と思う。
といより、どちらかというとステレオタイプなものが苦手な方かもしれない。
今では「あなたの言う普通の基準って何?」と平然と言い返せる大人になれた。
それでもやはりその場所による「普通」とか世代間の「普通」という目に見えないものもあるわけで。なんとなく「居心地悪いな」と思いながらも全身どっぷりつかることなく所属先を分散することで何とか成り立ってるところがある。
令和
これだけ多様性が浸透(とはいえまだ過渡期だと思うけど)してきた中で「このコミュニティがぴったり」なんて所属先が見つかる人の方が少ないよね?
裏で陰口言う感じの「八方美人」みたいなのはどうかと思うけど
「余計なことは言わない」感じで本心を分散させて生活するのもこの時代の生活の知恵。
大人って今まで生きてきた経験則や自分の中で育ててきた価値観がある分、その辺の変化にどうやって柔軟に対応していくかで幸せ度が違うと思う。
今までマジョリティ(多数派)だった人もマイノリティ(少数派)だった人もただ生きやすくなったわけでもなさそうな気がする。
昭和は「母としてこうあるべき」
平成は「女性ももっと違う生き方してもいいんじゃないか」
そして今、令和「女性としてこうあるべき」と
スローガンがすり替わっただけ。
結局はそれぞれが何を最優先にして人生をデザインしているかの違いだよね。
確かに子供を持たないことに関しては高齢化が進んでいる今、年金問題とかあるのかもしれない。
でも産むわけでも育てるわけでもない高齢政治家が「産めよ育てよ」なんて笑っちゃう。
そんなことより高齢者が多い状態でどう活用するか考えて何とかすればいいと思う。
子供を育てることに不安を抱える方もいれば、欲しても授からない人もいる中、
無責任に人に産ませようとするなって思う。
「高齢者を大切に」と若い世代にしわ寄せ行かせるつもりなら、自分が若かった時よりずっと丁重に育てて「近所の皆さんに育てていただいたから今度は私が…」と成長した子供たちに自発的に言ってもらえるような背中見せてからにしろよと強く思う。
それができないなら自力で何とかするよう、シニア予備軍の私は覚悟を決めねばと思っていたりもする。
私がよく話題にする祖母は「自分の家で死にたいけど動けなくなってから戻ると同居する身内に迷惑をかけるから」と動けるうちに戻ってしっかり家事サポートした上で癌になり、年齢的にあり得ないほどの進行スピードで癌が進行して介護する間もなく他界した。
ほんと、ばーちゃんすげぇって思う。
あのばーちゃんなら自分で癌の進行コントロールしてたって言っても信じる。
【子供の多様性】
私自身育児をしてきて思ったこと。子供って柔軟性が高い。あたりまえだけど。
「使ってる言語が違う」とか「車いすに乗ってる」くらいなら「で?」で済む子も多い。
何が言いたいかって「偏見・差別」は基本的に親が作ってるんじゃないか問題。
「○○だから・・・」って良い方にも悪い方にも親がどうやって子供に教えてるかで子供の価値観って違う気がする。
実際、私自身の同級生にも吃音の子とか自閉気味の子とかいたけど当時は「個性」で済んでいた気がする。本人や家族にはもっと深い悩みもあったのかもしれないけど。何回教えても私の名の発音ができない同級生に「もう、いいよ、それあだ名ってことで」受け入れていたし、吃音の子も早口でまくし立てる私から見たら「ひとつひとつ丁寧にしゃべる子だな」くらいにしか思ってなかった。
成長過程で周りの大人とかテレビとかそういった環境で「こういうのは普通じゃない」みたいなものが育まれていってしまう気がする。
実はうち、子供が何度か入院している経緯もあり、小さい頃から車いす生活をしている子とか入退院を繰り返している子、難病を抱えた子などと出会う機会が多かった。
そんな中、うちの子たちのパパとその両親は結構差別発偏しちゃう人で。
国籍とか性別に対してもまぁ、突っ込みどころ満載なんだけど一番困ったのは入院中のお友達のこと。
その子は詳しい病名は知らないけど生まれつき体の不自由な子で車いすにも座位で座っているのが難しい子。
でも、すごく明るくてウィットに富んでいて面白い子だったし私は大好きで。
うちの子も年齢も近かったし入院中結構仲良くなってた子。
その子に対して本人のいないところで「なんか気持ち悪い」とか「うちの子じゃなくてよかった」とかうちの子の耳に入るところで言っちゃうようなパパとその両親。
…さすがにキレた。
私個人としては差別するのも偏見を持つのも正しくはないと思っているけど、そういう価値観も頭から否定しちゃいけないと穏便に過ごそうとしていた。子供達には自分たちで感じて選んでほしかったから「私はああいうこと言うのは好きじゃないし、配慮が足りないと思う」とは言っていたけどパパたちを責める言い方はしてなかった…が限度はあるよね。
以降、差別的なものに関しては「それは違うと思う」と言うようにした。
そんな私も意図しなくても差別的な言動をしてしまうこともある。
ガイジンを略語と勘違いしていて外国人の方に「外人証明書」の提示を求めてしまったことがあるし、多言語操る最近の子供だなぁとアジア系の早口で話していた子に「外国語得意だからね」とか言い放ってしまったこともある。
だから自分が育児する時には「そんな間違いをしたこともある」ってちゃんと話して「私が正しいわけではない」って自分の頭で考えるようにしてもらっている。
そういうところ、親の責任重大だなって思う。
マイノリティの壁
「繊細さん」と言われるHSPや発達障害(グレーゾーン含む)について20年ほど学んできた。
本人が周りに違和感を感じているだけでなく、まわりが違和感を感じたり、直接的に攻めることも多い気がする。
<生きづらさ?個性?>
発達障害という言葉を知った頃「空気読めない人」というネガティブな表現が続いた後「発達障害は才能です」みたいな流れになった手のひら返しがちょっと気持ち悪かった。
言いたいことはどっちも理解できるけど。
そもそも「障害」という表記に問題提起する方もいて「障碍」という表記にこだわる方もいる。
でも私個人は「みんなと同じように反応する」という行為に対しての「障害」であって、別に本人にとっては害のないものだと思っているのでどっちでもいいと思ってる。
例えば私は裸眼視力が両目とも0.1以下なので眼鏡かコンタクトがないと自分の足に指がついているかどうかの確認もできないレベルだけど「視力障害」といわれても「見える基準からすればそうですよね」って思うからそういうことかなと。
もしもっと根深かったら配慮不足で申し訳ないけど。
まぁ、表記問題はさておき、当事者が「まわりに馴染まなきゃいけない」環境にいるなら障害だけど日常生活するうえで障害かというとそうでもないと思っている。
でも軽く見ているわけじゃない。致死性の病気のように命に直結することじゃないかもしれないけど尊厳とか生き方とかにはすごく関わってくる。うまく活かして生活しないと諸刃の剣として二次障害に繋がって命の危機にもつながってくるものだと思う。
もしお子さんや周りの方にHSPや発達障害に「該当するかも」って思う方がいるのなら。腫れ物に触れるような配慮は不要だと思うけど、あなたの価値観を押し付けるのはやめた方がいいと思う。
気質や特性の話ともリンクするけど。
いじめとか不登校の問題も私が子供のころ以前からずっと解決しなくて居座っているなと思う。まぁ、いじめは大人になっても存在するしね。
内容は変化しているけど根本は同じだと思う。結局人間の問題だから。
ここで最近気になるのが「どこからがいじめ/不登校でどこからが違うか」問題。
「いじめと感じている」のは被害者側の主観で加害者側は全くそんなこと思ってないケースもある。
「そう思ってなかった」って言っているだけの場合もあるけど。
実際、私が子育てしてきた中で「それって一歩間違ったらいじめじゃない?」と思うことがまかり通ることもあれば案の定いじめとして問題化したりもする。
結局セクハラや虐待と同じなんだろうなぁ…。
「いじめられた側が不快・傷つくと感じたらいじめ」みたいな。
ある程度の「ここからはアウトでしょ」な部分ももちろんあるけど、グレー部分も多いなと感じている。だから教師も親もうまく間には入れていない気もするけど…
同じように「不登校」も「行きたいけどいけない」子が一定数いて、フォロー案は必要だと思うけどその中に「いや、コロナで学校行かなくても何とかなるってわかっちゃったし」とか「最近フリースクールとか選択肢増えたじゃん?」とか「そもそも学歴なくてもよくない?」みたいな子も増えている気がする。
その意見、すべて一部当たりで一部外れだと思う。
「学校に行く」がすごく高い壁に感じている子がいるのは知ってる。
実際、私も学校行ってない時期もあったし、周りにもそんな子はいたし。
でもね、「行くという選択肢を放棄する」のとは違うと思う。
リスクを知っている上で「行けない代替案」だからこそ別の道は輝くのであって
「行こうと思えば行けるけど学校行かない選択肢もあるから別の道に行く」のは絶対人生無駄にする。親もそのあたり理解したほうがいいと思う。
私の知り合いには中卒で幸せに生きている人もいれば大卒でも「不幸だ」と嘆いている人もいる。
結局「本人が納得してその道を進んでいるか」だと思うので、安易に「学校行かなくていい」とは言えないし「無理して行け」とも思わない。
最近はいろんなケースに腫れ物に触る感じの人が増えて本当に気持ち悪いな…と思う。
生きづらさとの付き合い方
私自身、20年ほど前にHSPという気質について知った時「これじゃん」ってすごく腑に落ちた。以降、ずっと学び続けて自分の中で「諸刃の剣」に傷つかないよううまく立ち回れるようになってきたと自負している。
同じ頃、結婚相手が発達障害グレーと判明し、「空気を読めない(と当時は表現されていた)発達障害×空気を深読みしすぎるHSP」という組み合わせは正直メンタルをぼろぼろにした。
その間、カサンドラ症候群についても学び、そこまで泥沼に陥らずに今に至るし、うまく課題の分離をして離婚という選択を選んだことでパートナーとも子供たちともお互いにとてもベストな関係を築けている。
親子の多様性
私自身、子供の立場の時に母に土下座して「父と別れてください」と頼んだ経験がある。
それほど「カタチ」にこだわるのが苦しいと感じている子供だった。
結果、高校在学中に学校巻き込んで公式に一人暮らしするという行動に出たのだけれども。
当時から「形より本質」にはこだわっていた気がする。
大人になって子供が産めない身体認定されて荒れた後、人として尊敬できる人と結婚して運よく年子出産できた。けど先に書いたように「私の産んだ子供の父親」としてどうしても許せない部分があり、結局離婚している。
今は父子関係も母子関係も元夫婦関係もいい感じなので多分うちのメンバーにはこれが最適解だと思うけど傍から見たらおかしな家庭なんだろうな。
まぁ、うちの話はさておき、ニュースやネットを見ていると私自身も苦しくなるし、同世代でもあるうちの子たちも「なんで」というような事件がたくさん転がってる。
子供の同級生にも夜の世界に羽ばたいていった子やちょっとした地下アイドル、プチYouTuberなど「イマドキ」な子もたくさんいる。ただ、いわゆるトー横・グリ下(地元名古屋ではドン横という何とも間抜けなネーミング)的なところで「生活」している子はいなさそうだけど。
いわゆるティーンエイジャー版赤ちゃんポストのような気もするので見ていてとても苦しい。
私自身は先に書いたように「高校生だけどバイト掛け持ちして自活する」という「正統派家出」をしたから彼らの気持ちがわからなくもないし、なんとか他の道もあるんじゃないかとおせっかいながら思ってしまっていたりする。
ここで思う。「子供が欲しいのに親になりたくてもなれない人」(LGBTQ含む)が山ほどいるのに「親になったのに子育てからドロップアウトしてしまう人」がいるから居場所のない子供たちが生まれてしまうのではないかと…。
別にドロップアウトした親を責めているわけではない。実際、私のクライアント様には一方的に離婚されて子供に会えなくなった母親とか、「もともと病気があるから育児に自信がない」と言っているのにまわりの「みんなで育てよう」という言葉を信じて出産したら夫婦そろってメンタル壊して子供を乳児院に預けることになった夫婦もいる。
望まない妊娠で子供を抱えてしまう親だっているし(自業自得と言われればそれまでだけど、できてしまった後に言われても…という部分もあると思う)。
「育てられないからネグレクト」とかなってしまうよりキャパオーバーを感じた親が「誰か助けて」って助けを求められて、本当に愛に溢れた養親とともに実親×養親コラボ育児的なものがあったっていいと思う。
法律的なところは置いといて。
正直、大人たちもまだまだ発展途上な生き物なんだろうな。
子供たちよ、「親ガチャ外れた」「うちは毒親」と諦めるくらいなら「じゃ、自分の人生どうデザインしよう」に切り替えた方がずっとあなたが生まれてきた意味があると思うぞ。
「大人」「親」も結局は同じ人間。幻想を抱きすぎれば自分を傷つけると思う。
少なくとも、私はそうやって生きてきて、今、生きていることに後悔はない。
とりとめもなく書いてきたけれど、実は私は自身の育児卒業に向けて今後の人生をどう楽しもうか整理している時期だったりする。
自分の不器用さを知っているので育児最優先でやってきたけれど、このままでは子供の重荷になると思ったので自分への比重を増やしてバランス調整するために仕事を絞って、自分の棚卸をして、今に至る。
現状、ライスワークも結構楽しんでいるし、まだ子供を放り出す勇気もないので副業という形でライフワークを始めることにした。
自分のスキル・経験を最大限に生かして自分の人生を自分でデザインして楽しむ人を増やしたい。
自己肯定感アカデミーで認定教室講師になりつつも、資格に興味がない方にも対応したいと自分の一番やりたい方向をじわじわ模索している。
最終ゴールは「お互いを生かしあえるコミュニティ」なので「自分軸で生きたい人ウェルカム」すぎて何屋さんかわからなくなってる。
自己肯定感が高いということは自分を大切にできる人
自分を大切にできる人は相手も尊重できる互慈愛できる人
多少ぶつかることがあってもお互いのプラスになるような関係
お互いの得意を生かし、苦手を助けてもらえる関係
そんな共生できる場を作りたいと様々なコミュニティーを作って動かし始めている
最終形態は見えていないけど、たぶんこれからずっとやっていく活動。
自分がよければそれでいい⇒自我肯定感を満たそうとしている人がたくさんいる。
同調圧力で個性をつぶそうとする場所がある。
そんな息苦しいコミュニティに風穴開けて、上下なく横並びでそれぞれが主役の人生をデザインしつつ、都度誰かを輝かせる即興劇の中で生きていきたいと思う。
私にとって子育ては己育て。
得たものをさらに展開して他の親子にもその他の面でも活かすサステナブル育児。
育児が終わっても自分の人生をデザインするヒントがたくさん得られた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
