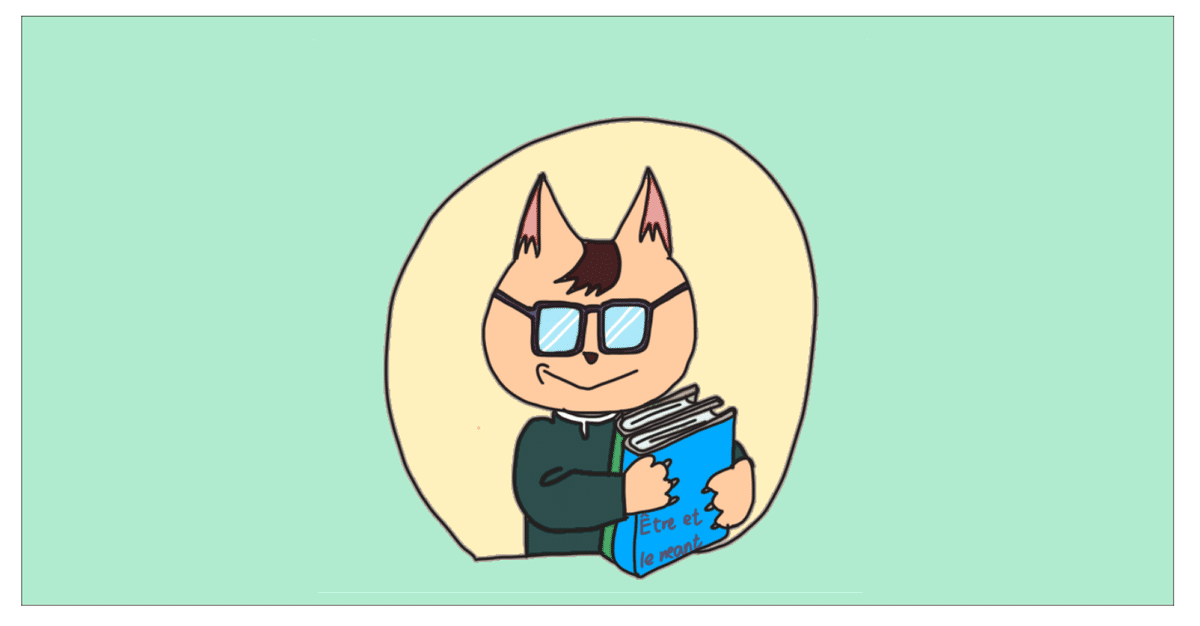
「芸術神学」批判序説 ~ 新しい公共劇場の在り方を模索するための省察 ~(10)
〈アート〉について歴史学的アプローチをしようとすると、たいてい西洋ローカルな芸術史になってしまう。まるで〈アート〉は西洋にしかないとでも言っているような感じだが、実際のところ、半分は正しいと思う。
〈アート〉について狭義の意味で語る場合、ぼくは「芸術」と表記するが、この「芸術」は一神教的土壌においてこそ育ってきたものだ。この「芸術」にまつわる価値観を(西洋ローカルを超えて)世界的に普遍化することはできない。
一方で、「想像界のアート」「象徴界のアート」「現実界のアート」の3区分について見てきたように、社会の中で暮らしている人間は、いわば「象徴界」という檻の中に囚われているとも言え、息苦しさから、違和感から、出口を、〈他でもあり得る可能性〉を求めることを止めることができない。社会的なものを成立させる(補強する)「象徴界のアート」も、アンチとしての「現実界のアート」も、人間が生きている以上、必然的に生み出してしまうものである。また、人間が想像力を失わない限り、「想像界のアート」もまた消滅することはない。そのような意味において、〈アート〉は人類史において普遍的なものである。
そこで、〈アート〉について歴史学的アプローチを試みるとするなら、あえて西洋を離れて、べつの地域における〈アート〉を取り上げていくのがベターな選択だと思われる。西洋的なものにとり憑かれてしまうと、「芸術」の中で〈アート〉を見失う。
ぼくらは日本人であるから、せっかくなので、日本史における〈アート〉について語ることにしよう。
ただしその前に、一神教的「芸術」史について、最低限の整理はしておこう。
西洋ローカルな「芸術」について、まずはキリスト教の普及前と後に分けて考えてみる。
前について、冗長になるのを避け、一冊だけ、プラトン(紀元前427-347)『国家』の中でふれられた「芸術」観についてふれたい。
古代ギリシア、プラトンの時代においても、世界とは「神」が創造したものであることに違いはない。「神」が創造したのであるから、世界はカオスではなく秩序があり、ぼくら人間のあるべき〈正しい生き方〉とは、その秩序に沿って生きることである。
具体的に言うと、植物が太陽の光のほうへ花を向けていくように、人間もまた〈善〉という光に向けて生きていかねばならない。それが〈善く生きる〉ということである。
とはいえ、太陽光が眩しすぎて直視できないように、人間もまた〈善〉を知ることができない。いや、知ることができる人間がいないわけではない。哲学者が、それだ。唯一哲学者だけが〈善〉がどちらの方角にあるのか知ることができる。ゆえに、哲学者が国家を統治し、人々を導く、というのがプラトンの論法だった。まぁ、そんなことはよい。
プラトンはここで、音楽と詩について言及している。音楽や詩は、人々を〈善〉の方へ誘う初歩的なツールとして活用可能だ、と考えたからだ。たとえば音楽の音階は一つの秩序であり、世界秩序の模造とも言える。また、音楽のうち優雅な調べは、調和に満ちた世界像を彷彿とさせるものだ。ゆえにプラトンは、いきなり哲学を学ぶにはハードルが高いわけであるから(そもそも哲学をマスターできるのは少数の選ばれた人間だけだ)、いわば〈善〉にふれる入門編として、〈魂〉の訓育(調教)に音楽はツールとして使える、と主張した。
ここでプラトン哲学の解説をするつもりはない。肝心なところは、
① 人間はその人生において、より〈善く〉生きねばならない。
② なぜなら、それが人間を造った「神」の意志に沿うものだからだ。
③ 〈善く〉生きるためには、この世界の秩序に学べばよい。
④ なぜなら、この世界を造ったのもまた「神」であり、この世界は譬えるなら〈善〉へと流れていくベルトコンベヤーに乗っているようなものであり、世界の秩序を知ることはすなわち、〈善〉へと向かう方角を知ることであるからだ。
⑤ 唯一哲学だけが、〈善〉の方角を知ることができる。
⑥ ただし、哲学には劣るが、秩序と調和に満ちた音楽もまた世界の秩序を学ぶツールとして使えるだろう。哲学を学ぶ前に、音楽を学ぶのがよい。
⑦ すなわち音楽(芸術)とは、初心者向けの訓育(教育)ツールである。
といった論法のうち、(1)「神」の意に沿い〈善く〉生きることが人間の定めであり、(2)哲学することこそ一番の方法ではあるが、(3)ツールとしてなら(哲学には劣るものの)芸術も使えなくはない、という部分だ。
この点を踏まえた上で、キリスト教普及以後、へ目を向けよう。
キリスト教普及以後、近代へ至るまで、人生の目標とは、まずは「神」の意に沿い〈善く〉生きることであり、最高の学問(方法)とは、当たり前だが「神学」となった。
「神学」すなわち「神の〈ことば〉」にふれることで、人間はどちらを向けば〈善く〉生きられるのかを知る。
この「神学」の相棒に「哲学」が浮上した。プラトンの場合、「神学」を飛ばして一足飛びに「哲学」が〈善〉にふれたが、そのポジションは「神学」に奪われて、「哲学」はむしろ「神学」的世界を論理的に言語化していくツールと化した。簡単に言うと、「神の〈ことば〉」にふれる「神学」は「哲学の〈ことば〉」を通じて論理的に言語化し、人々を教育する、というわけだ。
しかしながら、「哲学の〈ことば〉」を理解できる人というのはごく少数の限られたエリートでしかない。一般の民衆に伝わるわけがない。そこで、ここでも「模造」としての「芸術」がツールとして活用されていく。たとえば宗教画が、それだ。見ることで、「神の〈ことば〉」を、神的世界を、体感的に感じよう、といった教育方法。もちろん、それは知的ではない人たちのための一段劣った教化ツールでしかないが。
上述した価値観(世界観)は、プラトン時代とさほど違ってはいない。
まずは序列がある。
1位 神学
2位 哲学
3位 芸術
それぞれがそれぞれの仕方で「神の〈ことば〉」にふれようとするが、下へ行くほど濁ってくる、というわけだ。
ちなみに、そもそもなぜ「神の〈ことば〉」にふれないといけないのかというと、それが人間の定めであるからだ。
さて、ここで、トンデモないものが誕生してしまう。
「科学」である。
もともと「神学」と「科学」は相性の悪いものではない。というのも、「神」が造った世界の秩序を探求するのが「科学」なのであるから。現代の科学者でも「神」の存在を信じている人はたくさんいるし、古い時代になればなるほどその割合は増える。
「科学」は「神」が世界創造した、ということを前提している。なぜなら、「神」が世界創造したからこそ、世界はカオスではなく「科学」的に解明可能な秩序が生まれたのであるから。
科学者にとって、「神の〈ことば〉」とは「数(神の数式)」である。「神」への信頼なくして「科学」は誕生しない。
ところが・・・・・・である。「科学」と「神の〈ことば〉」が具体化したものである「聖書」の内容が対立してしまう。ガリレオ裁判が典型的な事例だ。
1位 神学 VS 科学
2位 哲学
3位 芸術
そして、宗教戦争を経て、世俗権力が増大し、政教分離となり、また、産業革命を経て、科学と資本主義がセットとなり、世の中を席巻するようになると、「神学」の権威が失墜していく。
前近代において、「神の〈ことば〉」あるいは「真理」を一手に握るものは「神学」であったが、近代が成熟していく過程において、「科学」「哲学」「芸術」がそれぞれ自律し、それぞれが「真理」の担い手となっていく。
ここから、現代社会まではほんの一歩だ。
人はより〈善く〉生きるために、「科学」「哲学」「芸術」を求める。
たとえば浦沢直樹の漫画『20世紀少年』を一読すれば、かつては半ば狂信的なまでに「科学」が〈善き生〉をもたらしてくれる、という信仰があったことが理解できよう。その象徴の一つが、「大阪万博」だったろう。
あるいは大陸系の西洋社会では、人文的教養として「哲学」が重んじられてきた。学校教育に「哲学」が科目として入っている。
「科学」は「真理」をもたらす。
「哲学」もまた「真理」をもたらす。
「真理」にふれることが、〈善き生〉をもたらしてくれる。
そしてここに、「芸術」を加えねばならない。
国家の目標(存在意義)が、国民に〈善き生〉をもたらすことであるとするなら、公金(税金)により、「科学」「哲学」「芸術」を支えることは、当然の責務となる。
それが、西洋社会のロジックだ。
ちなみに、芸術関係者はしばしば「日本人は芸術に理解がない」と愚痴るが、なぜ「日本人は哲学教育に理解がない」と併せて言わないのだろう。西洋社会のロジックからすると、義務教育に「哲学」が入っていなのは、そもそもダメである。
芸術関係者はぜひ、「義務教育に哲学を入れるべきだ」と主張してほしい。そしてそれはもちろん、暴論である。
今日、人々は人生に疲れて悩んだとき、「哲学」に救いを求めたり、「芸術」に救いを求めたり、あるいは「宗教」に救いを求めたりする。
哲学書のベストセラーは定期的に生まれる。芸術を観て癒される。信じる者は救われる。あるいは救いを科学に求めることもできる。私とは何か?という根本的問いから、脳科学へ進んだ人もいれば、世界とは何か?という根本的問いから、宇宙物理学へ進む人もいる。
生きていれば悩みは尽きない。その悩みの一元的な聞き手であった「教会」(宗教)は今や独占企業ではなくなり、「哲学」「芸術」「宗教」「科学」と、役割分担されるようになってきた。
それが、多元化していく近代ないし現代社会の流れである。
悩みが尽きない人生において、「哲学」「芸術」「宗教」「科学」は機能的等価物である。
さて、政教分離を前提としている近現代国家としては、人々に〈善き生〉をもたらすため、「宗教」は除外し、「哲学」を広く「学問」と解し、「学問と芸術」そして「科学」を公的に支援していくことになるのだった。
ちなみに、文化経済学界隈では、「芸術」は採算性が悪く、公的支援がないと持続不可能なので支援されてしかるべきだ、とする、ボウモル=ボウエン以来のボウロンがあるが、採算性は公的支援のロジックにはならない。
肝心なことは、「芸術」が〈善き生〉をもたらす、と、みなさんが信じているか否か、言ってしまえば〈共同幻想〉が社会的に成立しているか否か、にある。
日本と西洋が異なるのは、そのような〈共同幻想〉が希薄だ、という点においてであるが、希薄だからといって無いわけではない。実際、大なり小なり「芸術」が〈善き生〉をもたらす、ということについては誰もが否定しないだろう。だから「芸術にふれると〈心〉が豊かになる」「芸術は〈魂〉によい」と、みなさん異口同音に言いなさる。
ただ、注意が必要なのは、西洋の〈共同幻想〉は数千年に及ぶ歴史の中で生成していったものであり、それを「日本人は芸術に理解がない」からといって、日本へコピペ、移植せんとするのは土台ムリな話、という点である。もっと言うと、今さらそのような〈共同幻想〉に浸ることは、端的に言って退行であり、好ましいものではない。芸術関係者(の一部)が既得権益を高めたいと思っている、個人的欲望に根ざした妄言としか思えない。
さて、ここでようやく日本を土壌とする歴史学的アプローチへ切り替えたい。
〈善き生〉と「芸術」の話は、日本だとどうなってしまうのでしょう?
ここを理解せずして、経由せずして、一神教的「芸術」ではない〈アート〉も、世俗化した「教会」とは異なる公共劇場2.0についても、語れはしない。
公共劇場1.0は世俗化した「教会」であり、〈善き生〉の伝道師であった。
公共劇場2.0は「門」である、とぼくは譬えた。
日本〈アート〉史を探索することで、その意味が開けてくるだろう。
なぜならぼくら日本人は最初から一神教的〈善き生〉とは無縁の〈生〉を生きてきたから、である。
《つづく》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
