
「赤入れ」にへこたれるなライター!
まったくもって、一生懸命に書いたテキストを入稿し、バカスカといわゆる「赤(修正指示)」をいれられることほどガックリくるものはない。最近はかっこよくフィードバックなんぞと言う。
しかし、ひっくるめて直訳すると「ここダメだから直せよ!」である。
というわけで今回は「赤入れにへこたれるな!」がテーマで書いていこう。
■赤入れの種類とは
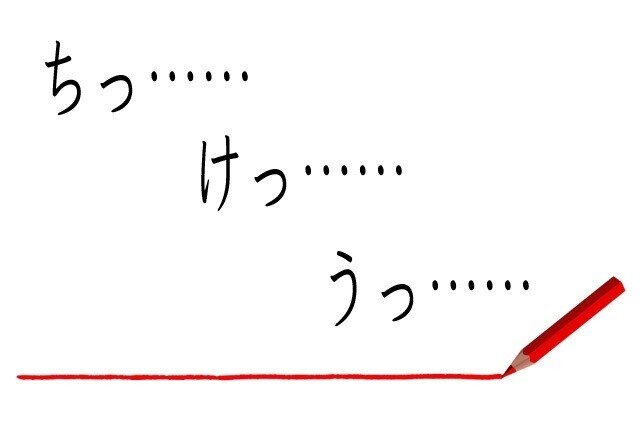
お戻し原稿をざっくり見て、わたしが最初につく「舌打ち」が、赤入れの種類を物語っている。
参考までに、赤を入れられた状況別の舌打ちと、その後の自分の心のケアについて解説しようと思う(いや、参考にならんか)。
「ちっ」
これは、おおむね指示は理解できるし、実際に直したほうがよいと納得はするが、そもそも、こちらが勘違いしてしまうような最初の指示があるから、そのような文章を書いたという状況のときに思わず出る言葉である。ちっ、だったら最初からもっとわかりやすく、そー言ってよね!あーハイハイわかりました、今度はわかりましたから直しますよって時だ。
「けっ」
これは、最初の指示や構成案から思いっきりかけ離れて「ここはこうして」と直しが入った時に多い、けっ、あーそうかい、そうきましたか、じゃ、最初の指示はなんだったんだよ、けっ、である。だったら直せばいいんでしょ、直すさ、直しますとも!けっ!と舌打ちのループになる。
「くっ」
ぐうの音がでない指摘があると、こうなる。「くっ」と漏れ出るときはその編集者さんなりクライアントさんなりが、大変に優秀で正しいときだから、うううう、と頭をたれて拝聴(拝見か)し、ただちに直しにかかるのである。こういう赤入れは、自分自身でも「学んだなぁ」と実感するので、直し自体に時間がかかってもあまりイライラはしない。
「げっ」
けっ、に似て異なるのが、げっ、である。げっ、は、明らかにこちらに非がある場合だ。最初から指示が出ていたのにやらなかったとか、失念したとか、どうしようもない誤字脱字とか、てにをはのまちがいで多い。げっ、なら、まだしも「げげげげげっ」となって仕事をなくしたことが暗い過去の思い出としてある(涙)
■編集者次第!?で変わる「赤入れ」にてんてこ舞い
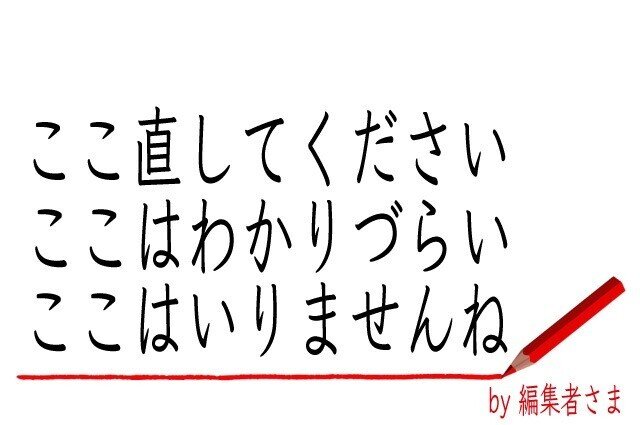
ところで難しい問題として、赤をいれる人の「好み」というのがある。赤、つまりは修正指示をいれる立場、大抵は編集者だろうが、相手は人間である。
わたしはよくフィギュアスケートの採点を考える。
ジャンプとかスピンとか、テクニックに関しては点数をつけやすい。失敗したら0点だろうし、着地でぶれたり、こけそうになればマイナスだ。
でも芸術点とかインプレッションとか、どうなんだろう。
それを見て美しいと思うか、感動したと思うか、この辺はたぶんに個人の感性が入ってくる。
もちろん、完璧なこともある。誰がどうみても「ああ、素晴らしい」というのならいいのだが、微妙なところがあって、見ていて「ええええ、今のよかったのに!」というのがある。が、隣の夫は「なにこれ、ダメじゃん」とか言う。まったく評価が違うことがある。
文章にもそういう「感性が合う」ものと、そうでないものがあるように思う。ある編集者が見れば良い文章であっても、違う人が見たら直しをいれてくるなんてことはざらにある。
編集者の好みがある程度わかってくると、意識して合わせることはできるが非常に疲れる。しかも書いた文章に満足感はない。
でも、わたしが満足するかどうかは問題ではない。それが仕事なのだ。
・ひとりひとりの編集者の好みが透けて見える「赤入れ」
たとえば、Aさんは「冒頭に結論、文字数重視、KW重要視」であるが、Bさんは「Webライティングだからと考えすぎずに、起承転結の文章のほうが印象が良い」、そしてCさんは「納期重視、エビデンスが重要、データしっかり入れた」そういう文章に対しては評価が高く、読み物的な部分を良しとはしない。
このように、それぞれの編集者さんに「ココが気になるところ」があるし「直し方」がある。それは媒体のカラーや方向性によることもあるが、編集者さん個人が持つ「好み」であることも多い。
その好みがわたしには理解できなかったり、合わなかったりすると、やりづらいし赤入れも多くなる傾向がある。これはもう仕方がないんだ。
どんな職業についても、気に食わない上司はいるものだし、悪い人ではないとわかっていてもやりにくい相手はいるものだ。
私は唱える。
「私が悪いんじゃない、誰かが悪いのでもない、そういうことなのだ、受け入れろ自分!」
・編集者だけじゃない!?赤入れで凹みまくるシーン!①
赤が入ることによって困ったな、ということも時々ある。特にエンドユーザーがいる場合だ。
最終的なクライアントとしてA社という大手不動産会社があるとする。その間にサイト制作なんかを請け負う会社が入り、そこから「会社の社長さんや社員さんを取材して、会社案内のところを書いてほしい」という依頼があったとする。
実際に取材に行き、現場の声を聞く。会社の雰囲気も見るし感じる。直接、会社の広報さんとも話すし、トップともお話をさせていただく。そうこうしているうちに、なかなか言語化しづらいニュアンスが伝わってくる。よく言われることだが「会社の風土」とか「カルチャー」である。
そこでライティングでは、会社の風土を活かして書く。
ここでたまに問題が発生する。
間に入っている会社の担当者は、自分が接している広報担当者や企画戦略部なんたら、とかいう人としか主に話をしていない。
だから、その人達が求めるものをライターに求める。当然ではある。が、わたしは知っているのである。会社が持っている、もっと素晴らしい雰囲気を言葉にしたいと考える。
さらにトップや活躍している人たちの言葉から想像するに(えーと、違うんじゃないかな〜、こういうことを書いてほしいはずなんだなぁ)と思うわけだ。
仕事なので、意見としては伝えるが、わたしの経験上ではこちらの意見が通るのは半々程度の割合である。半分の割合で、わたしの原稿はまっかっかになって戻ってくる。
時には原型を留めずに、めちゃくちゃになっているときもある。これは複数の人が(しかも編集のプロではない)テキストを見て、コメントと赤入れをしてくるからだ。冒頭にある「舌打ち4連発」には入れなかったが、この場合には「うっ」となる。
うっ、うっ。
打つ手なし。
その指示どおりに直した原稿が最終チェックでたとえば社長さんのところへ行く。すると社長さんの秘書さんあたりから、再び、赤が入ってくると、をいをい、だからさ〜、最初に書いた原稿のほうがよかったんじゃない?ってことになる。
しかも、だ。
その「たぶん、気に入ってもらえたであろう」最初の原稿はうずもれたままである。
何がツラいって、トップにいる人たちには「プロのライターに頼んで、あれほどわかってもらっていた感じだったのに、この程度なのか」と思われてしまうことだ。
わたしは叫びだしたくなる。
「違うんです!最初に出した原稿みてくださいってば!」
・・・でもそれは叶わない。
エンドユーザーがいる、間にもう1社(あるいは2社入ることだってある)入る場合には、こうしたことも受け止めなくてはならない。なぜなら、間に入った人には悪意がなく、彼らの立場で良かれと思ってやっていることだからだ。それだけにライターとしては逃げ場がない。だから、わたしは唱えるのだ。
「私が悪いんじゃない、誰かが悪いのでもない、そういうことなのだ、受け入れろ自分!」
・みんな言うこと違うのね!な赤入れで凹むシーンその②
わたしは、2社同時にほぼ同じテーマの文章を書いていて、ところがまったく正反対の指摘をそれぞれに受けたことがある。
A社「○○であるそう。期待できますね!」
B社「〇〇であるとのことでした。期待できますね」
といったような文章がどちらにもまじっていた。
するとA社の担当者から
「なになにであるそう、で文章を区切らないで下さい」
と言われて直した。あるそう、で止める文章はよくないというご指摘であった。A社はどちらかといえば編集でもSEO的な考えが強いところだったからかもしれないが、体言止めそのものも、なるべく避けてくださいと言われた。
ところが、B社の赤をみると、「あるとのことでした」が「○○であるそう」に直されているではないか。B社の編集者さんいわく「文章のリズム感を大事に」ということらしい。
これは、どちらが正しいとかではないのである。
こういう時はさっぱりと切り替えることだ。
それが、それぞれのライティングルールであるのか、編集者の好みであるのかはわからない。しかし、そこに理由なんぞ求めてもしょうがないのである。「私が悪いんじゃない、誰かが悪いのでもない、そういうことなのだ、受け入れろ自分!」である。
ちなみに、こうした違いはよくある。
何社か並行して書く場合には、明文化はされていないが結果としてよく直されるところを、それぞれのルールとしてメモにしておくとよい。つまらんことで直しが多くなって、嫌な気分にならないのが大事である。
■ウチの子に限って!ライターが親ばかになってはいけない理由
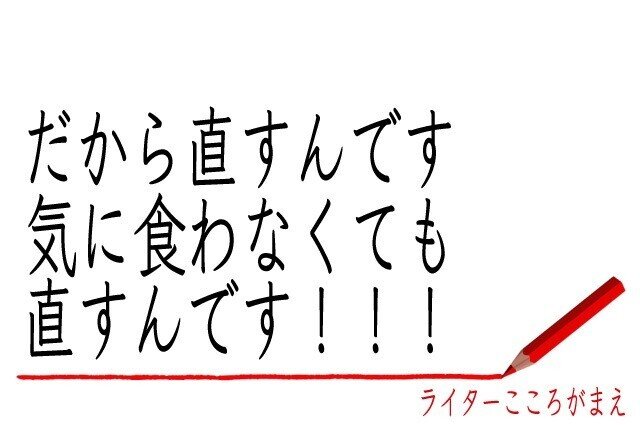
よくわが子自慢をする親がいて、聞いている方としては(はあ?)と思うことがある。
そして、ライターはときとして無意識に自分が書いた文章をまるでわが子のように思っていることがある。だから、少々デキが悪くても「うふふ、いい子なのよね」と思うところに、誰かから「ここダメだから直してよ」と言われうと、カチンとくるのである。
親バカというのは、悪いことではないのだ。親バカというのはなぜなら愛情だからである。自分が書いた文章に愛情を持つのはとても素敵なことだ。
が。
が、である。
だからといって、「しかし、ここはどうでしょう」と言われたら、そこは率直に受け止めるべきである。
子育てを御覧なさい。わが子は可愛いよ、可愛いが、えてして「うちの子に限って」ということがある。「そんなはずはない、こんなにデキのいいウチの子に限って」やらかすことはよくある。
つまり、その文章は一見とてもよくできていたとしても、だ。ダメなんである。自己満足では、ダメなんである。だから直すんです。気に食わなくても、直すんです。
あなたが悪いのではないが、あなたの書いた文章は多くの読者にとっては、どこかがひっかかり、何かがわかりづらく、どうしてかテンポが悪くて、読みづらい可能性は常にある。
第三者である編集者さんはそこを見ている。
うちの子に限って。
ライターは自戒せねばならない。わたしの文章に限って、こんなに赤が入るわけがない!などと思わないことである。
■その文章を読むのは「わたし」ではなく「不特定多数の誰か」なのだ

だいたいにおいて、ライターなら書いた文章を読み直し、校正し、よしよしできたぞと入稿するだろう。しかし推敲を重ねて、よくできた、うんがんばった、というテキストが、思いもがけぬほど「赤」が入ってくることがある。
これは凹む。
ICTマガジンでも異口同音に言われていることに「ライターの文章はブログではない」とか「小説家ではなくてクライアントが求めるものを言語化するのが仕事である」といった話がある。
まとめると、答えはひとつしかない。読む人は、ライターが何を思っているかなんて、基本的にはどうでもいいのだ。
読者なら、読みたいのが「読みたいもの」なのだ。書いている本人であるわたしが読んで満足しても意味がない。
読む人が「わたしが知りたかったのはこのことだ!」「ああ、これがまさにわたしがいま読みたかったものだ」というものを書くのがプロのライターの仕事なのである。
あるいはクライアントがターゲットに向けて伝えたかったことをきちんと伝えること、記事やコラムになんらかの目標や目的があるのなら、そのゴールに導くように書くこと、それがお仕事なのである。
■直しを入れられたのは文章であって「あなた自身を直せ」と言われているのではない!

さて、つまり、そうすると、文章をチェックする立場の人は、第三者であるからして、アレコレと直しをいれるのも当然である。
でも、ひとつだけ忘れないでほしい。
確かに書いた文章はまるで分身だ。しかし、たとえ、それがどれほど直されたとしても、「あなた自身を否定しているわけではない」ということだ。
なぜなら文章は成果物である。実はそれは、あなたが書いたものであっても「あなた」ではない。
ここを絶対に勘違いしてはいけない。
どんだけ赤をいれられても、時に「この場合には掲載はできません」的な、地獄に突き落とされるようなことがあったとしても、だ。地獄に落とされたのはテキストである。あなたが落とされたわけではない。
むろん、ひらりひらりと舞い落ちていく、自分の文章を見るのはツラい。
が、あなたは落ちていない。落とされたのは、廃棄されたのは、わたしやあなたが書いた文章であって、わたしもあなたもどこにも落ちていないということを、いつでも、何度でも思い出すべきである。
■素晴らしい編集者との出会いを逃すな!

なんだか編集者に対する愚痴ばかりのようだが、世の中捨てたものではない。わたしには信頼できる編集者が複数いる。
ひとりは広告関係からwebメディアの編集をし、独立して会社を作った。たいへん理知的で端正な文章をご自分でも書く。そして彼女は、私が知る限りではもっとも「赤入れの少ない編集者」のひとりである。
盆栽だと思っている。
彼女は本当に最低限しか剪定しない。ほんの少しいじるだけなのだが、それだけでうそのようにすっきりと読みやすくなる。
数文字を削るか、別の言葉に置き換えるだけで、洗練されたテキストに変身させてしまう。直された文章を見て、わたしはどれだけ学んだかわからない。
もうひとりは、ある意味真逆である。紙媒体の雑誌で編集者をしていたから、「PV?なにそれ?」である。必要なら赤入れもガンガン平気で入れてくる。
だが、ものすごく的確な指示を出す。最初の指示がとてもわかりやすく構成案もざっくりなのに、無駄がなく足りないものはない。だからそもそも書きやすい。書きやすいから、赤が入る余地が少なくなる。
時々は不思議に思う。これほどSEOを知らず、こだわらずに編集しているのに、なぜか彼女が担当した記事は「読まれる」のである。
もうひとりはこのICTマガジンを仕切っている夏野さんだが、内輪状態で絶賛するのもどうかと思うので今回はやめておく。
でも、どうしても伝えたいことはひとつ。
必ず素敵な編集者と出会う機会はあるはず。編集者はライターを育ててくれる。親のような愛情で見守り、もっといい文章を書いてほしい、なぜなら良い記事ができたら、なによりライターにとって大きなメリットがあるから、と考えてくれる、そんな編集者さんもいっぱいいる。
時に、ライターがそれに気づかないこともある。それはいけない。同じように赤をいれていても愛情あふれる人もいる、仕事として「ライターがもっと良い文章を書けばウチも助かる」ということであっても、きちんと指摘してくれる人がいることは、本当はライターにとってラッキーなのだ。
良い文章を書いてこそ自分の価値があがる仕事であり、親身になり真剣になり(時に辛辣であったとしてもだ)書いた文章を直してくれることは、本当に本当にありがたいことである。
そこに愛はあるんか?
とどこかのCMで言っていたが、どこかに、根底に、愛がある編集者さんがいたら、決してその人を逃してはいけない。言葉は悪いが、逃してはいけない。
その人はあなたを大きくしてくれるからだ。
でもって、どうしようもなく、どうしてもやっていけないような編集者さんがいたら、あっさり切り捨ててもよい。
同時に「どうしてもやっていけないライターだな」と思われたら、自分があっさり切り捨てられるということも認識しておかなくてはならないのである。
■赤入れと墓の話でしめてみる

わりと最近のことだが、子どもが帰宅して、カバンから、ほぼ蛇腹折りになったレポート用紙数枚を乱暴に取り出して、こう言った。
「オレさ〜、マジでやったわけなのに、なんなん?直しとかワケわかんないんですけど」
「なにこれ、オレのことが嫌いなんじゃね?」
ぎゅーっとカバンの底に押し込まれた、蛇腹になった紙を私は両手で伸ばしながら読み、そして、こう言った。
「あのねぇ、見てごらん?先生の直したところは正しいよね。この通り書き直したら、とてもわかりやすいでしょ」
「そして、ここね、どうしてこう思ったか、データはどこにありますか、ってとこ。それがあれば、読む人はなるほどと納得するし、この文章は信頼できるなって思うわけじゃん」
「別にあんたのことを悪く言っているわけじゃなくて、文章にしたとき、文字がどれだけあんたの言いたいことをちゃんと伝えられるか、その方法を教えてくれてるわけじゃん。怒るとこじゃないんだよ」
実を言えば、きっぱり割り切るとか言いながら、私も今なお赤を入れられるとカッとしたり、目の前に相手がいたら首ねっこつかまえて「で、どこが?これのどこが?」と詰問しそうなくらい、頭に血がのぼることは、やっぱりある。
わたしは息子に言いながら、違う、わたしは自分に言い聞かせているのだ、と、思った。
わたしは今でも、高校生の息子と同じく、小さなプライドがあって(高校生なら、そのプライドは青春の証だけど)反論しようとする気持ちを持っていて、常に、いつも、そこと戦っているのである。
プライドはとても大事だけれど、プライドは自分を大切にするためにとっておこう。
誰かに怒りを向けるためのプライドはいらない。ちきしょー!赤入れるんじゃねーわ!!!と怒りに任せて投げた石は壁にぶつかり、はねかえり、自分の額を傷つけるのがオチである。
その石を投げる前に、積み上げていこう。積み上げた石は、わたしがやってきた、あなたがやってきた、がんばってきた、耐えてきた、膨大な労力が眠る墓石である。
あああ、ついに、赤入れの話が墓になってしまった……。でもいいか、お墓の前では念仏を唱えるものだ。
さあご一緒に!
「私が悪いんじゃない、誰かが悪いのでもない、そういうことなのだ、受け入れろ自分!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
