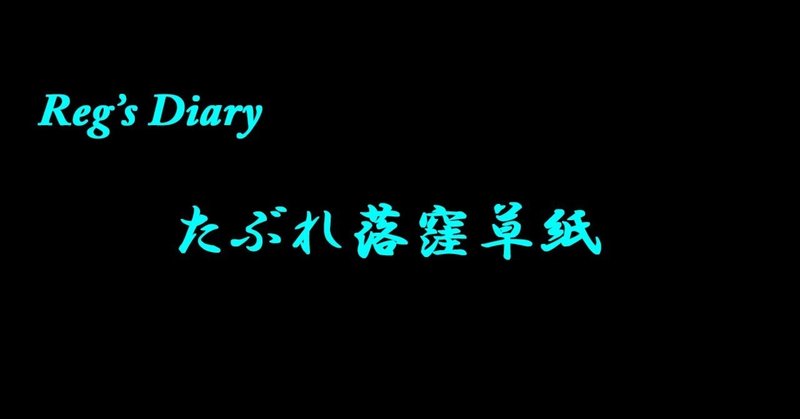
浅草寺ってそんなに古いんだぁ!
東京は台東区浅草にある浅草寺。大きな赤い提灯が下がる雷門で御馴染みの外国人観光客にも大人気のお寺である。その浅草寺の起原があまりに古くてびっくり。
浅草寺のホームページによると、遥か飛鳥時代、時は628年3月18日推古天皇の御代、近くに住む兄弟が漁をしていると一躰の仏像が網にかかる。この像を土地の長に見てもらうと聖観世音菩薩像と判明。翌日には童子たちが草で作ったお堂に尊像を安置する。その後645年に勝海という僧が寺を整備し本尊を秘仏としたという縁起があるらしい。645年といえば中大兄皇子と中臣鎌足が乙巳の変を起こし大化の改新が始まる年ではないか。少なくとも約1400年の歴史があるということだ。おそらくは仏教公伝以来仏像を祀る寺院や小さな草堂も含めると沢山の寺院が造られたに違いない。しかし、現世まで残っている寺院はそれほど多くない。代表的なものは、四天王寺、飛鳥寺、広隆寺、法隆寺、善光寺あたりであろうか。それと同じ頃関東にも浅草寺が創建されていたのだ。興福寺や薬師寺でさえ600年代後半建立だと伝わる。
古刹は焼失、再建を繰り返しているところが多い。昔は大火を消す手段などあるはずもない。浅草寺もご多聞に漏れずというところだが、関東大震災では、地元民らの連携もありそれほど損傷をうけなかったが、1945年の東京大空襲で多くを焼失した。現在の雷門、宝蔵門、本堂、五重塔は戦後に再建されたものである。戦争は人々が長い時間をかけて造り出し受け継いできたものを一瞬で灰にしてしまう。悲しいことである。
雷門は江戸時代の終わりに火災で焼失してしまい、その後は仮の門しかなかったようだが、昭和35年に松下電器の創業者、松下幸之助氏の寄進により再建されたと看板に書いてあった。
日本がまだ元気だったころの話である。
【REG's Diary たぶれ落窪草紙 1月4日(木)】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
