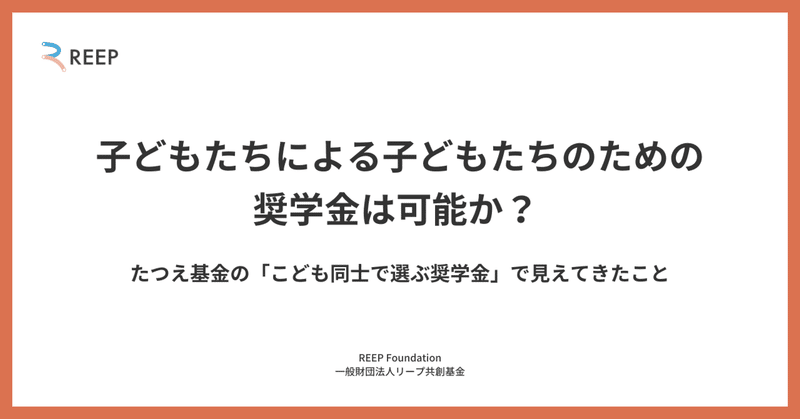
子どもたちによる子どもたちのための奨学金は可能か? たつえ基金の「こども同士で選ぶ奨学金」で見えてきたこと
義務教育を終えたあと、子どもたちが学ぶための費用、あるいは新しいことにチャレンジするための費用は、誰が負担するべきなのだろうか?
私立大学の初年度納入費は8年連続で上がっており、2021年には148万円を超えた。2020年に「高等教育の修学支援新制度(大学無償化)」が始まったが、利用できるのは住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯に限られている。
こうした状況の中で、家庭の負担を低減するのが、奨学金制度である。今回の記事では、現行の奨学金制度が持つ課題とともに、新しい奨学金プログラムの実践について紹介したい。
大学生の約半数が、なんらかの奨学金を受給している
2019年の国民生活基礎調査では、児童がいる世帯の平均可処分所得金額は、575万円。上記の私立大学の初年度納入費は、可処分所得の4分の1にもなる。生活意識として「大変苦しい・やや苦しい」と述べた、児童がいる世帯の割合は6割を超える。
1999年に65万人だった日本学生支援機構の奨学金の利用者は急増し、現在では倍の130万人となっている。なお、うち127万人は貸与型だ。
学校や地方公共団体等による奨学金制度も8800以上あり、そうした日本学生支援機構以外の制度を含めると、日本の大学生のうち49.6%、短期大学生のうち56.9%が、何らかの奨学金を受給して大学に通っている(日本学生支援機構 令和2年度学生生活調査)。
上記の調査によれば、なんらかの奨学金を「申請したが不採用」「希望するが申請しなかった」という学生も、2020年度に約7−8%ほどいる。世帯収入が多くて不採用だったという家庭もあるが、明らかに支援が必要な収入であっても奨学金を使えていない層が一定数存在する。
子ども支援のNPOによると、「保護者が進学に協力的でなく、収入証明などの書類を揃えられない」などのケースもあると聞く。特に、貸与型ではない給付型の奨学金を活用しようとすると、複数に応募するために書類を何セットも用意せざるを得ない状況もあるようだ。
80年の歴史の中で、厳しさを増す奨学金の状況
学ぶことは、昔からこんなに家計に負担を与えるものだったのだろうか? 日本の奨学金制度の始まりは、1900年代に遡る。
文部省の全国育英事業概況によれば、1927年頃には、すでに246の育英団体が、各地域に存在していた。しかし1929年の昭和恐慌をきっかけに、自治体の財政難、篤志家の寄付金の減少、就職難で奨学金返済の余裕がない若者が増加するなど、民間育英団体の資金は減少。また、戦争遺児の教育機会を確保する必要性にも迫られていた。
こうした背景の中で、国家規模の育英制度として大日本育英会(日本学生支援機構の前身)が1943年に創設された。この頃、奨学金は「無利子貸与」の仕組みであった。また、1953年には返還免除制度が導入され、教育職・研究職として一定期間勤務した場合、返還しなくてよかった。
奨学金制度の創立から今までの歴史を80年とすると、前半は、日本の奨学金は「無利子」かつ「一定条件のもとの返還免除」という特性を持っていた。
しかし、後半にその特性は覆されていくことになる。1984年の法改正では「有利子貸与」が導入された。また、教育職は1997年、研究職は2004年に返還免除制度も廃止。この時期、バブル崩壊後で新規採用が冷え込んでおり、滞納せざるを得ない若者が増え、社会問題にもなった。
「自分が奨学金を受けるに値する」と思えない子どもも居る
厳しい状況にある現行の奨学金制度だが、問題は他にもある。
浜銀総合研究所の「生活保護世帯の保護者・子どもの生活状況等の実態や支援のあり方等に関する調査研究」(2018年)によると、生活保護世帯の約4割の子ども達が、”自分は価値のある人間だと思わない””将来の目標がはっきりしない”と思っている。
そうした、自己肯定感やチャレンジへの意欲が低減している子どもたちにとって、「自分は、給付型の奨学金を受ける資格がある」という肯定や、「倍率の高い給付型奨学金だけれど、勝ち抜けるだろう」という自負を、持てない場合もあるのではないだろうか。
奨学金の選考では自己PR等の提出が必要なものも多いが、そもそも自分のやりたいことを考えたことがなく、周囲に尋ねられたこともない環境の子どもたちもいる。
自己肯定感が高い子ども、周囲に協力してくれる大人がすでにいる子どもにとっては、奨学金は飛躍の機会としやすい一方、そうじゃない子どもにとって、奨学金は格差を深めるものになっているのではないだろうか。
「子どもたちが、奨学金をもらう人を自分たちで選ぶ」奨学金
こうした中で、新しい奨学金プログラムとして生まれたのが、たつえ基金の実施した「こども同士で選ぶ奨学金プログラム」である。たつえ基金は、大正5年に生まれた小林辰重氏の遺産をもとに、2015年にリープ共創基金で運営されている基金である。

当初、子どもに教育機会を提供するNPOへと助成を行っていたが、助成を続ける中で、基金設立者であるご遺族は、「もっと当事者へ直接的に資金を届けられないか」というニーズを持つようになっていった。
設立者家族から、リープ共創基金に「経済的な機会に恵まれない子どもたちのための奨学金を考えてくれないか?」というオファーがあり、新たなプログラムとなる奨学金を企画した。
これまでの奨学金と大きく違う点として、「子どもたち自身が、奨学金をもらう人を自分たちで選ぶ」という相互選考の仕組みを採用。通常、奨学金は、選考委員など大人が選んで採用を決める場合がほとんどだが、子どもたちが主体的に関われるようにした。
また、奨学金の選考プロセスの中で、学びの機会を設けるプログラムを作成。奨学金の採用や落選という結果が通達されるだけのプログラムが多い中で、できるだけプロセスを透明化し、そのプロセスの中で子どもたちにフィードバックが生まれるようにした。
「周囲へ1番貢献した」学生が1位になり、ルワンダへ
募集は、故・小林辰重氏が大阪で塾を開いていたこともあり、関西エリアで実施した。生活困窮家庭の子どもたちを支援するNPOに対して、プログラムの情報提供をする形で行った。
参加した子どもたちは、7名。その中の1人が、高校2年生のすみれさん(仮名)。美術館巡りや茶道が趣味で、「話し下手だけれど、今の自分や将来の自分について深く考える機会にしたい」と参加した。
初回ワークショップでやりたいことを考えたときは、「留学して、異国文化を学びたい、貧しい人などが格安で泊まれるホテルを建てたい、両親にこだわりのマイホームを建てさせてあげたい 」 と答えていた。
2回目のワークショップでは、自身のこれまでの人生の深掘りや大切にしてきた価値観の整理を行い、それを踏まえてやりたいことを再度考え、「ルワンダの幼稚園やスラムにボランティアに行きたい」と具体的な夢にブラッシュアップ。
また、他の参加者の夢についても、「こういう風に書き直すとより伝わりやすいよ」と積極的にフィードバックし、周囲にも貢献した。
最終的に、参加した子どもたち同士が、夢を記した最終課題や、お互いの成長度、他の候補者への貢献を点数にして投票。夢はもちろん、周囲への貢献を非常に高く評価されたすみれさんは、1位を獲得した。
奨学金の20万はルワンダに行くために貯蓄し、現在はこのプログラムをきっかけに知った無償の短期留学プログラムに参加して、夏休みを活用してアメリカで文化や人権、差別問題について学んでいる。
お互いを励まし合う、かけ算のような奨学金プログラム
すみれさんは、プログラムに参加しての感想を以下のように述べている。
「今まで否定されることにものすごく恐怖心があり、自分の夢を話したり発信することはほとんどなく、苦手だった。やりたいことを話してフィードバックを受けるということが、今回はじめての体験だった」
「人と影響しあえる楽しさを知ることができた。自分のやりたいことを言葉にしてみる機会をもっと日常生活の中で持つことが大切だと思った。機会を待つのではなくて、自分から探したり作ったりしていきたい」
また、他の参加者からも以下のような感想が上がった。
「自分の夢や思いは、真剣にありのまま話せば他人は理解をしようとしてくれるということを学んだ。自分のことを理解して欲しいなら他人を理解しようと感じた」(大学1年生・大阪府在住)
「したいことをしたいと言うのはとても苦手だけれど、もっと貪欲にしたいことを発信することで、手助けしてくれる人がいるのかもしれないと気づいた。したいことを少しづつ実行してみれば、楽しいかもしれない」(高校2年生・大阪府在住)
また、資金提供者である故・小林辰重氏の遺族もワークショップに参加し、子どもたちとも交流。「お互いの励まし合いによって、使ったお金よりも大きなことが起こっていく、かけ算みたいな場だったなと思っている」という感想を、最終ワークショップで話した。
子どもだけでなく、資金提供者も成長する基金に
リープ共創基金の代表・加藤徹生は、一連の取り組みに対して、「たつえ基金は2015年に設立され、最初はNPOへ資金を提供していたが、今年から進化した。基金から資金を提供する中で、団体や資金の提供先である子どもも成長するが、資金提供者も学んで成長していくのが、基金の本来の姿。そうした基金のつくり方に、今後も丁寧に伴走していきたい」と語る。
また、リープ共創基金で奨学金プログラムのファシリテーターをつとめた桝田は、「今回の参加者には、母子・父子家庭という環境によっていじめられた経験を過去に持っていたり、自分の希望を我慢することがあたりまえになっていたりする子どもも多かった。ワークショップでは、戦争から帰還した人のトラウマケアなどに使われている心理療法であるクリーン・ランゲージを活用した。これまで角が立たない表現を選ぶなど、無意識に防衛してきたような子たちが、お互いの存在によって自己開示できる場になったと思っている」と話した。
奨学金というと、多くの人は大学の学費を補填するものを思い浮かべるだろう。しかし今の社会の中で経済的に困難を抱える家庭の子どもに必要なのは、受験よりもさらに前に、自分のやりたいことを言える環境をつくることなのではないだろうか。
経済的な補填だけでなく、自己肯定感を育てていけるプロセスをつくる。そうした機会を丁寧につくることからしか、子どもたちの持つ格差は埋まらないのかもしれない。
リープ共創基金では、子どもたち主体のワークショップ型の奨学金プログラムをこれからも実施していきたいと考え、新たな資金提供者を募っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
