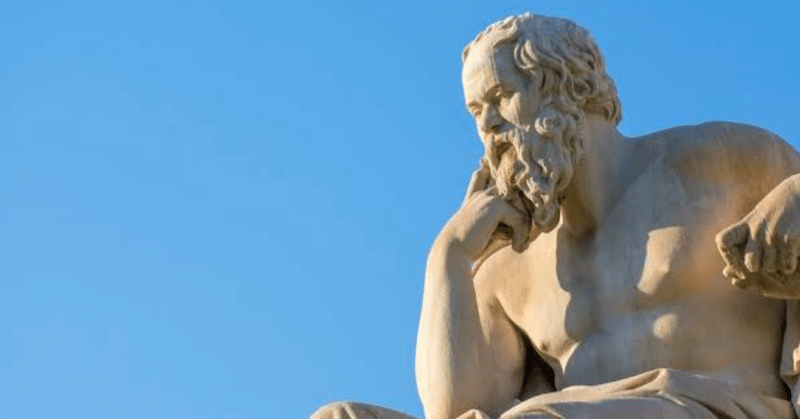
[雑記]無知の知と不知の知
「無知の知」。これは哲学者ソクラテスの哲学の概念とされています。
しかしこれは表現上、やや間違った意訳という話もあります。
日本語において「無知」とは、知識が欠けていることを意味していますが、ソクラテスが自覚し、概念としているのは「知らないこと、愚かであること=不知」を知る事(不知の自覚)であるため、「不知の知」という表現が正しいのではないか、という論です。
哲学的な解釈等については専門家に任せますが、言葉的には両者成立するものであり、日本語の意味合いの上では、私的には「無知の知」であってもらいたいと考えます。
”[雑記]情報の価値と客観性”でも触れたように、世の中には「情報」という言葉の意味することも、真実と事実の区別も分からず流布・拡散されているものも沢山あり、その中で正しい情報を見極める為には、情報が氾濫する現代において、目の前を流れる情報や求める情報を受信する時に、如何に客観的に見る事が出来るか、見出した事実を如何に考え検証するかが重要であることを書きました。
ちなみに、「事実」とは唯一無二で現実に起きた客観的事象、「真実」とは事実を受け手の主観に基いて解釈されたもの。
つまり、真実は人の数だけ存在します。
何事にあっても、”知らなかったことは恥ではない”のですが、そこから先を知ろうとしないこと、若しくは知ったかぶりは恥であることを認識しなければ結果「不知」であり、知ろうと探求すること、知るために努力しなければ「無知の知」にはならないのです。
よく「真似=悪」な風潮も聞きますが、本質を理解するには真似から入り疑問を持って向き合うのが一番最短ルートであるので、真似る事を否定する気はありません。もしそうして最初に学び得たことが間違っていたとしても、人に問いたり別の資料から新たな事実が判明したのなら修正すれば良いのです。しかし、表面上の真似に終始し本質を理解しようとせず、根拠なく理解した気になって驕るのは「不知」の典型とも言えるでしょう。
私が恐ろしいと思うのは、ネットワークの発達した現代においてマスメディア含め「発信者が”不知”で、情報というものを理解せず流布している」ことが多いという点です。
テレビ等、立場ある側から発信されたものは大概の人が冒頭から疑わず受け入れますが、発信された情報そのものが事実から湾曲した真実なら、間違ったものしか伝わりません。
例えば、今年はコロナ関連のニュースが連日大賑わいですが、同じ局の同じニュースでありながら毎日発言が変遷しているのを見てれば理解出来るでしょう。
私はミニ四駆という趣味から、結果に基づく検証の事実と、事実に基づく推察(真実)を出来る限り混同しないように情報発信を心掛けていますが、言葉というのは難しく、更になかなか1度で真意が全て伝わるものではありません。しかし、「何故か」という探究心を持ってもらえたら、概ねは伝わっていくことでしょう。
知らないことは恥ずかしい事ではありません。逆に最初から全て知ってる人も存在しません。知らないからちゃんと知りろうとすることの探究心、「無知の知」が大切なことなのです。
ミニ四駆1つとっても、私自身そうですが沢山の知らないことも、間違った知識も多分あるでしょう。
人により程度は様々ですが、だからこそ私は1つ1つを深く知りたいと思って取り組んでいます。
そうして知り得たものの中で、情報の少ないものや理解の難しいもの等を中心にnoteにすることによって、同じように壁にぶつかった人や知らなかった人等の”知る機会”に寄与出来たらと考えています。
新たな発見で、もっとミニ四駆をやりたくなる事を願って😌
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
