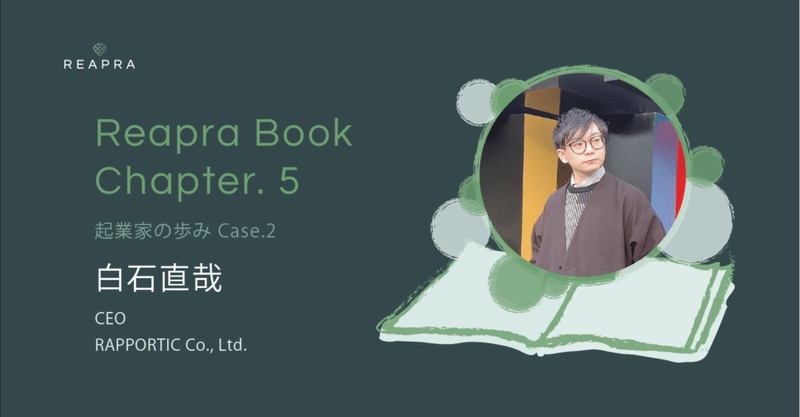
【Reapra Book連載シリーズ】第5章:社会と共創する熟達への道②
昨年、Reapraで研究と実践の過程や得られた知識をまとめるためのプロジェクトが始まりました。それが"Reapra Book"。
Reapra Book連載シリーズも第6回目となりました。過去の記事はこちらからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
前回に引き続き、今回も社会と共創する熟達を歩んでいる起業家へのインタビューを掲載いたします。昨年Reapra Book ver.1の公開に合わせてインタビューしたものです。具体的にReapraがどのように研究と実践を行っているのか知っていただければ幸いです。
起業家の歩み
移民という領域でビジネスを作っていこうとしている株式会社RAPPORTICのCEO 白石直哉氏 (以下、白石 敬称略)に2019年12月のReapraとの出会いから、現在Reapraから受けている支援について感じていることをインタビューしました。在学中に語学学校を起業されたり、大手ドラッグストアやヘルスケアテック系のスタートアップで働かれたりと、様々な経験をお持ちの白石氏。Reapraと出会った当初は、Reapraの社員として関わることを志望されていたそうですが、なぜ起業を選択されたのか、そして現在起業準備をされている中での葛藤についても伺いました。
Reapraとの出逢い
編集 Reapraとの出会いは2019年12月だと伺っています。出会った時のReapraの印象についてお聞きしてもよろしいですか?
白石 フィーリングが合うと感じました。根本的に自分がやりたいと考えていた「本質的な課題を解決する堅実かつ長期的な社会貢献装置を産み出す」というところで思想がマッチする感覚がありました。私が直前まで所属していたヘルスケアテック系のスタートアップからの反動もあったのだと思います。その会社は六本木にオフィスがあり資金調達も何度かしている”いわゆる勢いのあるスタートアップ”で、数億〜数百億円の売上を想定する新規事業開発に携わりました。ところがそこでは、本来長期的に持ち続けるべき問いに短期で答えを出す必要に迫られたり、組織へのミッション/ビジョンの浸透に時間を割きにくかったりと、スタートアップの構造上のジレンマを誰も抱えきれずにいました。極端な思考やアクションの間を揺れ動く特有の難しさがあるように見えたのです。そしてそれは、もともと自分が抱いていた大型資金調達型スタートアップに対するナイーブなイメージ、「社会にイノベーションをもたらす事に社員一丸となって大きな熱量を持って取り組み、その実現の為に適切な資金調達を重ねながら、絶妙なリーンアプローチでJカーブを駆け上がっていく」理想像とは雰囲気が少し違っているように見えました。その視点で改めて界隈を見渡した時にふと「果たしてこの登り方で本質的な課題解決に向き合い続けながら答えを出し続けられるのか?」と疑問を感じ、そうであれば自分が実践したい在り方・登り方とは距離がある、という気持ちが大きくなりました。
一般にこのようなスタートアップは、社会に対して提示する概念の自体の新規性がそもそも高く、場合によっては顧客課題も顕在化していなかったり顧客教育も並行して必要な領域であるにも関わらず、CPFやPSFが完了している前提で自社プロダクトありきの絵を描いてしまったり、或いはピボットする根拠や勇気や体力が足りないのにも関わらず不安に煽られて課題の存在を疑いたくなったり、投資家からの圧力で成果を急ぎ真の課題解決から逸れてしまったりしやすい構造があり、リーンにやるとはいえどやはり組織はある程度自社サービスを信じる力が問われるのだと思います。
一方で私は、しなやかに事業開発を行う中でソリューションありきではない真の課題を特定し、そこに真摯に向き合いPSFまでやりきって何度もPMFを繰り返しながら、確実に社会のアップデートを下支えしたい。しかもその事業は、自分の寿命を超えて価値貢献し続ける社会装置でありたいわけです。しかし、世の中はやはりソリューションありきの事業開発が主流で、私の願いはナイーブ過ぎるのではないか。このような葛藤を抱えていたところで、Reapraとの出会いがありました。出会いの当初は起業への向き合い方として、このような方法があるのかと驚きました。他のVCで求められた事業計画書もReapraの場合は全く見る気がないんです。彼らはその起業家の強い信念の有無やそれが社会性を帯びているかどうか、起業家自身が長期的に学習し続けられるか、などというようなところに特に注目しており、ゆえに投資アセスメントに際しては現時点の事業計画書は敢えて見ないんだという一貫した態度にも、私はとても心を動かされました。このような背景があり、私はReapraと手を組んでもう一度起業することを決意しました。
編集 Reapraと出会った時に、特に気になった概念や考え方があれば教えてください。
白石 「産業創出をする程の事業づくりをすることに対して自分なりの強いこだわりを持っていれば、あとは起業家が適切に学習を積み続け仮説や手法をしなやかに洗練していけば、長期的にはあの手この手で実現していける。それができる領域があり、また手法も存在する。」という考え方です。
Reapraとの出会いの前、他のVCとも会話していた頃は、自らの能力の”can”の中でどこまで自分をうまく見せて相手を納得させ資金調達を実現するか、といような挑戦をしている感覚がありました。ところがそもそも私は、現状の自分の実力と実現したい社会貢献の間には大きなギャップがあり、またそれらは埋めても次のギャップが発生し続けるので、自分は常に成長し続けるしかないという観念を持っています。そんな中で”can”を大きく見せて事業を進めていくやり方は、自分にはあまり向いていないのではないかと強く感じはじめていました。このような葛藤があり、当時は他のVCからの資金調達の目処も立っていましたが、やはり理念に共感できるReapraで修行しまずは実力不足を埋めるべきではないかと考え、はじめは社員としての入社を希望しました。それは、他のVCから現時点で多額の資金調達をしたところで、過去の起業でスモールビジネスの域を出られなかった自分から十分に成長できていないと感じ、また同じ結果になるだろうと思ったからです。特に足りないと感じてきたビジネスに関する網羅的な知識や、急激な組織拡大を伴う事業づくりの経験は依然として十分でなく、起業は選択肢から外しつつありました。そんな折にReapraの産業創造の方法論に出会い、共感し、起業の選択肢が再浮上してきました。
起業という選択
白石 心が動いたひとつのきっかけは、Reapraの社員か起業家っていうことを考えた時に、「社員の経験をする必要があるのか」という問いかけが当時のReapra社員からあったことです。そもそも、社員として働いてみる必要はないかも、と。自分の中では、「勉強でどこまで目的にたどり着けるのですか?」という問いに変換されて聞こえていて。全体を俯瞰して勉強するためには、確かに教科書的な勉強はすごく役立ちますが、何かやりたいものがすでに決まっているとか、ある程度熱量があるのであれば、荒くても実践の中で学習していった方が深く、スピードもつけて学べるなというのは過去の自分の経験からも感じていました。まさにそういうことを言われたのかなと思いました。独力だと実力が足りず難しいのでさらに修業期間をと思っていましたが、Reapraはハンズオンで伴走してくれるというところもあったので、自分が起業に対して持っていた一番大きな不安もある程度解消しました。
編集 独力だと難しいというところでは何が難しいと考えられていたのでしょう?
白石 早く行きたいなら一人で行け、みたいな言説がありますよね。逆に遠くに行きたいならみんなで行けと。自分は遠くにいきたいと思っています。なので、チームでやりたかったのです。あとは自分がいつ死んでも残る価値貢献のシステムを作りたいという願いが元々ありました。それこそが社会に貢献することだとも思っていました。自分ひとりがお金を儲けるのは興味がなくて。そういうことよりも価値貢献をするシステムを作ることに関心があります。それを達成するには、一人でやるには少々無理があり、組織作りをしないと実現できないという実質的な問題がありました。過去の起業経験では、「組織を作るということは仲間を抱えることであり、最終的に全ての責任は自分が背負わなければならない」と自分に重圧をかけていました。全部自責的に考えていて、自分と会社を切り離して考えられませんでした。結果として、人間関係がうまくいかなかったという強い課題感が残っているので、これからは人向き合いというところに焦点を当てて学習していきたいと思っています。
Reapraの支援
編集 Reapraのハンズオン支援の存在が企業への大きな不安の解消につながったというお話がありましたが、Reapraの支援に対して、当初どのような印象を持っていましたか?
白石 最初の印象は、言っていることはわかるけど腹落ちしてないという感じでした。IFD、FDといった自己向き合いが本当にどこまで役に立つのかって言う、ビッグピクチャーが全く見えていなかったので。重要そうということだけが分かっていても、腹落ちはしていませんでした。次のフェーズにどのように役立つのかというのが見えない状態だけど、とりあえず信じてやってみようという感じでいましたね。
編集 その中でも信じてみようとか、信じることを選択したっていうにはどのような背景があったのですか?
白石 これには複数理由があります。1つは、新しいことや自分にできないことにチャレンジする時に、全部に対して納得するまで腹落ちしてからやるというのは稀なことだと思っていて。私は格闘技やダンス、あとは外国語学習に挑戦した経験がありますが、それらの経験から、成功するにはとりあえず信じてやってみることが大切だと学びました。分からなくてもまず信じてやってみるというのは1つ自分が持っていた成功体験からの構造だったと思います。
では、なぜ信じる対象になったか。1つはReapraの概念に共感したこと。もう1つは、プロ集団であなたを引っ張ってあげますよみたいな態度ではなく、一緒に頑張っていきましょうという態度に見えたからです。自らも常に学習と実践を続け、前に進むことを決めている人たちの集団は、少し横にそれることもあるかもしれないですけれども、正解に近づかないわけがない。Reapraが前に進もうと情熱を持って取り組んでいる集団に見えて、信頼してみようと思うに至りました。
編集 実際にIFD※1を受けてみての感想はいかがでしょう?
白石 この手法に対する信頼が増しました。なぜかと言うと、後戻りがあまりないなと思うからです。「本当にこれでいいんだっけ」といちいち巻き戻っていると、右往左往をするような気がしますが、IFDを通すと、揺るぎない部分がきちんと根底から積み上げることができると感じています。
過去に起業した時には、自分が成し遂げたいことと、会社で掲げているカンパニーミッションとの区別が付かなくなってしまっていました。責任感から、そのカンパニーミッションを自分のやりたいことに上書きし、なんとしてでも自分の人生で成し遂げなければならないと。自己洗脳が働き、自分のやりたいことや気持ちをないがしろにしていました。実際に、洗脳が外れた瞬間にはとても混乱しました。それはもう二度と経験したくないと思っていたので、今ReapraでFD・IFDというアクティビティーを経て、同じような経験をしなくて済むかなというところに信頼がありますね。もちろん定期的に振り返って、本当にこれで良いのかは毎回見ていきますが、それは自己理解の解像度が上がっていったり、自分の自我が揺れるにつれてアップデートしていくことであって。再び別の自己洗脳を始めることも、自己洗脳状態が解けて、いきなり全く違う自分に気付いたみたいなことも、もうあまりなさそうだと感じていまして、そこには感覚と手法の両面から一定の信頼感があります。
※1FD/IFD:個人がよりよい人生を送るために、環境と自我の相互作用を通して自身の特徴(らしさ)が形作られてきた過程を時間軸を入れながら構造理解し、今後長期にわたり熟達していく方向性や目標を紡ぎ出すこと。そして現状との差分を明らかにし、自我と環境の両方に配慮しながら社会と共創する熟達を歩む土台を整えるプロセス。長い時間軸をとって実施されるFDに対し、新入社員や投資先起業家、その候補者を対象に短期間で負荷をかけてインテンシブ(集中的)に行うのがIFDです。
起業家と環境
編集 ここからは、環境に焦点を当てて質問をさせてください。まず、なぜ白石さんはPBF※2を「移民」という分野に定められたのでしょうか?
白石 移民になった、という感覚です。例えば過去の起業の経緯で行くと、自分の中で「語学学習」っていう日本全体でさっさと乗り越えるべき”くだらない障壁”があり、それが沢山の人達の思いの実現の足を引っ張っていると感じました。ですので、どちらかというとゲイン領域 (※課題を解決するようなペインがある領域ではなく、現状をより良くしていく領域のこと) で、もっとこんなことがしたい、という熱い思いがある人たちに対してサービスを届けていました。その人たちにとってみれば、ソリューションが無いと語学学習が進まないのである意味でペインですが、社会全体として見ると、既に生活も成り立っていてその生活を良くしたいと考えているのでゲイン領域です。
一方で、日本を取り巻く移民環境の現状では、移民と日本人で互いに言葉が通じないことが明確なペインで、この二つは似たようなことを見ているのに問題の性質が全然違っていると感じていました。僕にとってはこれもまた「くだらない問題」で、人々がそのせいで力を発揮できないとか人生を楽しめないみたいなことがあるのは凄く嫌なんです。突然幼稚な言葉になってしまいますけど、嫌なんです。それを解消したいという思いに到り、「移民になった」という背景が一つ。もう一つは自分の年齢や残り時間みたいなことを考えても、薬剤師資格をもっていることや過去の起業領域・経験などのレバレッジが効くような業界から登った方がよりインパクトのある社会貢献を実現しやすいという思いが少なからずあって、全く今までやったこともない領域に対してアプローチしていくという怖さはあったと思います。この二つの別の構造があって、それが結局移民というところに落ち着いたのかなと思います。
※2PBF:複雑性故にまだ規模としては小さいが、次世代に跨ぐ大きな社会課題を有しており、株式会社アプローチが有効で唯一無二のマーケットリーダを目指し得ると信じられる領域。さらに詳細はこちらをご覧ください↓
編集 ペイン領域に点在するキーワードから移民に絞っていったのか、移民というキーワードが浮かび上がったか、でいうと、どちらでしょうか。
白石 後者に近いですね。実は、Howとしてはあんまりやりたくなかった領域なんです。過去の苦い起業経験から、当時取り組んでいた言語教育という領域に漠然とした苦手意識があります。本当は見たくなかった領域なのだけど、一旦足を突っ込んでしまい、その業界のまだ残されている深く広い課題を見てしまった。移民というPBFでも言語障壁は大きな課題の一つであり、自分には転用できる経験がある。例えば、具体的な言語の運用場面を想定した課題特定に基づいて効用を最大化する設計や、学習者と教育側双方の視点を考慮したプログラム開発、そのデリバリー部分の品質担保や自己改善が働くような提供側の教育スキームの開発などができる。あとはビジネス側の実力を身につければこの問題が解決できるかもしれない、と感じました。であれば、この問題を見なかったことにはできない、という気持ちですね。あとはやはり自身の経験からレバレッジがかけられる領域であるがゆえに、移民に関して調べれば調べるほどソリューションのアイデアや業界としてやり込みが足りない「くだらない課題」が沢山見えてきて、間違ってなさそうだ、やっぱり間違ってない、みたいな。今になって思えば、見たいものを見に行っていた側面はあったかもしれないです。
編集 ご自身のPBFに対する想いを教えてください。
白石 打ち手がたくさん見いだせることは純粋に良いことだと感じています。例えば、技能実習生の受け入れに関して言うと、送り出し側や受け入れ側、それを取り巻く支援団体が直接的に関わっており、実習生そのものだけではなく送出機関のポリシーや受入施設の現場・経営側の双方のマインドや組織課題なんかを伴う状況になるので、組織改革として切り出して取り組める余地もあるんです。こんな風に様々な問題が複数の領域に跨って存在していて、どれを解消しても一応前に進むだろうなっていう風に思えるぐらい、いろいろな打ち手があるというか。この点はすごくポジティブに捉えています。
あとは、結構人間に近い業界だと思っていて。自分がやった仕事が誰かの人生の幸せに繋がると信じやすいかなと思います。「私の事業があったから誰がどんな風に幸せになった」ということを必ずしも実感する必要はないですが、「この事業があるからこんな人がこんな風に幸せになれるだろう」っていう想像をしやすい領域を選べたと思っています。まとめると、移民という領域には絶対に人がいて、そこにもまた、見過ごせないくだらない問題が沢山存在しているので向き合っていきたいっていう思いで選んでいて、幸運なことにそこには現時点でも沢山の打ち手があるなと。例えひとつの事業で手詰まりになっても、それだけで領域に対するアプローチ全体が停止することは恐らく無いだろうなと思います。
編集 逆に不安な点はありますか。
白石 やはりPBFを選んだプロセスに対する不安はありますね。一発でバシッと選んでしまったことに対する不安があって。領域を選ぶ時に一度日本や世界の産業全体をミクロとマクロの両面でリサーチするとか、ある程度広くフェアなプロセスを経ていれば、この不安も少なかったのかもしれないです。それはつまり、自分に出来ることは全てやりきって相対的に優位な領域を見つけたという腹落ち感を持ちたいということかもしれません。広く見て深く考えた上で選択したのであれば、選んだ領域に対するグリットが強くなると思うからです。色々見たけどやっぱりここしかなかったよね、という。自らの囚われや想いからくる市場の見立てを含むPBF像に納得し、なおかつ現実と噛み合わせて事業づくりをしていく際に必要になる信じ力を維持するためには、市場全体からみるという作業を通して思考プロセスの整合性を確認することもできるので、不安になってしまった時もそのプロセスを繰り返せばいい。しかし私は、今はそれの手段を持ってないんです。やっていないので。なので、不安になってしまう時は、今も実際そうなんですが、もしかするとPBFとしてより自分に向いている領域が他にあるかもしれないのに検討すらしていないままでよいのか。極端な例えですが、街中で石を投げて当たった人と結婚するご縁をどこまで信じきれるのか、そういう感覚になることはあります。
編集 起業自体がそもそも不安定で、将来が見えない状態で走らなければならないので、自分が選んでいる領域が正しいのかどうか不安になることも多いと思います。白石さんが迷った時には、白石さん自身が自ら根源を確認しにいける状態になることを目指して、伴走していきたいなと感じました。
本日はありがとうございました。
------------------------------------------
Reapra Bookはこちらから全文ご覧いただけます。フィードバックフォームもありますので、ぜひご感想、ご意見をいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
