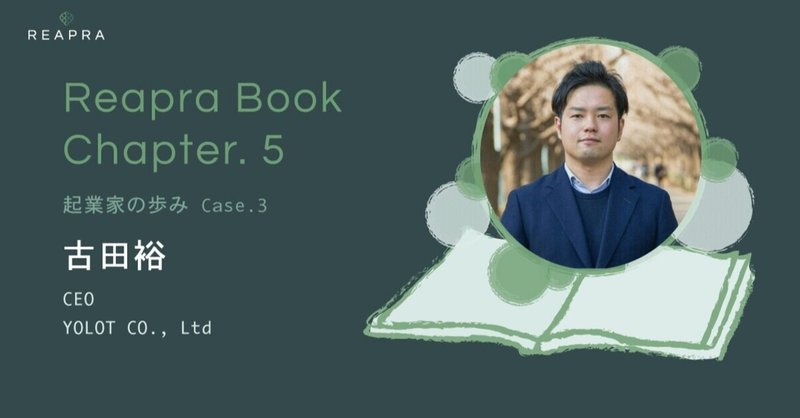
【Reaprabook連載シリーズ】第5章:社会と共創する熟達への道③
昨年、Reapraで研究と実践の過程や得られた知識をまとめるためのプロジェクトが始まりました。それが"Reapra Book - リープラブック"。
Reapra Book連載シリーズも第6回目となりました。過去の記事はこちらからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
前回に引き続き、今回も社会と共創する熟達を歩んでいる起業家へのインタビューを掲載いたします。昨年Reapra Book ver.1の公開に合わせてインタビューしたものです。具体的にReapraがどのように研究と実践を行っているのか知っていただければ幸いです。
起業家の歩み
2016年から旅行領域でビジネスをされている株式会社YOLOTのCEO 古田裕 氏 (以下、古田 敬称略)に、創業時の事業領域やその時の心境、ご自身の価値観の変化、そして今挑戦されている事業領域と今後についてインタビューしました。過去を振り返ることによって発見した自身の囚われがご自身の価値観の変化にどのように影響を及ぼしたのか、また、その価値観の変化がどのように事業に影響していったのかという部分を中心にお話頂きました。
事業領域の選定
編集 YOLOT創業期の事業領域についてお伺いしてもいよろしいでしょうか?
古田 元々の個人のライフミッションとして「誰しもが自分の可能性に挑戦できる社会を作る」というのを掲げています。YOLOTとしては「人生の原体験になるような体験機会を提供し、社会に貢献し続ける」がミッションです。僕自身が大学時に約70カ国を旅行した原体験が大きく影響し自分の人生が大きく変わってきたということがあって、身体性を伴う学習だったり、自身が普段いる場所から離れたりすることによって思考が深まり、新たな概念を獲得できるという経験をしました。いつか単に観光名所を巡るのではなく、そこに学習や新しい体験というものが付加価値として付いてるような旅行プランを販売したいなと思っており、2016年に立ち上げたのがEXUTRA(エクストラ)というサービスです。
EXUTRA(エクストラ)は、エクストリームトラベルの略で、日本人の富裕層向けアウトバウンドサービスです。彼らが海外へ行く時に、オーダーメイド型の旅行プランというのを作ってあげて、それを販売する。単価平均五十万で、一泊十万の宿の手配など、顧客のわがままを聞いてあげるご用聞きみたいなところからスタートしました。ただ、富裕層向けやエクストリームトラベルだけがやりたかったっていう訳ではありません。YOLOTとしては人生を変えるような体験機会の提供というのは、色々なセグメントに刺さると思っています。小中学校で言えば修学旅行のアップデートかもしれないですし、高齢者で言えば介護旅行、社会人で言えばスタディーツアーなのかもしれない。その中で初手として、少ないユーザーでも利益率をロックできて、業界内の繋がりたい人たちと繋がれそうということを考えた時に、富裕層向けから入るのが良いのではないかなと思って入りました。
自我の状態
編集 その頃、考えていたことやその時の自我の状態について教えてください。
古田 僕自身大きい囚われがいくつかあるのですが、この時期に顕著にあらわれていたのがお金への囚われでした。これには、幼少期が相対的に裕福ではなかったというのが背景にあります。事業も自己資金で始めているわけなので、リアルに自分のお金が減っていく感覚がありました。創業して3か月目でインターン生が8人になった時に、1日で10万円ぐらいお金が飛んでいく感覚が強くあり危機感を覚えました。人を雇うことは事業を伸ばすためには必要だと思いつつ、お金が減っていくのがとても怖くなったんです。出ていく分を補うために、個人でコンサルをして稼いでくるというのが癖として常態化していって、本業に集中できない時間が多くなってしまいました。インターン生に対しても、パフォーマンスに固執するというか、短期で人を見てしまう傾向にあったと思います。
編集 他にもご自身の癖として認識されているものはありますか?
古田 そうですね。僕元々DeNAっていうウェブ企業にいたので、ウェブ的な伸ばし方しか知らないっていうのがあって。先程のEXUTRA(エクストラ)というサービスをやっていく中でも、自分の得意なところばかりに力を入れていました。エフェクチュアルにと考えると、とにかく行動してみるとか、ウェブ以外でできることがあると思うのですが、当時の自分は自分の手触りがある事業領域で手触りのあることしかやらない状態が続いていました。社会人生活で染み付いてしまった癖みたいな感じですかね。 今もその癖が出てくる時があるので、向き合っていかないといけないなと思っています。
編集 少し視点を変えて、お話しできる範囲で構わないのですが、当時プライベートの部分で、どのような葛藤があったのかを教えていただけますか?
古田 振り返ってみるとプライベートと仕事を二項対立させる傾向がありました。これには私が10歳の時に父親を亡くしたことが強く影響しています。父が死んだ後、母親が掛け持ちで働かざるを得なくなり、それまでと生活スタイルが一変していきました。その経験から、仕事を頑張り過ぎると家庭がおろそかになる、家庭ばかりでもずっと貧乏なまま抜け出せない、という囚われが2019年まで自分の中に根強くありました。
これは、僕が社会人になった後も、起業する時の価値観にも強く影響していました。社会に対して貢献したい欲や、課題を解決したい欲はあるのですが、それを達成するためにはまず自分を満たしてあげないことには始まらないとか、結婚するにも家族を養えるぐらいの経済力がないことには結婚できないというように、自分に相当制限をかけていました。だから、起業する前にも、3億でエグジットしたいとか、一旦30歳までに成功したいですという話をよくしていたんだと思います。起業してからもそうで、価値の源泉が積み上がっていくようなアクションをするというよりかは、目先の単発で単価が大きそうなものを一発狙うみたいなのがあって。プロミシングな領域で、中長期で伸びていく領域でやっているはずなのに、施策がワンプロダクトよりに寄っていく傾向がありました。
自我に起きた変化
編集 プライベートと仕事に対する考え方に変化が起きたきっかけはあったのでしょうか?
古田 2019年10月に、諸藤さんと話をしに福岡に行った時に、自身の社会の見方が変わった気がします。それまでの見え方だと、仕事とプライベートの2軸の天秤があり、どちらに重心を寄せるか、どのバランスで生きていくかを考えていたイメージでした。それが話をして行く中で、自分を中心とした同心円状に家族、仕事、社会などが広がっていくイメージに変わっていきました。プライベートも仕事もシームレスに繋がっていて、すべて相互に作用し合っているし、Reapraの経験学習的にいえば、家族や家庭から仕事に還元できることもあるし、仕事から家族と家庭に還元できることもあるだなとある種アハ体験をしたという感じです。自身の働き方に対する考え方や、起業家像にも変化がありました。元々思っていた起業家像は、朝から晩まで死に物狂いで働くという感じだったのですが、別にそうでなくてもよいなと。それは、バランスよく働くという意味ではなく、あらゆるところから学習できる起業家になりたいと思い始めました。自分自身が歩みたいと思う起業家像っていうのが見えてきたっていう感じですね。
編集 他にReapraとの関わりの中でご自身に起きた変化はありますか?
古田 時間軸を広げて考えることや、超長期で産業を作る・次世代に残る何かを作るという部分を考えていたら、必然的に思考が深くなりました。あらゆるものを考えないといけないので、自然と時間軸が広がったという感じですね。元々創業時の価値観では、3年先の自分のことしか考えていなくて。でも、Reapraとの対話の中では、基本的に会社が次世代に跨がることを前提とするので、何十年先で、自分以外の経営者も想定して社会に何ができるかという視点で考えるようになりました。そうするとそれまで自分が見ていた視点だと時間軸が全然足りなくて、超ロングで考えないとけないし、自分に向き合わされる回数が尋常じゃないなと思っていますね。
環境に起きた変化
編集 現在取り組まれている介護旅行の事業をすることになった背景をお聞きしてもよろしいでしょうか。
古田 EXUTRA(エクストラ)はAgodaやExpediaのような旅行予約プラットフォームだったので、競合とはマーケティング予算をどこまで確保するかという札束の殴り合いになってしまって、ワンプロダクトっぽい勝負にならざるを得なかったんです。徐々にマーケ勝負みたいになっていったので、そこで付加価値を出し続けるのが難しいなと思ったんですよね。顧客は「サイトはどこで予約しようと変わらないから、基本安いところで予約します」という方が多いので、そうなってしまうと売り上げが数十億出たとしても、自分自身がやる意義があんまり感じられませんでした。一方で国内に目を向けてみると、日本の人口は減少していても、高齢者は25年間増加し続けていて、今は65歳以上のシニアだけで約3600万人(2021年9月15日現在推計)います。その人たちが余暇のために貯蓄していて、どこかに行きたいという思いを持っているアクティブシニアが多いというインサイトを得ました。でも実際には介護が必要な方は諦めてしまっていたり、そもそもこの領域でビジネスをオペレーション強く回している企業が少ないという現状を見て、プレーヤー型モデルだったら一番参入しやすいんじゃないかなと思って始めました。私自身、祖父が全盲で祖母が認知症だった背景もあり、自分自身がやる意義を強く感じています。
編集 補足として、プラットフォーム型やプレイヤー型と呼んでいるものがどういうものなのか、少しだけご紹介いただけますか。
古田 プラットフォーム型とは、いわゆる旅行の手配だけすれば済むような形で、自身がお客さんと一緒に旅行する必要はないものです。プレーヤー型と呼んでいるのは、受注型の企画旅行で、一緒にお客さんと旅行に行ったり、その旅行自体をより作り込んであげる必要があるもので、個別の案件に丁寧によりそうものです。
変化の要因
編集 ありがとうございます。結果的に事業領域をEXUTRA(エクストラ)から介護旅行にピボットすることになったのは、古田さんご自身の自我のどのような変化が要因となっているのですか。
古田 ピボットした感覚は実はそんなにないんです。先にもお話したように、YOLOTとしては人生を変えるような体験機会の提供というのを掲げており、色々なセグメントに刺さると思っています。同じミッションの下で対象となるセグメントを変えて、提供する価値をより個別カスタマイズ性の高いものに変えたっていう感じですね。介護旅行の事業を実際に初めてみると、これまでとは事業の手触り感の違いがありました。例えば、昨日もお問い合わせで、88歳ですい臓がんの父親を持つ女性のお客様から、「父の寿命が近くて年内もつかどうかなので最後に旅行に連れって行ってあげたい」というお問い合わせをもらって。お客さんは右上肢麻痺だったのですが、短い距離なら自足歩行ということだったので、左側に手すりがあるバリアフリーで、介助しながら入れる内湯があって、紅葉が綺麗な場所を巡るプランを作ったり、カメラマンの撮影を手配したり、とかっていうのをやってるんです。この事業を始める時点ではあまり考えていなかったんですが、実際には旅行の手配を通して売上が立つこと以上に幸福度が高まるというか、自分の事業が人の人生のためになっているのをめちゃめちゃ感じられるようになってきていますね。
自分自身との向き合い
編集 確かに今の話聞いてちょっと鳥肌が立ちました。すごいことだなと。引き続き、自我の部分についての質問なのですが、今年IFD※1を実施したことで何か変化はありましたか?
古田 そうですね、もともと相対的に人より自我について考えてきた方だと思うのですが、「なぜ相対的に人より自我について考えてきたのか」自体を考えるきっかけになったのがNewでした。もともと哲学的な問いをずっと考えてしまうことがあり、例えば生きる意味とはなんだろうとか、宇宙はなぜ存在しているのだろうとか、石に命はあるのかとか、ちっちゃい頃から考えてはあーでもない、こーでもないと考えていました。最近改めて哲学の勉強しているんですが、やっぱり面白いなって思っていますね。科学は物事がどう成り立っているかといったHowの部分が対象だと思うのですが、なぜあるものが在るかというWhyところに対する疑問は哲学だと思っています。哲学の分野では三千年ぐらいの歴史の中で色んな人が「生きる意味とは」って説いていて、めっちゃ面白いんですよね。IFDを通して、なぜ自分が在るのか、という思考回路になっているかを振り返る良い機会となりました。
※1FD/IFD:個人がよりよい人生を送るために、環境と自我の相互作用を通して自身の特徴(らしさ)が形作られてきた過程を時間軸を入れながら構造理解し、今後長期にわたり熟達していく方向性や目標を紡ぎ出すこと。そして現状との差分を明らかにし、自我と環境の両方に配慮しながら社会と共創する熟達を歩む土台を整えるプロセス。長い時間軸をとって実施されるFDに対し、新入社員や投資先起業家、その候補者を対象に短期間で負荷をかけてインテンシブ(集中的)に行うのがIFDです。
編集 古田さんの中で結婚が大きな転機だったと伺ったのですが、ここで変わった価値観を具体的に教えてください。
古田 結婚に対する価値観がいい意味で変わったのが先ほどもお話しした2019年の10月ぐらいで、実際その二か月後ぐらいにプロポーズしてるんです。諸藤さんとのセッション以降、仕事とプライベートという二項対立ではなく、自分を起点にあらゆるものを取り込み学習し続けていくことが大切だし、そういう起業家になりたいなと思ったら「俺、結婚していいじゃん。」と思ったのを覚えています。
結婚をしてからは、夫婦で自分たちの子どもについての話す機会が増えまして、前まではReapraでいう百年続くとか永続するとかとかがずっと遠くに感じていて全然手触り感なかったのですが、自分の子どもってなると結構リアルで。2100年ぐらいだったら自分の子どもは生きるだろうなって考えると、こういう世界であってほしい、という願いが色濃くなってきました。あと変化としては、高齢者を見てこの人も誰かの子どもなんだなって思うようになり、今まで生きてきた30年であまり思ったことはなかったんですが、より時間軸をリアリティを持って体感できるようになりましたね。80ぐらいのおばあちゃんを見ると、この人は戦後にきっとこういう時代背景で生まれたんだろうなとか、そう考えるようになりました。自分自身歴史が好きなので、脈々と繋がれてきた歴史を、なるべくより良い形で繋ぎたいなと以前より強く思っております。
描いている未来
編集 次は未来の話に移っていければと思っていて、今後のご自身の事業に対する向き合いポイントや、直近で描いている未来像があれば教えてください。
古田 大きい囚われがいくつかあるので、それに向き合いつつ、来年には単体事業で黒字まできちんと持っていく、そして多角化していきたいなと思います。「誰しもが自分の可能性に挑戦できる世界を創る」ために、「人生を変えるような原体験の提供」をやっているので、YOLOTを通して旅行をした人に「余命半年でもこんなこと出来るんだ」と感じてもらったり、家族にとっては「最後に一緒に旅行に行けたのが宝物の思い出」となるような旅行を提供したいです。介護旅行はすごく意味があることだと思っていますし、介護のみならずあらゆるセグメントに対して、よりよい方向に人生を変えるような原体験を提供していきたいなっていう風に思っています。
加えて、ゆくゆくで言うと僕自身の哲学的なテーマで「より良い生と死は何か」ってずっと考えていて、これを科学したいと考えています。例えば「かわいい子には旅をさせよ」とか「移動距離とクリエイティビティは比例する」ってよく言うじゃないですか。旅行に行って思考が広がったとか、学びが広がったとかまだ感覚的にしか伝わっていない旅の効用をきちんと大学とかと組んで共同研究とかして科学したいと思ってます。認知症予防と旅行回数の相関データとか、介護旅行と幸福度の関係とか、そういった実証データをもとに事業を作り込んできたいです。
編集 最後に、何か現時点で自我や事業に関してアップデートしようと考えていらっしゃることがあれば、お聞かせください。
古田 起業してから事業、そして自分に向き合っていく中で、コンディションが大きく浮き沈みすることがありましたが、少しずつ良い方向により自信をもって取り組めているなと思います。このコロナ禍で旅行業全体が大変な中ではありますが、ウェブ経由で個人のお客さんからお問い合わせをいただく機会も増えてきました。今までユーザー数や売上といった数値でしか満たされていなかったものが、世の中に必要な事業だとより実感を伴って誰かのためになっているイメージが見えてきています。これが組織として回るようになれば凄く幸せなことだと思ってるので、早くそこまで行きたいですね。そこに行けたらまた次の未来が見える気がしています。
編集 本日はありがとうございました。
------------------------------------------
Reapra Bookはこちらから全文ご覧いただけます。フィードバックフォームもありますので、ぜひご感想、ご意見をいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
