
仕事でも、仕事じゃなくても【ブックレビュー】
「大奥」「きのう何食べた?」などの、漫画家よしながふみさんのインタビュー集をご紹介します。
ライターの山本文子さんが、よしながふみさんにインタビューした内容だけで一冊の本になっています。
元々、人のインタビューを読むのが好きなんです。
作家じゃない人で、一芸を極めた人のエッセイとかも割と好きでよく読みます。
たぶん“自分の知らない世界”を覗き見るような感じ、が好きなんだろうと思います。だからNHKの「50ボイス」「100カメ」とか「プロフェッショナルの現場」などのドキュメンタリー番組も好きです。

エッセイよりもインタビューの方が、その場で思ったことをそのまま文字にしているので、本音に近いと思うんですよね。インタビュアーの腕も大いに関係する部分ですが。
noteでも、無名人インタビューさんの記事をよく読ませていただいてます↓
さて、目次はこちらになります。
第1章 漫画に心奪われて――幼少期/小学時代/中学時代
第2章 夢に見た漫画家へ――高校時代/大学時代/商業デビュー/『月とサンダル』
第3章 BL誌でも、少女誌でも――『本当に、やさしい。』/『ソルフェージュ』/『1限めはやる気の民法』/『こどもの体温』
第4章 解決しないことの中に――『執事の分際』/『彼は花園で夢を見る』/『ジェラールとジャック』/『西洋骨董洋菓子店』
第5章 ドキュメンタリーのように――『愛すべき娘たち』/『それを言ったらおしまいよ』/『フラワー・オブ・ライフ』/『愛がなくても喰ってゆけます。』
第6章 女性と仕事――『大奥』
第7章 一緒に歳を重ねて――『きのう何食べた?』
第8章 ずっと漫画と――これまで/これから
あとがき
コミックス解説
第一章は、よしながふみさんの漫画が好きな方はもちろん、1970〜90年代の少女漫画が好きな方も「同じの読んだ!わかるわかる〜」となる内容で、私なんかはモロ被りで嬉しくて身悶えしました😁
それに加えて、自分でも物語を作る方にとっては、よしながふみさんの物語作りのスタンスとか、価値観みたいなものを知ることで、自分の作品や思考を振り返る機会にもなるんじゃないかなあ、などと思ったりもします。
ただ……小説書くくせに読書感想文は苦手なので(だってnoteって、スンバラしい書評を書くライターさんがひしめいてるしね!)下手な感想を書くよりも、感銘を受けた部分を抜粋して、それに一言ずつ所感を挟む感じでレビューしていく方が、よりカラスっぽい内容になるかなと思いました。
第一章「漫画に心奪われて」
山(山本):──小学校では家庭科の授業で調理を学ぶ機会がありますが、授業以外でも自分で作ったりしていましたか?
よ(よしながふみ):四年生くらいの時から、休日に早起きして朝食を作るようになりました。親には「怠け者の節句働きとはまさにこのこと」などと言われましたが(笑)「ガラスの仮面」に出てくる姫川亜弓さんというキャラクターが食べていた朝食が素敵で、真似したくなったのがきっかけです。
亜弓「そうクイーン・メリー(紅茶の名前)がいいわ。薄く切ったオレンジを浮かべて……それから私をひとりにして」……マヤより亜弓さん派のカラスです。
ねとらぼ2021年人気投票、こちらの記事によるとランキングは以下↓
1位 姫川亜弓(さもありなん)
2位 速水真澄(よっヘタレ社長!安定の白目クオリティ)
3位 北島マヤ(一応、主人公だしね……いや好きだよマヤも)
4位 青木麗(麗様、お元気かしら)
5位 月影千秋(先生、夏場はもっと涼しい格好して下さい)
この章ではたくさん漫画が出てきますが、がっつり「沼にハマった」のは「ベルサイユのばら」だそうで、そこで主従萌えが刻まれた、ということらしいです。
で、二次創作で漫画を描き始めて、BLにも目覚めてゆく、と。
あれっ小説書き始めたきっかけについて、同じようなこと言ってる人がnoteにもいたぞ(いや私かw)
第二章「夢に見た漫画家へ」
第二章では、高校時代と大学時代、同人誌活動から商業デビューに至る流れが語られています。
ただ、二次創作をすることで、自分がどんなタイプの性格をしたキャラが好きかの気づきは得られると思います。オリジナルだけ書いていると、話が先行になってしまうことが多く、どんなキャラを自分が好きなのかは明確に自覚しにくいと思うんです。
逆に二次創作の場合は、自分はこういうキャラが好き、こういう関係性が好きというのがまずあるので、そこを出発点にできるのは大きいんじゃないでしょうか。特にBLだと、自分が好きなものを描くというのがすごく重要で、結局それが面白さにダイレクトに結びついたりするんですね。熱量が勝るというか。
そうBLは“萌え”が重要。そして、なんか私はめちゃ肯定された気がする!だってnote界隈ってオタクもBLも少数派な気がしていたので。いやあ励まされますね。
第三章 BL誌でも、少女誌でも
初期の頃の作品にスポットを当てて、当時の創作上のエピソードなどが語られます。

山;──(「ソルフェージュ」について)久我山の友人であり、田中のもう一人の恩師でもある後藤は、妻子もいる常識人で、作中ではある意味、二人を取り巻く社会というものの象徴だったと思います。その後藤が二人の関係に憤ることで、久我山と田中の関係が社会的にインモラルであることが改めて明示されて、二人だけの世界で恋愛をしていたわけではないことを痛烈に感じさせます。
よ:(略)私の場合は、恋愛が描かれていてもいなくても、登場人物が必ず社会と繋がっていることを描くことに面白みや快感を感じている気がします。なので作中に恋愛要素があるときも、どんなに恋愛をしていても四六時中恋愛のことだけを考えて生きていけるわけないよね、と思いながら描いています。
仕事があって、家族がいて、人生全てを恋愛が占めているわけではない、という観点で描きたい、という気持ちは、このとき既に明確にあったと思います。
ああ、なるほどです。
私の体感ですけどテーマが「恋愛」の漫画に関して言えば、こういう“キャラクターの背景も含めた世界を描こうとする”感覚って、少女漫画と女性(+青年)漫画が分かれる大きな要素じゃないかなーと思います。
少女漫画で恋愛メインの場合は、キャラを取り巻く世界観って、お相手+学校の友達+親、止まりのことが多いなと。いやもしかして、その方が“子供のリアルな視点”に近い……のかもしれないな、とも感じるんですけども。
青年漫画とか女性漫画だとこれに「職場」とか「親戚」というファクターが加わったりするのですよ。そうすると一気に世界が現実味を帯びて登場人物も増えるというか。
よしながふみ先生の作品にある、ジャンルが中世ヨーロッパだろうと日本の時代劇だろうと“地に足ついた”感は、ここからきてるのかもしれないと思いました。
そして、ちょびっと自分を振り返って反省したりして。
いや……第三者を登場させるって、確かに物語をぐんと深くするんですけど、作劇の難易度もドカンと上がるので。
山: ──その西園寺の照れに繋がってくるのが、バレリーナだった離婚した母親です。ドイツに行く母親との別れの時に照れて手を繋げなかったことが西園寺の心に蟠りとして残っているわけですが、照れの話であると同時に「ホームパーティー」や「僕の見た風景」にも重なるような、喪失の後の話だと思いました。残された人たちの日々の話なんだなと。
よ:(略)もとの状態には復元できないような喪失を抱えている人の話が好きなんだと思います。何も悪いことはしていなくても悲しいことが起こるものが好きというのと同じですね。(略)才能もそうですが、世の中には自分のコントロールが不可能な範囲で決まってしまうことがとても多いでしょう。どんなに正しく生きようと、人に優しくすることを心がけてるいい人だって、災害や事件が突然降りかかってくることはあって、それはその人が悪いからではないし、起こってしまうことは自分でコントロールできないんですよ。私が家族ものを好きなのも、それと同じなんじゃないかと思います。家族は自分の好きなようには選べないし(略)
……「家族」と「喪失と残された人たち」って、私も好きなテーマなので、ここも共通してるなあなどと勝手に共感しました。
まあ、人間ドラマを書こうとすれば「家族」と「社会」は外せないもののはずで……ただ、面白く描けるかどうかは、また別の話なんだよなぁ、などと。
第四章 解決しないことの中に
「執事の分際」「ジェラールとジャック」「西洋骨董洋菓子店」の創作エピソードなどです。
山;──朝がくると信じて、バトンを繋げていくことが大事なわけですね。
よ: 何かプロジェクトのようなものも同じことが言えると思います。成功する結果まで見届けられるかわからないけど、必ずいつか成果が出ると信じて続けていくしかない。「大奥」のワクチン開発なんて、まさにそういう気持ちで描いていました。それをやっているときに報われることがなかったからといって、無駄ではないんです。生前に名声を得られなかった芸術家だって、後世の芸術に多大な影響を与えているわけです。それでも本人は苦渋の中で生きていたあたりに「人生とは…」と物語を感じたりもするわけですが。
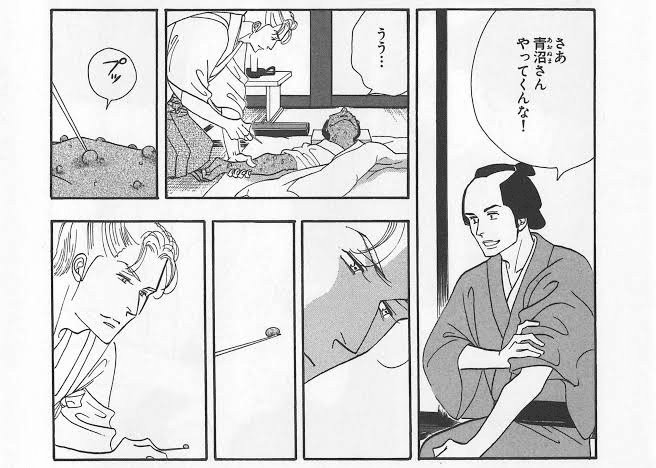
まさしく。人類の進歩って、そういう信念の積み重ねだと思うんですよね。現在に至るまえに、長い長い“これより以前”があるはずで。中世の化学の歴史なんてまさにそのものというか、体制(教会など)からの過酷な弾圧に負けずに、たとえ殺されても、誰かが志を受け継いで真理を追求し続けた、その膨大な屍の上に現代の文明がある、という。
私が科学者を信頼し尊敬しているのも、これこそ人間の崇高さだと思うからです。
そして、名作「西洋骨董洋菓子店」へと。
意外だったのは、連載終了直後は「明らかなハピエン」ではなかった(?)ラストについて「あれってどうなの?」みたいな反応が結構あってショックだった、というエピソード。
そうなんだ…うーんそう言われてみればそうか?いや、私はいいラストだよなぁと感じたので、それはちょっとよくわかんなかった。
山: ──誘拐事件の真相を追ったり解決したりするまでを描くつもりは、その時点で既になかった?
よ: エンターティメント作品の中で、何かの事件に巻き込まれてトラウマを負った登場人物が、事件が解決されたりすることでそのトラウマが晴々と解消されるものがよくあるんですが、物語の展開として納得しつつも、何かをきっかけにそんなにスッパリと解決するものなんだろうかと思っていたんです。トラウマを負った人と似た体験をしている受け手の方が、ドラマの中で事件なり問題が解決してトラウマが解消されるのを目にした時に、つらくなる気がしたんですよね。現実はそんなにうまく行かないじゃないですか。
(略)解決しないとトラウマは解消されず、すっきり幸せになれないのだとしたら、その展開しか提示されないんだとしたら、それはつらいと思って。(略)
失ったものと全く同じものを手にすることはほとんどないし、失くしたことをなかったことにはできないけれと、それは幸せではないこととイコールではないはずなんです。それでも幸せにはなれるよと、そういう話にしたいと思いました。
よしながふみ先生の作品が私の心にガツンとくるのは、きっとこういうところなんだろなぁ。
いやあ、リアルタイムで作品を読めることがとっても幸せだなぁ。

第五章 ドキュメンタリーのように
「愛すべき娘たち」「それを言ったらおしまいよ」「フラワー・オブ・ライフ」「愛がなくても喰ってゆけます。」……現代劇を中心にした作品エピソードです。
山: ──これもその時までに考えていたことが滲み出たのでしょうか
よ:(略)特に女性作家で漫画を描いていると、恋愛ものが描けないことでクリエイターとしては落伍者なように見られる空気が当時はありまして。純粋な褒め言葉として、たとえ描いているものがBLでも「いい恋愛ものを描いている人は、やっぱりいい恋愛をされている感じがしますね」とか言われるわけです。
私自身に向けてじゃなくても「人を愛したことのない人は可哀想」みたいな言葉を投げられたり。でも、私は人を愛するということを最上の善とすることに懐疑的でして、だって、自分の愛する者を殺されて収まりがつかずに相手を殺したり、そういう諍い、ひいては戦争のようなものだって愛があるからなんじゃないの、と
アガサ・クリスティの短編のなかで、ミス・マープル(だったかな?)の台詞に「愛はこの世で最も恐ろしいもの」みたいなのがあって、読んだ時は中学生くらいで、よくわかんなかったんですけど。大人になるにつれてそういうことか、と腑に落ちました。
古典ミステリの犯人の動機って「愛か金」ですもんね。「憎しみ、恨み」も愛から派生してる場合が多いわけで。
あとポアロの「人間の悲劇は、人が本質的には変わることができないという事実から起こる」的な台詞も印象に残ってます。
思春期の読書って、その後の人生に対する考え方とか価値観に大きな影響を及ぼすよね、という。考えてみればアガサ・クリスティってとっくに死んだ昔のイギリス人ですけど(1976年1月12日没)そうやって現代に生きている日本人に影響を及ぼしてるんだから、偉大な作品は国も時代も越えるなあと思います。
私は、売れる漫画家と売れない漫画家にはたいした違いはないけれども、食える漫画家と食えない漫画家には大きな差があると思っていて、食えないということは、その先の仕事にも繋がっていかないことになるので(略)
この辺りは、まあ、覚悟の違いってことなのかもしれません。それとも自戒のつもりなのかも。ああ、小説売るにはどうしたらいいんだ問題……。
第六章 女性と仕事
そしていよいよ名作「大奥」の話。
山: ──男女の恋愛ものを描いてみたいという気持ちがあったのですか?
よ: それはもうずっとありました。でも描けずにいて、描けると思った「大奥」でも、ここまで世界を歪ませないと恋愛が描けないという己の心の闇を知るわけですけれども(笑)要するに、現代ものでは、自分は男女の恋愛を描けないんだなと痛感したんです。そういう意味でも「大奥」はぴったりの舞台装置でしたし、描きたい話を描くためにも、男女を逆転させるというのが生きてくるなと。

この場面はもう号泣…
山: ──そのケージ(檻)にうってつけだったのが大奥という場所だったのですね。
よ: あそこはまさに繁殖のための場所だったんですよね(略)
有功(=お万の方)が「けど私も男です!」と、あなた(家光)の体も私だけのものにしなければ我慢できないという場面があるのですが、これは有功が男だからとか、支配欲求があるとかそういうことではないのです、と(ドラマの時に、堺雅人に)言った覚えがあります。
江戸時代は「人間」という言葉がないから「男」と言っていますが、性別としての男ではなく「人」という意味で、血が流れている一人の生きた人間です、という叫びなんです、と。
山:──有功は人生を道具のように使われてきた人ですよね
よ: そうなんです。ずっと我慢して出た言葉なんですよね。「大奥」を描き始めて割とすぐに、血族で繋ごうとする政の歪さを感じていました。血で繋ぐということは、男も女も人権を奪われるわけで、それは将軍も同じなんです。

綱吉;大体辱めとは何じゃ!?私の前でまぐわえと言った事のどこが悪いのじゃ!!
私は毎夜!!毎夜そうして添い寝のものに己の夜の営みを聞かれてきたのだぞ!何が将軍だ!若い男達を悦ばせるために私がどれほどの事を床の中で覚えてきたかそなたに分かるか!?
綱吉: 将軍というのはな、岡場所(=非公認の私娼が集まる街)で体を売る男達よりもっともっと卑しい女の事じゃ。ふふ。ふふふふふ……
この「大奥、誕生秘話」を読むためだけにでも、この本買う価値ありますよ!
いや衝撃でした。だってフィクションとか……なんなら現在のリアル王族も普通に、世継ぎを〜とか言われて子供作らないといけなくて、それは“ロイヤルの世界では当たり前”と、スルーしてる自分がいたんですよ。でも考えてみればそういうことだなと。
大奥の世界は、女性が力仕事も政治もして、なおかつ子供も産まなきゃいけない世界なんですよね。でもって男性はなにも労働せずに“子種として”大事にされる、あるいは“そこにしか価値がない商品として”扱われる、というね。誰かと結ばれる=子孫を残す、ことの意味。それを改めて考えるきっかけになるという。
……これが漫画で読めるって日本はすごい国ですよね。
日本のサブカルすげえなって、最近は漫画にしか感じないんですけども。うん、高校生以上の女子に、手にとってほしいなあ。
第七章 一緒に歳を重ねて
こんなに長く連載が続くと思わなかった、という「きのう何食べた?」
よしながふみさんの好きな「BL」と「食べ物」ずっとやりたかった「弁護士もの」(作者は法学部出身)。全部載せにしたお話、だそうで。
民事弁護士のシロさんと、美容師のケンジが美味しいご飯を作ったり食べたりして仲良く暮らすという現代劇です。
ドラマにもなったんで、皆さんご存知ですよね。
数あるBLとの最大の違いは「親、そして彼らを囲むまわりの人々と社会」がしっかりガッツリと描かれていること。あとラブい要素はあっても、ラブが話の中心じゃないこと。
主人公の二人は、最新刊ではそろそろ還暦(!)。
お爺さんになるまで連載続くかなあ。続いてほしいような……すこし怖いようなw
山: ──登場する料理やシロさんが料理を作ることが直接物語に関わっていないことに、読み進めるときの心地よさを感じているのですが、意識的に話の筋と引き離しているところはありますか?
よ: そうですね。「西洋骨董洋菓子店」を描いていた時も言っていたのですが、あれもケーキが登場する話ではあるものの、ケーキで人が救われる話ではないんですね。橘が言っていたように、ケーキはすごく幸せなことがあった時なんかの素晴らしい脇役なんです。とても悲しいことがあった人がケーキを食べて幸せになれることはないと思って私は物語を書いているので、論理的にはそれと同じです。料理を作ったからってシロさんの心に劇的な変化が起きるわけではないし、料理が何かを解決してくれるわけでもない。だから長いこと描けるんだとも思います。
この作家さんは「フィクションとはいえ我ながら白々しい嘘」と感じながらお話を描くことができない方なんでしょうね。現実劇でも他の時代でも、自分の中のルールに反することは書かない、描けない。それがブレない感じというか、説得力に繋がっているのかもしれません。
良いものを生み出せる作家ってどっかそういう頑固さというか、筋の通し方をする方が多い気がします。ポイントなのはそれが独りよがりではなく徹底して「読者ファースト」という点でしょうか。
影響を受けたという作品群から学んだ姿勢かもしれません。
そして話はご近所の主婦友、佳代子さんのことへ。
結構、隠れファンも多い脇役なんじゃないですかねー。そのへんに普通にいそうな「おおらかでわりと料理上手なオバちゃん」。

シロさんとケンジだけの話だと閉じて狭くなってしまうから、最初から必ず友達を作るつもりでした。しかも、ゲイについて何の見識もなくて、それゆえにちょっと無神経で、主人公とほどよく距離が離れている人を。佳代子さんも言っていますが、シロさんは友達だけと自分の家族ではないからこそフランクに接せられるわけで、そういう関係性の人が主人公の近くに欲しかったんですね。無関係で無責任だからこそフラットに付き合ってくれる人がいたら、主人公はどんなに楽になるだろうと思って。
ほんとBLって、ストーリーの尺が短いからってのもあると思うんですけど、直接はなしに絡まない人って出てこないんです。そもそも女性が出てくることも稀だし、ご近所さんみたいなキャラは皆無。
だから佳代子さんのような、コストコでまとめ買いした6本パックの歯磨き粉を分け合う友達、みたいなのは初めてみたかもなーと思います。けっこうエポックメイキングなキャラなんじゃないかな。
第八章 ずっと漫画と――これまで/これから
この章では、今までのインタビューを振り返っての総括と、今後の作品づくりへの気持ち、読者に向けたメッセージなどが入っておりまして、個人的には
「創作する後輩たちにご自身が何かを伝えるとしたら?」という問いかけに対するお答えが「おおー!」と、思いました。
……が、それは実際にこの本をお手にとって読んでいただいた方がいいかなと思います。よしながふみの作品が好きで、自分も後を追いたい、漫画家になりたいと考えている人がいたら(こういう本を買う人の中にはたくさん居そうですけれども)間違いなく勇気をもらえる言葉だと思います。
巻末には、よしながふみの作品の紹介が載ってて、なかなかお得感があります。
「大奥」映画になったの知ってるけど、原作読んでないわ〜という方!
「きのう何食べた?」ドラマしか観たことなかったけど好きだったなあという方!
原作を読んでみましょー
あと「西洋骨董洋菓子店」も、かなりおすすめですよ〜
漫画好きとして保証します。絶対に面白いっす!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
