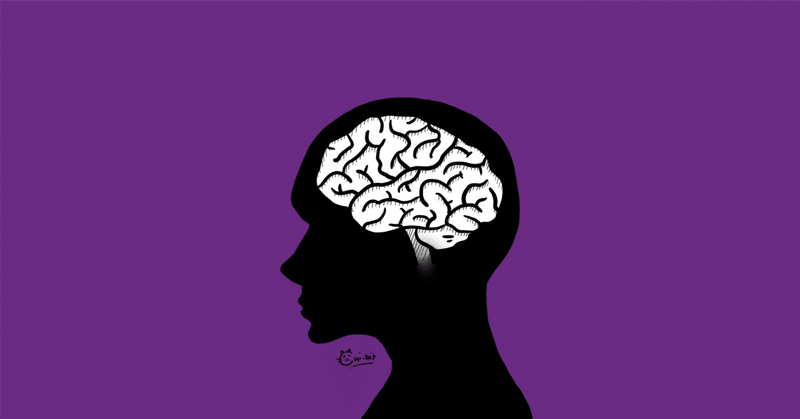
『人を賢くする道具』「第6章 分散された認知」のまとめ
この章には何が書かれているのか?
話の起点となるのは「大きな制御装置」の話。
昔はコンピュータが小型化していなかったので大きな部屋に巨大な装置があり、多くの人がその部屋で一緒に仕事をしていた。今からみると非常に効率が悪い。
しかし、そうして一緒に仕事していたことで暗黙的な「コミュニケーション」が行われていたと著者は指摘する。つまり、大きなパネルを操作しているなら「ああ、あの人は今温度設定をしているんだな」と他の人から見てわかったり、バルブを閉めているなら「ああ、あの人は今栓を閉じているんだな」と他の人から見てわかったりする。つまり、情報共有が行われている。
それに対して、それぞれの人がパソコンに向き合って操作している状況では、他の人がいったい今何をしているのかがわからない。もし仕事が協調的な動作を必要とするならば、そうした情報共有の有無は大きな違いになってくる。
ここから著者は、人間というのは脳単体で(あるいは脳に閉じこもって)考えているのではなく、あらゆる外部・環境を一つの"道具”として思考しているという話につなげる。というか、"道具"というのは現代から見た恣意的な表現で、むしろ生物の進化で考えれば、それは"前提"だろう。外部・環境において生き残るために、そこにある情報を利用するというのは当然のことだ。そういうのがうまくいくように人間という生物は進化してきたわけだ。
しかし、現代ではどうにも個人・脳・心単体で行われているという捉え方が多く、それに基づいて作られるシステムはあまり人間に優しくない。
たとえば人間の脳にとっては「正確さ」というはほぼ重要ではない。ライオンのヒゲが正確に何本なのかを覚えていることは、生存にとってちっとも利益にならない。そんなことよりも「ライオンっぽいもの」を認識、「危なそうな雰囲気」を発しているなら即座に逃げる、という判断ができた方がはるかに有利だ。
よって人間はそうした理解を助けるもろもろを得意としている。対してテクノロジー(というかデジタル・コンピュータ)は、正確さを得意としている。この二つは役割が異なるわけだが、テクノロジーが生活の中に入り込み、そちらに産業の重点が置かれることによって、人間にもテクノロジー的な正確さが要求されるようになってしまっている。当然得意ではないことをやらされているのだから人間は「ポンコツ」に見える。でも、それは不当な評価ではないか、というのが著者の主張である。これは本書でも強調されているが、むしろ本書全体に統一するメッセージでもあるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
