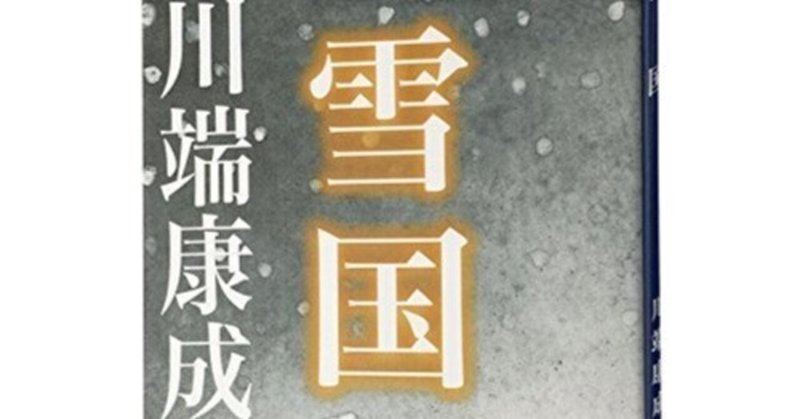
エッセイ:究極の絶対審判と雪国
デカくて強い言葉が好きで、「究極」も「絶対」も「審判」も全部デカくて強くて、自分という存在から程遠い言葉だから、3つ組み合わせて「究極の絶対審判」と造語しました。
そんな言葉を何かあるごとに呟いています。これは究極の絶対審判が近い。この状況は究極の絶対審判のようなものだ。究極の絶対審判の導きである。仕事中だろうが、なんだろうが、いつだってどこだって。
造語なのでもちろん意味なんかない。呟くのはただ精神の安寧のため。南無阿弥陀仏と同じなのです。
川端康成の「雪国」を人生で初めて読みました。
日本文学史上恐らく五指に入る超有名な冒頭、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という美しすぎる情景描写から、流れるようにイカれた抒情の持ち主である島村という限界中年男性の激烈にキショい思索に触れることになり、かなり面食らいました。
人生で初めて「伊豆の踊子」を読んだ時にも思ったことですが、もしかして川端康成という人物はとんでもない猟奇的な変態的性嗜好があったのではないかと勘繰ってしまいます。つまり、行間に含まれる違和感に対して抱く抒情と変態性がどうも紙一重である印象があり、その紙一重さが何故か「美」を備えて儚くも鈍く輝いて見える瞬間がある。
しかも恐らくそれを意図的に演出しているようなのです。
恐ろしく美しいのに悲しみを携えた抽象的心理描写の連続で、エロゲで人物感情と男女恋愛に対する理解を鍛え上げたキモオタクの僕にとってはあまりに難解としか言いようがありません。非常にかみ砕いて解釈するのであれば、移ろいゆく男女恋愛の心理表象における決別と終わりの物語なのでしょう。
島村とかいう妻子持ちのイカれ中年、駒子とかいうイカれ中年に狂ってしまった不幸な生い立ちと複雑怪奇な感情のレイヤーを持つ超高難易度女、葉子とかいう薄氷一枚でギリギリ保たれている陰鬱で先行きの無い男女恋愛の全てを意図せず滅茶苦茶に蹂躙する意外とデカい感情を持ってる女。
三者三様のイカれた行動が何かしらの、あるいは全ての「決別」に収束していく様は、やはり終わりの美があるように感じました。
最後、駒子が葉子のこと割と好きで、「これって広義の百合か?」と余計に混乱してしまったけど、そんなことはなく、あまりにいきなり物語が終わったので、百合疑惑の混乱と相まって感情をかき乱されてしまいました。
悲劇に成りきる前に終わるというあまりに高度で本当に恐ろしい文章の羅列です。
それに比べて何が「究極の絶対審判」なのでしょうか。
自身の精神的負荷への軽減を信託する言葉としてあまりに弱すぎて、美しくなくて、ほとほと嫌になってしまいました。
そうやって終わっていくのかな。
終わりに対する恐怖だけ、ずっと背後に付き纏っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
