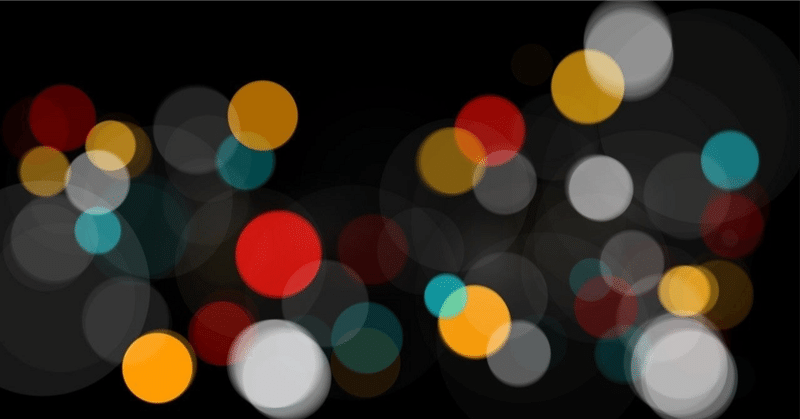
『すももももも』 隠れた傑作、これいかに? 第14回
『すももももも』 1995年 / 日本
監督:今関あきよし 出演:持田真樹、浜崎あゆみ、加藤晴彦、他
今関あきよしという監督は、日本映画史の中にどういった位置付けをされているのか、今一つ伝わってこない憾みがあります。
あまりまともに言及されていないというか、たまに名前を見かけても少女趣味、ロリコン趣味というイメージでしか語られていない気もするのですが、それが04年に児童買春他の罪で実刑判決を受けている事と関係しているのだとしたら、非常に残念な事です。
もちろん私とて、芸術家もできれば高潔な人物であって欲しいとは思いますが、作品は作品として、ロマン・ポランスキーやウディ・アレンの映画も好んで観ますし、岡村靖幸や電気グルーヴのCDも変わらず聴いています。
今関監督は83年、大林宣彦製作の『アイコ十六歳』で劇映画デビューしていますが、私は大林作品ほどロリコン趣味は感じません。
少女たちへ向けられた今関監督の視線は、性的なニュアンスではなく、もっと内面的なものへの共感といえます。
より砕けた言い方をすれば、それは「応援」の目線です。
逆に、今関作品では大人達、とりわけ学生にとって最も身近な大人である教師への目線は厳しいです。
それは時に、ほとんど断罪に近い。
今関作品の多くは、少女達の人生の一時期をなす振幅と結び付いているため、思春期以前の幼い少女はあまり描かれないし、過剰な映像的ギミックもなく、やたらとヌードが登場する事もありません。
描かれるのは多くの場合、思春期の不安定な心の揺れや屈折で、それは死のイメージと結び付いている。
自殺や、自殺に見える行為は、今関作品にはしばしば扱われるモティーフです。
優等生的でポジティヴな生命力に溢れている大林映画の少女たちとは違い、
今関作品の少女は人生に倦怠し、若さを持て余し、鬱屈している。
大林映画の健全なヒロインは、学校に行かず海辺で煙草をふかしたり、他人を見下したり、同級生の男子や教師にちょっかいを出し、ふと気まぐれに死を選び取るような事は、絶対にしません。
本作は、この5年前に発表された『16歳のマリンブルー』と姉妹編のような雰囲気があります。
いずれも女子高生が主人公で、時に周囲からは奇行に見えるほど、自我を持て余し、現実と折り合いがつかずにいる。
思春期特有の不安定な自意識をデフォルメして投影したようなキャラクターで、
観る人によってはそれは決して誇張でも何でもなく、正に自分自身かもしれない。
両作ともに神奈川の海辺の街を舞台とし、
主人公には兄弟姉妹もいるし、一応は友達や仲間もいて、必ずしも社会から孤立しているわけではない。
いずれの主人公も自殺やそれに近い死を試み、片方は生還し、片方はそのまま戻ってこない。
主人公が瀕死の状態で階段を這う場面があるのも、両作に共通する特徴です。
原作物だった前者と較べると、本作は監督自身によるオリジナル脚本であり、その分より「死のイメージ」が大きく前景化したとも言えます。
主人公・小桃が意図的に口を閉ざす設定の上、映画の大部分を彼女の心象風景で構成しているので、
セリフが少なく、ポエティックな幻想性が強まっているのも特色。
とはいえ、ほとんど同じテーマを扱っていても、5年の空きがあるので映画の雰囲気はかなり違います。
『16歳のマリンブルー』は初期の今関映画の雰囲気を大きく引きずっていて、
絵画的な遠景ショット、アフレコされた平板なセリフ、波音や虫・鳥の声など自然音のフィーチャーなど、
小津安二郎作品の影響が濃厚(鎌倉を舞台にしているせいもあります)。
一方本作は、主演俳優陣のクオリティが上がっている事もあり、
ずっと現代的で、90年代らしいポップさもあります。
フィックスの映像が古風で成熟している一方、モノクロの併用や動的な移動撮影、斬新なアングルなど、多彩な技巧を盛り込んで対比させるやり方は、自主映画出身の今関監督がもともと得意としている手法です。
本作で特に重要だと思うのは、女優時代の浜崎あゆみが演じる妹・栗子の存在。
ほとんどセリフがない小桃の描写と心象風景がメインとなる本作において、
現実的な行動と言葉で切り込んでゆくのは栗子の役割です。
意識不明でベッドに横たわる小桃にささやきかける彼女のセリフは、
ヴィヴィッドなようでいて、その裏に姉への切実な真情が込められています。
思わずはっと胸を衝かれる展開で、描写として非常に映画的でもある。
恐らくこれは、監督自身が主人公に訴えたい言葉で、
つまりそれは、小桃に共感して自己投影している観客に向けられた言葉でもあるわけです。
この場面はその後の、平静を装っていた栗子が衝動的に泣き崩れる売店のシーンに呼応しています。
今関監督の態度はいつも、少女(あるいは少女に象徴される若い世代)に対する、応援の色合いが強い。
これが7年後の長編『十七歳』になると、
主人公が画面に向かって直接『逃げるなよー!』と叫ぶまでになります。
今は、「逃げる事も大切」という風潮になってきました。
私もそう思います。
でも、今関監督の言う「逃げるな」にはもっと多彩なニュアンスと奥行きがあり、
だからこそ、死に興味を持つ少女を繰り返し描いてきました。
今関監督は『十六歳のマリンブルー』の劇場用パンフレットに寄せたコメントで、こう締めくくっています。
「今、本当に生きていくって大変な時代。
戦争も飢えも何もないけど、ホントの自分を探して、自立していくってことがムズかしい、自分の生きる存在価値を見いだすなんて、とてもじゃないけど、できやしない。
僕はもう(まだ)30才だけど今の十代の人に同情すると同時に、陰ながら声援を送っている。みんなガンバレ!!」。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(見出しの写真はイメージで、映画本編の画像ではありません)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
