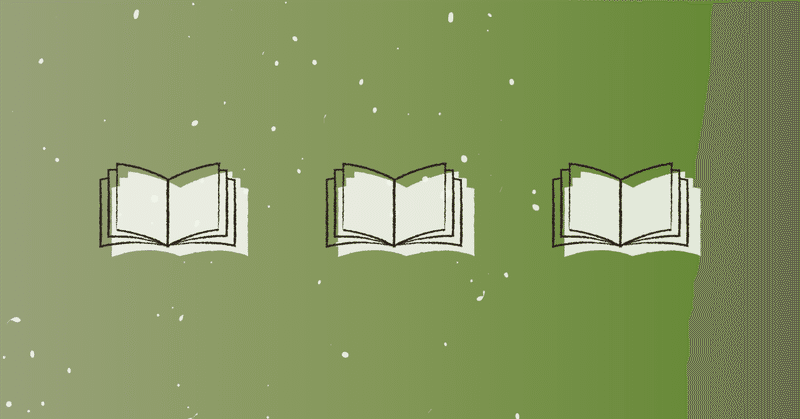
事業承継で経営革新を果たした企業(共同代表 峯尾編)
こんにちは、Rand.共同代表の峯尾 喜一(みねお きいち)です。
自らが事業承継経験者である藁科と共に、事業承継の後継者支援サービス Rand.の共同代表を務めています。
今回は、ファミリービジネスの先行研究やフレームワークについて、解説をしたいと思います。自身の事業承継や支援のヒントが得られたら幸いです。ぜひご一読ください。
ファミリービジネスにおける「ベンチャー型事業承継」の研究
ファミリービジネスとは、創業者一族が企業経営を担っている、もしくは、株式を保有している会社のことで、一般的に「オーナー企業」「同族会社」「同族経営」などと呼ばれています。欧米では早くから経営学の学術分野として注目されています。そこでは「ファミリービジネス」と呼ばれ、長寿企業や業績好調のヒントを探る重要な切り口として様々な研究が行われています。
また、(一社)ベンチャー型事業承継の定義によると、ベンチャー型事業承継とは、若手後継者が世代交代を機に先代から受け継ぐ経営資源をベースに、新規事業・業態転換・新規市場参入等の新たな領域に挑戦することで、永続的な経営を目指し、社会に新たな価値を生み出すことを言います。第二象業との違いは、同族経営および世代交代のタイミングに限定していることです。
日本企業の特徴
ここで、日本企業の特徴を見てみましょう。中小企業白書によると、日本では中小企業が全企業の99.7%、付加価値額は全体の約53%を占めています。また、付加価値額の変化を開廃業・存続企業別に見たときに、存続企業が付加価値額を伸ばすことで日本全体の付加価値額を押し上げていることが報告されています。
つまり、日本の稼ぐ力をより強くするには、特に中小企業で、稼ぐ力を持っていながら後継者不味で廃業せざるを得ない事業や経営資源を引き継いだり、新たに創業したりした企業が軌道に乗るまでの支援を強化することで、これらの層の付加価値額を伸ばしていくことが極めて重要と言えます。
さて、日本国内でもファミリービジネスの研究が始まり、その特徴が明らかになってきています。中でも注目すべきは、ファミリービジネスは、収益性、安全性、成長性の全指標で他の一般企業を上回っているという点です。米国を始め、世界各国でも同様の分析結果が明らかになっています(後藤、2018)。そして日本は、世界の中でも数と歴史において最大・最古の「ファミリービジネス大国」(奥村、2015)。創業から100年以上が経過している老舗企業の数は3万社を超え、世界でダントツ(2位の米国は2万社弱)。そんな長寿企業には、じつはファミリービジネスが多くを占めているそうです。
なぜ、ファミリービジネスが長寿や堅調な業績を達成できているのか。ここで少し経営学の研究(フレームワーク)として、「スリーサークルモデル」と「4Lフレームワーク」の2つをご紹介します。
スリーサークルモデル
R.TagiuriとJ.davisによって1982年に提唱されたファミリービジネスの基本的なフレームワークの1つで、ファミリービジネスにおけるステークホルダーの重なりを表しています。マネジメント(経営層)、オーナーシップ(株主)、ファミリーの3つのサブシステムが重なり合い、作用し合い、依存し合っているシステムであることを表しています。このフレームワークから見えるファミリービジネスの特徴として、奥村(2015)は、「ファミリービジネスの経営がいわゆる普通の企業と異なるのは、まさにファミリーという非経済的な要因が経営に入り込むことである。」と述べています。
また、このフレームワークは、それぞれの円が事業の拡大や時間の経過により拡散していく中、それぞれが重なり合う部分で発生しやすい課題についても分類して表現してくれます。①の領域では、株式の持ち分や分散した株式の取りまとめ、相続対策など。②の領域ではビジネスにおけるファミリーの関与度合い(ファミリーを社員として雇用するなど)。③の領域ではビジネスの経営状態や配当。④の領域ではファミリーを含めた多様なステークホルダーとの利害調整、コミュニケーションが、課題になりやすいとされています。

4Lフレームワーク
経営者がたどるべき学習と人生のサイクルについて検討する助けになるフレームワークです。

L1の段階では、基本的なビジネススキルを社外で学ぶことが推奨されています。社外の経験が後々のファミリービジネスに寄与するからです。
L2の段階では、自社のビジネスを学ぶことが求められます。L1で学んだことを活かし、自社のビジネスの中で特別なものとは何かを認識することが必要で、これを「企業の永続的な価値観」としています。
L3の段階では、自社のビジネスを率いることを学びます。ファミリー企業のリーダーとして、先述のスリーサークルモデルで見たマネジメント(経営陣)、オーナーシップ(株主)、ファミリーという3つのサブシステムそれぞれにおいてリーダーシップが求められます。
L4の段階では、自分からビジネスを手放すことを学びます。このフレームワークで最も重要なパートと言われています。これは後継者にビジネスを譲り、自身がビジネスの一線を退くことであり、いかにスムーズに後継者に譲ることができるかが事業承継の鍵となります。
また、Justin B. Craig, Ken Moorse(2017)は、リーダーは、「主導権を手放す事において主導権をとる」ために、「手放すこと」を学ぶ必要があると述べています。同研究では、ファミリービジネスの経営者の退任スタイルを以下の4つのタイプに分類して示しています。

L4は、通常滅多に起こることではありません。多くの経営者にとっては一度しか経験しないことです。それが決断を難しくさせているのですが、スムーズな事業承継の観点からは、大使型やガバナー型の退任方法が望ましいといえます。自分がどのタイプになっているのかを客観的に見るヒントにして頂ければ幸いです。
今回の解説は以上になります。ファミリービジネスの学術研究は、海外を中心に活発に行われていますので、また興味深いものがありましたら記事にしたいと思います。また、今回解説したフレームワークなどと照らし合わせながら、実際の企業を例に解説する記事も作成予定です。どうぞお楽しみに。
私たちが関わることで、承継者の主体的な行動を促し、事業承継を「宿命」から「自己実現の舞台」へ変えていく。そして、事業承継を契機に魅力的な新サービス・プロダクト、事業改善策が生み出され、彩り豊かな地域社会を実現することに貢献していけたらと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
