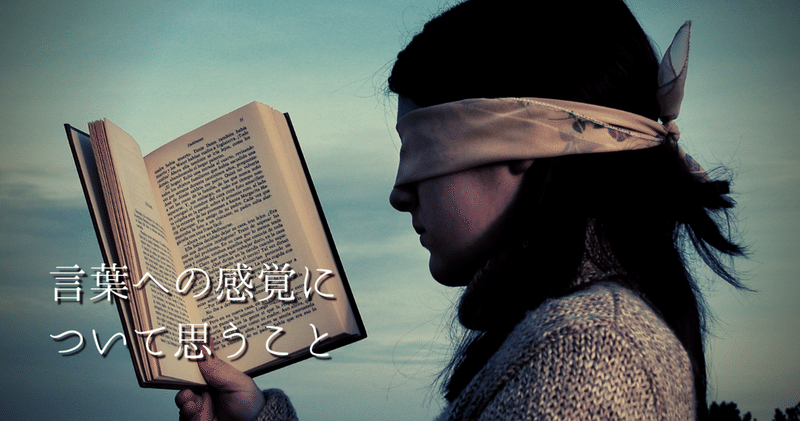
言葉への感覚について思うこと
「ググる」はGoogleで検索するという動作から来た言葉で、ネットで調べること全般を指して使われる。「ツイートする」はTwitter に投稿することを指している。「LINEする」はLINE を使用してメッセージを送信することを指し、「フェイスブック」はFacebook という実名登録が基本になっているネットワークサービスを指す。
わたしはこれらの言葉を小説の中で使わない。
最近、文芸誌に載っている小説などでも、これらのような言葉、ある特定の企業が提供するサービスの固有名詞や商標などから生まれた言葉を無自覚に使っているものが散見される。このことにわたしは危機感を覚える。アマチュアの作品ならいざ知らず、文学の前線であるはずの文芸誌、それも純文学に寄ったものの中に、自覚的にならまだしも、無自覚にこういった言葉を安易に使っている小説が掲載されるという事態は、由々しきことではないかと思う。
意図的に使うのであればいい。こうした用語は時代と密接にひも付き、あっという間に過去のものになるリスクと同時に、その時代を象徴できるかもしれないという力も秘めている。時代を浮き立たせるためにあえて「LINEする」といったワードを使うことには意味がある。でも多用されているほとんどのケースで、作者はそのことに無自覚であるように思える。
例えば90年台の小説にジュリアナ東京やヴェルファーレを登場させる、ポケベルでのやり取りを記号的に取り入れる等をすると、今の人が読んでもなんのことやらわからないものになる。同時に、その時代を色濃く反映したものにもなる。時代の先端に深く刺さりこんで、その時代と心中する意図で書かれるものであれば、今しか通用しないような言葉を使うことに意味がある。しかしそういう意図でないものに、こうした用語を使うことにはもう少し敏感であるべきではないかと思うのだ。
例えばスマホ。スマートフォンの略語だが、わたしは最初にスマートフォンと呼ばれた端末、ウィルコムのW-ZERO3という機種を持っていた。それがスマートフォンと呼ばれる前から使っていて、ある時、その種の(当時は物理フルキーボードが搭載されていて、WebブラウジングなどがPCと同じようにでき、オフィスソフトのファイルなどが開けるもの全般を指した)ものをスマートフォンと称するようになった。わたしはそのタイプのスマートフォンを、新型が出るたびに買い替えて使ったが、その後PHSのサービス自体がなくなり、ウィルコムも姿を消した。
そして、その後登場したiPhone に代表される、端末のほぼ全面が液晶モニタになっているタイプのものをスマートフォンと称するようになった。
つまり、スマートフォンという言葉が指しているものは時代によって異なっている。それにここに出てきたのでついでに言えば、PHSという通信端末はピッチという略称で呼ばれ、携帯電話とは電波形式の異なる通信手段として共存していた。持っている端末に対して「それピッチ? それとも携帯?」といった会話が割とふつうに行われていた。
今、このような会話を作中で出せば、若い世代には意味がわからないだろう。ピッチとはなんなのか。携帯という言葉はまだ残っているけれど、いずれ「スマホ」だけになるやもしれない。
小説に時代性が反映されるのは致し方なく、また同時に、ある程度時代性を取り込まなければ現代に問う意味もないという事実はある。しかし、どういう状況であれ、小説を書くのであればそこに使う言葉には自覚的であるべきだと思う。「LINEする」と書いている著者のうち何人ぐらいが、この言葉が特定の企業が生み出した一サービスの名前にすぎず、10年後には意味を消失しているかもしれないということを認識しているのだろう。そこまで考えてあえて書くのならまだしも、そうでないまま無自覚に書いているとしたら、小説書きとして意識が低いと言わざるを得ない。
一方で、現代の若い世代を描くにあたり、「LINEする」を使わずに彼らのコミュニケーションをどうやって描くのか、というのは難問だ。
わたしは「雪町フォトグラフ」という作品を書くときに、このことをまず考えた。この作品は写真部の女子高生を描くもので、写真というアートと女子高生、そして北海道の上川郡にある東川町という町を描く、という三つの柱で取り組んだものだった。
写真を描き若い世代を描くのでインスタも避けられない。Instagram という写真中心のSNSがあり、それを積極的に利用するユーザをインスタグラマーと呼ぶ。インスタ映えといった言葉まで生まれるほどのサービスとして浸透しているこれを、やはり避けて通ることは難しい。加えて女子高生が友達とやり取りするのに、LINEのようなものを使うのはもはや当然で、これも避けられない。
そこでわたしは似たような架空のサービスを捏造した。インスタみたいなサービスとしてPhorest(Photo + Rest)と書いてフォレストというサービスをでっち上げ、そこに写真をアップするユーザが「フォレスター」と呼ばれていることにした。さすがにフォレスト映えという言葉は出さなかったけれど、それを追求して写真を撮る人たちの存在は書いた。
またLINEのようなサービスとしてCanverse(Canvas + Conversation)と書いてカンバスというサービスも作った。それぞれどういうものかという説明をした上で登場させ、以降この世界ではインスタみたいなフォレストとLINEみたいなカンバスを使って登場人物たちは動き回る。これによって特定のサービスの呪縛から作品世界を切り離した。
リアリティを問うという意味において、現実世界にあるサービスの名称を避けるということにも賛否はあろうと思う。しかしわたしは、インターネットというテクノロジーを使用したそういうコミュニケーションや、デジタルデバイスの存在、活用方法などを描写しさえすれば、ある程度時代性を伴ったリアリティを描けるのではないかと考えている。それにもちろんそうしたことを考えた上であえて「LINEする」と書いている作者に対しては異論ない。わたしとその人は問題意識は似通っていてたどり着いた結論が異なったというだけだと思う。しかしそうした考察がなく無自覚にこういうワードを使うことに対しては大いに異議がある。特に、純文学系の文芸誌がそういうものを安易に掲載するという事態は文学の後退を招くのではないかと、本気で思う。
最近読んでいて特に気になるのは「LINEする」「ツイート」「ググる」の三つ。すでに一般化しつつある言葉であるだけに、小説のプロであればそれが一般化している事自体に疑問を投げるべきだろうし、それに気づかせるようなテーマをこそ書くべきではないのかと思えてならない。
というようなことをプロでもないわたしがこんなところで主張したところで滑稽なだけではあるけれど、純文学の衰退はなにも電子書籍や他ジャンルの台頭やら読者のレベルの低下とかそういった問題だけが原因なのではなく、提供している側の意識低下によって読者が離れているという事実もあるのではないかという気がする。
なお、最後に公平のために、わたしが無自覚に作中に使った商標について書いておく。それは「ラジコン」という言葉だ。
正直に言うけれど、知らなかった。一般名詞だと思っていた。しかしもちろん、小説を書く人間として、「知らなかった」では許されない。文字通り無自覚に使用したのだ。言葉に対して感覚が行き届いていなかったという事案である。しかも「ラジコン」という言葉は過去に何度も使ってしまっている。前述の「雪町フォトグラフ」にも出てくるし、そのスピンオフである「サイカイカフェ」にも出てくる。商標だったとは…。
こういうこともあるのだ。使う言葉にはどんなに意識的になっても意識しすぎるということはないのだろう。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。

