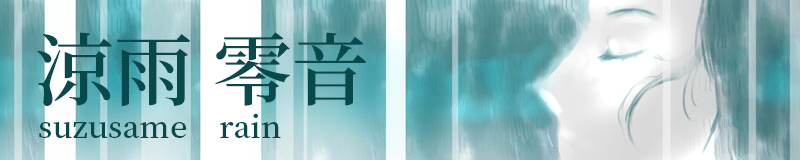[戯言戯言日記] 作者の言いたいことは
6月28日(月)
わたしはアマチュアの端っこの方ではあるものの自分では小説だと思うものを書いている。自分の書いた作品については一応作者だ。
これまで先人の書いた小説を読んで、この作品のテーマはこういったものだとか、この作品を通して作者が表現したかったのはこういうことだとか、そういったことに想いを巡らすことが多かった。しかし自分が書く側になってみて、「作者」というものは果たして言いたいことがあるから小説を書くのだろうか、ということが疑問になってきた。作品を読んで「この作者はきっとこういうことが言いたいのだろう」と想像するのは読者の楽しみで、そのように読者に伝わるものはそれなりに本質としてあるだろう。作者の主張はきっと、読者が受け取ったものとそう遠くないところにあることが多かろう。が、果たして作者はそれを伝えようという想いで作品を書いたのだろうか。
わたしが最初に書いた小説は、一番書きたい作品を書くだけの力を自分が備えていないという自覚があったため、その前の習作のつもりで書いたものだった。軸になるモチーフ(そのときは人工的に作られた人間)を決め、作品の世界観を決め、だいたいのストーリーを決め、そして「言いたいこと」を見据えた。この作品を通じて届けたいものはこれだ、と「言いたいこと」をはっきり持って書いた。
その結果できたものは小説になっていない小説らしきなにかで、今読み返すと文芸になっていないレベルのものだった。この作品を書いたおかげで小説とは何かということがいくらか見え始め、二作目として一番書きたかった作品「雪町フォトグラフ」を書いた。
「雪町フォトグラフ」で作者が「言いたいこと」はなにか。もし国語の問題でそのような問いがあったとしたら、あの作品を読んでくださった皆さんはなんとお答えになるだろうか。
わたしがあの作品を書いたとき、作品を通して言いたいことというのは一切なかった。町を描きたかった。そこに暮らす少女たちを描きたかった。少々風変りだけれど魅力的な人物を描きたかった。ただ、それだけだ。これを伝えようという想いは無かった。
が。今読み返してみると、作品の底に流れている想いのようなものを感じる。書いているときには意識しなかったもの。表向きのストーリーからは少々離れたところにある、伝えたいというよりは感じてもらいたいといった種類の何か。
これまでわたしが読んできた先人たちも、もしかしたらこうだったのではないか。なにかを伝えようとして書いたのではなく、自分の内側から出てきた衝動に任せて書いた結果、自分のどこかにあって自分でも意識していなかった何かが伝わるものになったのではないか。
そもそも自分が何を言いたいのか、わたしは自分で本当にわかっているのだろうか。おそらくわかっていない。小説を書いてみるとそれが見えてくる。なにかを感じて書かれた創作のどこか裏側みたいなところに、意識の外にある何らかの問題意識が染み込む。書いたものを読み返すことでそれを感じ、もしかしたらわたしはこういうことを言いたいのではないか、と想像できる。
ここ数年小説を書いてみて、国語でよく問われた「作者の言いたいこと」というのは、実は作者自身もよくわかっていないのではないかと思うようになった。よくわからないから書くのではないか。自分の中の得体の知れない何かが筆を取らせる。書かずにいられないという衝動が頭をもたげる。そうして書かれたものは緻密に計画を立てて書いても自分のコントロールから外れて奇妙な形を帯びる。それを読み返すことで自分の知らなかった自分と出会う。
作者は言いたいことがあるから書くのではなく、自分の言いたいことに耳を傾けるために書くのかもしれない。
いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。