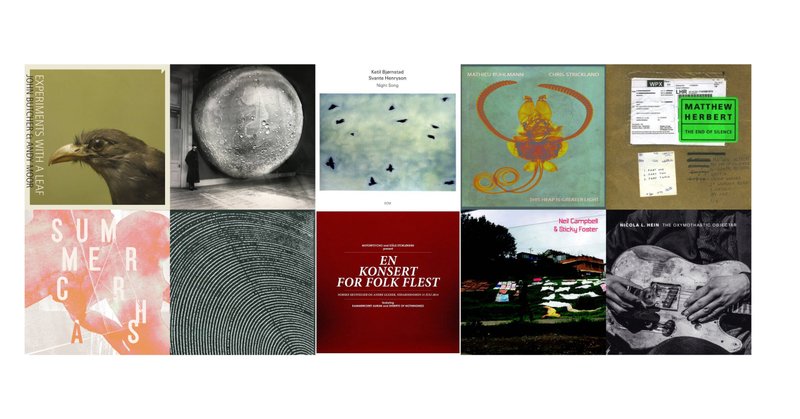
My Timeless Favs of 2010's: Part 8
71-80枚目。
71. John Butcher & Andy Moor [Experiments with a Leaf] (Unsounds / 2015)

John Butcher(サックス)とAndy Moor(エレキ・ギター)による、おそらく即興演奏の録音。なんとなく音としてサックスとギターがあるのはわかるけど、南国の珍しい鳥たちによる聞いたこともないような鳴き声のようにも聞こえる(ジャケットの撮りに引っ張られている部分もあるかも)。フリー・ジャズとは違って、それぞれがガチャガチャと収拾がつかないような演奏しているわけではなく、二人で似たような音を繰り返したりしていて、つがいの鳥たちが会話しているみたい。Part 1のなかでAnne-James ChatonとAndy Moorの共作について書いたけれども、Andy Moorは本作とそのときとで結構違うアプローチをしていて、彼の音楽的なボキャブラリーの豊かさにはすごく感心した。
72. Joseph Clayton Mills [Huntress] (Suppedaneum / 2014)

人が住まなくなってボロボロになった人里離れた家のピアノでも弾いているかのように、ぽろん…ぽろん…と音がその場で静かに、そして少しかすれ気味にこだまする。物音や言葉、それらすべてが静かで美しい音楽。本作(CD)は封筒のなかに詩集みたいな本と一緒に入れられていて、それも含めて、まるで誰も住んでいないはずの家から手紙でも届いたかのよう(ホラー映画のはじまりみたいな感じじゃないよ!)。このSuppedaneumというレーベルはそういった繊細な作品をいくつも発表していて、そのムードが結構好みなので、今でも新譜を追いかけてる。
73. Ketil Bjørnstad & Svante Henryson [Night Song] (ECM / 2011)

試聴: ECM Website
ECM、毎回新作は聴くようにしているけれど、僕のなかでは強く印象に残るような作品は少ない。聴きやすいものが多いからか、はじめて聴いたときに何かを感じても聴いているうちに褪せていってしまう。今回Foodの[Mercurial Balm]やStefano Battagliaの[The River of Anyder]などを選ぼうかと思って久しぶりに聴きなおしたら、どちらも全然響いてこなくてびっくりしたくらい。けど、本作はちょっと違った。Ketil Bjørnstadのピアノはあまりジャズっぽくないし、Svante Henrysonのチェロもクラシックか何かを聴いているような感覚。[Night Song(夜の歌)]というタイトルにも納得できる。部屋の電気を消してベッドに入ってから聴くと、遠い昔の記憶がぼんやりとよみがえってくるような感覚に陥る音楽。あ、それとジャケットもきれいで好き。
74. Mathieu Ruhlmann & Chris Strickland [This Heap Is Greater Light] (Glistening Examples / 2016)

当時どこに共感したのか、今では自分でもよくわからない。けれども、本作を聴いて、そのあと当時作っていた作品を聴いて、ここに一度デモを聴いてもらいたいなと思ったのが始まりだったんだなあ、と、しみじみ思ったり(その作品は[The Notional Terrain]として翌17年に発表されました。よかったら聴いてね)。物音や環境音などの具体音がアナログ感のあるシンセの音と一緒になった作品で、その有機的な質感だったり、微妙にノスタルジーを感じさせる雰囲気をもっていたり。そういった部分に共感して、たぶんこのレーベルなら…!と思ったんでしょうかね。もう昔の話なのでうろ覚えだけど、いまだに本作のそういった部分に惹かれて、今でも時々聴いたりしてる。2010年代に限らず、僕野人生においてもかなり重要な作品でした(さすがにちょっと大げさか?)。
75. Matthew Herbert [The End of Silence] (Accidental / 2013)
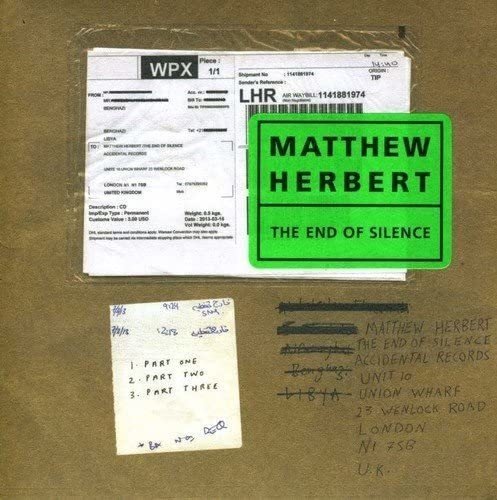
作るときには自分も同じような状況になることが多いのに、聴き手にまわるとテーマありきの作品(のそのテーマそのもの)に対してあまり興味がわかない。その作品の主語がやけに大きくなってしまうのがつまらないと感じているのと、僕としては日常のすごく些細な部分を拡大して眺めるほうが好きなので。本作はジャーナリストが撮った映像に含まれていた約10秒間の爆撃の音をサンプリングして作ったというもので、やはり主語が大きい。そしてシリアス。重い。いっぽう、音の面だけ取り出して聴いてみると、約10秒間ぶんのサンプリングという時間的な短さを感じさせない。色々な音があるように思えて、50分以上もある長さのなかで「あ、この音前に聴いたかも...」となる瞬間があまりない(たぶん引き延ばしたり何したりと加工しているんじゃないかと思う)。音の加工の仕方、あるいはそれの演奏の仕方にはMatthew Herbertのカラーが強く表れているので、好き嫌いは聴き手によってはっきり分かれるかと思う。けれど「約10秒間の素材からサンプリングする」というポイントと、「音のジャーナリズム的なショッキングさ」というポイントにおいて、本作はこの10年のなかでも印象的な作品だった。僕のなかでは当時は印象的だったけれど、今の社会情勢を見ていると再度聴きなおして評価し直す必要がある作品となるかもしれない。
76. Maya Dunietz & Tom White [Summer Crash] (Singing Knives / 2017)
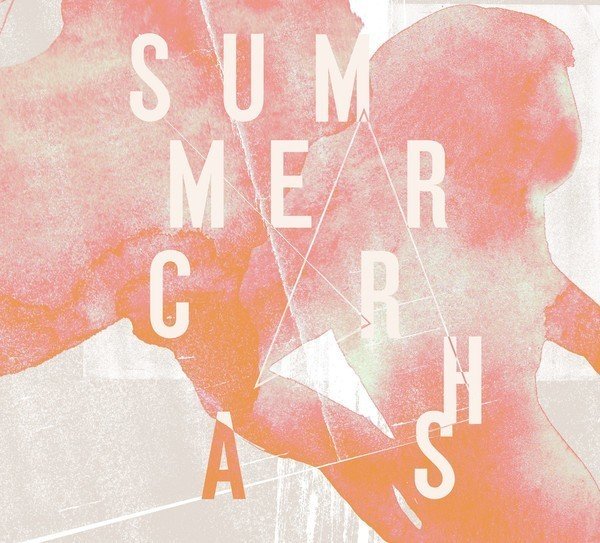
Maya Dunietzが声とピアノを、Tom Whiteはテープの操作などをおこなった作品。Maya DunietzはGhédalia Tazartès(!)とも仕事をしていて、ピアノを弾いても声を出すときも何とも不気味だったり個性的だったりするところが面白い(あのGhédalia Tazartèsと共演している時点でもう想像に難くないですよね)。そこに粘り気のある変なビヨビヨという音やインパクトの強いループをTom Whiteはオープン・リールから生み出す。ここでの両者の音はあまりぶつかり合ったりすることなく、寄りそうように聞こえてくる。Vimeoなどでは一緒にライヴをやっている映像も観られるけれど、そこでのパフォーマンスとはちょっと違うというか、あまりまとまりがないので、あんまり参考にならない、というか、してほしくないです(なので本記事には載せません)。
ところで去年Tom Whiteが来日する際、本人から直接声をかけていただいて共演できたのは嬉しかった。録音作品とずいぶん違う演奏だったので、本人がそれをどう思ったのかは怖くて聞けなかったけど、楽しんでくれていたならいいんだけどな。
77. Metasplice [Infratracts] (Morphine / 2013)

試聴: Boomkat / M1('Arterial Protocol') / M3('Dioxinition')
粘り気のあるアシッドな電子音の放射。MorphosisことRabih Beainiによる「モルヒネ」というレーベル名がよく似合う。Morphosis自体クラブ・ミュージックというフィールドからやや離れた存在に思えたけれど、Metaspliceによる音はそのまた何倍も次元の違う雰囲気がある。ビートだの反復だのがあって体裁こそかろうじてダンス・ミュージック的なものを感じさせるものの、よく拡大して見てみると地球外生命体みたいな、それも感情をもち合わせていない細胞みたいな変なもののよう(あれです、「エイリアン」とかじゃなくて「遊星からの物体X」みたいなそれ)。アルコールとかで感覚とか判断力が麻痺しているなかめまいが一時にやってきて、みたく、頭の中でぐわんぐわんと鳴り響いている感じ?気持ち悪くて気持ちいい。
78. Motorpsycho & Ståle Storløkken [En Konsert for Folk Flest] (Rune Grammofon / 2015)

北欧のバンドMotorpsychoによるライブ盤。パイプ・オルガン(会場が教会なのかな?)やオーケストラなども参加していて、結構大所帯でのコンサートのよう。声楽とかも入ってる。しかも10曲にトラックが分かれてけれど、途中に休みもなく、1時間以上の長い演奏となっている。プログレッシヴな音楽のなかでもかなり贅沢じゃないだろうか。そして、本作をはじめて聴いたときには[Tales From Topographic Oceans(邦題: 海洋地形学の物語)]以降のYesの匂いを感じた。そして知らない言語で歌われる声楽隊の特殊なメロディーなどを聴いていると、行ったこともない北欧の風景を勝手に思い浮かべてしまう。レコード屋さんのプログレ棚を見るとよく国別で分かれていて、これじゃ僕ら素人にはわからないよ…と思った記憶があるけど、ひとくくりに「プログレ」と言っても、国によって雰囲気がだいぶ違うんだもん。そういう意味でなのか、と認識するきっかけにもなった。
ちなみにプログレッシヴ(progressive rock)とプログレ(prog. rock)のあいだには意味に微妙な違いがあるらしく、後者はあまりいい意味ではないらしい。昔のプログレ・バンドの真似事をしているバンドとかの音楽を指すみたいなので。使う時は気をつけようっと。
79. Neil Campbell & Sticky Foster [Enge Chaleur Telegraphique] (Chocolate Monk / 2018)
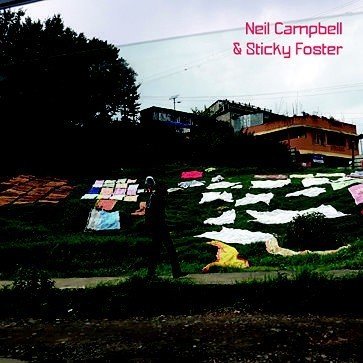
"Neil Campbell, Sticky Foster and Richard Youngs: Colour Out of Space 2020"
Chocolate Monkの作品はどれも変わっているというべきか、LAFMSとも違う雰囲気なのでざっくりとした説明はなんとも説明が難しい(しかも試聴がなかなかできないので買う時もこう説明する時もかなり難しいのです)。本作はNeil CampbellとSticky Fosterによる25分ほどのライヴ盤。上の動画はこの2人組のほかRichard Youngsが参加して作られている音と映像なので、本作とはちょっと違う雰囲気なのですが、テープレコーダーか何かから出している変な録音と語りとが丁寧に続いて風景が流れていく。ライブだというのに長回しの映画のように音のシーンが緩やかに変化していくのは僕のなかでは結構面白かったポイントで、あらかじめ展開を打ち合わせしたかどうかは分かるすべがないけれど、そういったことを想像しながら聴くのも楽しかった。
80. Nicola L. Hein [The Oxymothastic Objectar] (Shhpuma / 2019)

(※上の動画はCDとは別で演奏の様子なので、厳密にはCDの内容と異なる部分があると思うけれど、この演奏のほうが内容が伝わりやすいと思います)
冒頭から金属ノイズ。そりゃジャケット写真にあるテレキャスターがものすごく傷んだ状態だもん、普通に弾く人だとは考えがたい。カセットで録音したかのようにローファイかつディストーションまみれの音。音質はクリアーなんだけど。ギターを「ギターとして弾く」ことを拒絶したような、メロディーらしいメロディーがほぼ皆無な演奏。楽しすぎる。笑いが止まらない。
ところで、(コロナの影響で来られるのかわからないですが)今年の秋ごろ東北沢OTOOTOなどで演奏するそうです。来日公演をやることになったら観に行きたいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
