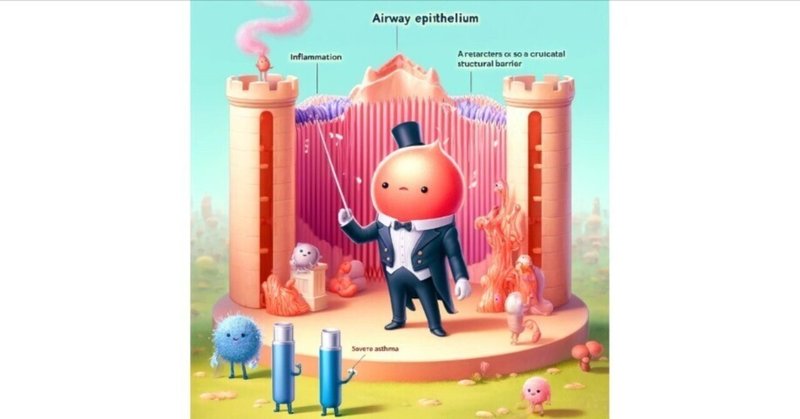
気道上皮:炎症の指揮者、重要な構造的バリア、そして重症喘息の治療ターゲット
Russell, Richard J, Louis-Philippe Boulet, Christopher E Brightling, Ian D Pavord, Celeste Porsbjerg, Del DorscheidとAsger Sverrild. 「The airway epithelium: an orchestrator of inflammation, a key structural barrier and a therapeutic target in severe asthma」. European Respiratory Journal, 2024年3月7日, 2301397. https://doi.org/10.1183/13993003.01397-2023 .
喘息は、環境に対する過剰な炎症反応と気管支収縮反応によって特徴づけられる多様な病理を持つ疾患です。この病気の臨床的表現は、時間を経て環境要因と宿主要因の相互作用の結果であり、遺伝的な感受性、免疫の調節不全、気道の再構築を含みます。宿主と環境の間の重要な接点として、気道上皮は環境的挑戦に直面してホメオスタシスを維持する上で重要な役割を果たします。上皮の完全性の破壊は、喘息病理における多くのプロセスに寄与する鍵となる要因です。
このレビューでは、まず喘息管理における未解決のニーズについて議論し、気道上皮の構造と機能の概要を提供します。
次に、気道上皮で発生する主要な病理生理学的変化に焦点を当て、上皮バリアの破壊、免疫の過反応、リモデリング、粘液の過剰分泌、粘液の閉塞を含む、これらのプロセスが臨床的にどのように表れ、現在及び新規治療薬によってどのように対象とされ得るかを強調します。
序文
喘息は、過剰な炎症反応と気管支収縮反応を特徴とし、さまざまな基礎病理学的メカニズムと異なる臨床的表現を持つ多様な疾患です。
喘息の発生と悪化は、時間をかけての環境要因と宿主要因の相互作用の結果です。環境トリガーには、ダニ、カビ、花粉、煙、その他の空気中微粒子など、主に吸入される抗原、ウイルス、刺激物が含まれます。
食物抗原や変化したマイクロバイオームを含む広範な環境への暴露も、喘息の発展に寄与することが示されています。
遺伝的感受性は特に早発性喘息で重要で、免疫の過反応、気道のリモデリング、気道機能の障害につながります。これにより、可変性の気流閉塞、喘鳴、呼吸困難、咳、痰、悪化などの臨床的表現が生じます。
気道上皮は体と外部環境との間の界面であり、アレルゲン、病原体、環境毒素に対する最初の防御線です。これは、バリア機能だけでなく、環境刺激に対する免疫反応の重要な調整者でもあります。
上皮の構造と機能の変化は、喘息の発症と臨床的特徴において中心的な役割を果たします。喘息患者では、上皮の恒常性が損なわれ、固有の防御機能が低下し、持続的な2型(T2)炎症、バリアの破壊、組織のリモデリングが生じます。
このレビューでは、喘息管理の未解決のニーズについて議論し、気道上皮の構造と機能の概要を提供した後、上皮バリアの破壊、免疫の過反応、リモデリング、粘液の過剰分泌、粘液の閉塞など、気道上皮で発生する主要な病理生理学的変化に焦点を当て、これらのプロセスが臨床的にどのように現れ、現在及び新規の治療法によってどのように対象とされうるかを強調します。
喘息管理における未解決のニーズについて議論し、気道上皮の構造と機能の概要
Unmet needs in asthma management
かつては、気道壁への免疫細胞の浸潤とそれに伴う免疫細胞の活性化、サイトカインの放出が喘息における上皮異常の原因であると考えられていましたが、現在では気道上皮と肺の他の構造成分が喘息の環境リスク因子に直接反応し、炎症カスケードの主要な開始者および調整者であることがわかっています。
現在の喘息治療は、気道壁の炎症と平滑筋の収縮を主なターゲットとしていますが、治療が気道上皮に及ぼす効果はそれほどよく研究されていません。
吸入ステロイドなどのコントローラー療法は、多くの患者の喘息症状を改善しますが、約5~10%の患者は重度の疾患であり、最大量のコントローラー療法を適切な治療順守で受けても症状と喘息の悪化が続きます。
生物学的製剤は、多くの患者にとって有効ですが、T2バイオマーカーのレベルが上昇していない患者には効果がありません。一部の患者は、炎症下流標的に影響を与える生物学的製剤では対処されない炎症経路や他のメカニズムを持っているため、部分的または反応がありません。
最近承認された生物学的製剤テゼペルマブ(上皮サイトカインである胸腺ストローマリンポポエチン(TSLP)を標的とする)は、T2バイオマーカーのレベルが上昇していない患者において効果を示しており、上皮サイトカインを標的とする生物学的製剤が喘息病理の広範囲な側面を治療する可能性があることを示唆しています。しかし、これらの療法が気道上皮の構造と機能にどのような影響を与えるかは明らかではありません。
Structure and function of the airway epithelium

気道上皮は、線毛細胞、クラブ細胞、杯細胞、基底細胞、基底細胞上層の5つの主要な細胞型で構成される疑似層状の組織である。
線毛細胞は、粘液に捕捉された物質を除去する役割がある。
クラブ細胞は、気道の防御と修復に関わる物質を分泌する。
杯細胞は、粘液を分泌し、その粘性に寄与する。
基底細胞は、損傷後に分泌細胞と線毛細胞を再生する幹細胞を含む。
単一細胞RNAシーケンシングにより、気道上皮の細胞同定と系譜が明らかになってきている。
上皮の物理的バリア機能は、細胞間接着の完全性に依存する。
上皮は、抗菌物質や分泌型抗体を産生することで免疫バリアとしても機能する。
大気汚染物質は、上皮細胞間接着の破綻や線毛機能障害を引き起こす。
上皮の損傷は、"アラーミン"と呼ばれる炎症性サイトカインの放出を誘発し、免疫応答と修復を引き起こす。
重症喘息の病態メカニズムと、上皮を標的とする治療法が概説されている。

気道上皮で発生する主要な病理生理学的変化に焦点を当て、上皮バリアの破壊、免疫の過反応、リモデリング、粘液の過剰分泌、粘液の閉塞を含む、これらのプロセスが臨床的にどのように表れ、現在及び新規治療薬によってどのように対象とされ得るか
Airway epithelial barrier disruption
気道上皮バリアの破壊により、アレルゲンや病原体が侵入し、感作と慢性炎症が引き起こされる。これが喘息の発症、持続、増悪の主要な要因とされている。
アレルゲン刺激によって上皮細胞間接着が破綻し、アレルゲンの侵入が増加する。これにより、肥満細胞やタイプ2自然リンパ球が活性化され、さらに上皮バリアが損害される。
喘息患者では、接着因子E-カドヘリンの発現が低下しており、これに関連して上皮間葉転換が起こる可能性がある。
上皮損傷に伴う線維化性サイトカインの放出が、上皮バリアの悪化と気道リモデリングの悪循環を引き起こす。
喘息患者では、上皮細胞の再生機能が低下しており、この障害が気道リモデリングに関与すると考えられている。
ウイルス感染は、上皮バリアを破壊し、喘息患者ではIFN産生が低下しているため、上皮損傷が進行する。
喘息治療薬の作用機序の一つが上皮バリア機能の改善であり、バイオ医薬品などの新しい治療アプローチが期待される。
しかし、現時点では、上皮バリア障害の臨床的な指標がなく、治療効果の評価が困難な状況である。
Immune hyperreactivity
喘息では、気道に対する過剰な免疫反応が起こり、炎症性サイトカインが過剰に産生・放出される。
喘息患者の上皮は、基礎状態および吸入アレルゲンやウイルス感染時に、TSLP、IL-25、IL-33などの上皮サイトカインを高産生する。
これらの上皮サイトカインは、自然リンパ球やT細胞を活性化し、2型炎症を促進する。
2型炎症に関与するIL-4、IL-5、IL-13は、気管支収縮、粘液産生、気道リモデリングなどの喘息症状を引き起こす。
一方で、中性球性炎症も喘息の病態に関与しているが、その位置づけは不明確である。
吸入ステロイドは炎症を抑制するが、根本的な疾患修飾は困難であり、生物学的製剤の有用性が期待されている。
上皮サイトカインを標的とした生物学的製剤(テゼペルマブ)は、2型炎症を抑制し、喘息症状と肺機能を改善する可能性がある。
Airway remodelling
気道過敏性亢進(AHR)は、気道平滑筋(ASM)の変化に関連しており、喘息の重要な特徴の一つである。
喘息では、ASMの肥大、増殖、過剰収縮が認められる。これには、上皮サイトカインであるTSLPやIL-33が関与している。
TSLP刺激により、マスト細胞とASM細胞が化学因子やサイトカインを産生し、ASM変化とAHRを惹起する。
細胞外基質(ECM)の蓄積と亢進も、気道リモデリングの特徴であり、上皮細胞や線維芽細胞による産生亢進が関与する。
時間とともに進行する気道リモデリングにより、気道が硬く肥厚し狭窄し、可逆性の閉塞が生じる。
吸入ステロイドは、一部のECM成分の低下を示すが、十分な改善効果は得られていない。
生物学的製剤(オマリズマブ、メポリズマブ、ベンラリズマブ)は、一部のリモデリング指標の改善を示す。
TSLP阻害やIL-33阻害は、動物実験で気道リモデリングの抑制を示し、新たな治療ターゲットとなる可能性がある。
Mucus hypersecretion and mucus plugging
健常な気道では、粘液が微生物や塵埃を捕捉し、線毛運動によって排除する。
喘息では、粘液の量的・質的な変化が観察される。
IL-13の産生亢進により、MUC5ACなどの粘液関連遺伝子の発現が増加し、杯細胞過形成が引き起こされる。
非T2型喘息でも、CLCA1やMUC4、MUC5ACなどの発現上昇が見られる。
IL-4、IL-9、IL-13は杯細胞の増生と末梢気道への異所性拡散を誘発する。
IL-13は線毛細胞の機能を障害し、粘液クリアランスを妨げる。
IL-33やTSLPも、粘液形成と塞栓を促進する。
慢性的な気管支収縮も、杯細胞増殖と粘液分泌を誘発する。
粘液過剰産生と排出障害は、気流閉塞、喀痰、増悪などの臨床症状を引き起こす。
吸入ステロイドはMUC5ACなどの発現を抑制するが、薬物治療では粘液プラグの改善が限定的。
抗IL-5/IL-13療法は粘液過形成を抑制する可能性がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
