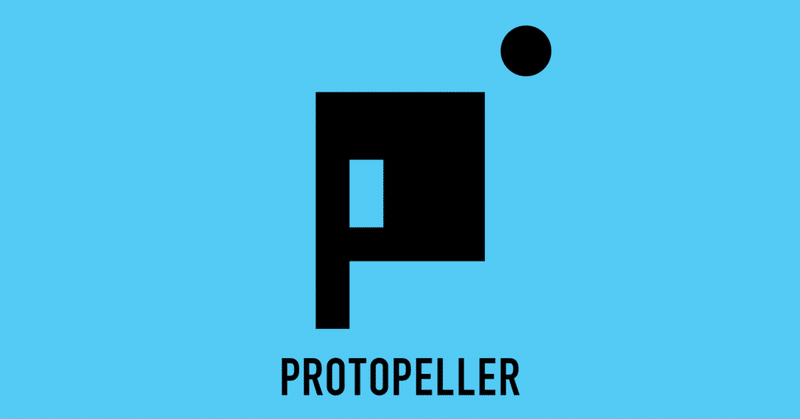
0400 - ことば、えいきょう、じふ、びんかん
t= 5 d= 5
仕事としてテキスト作成やキャッチコピーを作っていることもあるが、言葉には人一倍敏感だなと自負している。
同じ意味でも言い方1つで印象がガラリと変わる。何かしてもらった時に「すみません」と言うのか「ありがとう」と言うのか。左利きのことをギッチョと呼ぶのかサウスポーと呼ぶのか。無職なのかフリーターなのか家事手伝いなのか。
先日、受講しているオンラインアカデミーで語られていた例えも面白かった。
キャバクラに行って、キャバ嬢が「普段は東大の大学院生に通ってるんです」と言うのと、東大のキャンパスの中で、大学院生が「キャバクラでバイトしてます」と言うののとでは、入ってくる情報は全く同じでも印象がガラリと変わる。
たしかにそうだ。語る順番(流れ)も大事というお話。
先日、一緒に地域活動を行なっている仲間と飲んでいた時に「よしふみさんは昔から国語が得意だったんですか?」と訊かれた。
あれ、どうだったっけ?と悩むことなく、全くもって得意ではなかったと断言できる。
そもそもが勉強嫌いだったので成績が良いわけがなく。子供の頃はマンガは大好きだったけど活字の本は1冊も読破したことが無く。読書感想文には毎年頭を抱えつつもんどりうっていたし。少し前に小中学生時代の文集を見つけて読み返してみたが、主語と述語が繋がってなかったりで文法が滅茶苦茶すぎて気が遠くなったし。
そんなレベルだった。
ただ、小学生の頃から「人は『言葉』にものすごく影響を受けるんだな」とは思っていた。もちろん、当時はそこまでハッキリと意識できていたわけではないが。
友達が言った言葉。先生が話してくれた言葉。親から言われた言葉などなど。誰かの一言が、すごく嬉しくて頑張ろうと思えたり。とてもショックでその後の行動に大きな変化をもたらしたり。言葉の影響力の大きさを、なんとなく感じていた。
また、マンガやアニメに出てくるちょっとした言葉がすごく響いて、将来を考える上での指針になったことも1度や2度ではなかった。
あと、この言葉はカッコいいな、この言葉は言われたら気分が悪いだろうな、などなど。目にしたり耳にしたりする言葉を「これは積極的に口にしよう」とか「僕は絶対に使わないようにしよう」といった具合に自然と自分の中でジャッジしていた。*例えば、個人的に子供の頃から「ムカつく」という言葉が苦手なので自分は使わないように心がけていた
書きながらふと思ったのだが、「ザ・ベストテン」や「夜のヒットスタジオ」などの歌番組が大好きだった影響も強いように思う。歌詞というよりも、印象に残る歌のフレーズに敏感だった。なので現在も「言葉の力強さ」以上に「言葉の語感やリズム感」を重視する傾向にある。
音楽繋がりで更に思い出したのだが、中高生の頃には、CDを買った際に付いている帯に書かれたコメント(キャッチフレーズ)も印象に残るよなーっと感じていた。大袈裟ではなく、その一言によってCD(アルバム)の世界観が決まるほどのインパクトを放っていたものも多い。よく「音楽は言語の壁を超えて伝わる」と言われていて、それは間違い無いが、言葉が合わされることによって、より色味を増したり深く刺さったりする効果があるということに異論を唱える人は少ないだろう。
自分の場合は、勉強ができたというよりも、単純に興味があったから言葉に敏感になったのだろう。シンプルに表すと「好きこそ物の上手なれ」である。
これからも、人に影響を与えやすいという意味でも「言葉」は大切にしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
