
ARゲーム開発の進め方
Hi 👋, everyone! プレティアでエンタメチームのプロダクトマネージャーをしている鈴木です。世界中の人々がAR技術を意識することなくAR体験する世界を作るべく、日々(+夜)邁進しています。
今回は、これまでのARゲーム開発で踏んできた地雷をもとに、あらためてゲームとは何ぞや?というところから記事をまとめてみました。
長いので、1日に一章ずつ読んでいただけたら嬉しいです。
鈴木 太樹(すずき たいじゅ)/ Taiju Suzuki
プレティア・テクノロジーズ株式会社/リードプロダクトマネージャー
----
1977年生まれ兵庫県西宮市出身。信州大学工学部卒。2000年、任天堂に入社。宮本茂の下でゲーム制作を、近藤浩治にゲーム音楽を学び在籍19年間で「スーパーマリオ」「ピクミン」シリーズを始め数々のファーストパーティタイトルを手掛ける。2019年に退職後、面白法人カヤックでVR事業を経て、現在はプレティア・テクノロジーズ Entertainment & Media事業部/リードプロダクトマネージャー。ゲームに限らないARエンターテインメント制作に取り組んでいる。
第1章 「ゲーム」とは遊ぶ人を幸せな気持ちにするもの
ARゲーム開発について語る前に、そもそも「ゲーム」とは何かを定義することで、通常のゲームとARゲームとの差分を明確にし、開発において何がどう異なるのかを語っていこうと思います。
ゲームとは何か、私はインタラクション(相互作用)の集合体だと考えています。いきなり抽象的な定義が出てきて、今ひとつピンときませんよね。もう少し「インタラクション」という単語を噛み砕いてみましょう。
インタラクションは日本語で「相互作用」。相互という単語が含まれています。相互なので、何かと何かがあって、それが作用することがゲームだということになります。ではこの何かと何かとはなんのことでしょうか?私はここには「入力」と「出力」という言葉をはめて、ゲームというものを捉えています。
「入力」、これはプレイヤー(基本的に自分自身)によるものです。プレイヤーが意図して、または反射的に何かの信号を送った状態です。
「出力」、これは入力に対するリアクションです。プレイヤーが送った信号を受けて、コンピュータや人、その他自分自身以外のものがそれに対する反応をした状態です。
つまり、入力と出力のキャッチボールがインタラクションであり、これを連続させたり積み重ねたりしながらまとめた集合体が「ゲーム」と呼べるのではないかと考えています。

さらに具体的に見てみましょう。
「入力」は基本的に自分自身だと言いました。ですから「出力」の方を色々と変えて考えます。みなさんが「ゲーム」という言葉を聞いて、まず思い浮かぶであろうビデオゲームの場合、出力はPS5やNintendo Switchといったゲーム機(コンピュータ)です。
一見、出力とはTV画面や液晶ディスプレイのように思いがちですが、これらは入力と出力を視覚化するための「仲介屋」です。他にも入力を伝達するためのデバイス、いわゆるコントローラも仲介屋です。

このような仲介屋はインタラクションのための手段であり、様々なものがあります。ゲームにとっては大事な要素なので、これは後ほど掘り下げることにしましょう。
ビデオゲームでは、あなたが操作しているキャラクターをジャンプさせたいと思ったら、コントローラのボタンを押すことで、その意思をゲーム機に伝えることができます。これが「入力」です。
ゲーム機はこの入力を受け取って、キャラクターをジャンプさせるように命令します。これが「出力」です。
あなたはTV画面などを介して操作中のキャラクターがジャンプする様子を見ることができます。このシンプルな流れがインタラクションの最小粒度であり、ゲームの基本単位と言えます。
もちろん、出力側は人でも構いません。例えば、トランプを使って遊ぶババ抜きはどうでしょうか。
あなたが誰かの手札から一枚引くという入力に対して、他の誰かがあなたの手札から一枚引くという出力が生まれます。これがババ抜きにおける最小単位のインタラクションです。実にシンプルですね。
唯一このインタラクションだけで「誰よりも早く手札を0枚にした人が勝ち」という目標に向かってプレイヤーはゲームをするわけです。
さて、話をビデオゲームに戻しましょう。
あなたはなぜキャラクターをジャンプさせたいと思ったのでしょうか?
高いところに登ろうと思ったから
敵を踏もうと思ったから
落とし穴を飛び越そうと思ったから
このように何か達成したいことがあって、キャラクターをジャンプさせようと判断したのではないでしょうか。
そしてこの「達成したいこと」を達成した時に、あなたはどう感じましたか?大小はあれど「やった!」といった達成感を感じませんでしたか?
人は達成感を感じたときに、ドーパミンという神経伝達物質を分泌すると言われています。そしてこのドーパミンがもたらすものは何か。それは「幸福感」という幸せな気持ちです。
つまり、みなさんは 幸せな気持ちを感じるためにゲームをしている のです。

幸せな気持ちになるために、インタラクションを使って目標を達成しているのです。誰も不幸せな気分になるためにゲームをしませんよね。実際、ゲームをしていて気分が悪くなることがあると、あなたはそのゲームをやめてしまうはずです。
ババ抜きでは「達成したいこと=誰よりも早く手札を0枚にする」でした。シンプルです。
一方、ビデオゲームではこの「達成したいこと」の大小や種類がたくさんあり、それらが絶妙な間隔やタイミングで用意されています。言い換えれば、ビデオゲームの中には、みなさんが幸せになるための仕掛けがたくさん用意されているわけです。
ではこの「みなさんが幸せになるための仕掛け」を用意しているのは誰でしょうか?そうです。それを用意している人たちがゲームデザイナーと呼ばれる人たちです。ゲームデザイナーはプレイヤーを幸せな気持ちにするために
高いところに欲しいものを配置する
あなたをやつけようとする敵を向かわせる
落とし穴の幅を絶妙に決める
という「設計」をしています。このように設計をすることがゲームデザインであり「ゲーム開発」です。
もちろん、今の時代においてはゲームデザイナーだけではビデオゲームを完成させることはできません。エンジニアやグラフィックデザイナー、サウンドデザイナーなどが集まってみなさんを幸せにしようとしています。
まとめると「ゲーム」とは遊ぶ人を幸せな気持ちにするものであり、そのおもてなしの準備をする行為が「ゲーム開発」 と定義できます。
第2章 ARゲーム開発とは、プレイヤーが幸せな気持ちになるための「おもてなし」
さて「ゲーム開発」とは何かが定義できたところで「ARゲーム開発」とは何かを見ていきましょう。
第1章で私は「ゲーム」とは遊ぶ人を幸せな気持ちにするものであり、そのおもてなしの準備をする行為が「ゲーム開発」だと述べました。
ここに「AR」という単語が付いても開発者が目指すものは変わりません。遊んでくれる人が幸せな気持ちになるよう最高のおもてなしをする、これに尽きるわけです。
では「AR」が付くことで何が変わってくるのか?
それは「仲介屋」たちです。
仲介屋とは何だったか覚えていますか? 第1章でみなさんが幸せになるためのインタラクションを伝達してくれるデバイスだと説明しました。つまり、ARゲームではプレイヤーの入力を伝える手段と、それを受けて出力されるリアクションを伝える手段が異なってくるのです。

具体的にどのようなデバイスが考えられるでしょうか? 今の時代、一人に一台は確実に普及していると言えるスマートフォン。これは最も手軽にARを体験できるデバイスです。
そのほかに、AR体験を専用に取り扱うものとして、ゴーグル型やメガネ型の形状をしたARグラスや、より裸眼に近い形で体験できるように研究が進められているコンタクトレンズタイプのものもあります。
ということは、ARゲーム開発とはAR体験が可能なデバイスを介してプレイヤーが幸せな気持ちになるようおもてなしの準備する行為となるわけです。
しかし既にこの時点でいくつかの地雷が存在することに気付かなければなりません。その地雷を見つけるためにも、ここで一度「AR」とは何なのか?「AR体験」とはどのようなものなのか?に触れておきましょう。
ARとは、学術的な言い方をすれば「Augmented Reality」日本語だと「拡張現実」と呼ばれるものです。
一般的にイメージされるものは、目の前のコーヒーカップをAR体験が可能なデバイスを介して見てみると、そこにコーヒーカップの価格が表示されたり、材質が表示されるなど現実世界のものに対して付加情報が表示されるようなものだと思います。
また、現実世界の道路に目的地までのルートが付加表示されるようなナビゲーションサービスなどもイメージしやすいでしょう。つまり、現実世界に情報が付加されることによって現実世界が拡張されるのです。
このような体験を少し別の視点から見てみると、AR体験とは「現実世界」と「仮想世界」の境界がほぼない、もっと適切な表現をするならば、現実世界というレイヤーの上に、仮想世界というレイヤーが覆い被さっているような世界で何かを体験すること、と言えるのではないかと思っています。
みなさんにとってAR体験は、実は現実世界での日常生活とあまり変わらないもの、日常のちょっとした延長線上にある非常に距離が近いものと言えるのではないでしょうか。
ただ、そのような世界を使ってゲーム開発をするとなると、問題となる点がいくつか出てきます。代表的なものに下記のようなものがあります。
プレイヤーの立ち位置
直感的な入力
出力の伝え方
順に見ていきましょう。
まず、プレイヤーの立ち位置について。AR体験をしてもらう際に、プレイヤーがどの位置や方向から体験を試みているかを考慮する必要があります。
先ほどのコーヒーカップの例では、コーヒーカップの取っ手を右側にした状態で見ているプレイヤー(下図A)と左側にした状態で見ているプレイヤー(下図B)とでは、立ち位置が異なるということです。

通常のビデオゲームやスマートフォンゲームの場合、プレイヤーはTVやディスプレイの前にいると言えます。TVの裏側に立って、裏の配線を見ながらプレイしている状況は考えにくいですよね。
しかし、AR体験の場合は、現実世界というレイヤーの上で体験する以上、それが起こり得ます。考慮する必要があると言いましたが、ゲームデザイナーが考慮するかしないかは自由です。
取っ手を右側にしてコーヒーカップを置いているプレイヤーと、左側にして置いているプレイヤーに対して、同じ体験を提供するかどうかは自由だということです。ただ、ARの世界ではそれらを分けて取り扱い、異なる体験を提供することが可能なのです。
問題となるのは、この考慮をプレイヤーに求めはじめたときです。「正しい体験を得るには、カップの取っ手を右側にして見てくださいね」と求めた途端、それはプレイヤーがAR体験をする前のハードルへと変わります。
先ほどの図で言えば、Aの位置からでないとARが正しく表示されない場合です。この場合、お客様が気を遣ってプレイしなければならなくなるのです。そしてこのハードルは、次に説明する2つ目の問題点とも関係があります。
2つ目の問題点は、直感的な入力についてです。次の状況を思い浮かべてみてください。現実世界のあなたの目の前には、何も置かれていないテーブルがあり、AR体験が可能なデバイスを介して、その上に架空のコーヒーカップが置かれているとします。
「現実世界の〜」とか「架空の〜」を文字で説明している時点で、既にカオスではありますが、つまりは何もないはずのテーブルに、あなたにはコーヒーカップが見えているということです。そして「そのコーヒーカップを持ってください」と言われたらどうしますか?

AR体験が可能なデバイスがスマートフォンだったら、あなたはその画面に見えているコーヒーカップをタップするかもしれません。いやいや、持つんだからロングタップ(長押し)でしょ、という人もいれば、もっと現実に近い形で、カップの取っ手の部分を下から上にスワイプ操作するかもしれませんね。
では、デバイスがARグラスだったらどうしますか?あなたは自らの手でコーヒーカップを触ろうと、何もないテーブルの上を何らかの感触を求めて探るのではないでしょうか。そして、ある人は「持って!」と音声コントロールを試みるかもしれません。
従来のビデオゲームでは【(A) 持つ】とUI表示があれば、ほぼすべてのプレイヤーはコントローラのAボタンを押して、コーヒーカップを持つことができたでしょう。
この例でも、コーヒーカップを表示しているデバイスの画面に【タップ: 持つ】と表示されていれば、プレイヤーは迷うことは少ないはずです。
しかしゲームデザイナーとしては、AR体験が可能な世界では、それが日常生活の延長線上にあるような距離感であるが故に、その体験も普段の生活と変わらない所作で味わってもらいたくなります。
ただそれは、新しい体験を提供したいと考えるゲームデザイナー側の意思が大きく、実際には現実世界のレイヤーにおける入力を仮想世界のレイヤーで直感的に伝えるには、技術的にも体験的にもまだまだハードルがあるのです。
そして最後に、3つ目の問題となる出力の伝え方についてです。ここまで2つのハードルについて見てきて、あなたはどうにかベストなAR体験ができる位置に立ち、どうにかコーヒーカップを持つことができたとします。
そして、ふと右横を見ると架空のカフェ店員が立っていました。目が合うと「お替わりはいかがですか?」と声を掛けられた・・・そんなAR体験を想像してみてください。

この体験の中には、2つの入力がトリガーとなってインタラクションが発生し、体験フローが進行しているのですが、何がトリガーとなったか分かりますか?
次の2つです。
架空のコーヒーを飲み干した
架空の店員を見た
ただ、初めてこのAR体験をするプレイヤーにとって、この2つの入力をすれば何か状況が変化するなんて、知ったことではありません。ですから、架空のコーヒーを飲み干した後、いつ、どこから架空の店員が現れたか、また体験を進行させるために、この店員を見る必要があるということに気付かない可能性があります。
これが出力の伝え方の問題です。通常のビデオゲームやスマートフォンゲームではほとんどの場合、プレイヤーはTVやスマートフォンの画面を注視しています。ですから、出力されたものはその画面の中で伝える工夫を考えればOKでした。
一方、ARゲームの場合、先ほどの例のようにプレイヤーは演出を見ていない可能性があることを考慮しなければなりません。
これを考慮せずに「見ていないからいけない」「見ないから話が進まないんだ」とプレイヤー側に非があるような、または非があると感じさせてしまうようなゲームデザインにしてしまうと、お客様が幸せな気持ちになることを妨げるハードルになってしまいます。
さて、ここまでARとは何なのか、そしてARゲーム開発をする上でハードルとなりうる問題について語ってきました。
最終的には、通常のゲーム開発もARゲーム開発も、開発者が目指すべきものは変わらずプレイヤーが幸せな気持ちになるようおもてなしの準備をすることなのです。
ただ、仲介屋が変わることで、プレイヤーが幸せな気持ちになるまでにハードルが生まれやすくなります。このハードルを下げる、できれば下げるだけではなく取り除きながら、プレイヤーに幸福感を与えるのがARゲーム開発だと言えるでしょう。開発者にはより一層の”おもてなし力”が求められるのです。
第3章 地獄のエンドレス開発から抜け出す最適解とは
ここまでゲーム開発とは何か、そしてARゲーム開発で生まれるハードルについて語ってきました。ARゲーム開発では考慮すべきことが増えはするが、どちらも最終的に開発者が目指すべきゴールは変わらないと述べました。
この章ではまず、ゲーム開発に共通する部分として、どうすれば最高のおもてなしを準備することができ、その準備を効率良く終わらせることができるかについて述べ、その後、ARゲーム開発におけるハードルについて、語っていきたいと思います。
この記事の前半で紹介した「ババ抜き」の話を覚えていますか?
もしあなたがこれから「ババ抜き」を開発することになったら、どのぐらいの工数がかかると見積もりますか? いわゆる要件定義という形で、一緒に考えてみましょう。

入力 … 1 (隣のプレイヤーの手札から1枚引いて自分の手札に加える)
出力 … 1 (自分の手札の中に同じ数字があれば、その2枚を捨てて良い。そして次のプレイヤーの順番になる)
目的 … 1 (一番早く手札を0枚にしたプレイヤーが勝ち)
確定要素 … 1 (1〜13までのカードを4セット + ジョーカーを使う)
こんな感じでしょうか。入力が1パターン、出力も1パターン、目指す目的も1つだけ、そして使用するアイテムも1つだけ。非常にシンプルだと思いませんか?
このように変数が少ないゲームは、プレイヤーにとって非常に分かりやすいものとなります。目的も明確で、ルールも覚えやすいわけです。また、仲介屋も存在しないので、プレイヤーにとってのハードルもほぼないと言えます。
シンプルなゲームは、プレイヤーにとっても開発者にとってもベストのように思えますが、唯一欠点とも言える点があります。それは飽きるのも早いということです。開発者にとっては飽きられるのが早いになりますね。
いくらシンプルで面白いゲームだからと言っても、ババ抜きを2時間も3時間も遊んでいられますか? 私はせいぜい4、5ゲーム、30分も遊んだら、もう違うことをしたくなると思います。
このようにゲームのシンプルさと飽きの早さには密接な関係があります。
だからこそ開発者は、せっかく作ったゲームに飽きられないように、複雑なルールを用意したり、難しい入力を求めたり、ランダムな出力を返したり、そのような仕掛けを絶妙に組み合わせて、10時間でも20時間でも100時間でも遊んでもらえるゲームを用意してプレイヤーをもてなすのです。
ただ、さまざまな仕掛けは、第1章で述べたようにプレイヤーを幸せにするために用意されるべきであり、早く飽きられないようにするため、シンプルさを解消するため、のような目的として用意してしまうと、それは第2章で述べたプレイヤーにとっては「幸せへのハードル」へと変わってしまいます。
例えば、ババ抜きに次のような特別なルールを追加してみましょう。
相手の手札から7のカードを引いた時は、もう1枚引ける
さて、どのような遊びになるか、少し想像してみてください。
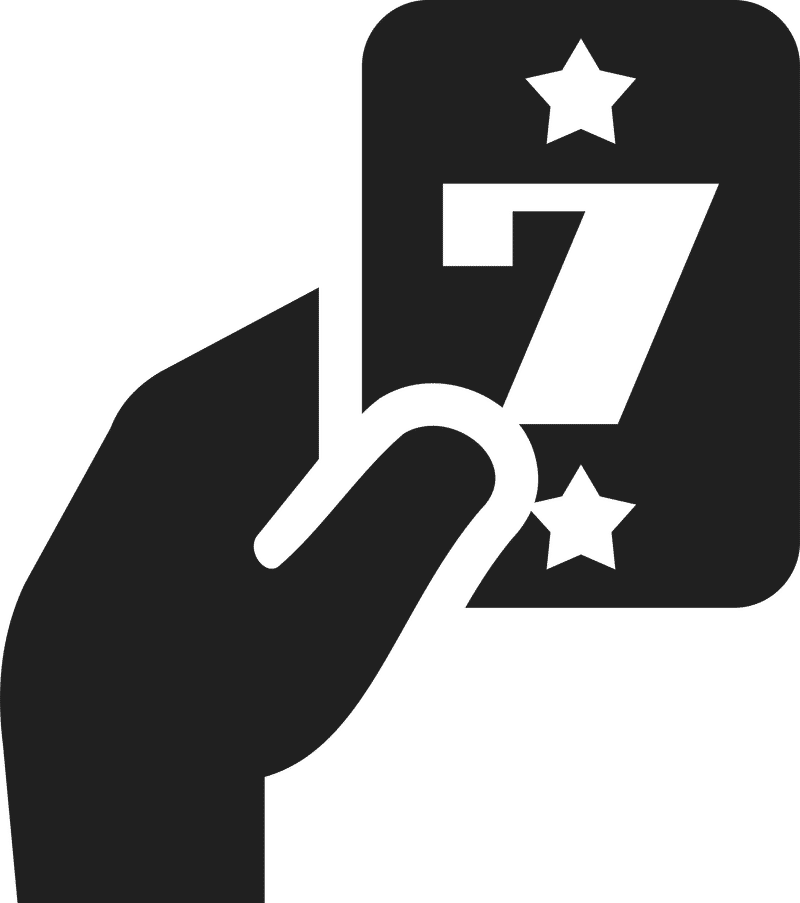
7というカードだけ、少し特別な存在になりましたね。自分が誰かから7のカードを引いた時、もし自分の手札に7のカードがあれば、それらを捨て札にできる上に、もう1枚引けることでさらに手札を捨てられるチャンスとなるわけです。
そして実は、カードを引かれているプレイヤーも7のカードを引いてもらえれば、もう1枚自分のカードを取ってもらえるので、早く手札をゼロにできる可能性が上がりますよね。
つまり、7のカードを引けるかどうか、また引いてもらえるかどうかに、とてもワクワクする遊びとなるわけです。
そのほかの影響を考えてみましょう。
ババ抜きでは自分の手札の中身を教えることもなければ、相手から引いたカードを申告することもありません。ですが、この特別なルールのおかげで、7のカードが動いたかどうかをプレイヤーたちが非常に気にするようになります。
7のカードが動いたにも関わらず、特別ルールを発動することを忘れていたら?
最初に全員に均等な枚数を配ったのに、ある人だけ2枚引いたらバランス大丈夫かな?
このように、非常にシンプルだったゲームがルールが2つになったことで一気に複雑なゲームになった感じがし、かつゲームバランスが崩れていないか不安な感じもあります。
多少のハードルを越えさせることで、目的を達成した時のプレイヤーの幸福感を増すことができるでしょう。先の例だと、ルールを増やしたことで、7のカードを引くことと引かれることに幸福感を覚えることでしょう。
ですが、第2章で述べたように、これらのハードルはお客様に気を遣わせるものであってはなりません。
では、どうすればプレイヤーに気を遣わせずに幸福感を高めるハードルを用意することができ、シンプルだけど飽きられないゲームを作ることができるのでしょうか。
「飽きられないゲーム」と言いましたが、人間は必ず飽きる生き物です。ですから「なるべく飽きられないゲーム」「飽きるまでの時間を長くするゲーム」と定義し話を進めます。
実は、ババ抜きには要件定義には書かれていない「不確定要素」があります。いくつか考えてみましょう
プレイ人数
最初に配られるカードが毎回変わる
相手の手札からどれを引くか分からない
人間は必ず飽きるのですが、”飽き” の一番の要因は、同じことが繰り返されることに気付くことです。
遊ぶメンツがいつも同じで、配られるカードが毎回同じ、さらに相手から引くカードがいつも同じだと、もはやどこにおもしろみがあって、何のためにゲームしているのか分かりませんよね。これらが不確定要素として存在することで、シンプルなゲームでも30分程度は遊んでいられるわけです。
最終的にババ抜きというゲームを式にしてみると、
(入力 1)×(出力 1)×(目的 1)×(確定要素 1)×(不確定要素 3)となり
1 x 1 x 1 x 1 x 3 = 3のように言えます。この「3」という数字が、ゲームのシンプルさを表しており、大きい数字になるほど複雑なゲームと言えます。
大きい数字ほど、開発者が考えなければならないこと、作るべきもの、テストすべきものが増え、制作コストが大きくなります。また、この数字はプレイヤーが飽きるまでの早さでもあります。小さい数字ほど飽きるまでが早く、大きい数字ほど基本的には長いでしょう。
そして、この “飽き” を緩和するための不確定要素はプレイヤーにとってのハードルになることが多いです。
ババ抜きでは不確定要素の3つにある共通点があります。この共通点こそが、最高のおもてなしをするための重要なポイントだと私は考えています。
それは、プレイヤー自身のせいにできることです。
プレイ人数が2人なのはプレイヤーのせい。
3人で遊んでも、
4人で遊んでも、
それはプレイヤーたちが決めたこと。
ババ抜きは2人で遊んでもあまりおもしろくありません。また最大53人まで遊べる気がしますが、きっとおもしろくないことになる気がします。なんとなく26人までが限界でしょうか。でもおもしろくない人数で遊ぶことを決めたのは、プレイヤー自身です。
最初に配られるカードについても、完全にランダムであり、もし偏りがあったとしたら、それはカードをシャッフルしたプレイヤーのせいです。
手札を引いた時に、ジョーカーを引いてしまっても、揃わない数字を引いてしまっても、それはすべてプレイヤー自身のせいです。
「プレイヤー自身のせい」言い換えれば「開発者の責任ではない」のです。この状態のハードルについては、プレイヤーは誰にも責任を押し付けることができず、自分自身で乗り越えるしかなくなります。
ババ抜きがもし「4人専用ゲーム」だったとしたら、3人しか集められないプレイヤーにとっては、このゲームを作った開発者に対して「なぜ4人じゃないと遊べないのか」という感情が生まれ責任を押し付ける形になってしまいます。
最高のおもてなしを準備するとは、まずシンプルな式によって小さな数字を目指すこと、そして幸福感を高めるために用意するハードルは、それを乗り越えられるかどうかをプレイヤー自身のせいにできるものにすることなのです。
この2つのことは、どちらも開発者がすべきことを減らしてくれ、かつ責任から解放してくれるため、おもてなしの準備を効率良く終わらせるために非常に重要です。
もうワンランク上のおもてなしをするならば、プレイヤーがハードルを乗り越えられなかったとき、いわゆる「失敗」の状態が楽しいものにデザインされているべきです。
配られるカードが毎回同じ
2人だけで遊ぶことになって、どちらにジョーカーがあるか分かる
1/2の確率でジョーカーを引いてしまった
これらは、なんとなくおもしろ可笑しいですよね。
ババ抜きだからシンプルに整理できた部分もあると思いますので、ここでスマートフォンゲームやARゲームの場合についても、先ほどの式を簡単に見てみましょう。
スマートフォンゲームの中でも、いわゆるガチャシステムを搭載しているものについて、その部分だけで見ると
(入力 1)×(出力 ∞)と言えます。「ガチャする」という1タップの入力に対して、開発者は大量の出力を準備しなければなりません。
またシンプルな落ちものパズルゲームはどうでしょうか。色々なタイプがあると思いますが、
(入力 1〜3)×(出力 1)が基本的なタイプではないでしょうか。非常に簡単な操作でオブジェクトを動かし(入力)で、いくつかのオブジェクトが揃うと消える(出力)という構造です。ここにオブジェクトの種類数が掛け算されることでハードルの高さに変化が生まれ、オブジェクトの初期配置(ステージ)がランダムにセットされることで不確定要素が掛け算されます。
難しい入力の成功と失敗をプレイヤー自身に委ね、成功した時の達成感から幸福感を生み出す理想的な手法だと言えます。
一方、ARゲームでは「直感的な入力」と「出力の伝え方」がハードルになりがちだと述べました。式で表すと次のようになります。
(入力 + 仲介屋がもたらすハードル)×(出力 + 仲介屋がもたらすハードル)×(内的不確定要素)×(外的不確定要素)
式が長い上に、結果の数字を大きくしてしまう要素がたくさんあるように見えます。結果の数字が大きいことで飽きるまでの時間が長い場合は良いのですが、ARゲームの場合、単にハードルだけが増えて得られる幸福感が少ない、ということにならないよう注意が必要なのです。
入力方法を増やせば、都度ハードルが加わり、その出力に対してもハードル付きで返ってきます。さらに、ゲームの飽きを緩和するための内的な不確定要素が掛け合わさり、初登場となる「外的不確定要素」も掛け合わさってきます。

ARゲームにおいて、仲介屋がもたらすハードルについては先の章で述べましたので、この章の最後ではARゲーム特有の「外的不確定要素」について、お話しようと思います。これはARゲーム開発者に課せられるハードルとも言えるでしょう。
「外的不確定要素」とは、簡単に言えばARゲーム開発者がコントロールすることができない外的な要素のことを指します。ARゲームでは、何らかの現実世界のものが体験に関わってきます。具体的には次のようなことです。
マーカーとなるオブジェクトの状態や変更
天気など環境光の変化
1つずつ見ていきます。
渋谷の忠犬ハチ公像をマーカーとしたAR体験を考えてみましょう。スマートフォンのカメラでハチ公をスキャンすると、飼い主がどこか遠くから近づいて来るような体験の場合、もしハチ公像が修復作業中のためブルーシートで覆われていたらこの体験はどうなるでしょうか。
AR体験のきっかけとなるマーカーが見つからないため、作業の間お客様はプレイすることができません。ただこの場合、プレイできない期間は一時的でしょう。修復作業が終わり、ブルーシートが外されれば、お客様は再びプレイすることができます。
ところが、このハチ公像がある日を境にネコ像に変わってしまった場合はどうでしょうか。マーカーが全く異なるものに変わってしまったため、お客様は二度とこのAR体験をプレイすることはできません。
このように、現在のAR体験はマーカーの状態や変更にとても影響を受けやすいものとなっています。ARゲーム開発者がこのタイプの外的不確定要素を減らすには、長期間変更予定のないマーカーを使用するしかありません。
しかし、ベストな体験を提供したいマーカー(場所)が不変とは限らないため、この点で頭を悩ませることもあるでしょう。
2つ目の「環境光の変化」とは、主に天候や照明による影響です。晴れた日のハチ公像と雨の日のそれでは別物と判定されることがあります。また、ARは基本的に夜間の使用に適していませんが、もしハチ公像が鮮やかにライトアップされているなら、スキャンこそ可能だとしても日中のそれとは別物だと判定されるかもしれません。

このタイプの外的不確定要素に対して、ARゲーム開発者が取りうる対策は次の2つです。
1つ目は、どんな環境光の違いも吸収可能なマーカー(マップ)データを用意することです。晴れの日、曇りの日、雨の日などそれぞれのデータを収集し、それらを一つにマージしたデータを作成します。そうすることで天候などによる違いを気にすることなくAR体験を提供することができます。
2つ目は、環境光の違いによって提供する体験を変えることです。先のハチ公像の例であれば、晴れの日、曇りの日、雨の日など区別しうるマーカー(マップ)データをそれぞれ作成しておき、晴れの日であれば半袖の飼い主が、曇りの日であれば長袖の飼い主が、そして雨の日であれば傘をさした飼い主が現れる、といった感じです。
2つ目の対策の方が、インタラクション面ではより自然で望まれる体験だと考えられますが、例の式に当てはめてみると、外的不確定要素は減るものの出力が増えることになりますので、工数に変わりはないことになります。
ただ、お客様にとってハードルとなりうる不確定要素が増えるよりは、開発者側でよりコントロールしやすい出力が増える方がAR体験としては良いものになると言えます。
この章では、式を使ってゲーム開発を表現し、ゲームのシンプルさと飽きまでの速さの関係性、内的不確定要素がもたらすゲームのランダム性、そして各項がお客様や開発者に及ぼす影響を見てきました。またARゲーム開発の式に外的不確定要素の項も加わり、開発者のハードルとなる事例を示しました。
不確定要素については、プレイヤー自身のせいにできる設計が理想だと述べましたが、これは入力に対しても同じことが言えます。より大きな達成感を与えるために要求する難度の高い入力は、失敗したときにプレイヤー自身がそれを受け入れられる、もっと言えば失敗したことが楽しく誰かに言いたくなる設計になっているべきです。
ゲーム開発者は、予算やゲームのライフサイクルを考慮しながら式の各項についてバランスを取っていくことが求められます。次の最終章では、私が思うARゲームの手触りについて語ります。
最終章 「入力」への挑戦がARゲームの未来を作る
第2章で、AR体験とは現実世界というレイヤーの上に、仮想世界というレイヤーが覆い被さっているような世界で何かを体験すること、だと述べました。
現実と仮想という2つの世界が非常に近い関係にあることを考えると、第3章で説明したゲームの構造式において、どの項に注力することが最もARゲームらしい体験を作ることができるでしょうか。
私は「入力」部分だと考えています。
「出力」も大事な要素ではありますが、プレイヤーはある程度の予測や期待を持っていることが多く、それに対して差異があるほどプレイヤー自身のせいというよりは開発者に対する不満に繋がります。
ガチャ方式のゲームのように、極めて高い幸福感(良い出力)を感じてもらうために大量のガッカリ感(悪い出力)を用意しなければならない部分も開発者の負担となります。
その他の項については、ARゲームだから特別というわけでもなく、ゲームとして通常デザインすべき部分と言えるでしょう。ですからARゲームでは「入力」を磨くことがプレイヤーにとっても開発者にとってもハッピーな状態になると、私は信じています。
AR体験ができる仮想世界は現実世界に覆い被さっているのですから、そこに対する入力は、可能な限り現実世界と同じ感覚で行えることが望ましいです。
何かオブジェクトを持ち上げるときに「もつ」というボタンをタップするのではなく、そのオブジェクトに対して作用したくなるような表現を心がけるべきです。
出力も、可能な限り現実世界と同じフィードバックであることが望ましいですが、視覚や聴覚以外のフィードバックも達成しようとすると、まだ技術の進化を待たなければなりません。
ババ抜きの入力では、ちょっとした隙に相手の手札を覗き込もうとしたり、カードを選ぶときに相手の顔色を窺いその反応を見て引くカードを変えたり、といったことができます。
このような入力は、デジタルな入力にはないアナログな入力だと言えます。
そしてこのアナログな入力は、実は出力には一切関係がありません。どのように引いたって結果は同じなのです。でもプレイヤーはこのアナログな瞬間を楽しみます。

ARゲームでは、このようなアナログな入力を盛り込めるチャンスが多く、また盛り込むことでARらしい体験になる可能性があります。出力は変わらないのに入力部分をアナログで楽しめることで、結果ゲームを長く楽しんでもらえます。
またアナログな入力は、開発者がプレイヤーに強要するものではなく、プレイヤー自身がしたいからするわけで、もし上手くいかなくてもプレイヤーは自分のせいだと思ってくれるのです。
では、アナログな入力を盛り込むために、開発者にできるおもてなしは何でしょうか?
次の2つがあると思います。
プレイヤーがしてみたいと思ったことに対して受け皿を用意すること
プレイヤーが入力してみたいと思うように見せること
以前、仮想世界の中で積み木ができる体験を作ったことがありました。そのとき、私は仮想世界の中のオブジェクトを回転したり拡縮できないようにデザインしました。スマートフォン上でスワイプやズームイン・ズームアウトをさせなかったのです。
ARではないゲームでは、プレイヤー自身が動く必要はなく、轆轤(ろくろ)のようにオブジェクトを回すと反対側を見ることができました。ですが、仮想空間の積み木では反対側を見るためには、プレイヤー自身が積み木の回りを移動して反対側に位置する必要があったのです。
現実世界で子どもが積み木をするとき、積み木を中心にあっちへ行ったりこっちへ行ったりして作っていますよね。そして積んだものが高くなってきて自身の身長を超え始めると、子どもは踏み台などを使って、自然とより高いところから積み木を積もうとします。

私はこのような体験をARで実現したかったのです。さらにこの体験では、移動中にスマートフォンを揺らしすぎると仮想世界の中の積み木が崩れるようにもデザインしていました。
ところが、スマートフォンゲームに慣れたプレイヤーは「自分が動く」という発想に至りませんでした。画面内のオブジェクトを違う角度から見たい場合はスワイプしようとし、高さが高くなってきて画面内に収まり切らなくなると縮小表示しようとしました。
これに対して、私はスワイプや拡縮操作に対応しておくべきだった、つまり受け皿を用意しておくべきだったとは思いませんでした。足りなかったのは開発者がすべきことの2つ目に挙げた「してみたいと思うように見せること」ができていなかった、と反省しました。
AR体験に相応しい受け皿を用意することは大事です。スワイプや拡縮操作を受け付けてしまうと、ARらしい体験ではなくなります。ですがそれだけだと開発者の押し付けです。開発者は意図が伝わらないことでやり切れない思いになり、プレイヤーはしたいことができずにストレスを感じてしまいます。
プレイヤーが自然と入力してみたくなるように見せることも大事なのです。
「入力」はARゲームに限らず、ゲームにおけるすべての始まりであり、プレイヤーの欲求に答える入り口、受け皿にあたる部分です。
そしてARゲームでは、この入力方法が従来のゲームと異なり、より現実世界に対する入力と近しくなります。入力の仲介屋が唯一、2つの世界の境界となり、プレイヤーの直感的な操作に対してハードルとなります。
このハードルを逆手に取るようなアイデアが出てくれば、意図したAR体験を提供できる開発者になれるかもしれません。私はこの境界のギャップを上手く使った、現実世界に見えるのに不思議な体験が可能な新しい世界の提供に挑戦を続けています。
Pretiaはこれまで様々なタイプのAR体験を制作してきました。その多くは道が整備されておらず、自らで切り開いてきたものなので、Pretiaだからこそのノウハウが貯まっています。今回の記事では、ほんの一部の例を取り上げていますが、ARゲームの企画の際には、ぜひ参考にしてみてください。
また、企業の方でPretiaと一緒にAR体験を企画してみたい、というご担当者様はご連絡ください。過去にAR施策をやってみたけれど、そこまでインパクトのある体験にはならなかったという場合、多くは「入力」部分の練り込み不足が原因だと考えられます。一緒に不思議な体験を提供しましょう。
採用サイト
Meety
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
