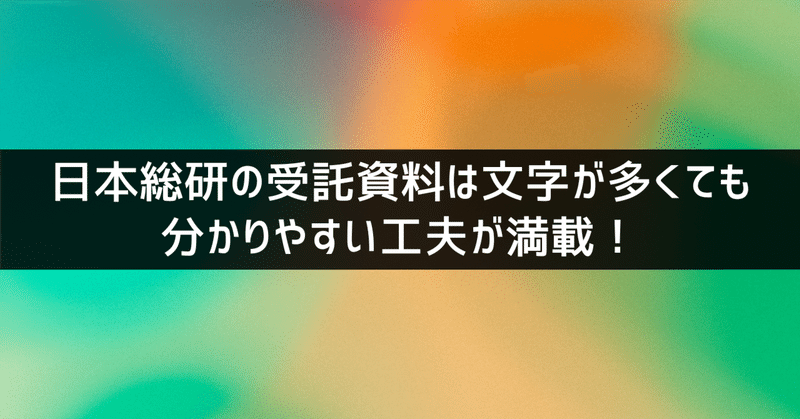
【パワポ研のパワポ資料探訪33】日本総研の受託資料は文字が多くても分かりやすい工夫が満載!
様々なパワーポイント資料について解説するこのシリーズ。
毎回大変好評をいただけておりまして、おかげざまで引き続きシリーズを重ねられております(好評だった初回Goodpatch様の記事は以下)。
今回も見どころあるパワーポイント資料について紹介させていただきます。
対象とするのは、日本総合研究所(日本総研)社の令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費(グリーンイノベーション基金の成果最大化に向けた懸賞金型事業導入に関する調査)-最終報告資料-。いわゆる、経産省受託資料です。日本総研は三井住友フィナンシャルグループ(SMFG、SMBCグループ)に属する日本の大手シンクタンク企業です。
(リンク:令和5年度地球温暖化・資源循環対策等に資する調査委託費(グリーンイノベーション基金の成果最大化に向けた懸賞金型事業導入に関する調査)- 最終報告資料)
それでは早速見ていきましょう。
表紙

特にコメントはありません。経産省も規定のフォーマットがあるわけではないので、ここは自由です。
目次

とりたてていろいろあるわけではないのですが、とにかく長い! 100ページ以上ですので、かなりの省力化が資料作成には求められます。
調査の背景および目的

さて、ここからが本論です。
この資料全体として、文字がとても多いです。通常スライド、特にプレゼン用のスライドでは文字が多いことは避けられる傾向にあります。なぜなら、そのような資料はあまり読まれづらいからです。パっと見て頭に入らないスライドは、「読み込む」という作業を相手に強いるため、プレゼンの場では嫌われます。
他方、プレゼン用ではなく「読む」用の資料では、多少文字が多くても構いません。なぜなら、相手は「読み込む」ことを前提としてその資料を向き合うためです。
とはいっても、無秩序かつぎゅうぎゅうに文字が詰め込まれていてはワードと何ら変わりません。この資料は、そのような残念なスライドにならないための工夫が多数組み込まれているので、それを紹介していきます。
まずこのスライドで言えば、「タイトル」と「メッセージ」が上にあること。この2つに関してはほぼ全てのスライドにおいて位置が固定してあるため、最低限そこは目に入りやすくなっています。そして、それ以外の部分は背景を青色にして差分を出しています。
懸賞金事業実施目的の定義

これも文字が多いスライドですが、ブロックもといマトリクスで区切ってあり、縦軸と横軸に情報が整理されています。これが箇条書きでだらだらと並んでいると、読み手に負担を強いることになります。こういうものが、情報量が多くても見やすく感じさせる工夫の代表例ですね。
検討経緯

資料を引用しているスライドです。そのため文字が小さく情報量がかなり多くなっていますが、それでも注目すべきポイントが青枠で囲まれています。引用の範囲が広い場合は、このようにどこが最も伝えたいのかを明確にするべきですね。
検討経緯

これも別資料などから引用したスライドになります。議事録を引用することはしばしばあるかと思いますが、抽出して転記する方式と、このように議事録の多くを引っ張ってきて、その一部をハイライトする方式に分かれます。前者は見やすいですがチェリーピッキングを疑われる恐れがあるので、不安ならこのように多くの文章(あるいは全文)を引っ張ってきて、そこからハイライトをかけるようにするとよいですね。
なお、このスライドは前のスライドとタイトルが同じ(経済産業省における「アワード型研究開発事業」の検討経緯)なのですが、あまり得策とは言えません。スライドを指定して議論する際に少しまごついたり、あるいは二つのスライドで同じタイトルというのは(ややもすると)考え込みが足りないと思われるかもしれません。少なくとも、「1」「2」とかの番号を振ってあげるとよいかもしれません。ただ、100枚もスライドを書いているとこういうものがあっても仕方ないと思います。誰しも予算以上のパワーは出ないので……。
あと、少し細かいですが行頭のポチ(・)が青色になったりしています。別段問題はないのですが、箇条書きから文字の色をそのまま変えてしまうと行頭もそれに引っ張られてしまうので注意が必要です。これは箇条書きの設定から色を変えることができます。もっとも、そこまでする必要はほぼほぼありませんが……。
22分野との比較

これ文字、というか固有名詞が多いですね。こういうのをスライドに並べるときは、躊躇せずにエクセルから転記してしまってもよいと思います。オブジェクトをえっちらおっちら並べてそれに手打ちしてもいいのですが、それはそれでしんどいと思います。確かに見栄えは良くなるかもしれませんが、プレゼン資料ではなく調査報告資料というのなら、このようにベタ貼りでもなんら問題ないでしょう。
ちなみに、パワーポイントやワードでこのような表を作るよりもエクセルで作ったほうが圧倒的に楽です。その後の文言の入れ替えなどで少し苦労するかもしれませんが、エクセルを使ったほうがトータルで楽になることの方が多いです。
事例調査

実は、このスライドと同じようなフォーマットの資料が30枚くらいこの資料には含まれています。100枚の調査報告で100枚バラバラのフォーマットが出てくれば、そちらの方が大変でしょう。このように、汎用性のあるフォーマットで提出された方が、受け手も比較・検討がしやすいというものです(特にこのように文字数が多い場合は!)。臆せずにフォーマットを使いまわしましょう。大切なのはスライドの中身です。ガワは(極端に言えば)そこまで重要ではありません。
実施プロセス

これはある種のフロー図と言えますが、これも箇条書きで並べるよりもブロックに区分けして線で囲って繋いであげると読み手は見やすかったりします。
法的論点

最後に箇条書きの工夫事例を。おおむね箇条書きは「多くても4つまで(3つ程度が望ましい)」と言われています。しかし情報量が多くてそれに収まらない、というときはこのように構造化をすることで、内容を散らすことができます。ここでは「現在の制度」と「制度上の課題」と「解決方法」の3つのブロックに区分けすることでそれぞれの情報量を落とすことに成功しています。
各ブロックでも上下の構造を利用しており、例えば一番上のブロックでは「GI基金は、補助金を前提とした制度となっている」というのを一番上に置き、その具体として下の2つを紹介しています。さらに「解決方法」のブロックでは、箇条書きに①②➂の番号を振ることで、読みやすさが上がっています。
まとめ
建付け上、とにかく情報量が多くなってしまう資料というものは現実に存在します。その中で、どれだけ楽に見やすくなる工夫をしているかというのが大事になってきます。手間暇と予算をかければ見栄えはもっとよくなるかもしれませんが、それが難しい場合は、箇条書きやフォーマットの使いまわし、ハイライトの工夫などでこの資料のように対応するとよいでしょう。ワードでつらつらと書き連ねられるよりは、ずっと見やすいと思います。
パワポ研オリジナルテンプレート
パワポ研では「ビジネスシーンで使える」パワーポイントテンプレートを公開しております。デザインを整えるのみならず、ロジックやストーリーを整理するのにも役立つパッケージになっておりますので、関心のある方は下記ページも併せてご覧ください!

パワポ研からのお知らせ
上記の記事のように、noteではフォローしているだけでビジネスにおける「資料作成のコツ」と「デザインのセンス」が身に付くアカウントを目指して情報配信を行っています。
今後もコンスタントに記事を配信していく予定なので、関心のある方は是非アカウントのフォローをお願いします!
Template販売
https://powerpointjp.stores.jp/
書籍
https://www.amazon.co.jp/dp/4046060476
note
https://note.com/powerpoint_jp/m/mc291407396da
X(旧Twitter)
https://twitter.com/powerpoint_jp
お問い合わせはこちら
https://power-point.jp/contact
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
