
【トークイベント】社会から孤立するスポーツ(11/7)
ポスト研究会(ぽすけん)トークイベント第14弾は、スポーツライターの小林信也さん、文化研究者の小笠原博毅さん、スポーツ社会学者の山本敦久さんによる「スポーツと社会」をめぐってのクリティカル・トークです。
ぽすけん企画 第14弾 トークイベント
社会から孤立するスポーツ
出演者:小林信也×小笠原博毅×山本敦久(司会)
日時:2020年11月7日(土)19:00〜21:00
場所:書店readin’ writin’ &zoom配信
【トークテーマ】
いまスポーツは社会から孤立しているのではないか? これがトークイベントの出発点となる。社会のなかにスポーツがあるという自明性を疑い、むしろスポーツは社会のなかでの存在意義を失いはじめているのではないかと問い返す。大企業、広告会社、巨大メディア、ナショナリズム、家族といったプライベート空間との関係を深めてきたスポーツが社会から孤立していく過程を検証し、スポーツの真の価値をもう一度探求する。勝敗を競い合うことを否定せずに勝利主義を批判することは可能か。スポーツには何の価値もないからこそ価値があるということによって資本主義の剰余価値から離れることは可能なのか。スポーツのシーンに立ち会うとき、ひとりひとりのなかに沸き上がるものの共有を、ナショナリズムやファシズムとは違ったものとして語るためにどんな言葉が必要なのか。オリンピックに包摂されないスポーツとはどのようなものか。いくつもの問いを立て、それらを3人で思考しながら、スポーツを社会へと戻していくための道筋を探る。新たなスポーツへの展望を徹底的に語り合う。
【出演者】
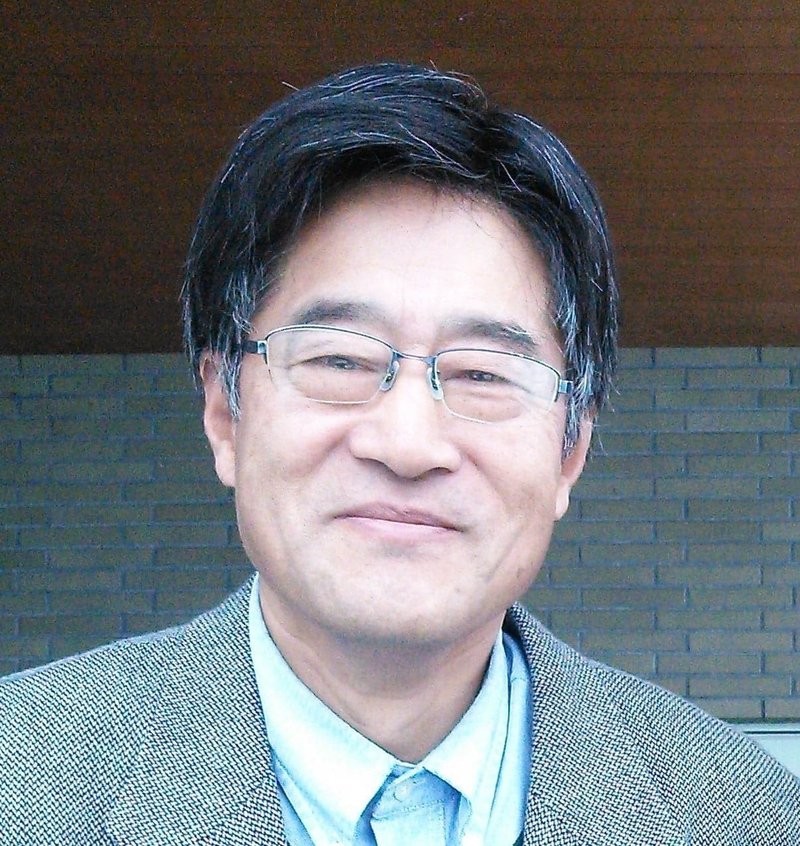
小林信也(こばやし・のぶや)
作家・スポーツライター、コメンテーター。 大学在学中から取材執筆を始め、一貫して日本スポーツ界の悪しき精神主義、非科学的練習、理不尽な構造といった貧しい現実と価値観を一変させる具体的道筋を求め続けてきた。自ら選手、コーチ、指導者、スポーツ組織の会長、イベントプロデューサー等、多くの立場で実践を続けてきた。中でもフリスビーを通じたアメリカの新しいスポーツ観、武術に学んだ日本の身体文化に大きな気づきを与えられた。主な著書に『野球の真髄』『宇城憲治師に学ぶ 心技体の鍛え方』『子どもにスポーツをさせるな』『高校野球が危ない!』など多数。

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)
神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は、カルチュラル・スタディーズ。著書に『真実を語れ、そのまったき複雑性においてースチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)、『セルティック・ファンダムーグラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)、『反東京オリンピック宣言』(共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット、2019年)他多数。

山本敦久(やまもと・あつひさ)
成城大学社会イノベーション学部教員。専門は、スポーツ社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文化論。著書に、『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020)、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(小笠原博毅との共著、岩波ブックレット、2019年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(田中東子、安藤丈将との共編、2017年、ナカニシヤ出版)など。
【以下、トークの内容】
山本:みなさんこんばんは、ポスト研究会第14弾です。今日、司会をします成城大学の山本敦久です。「社会から孤立するスポーツ」というテーマでこれから2時間、3人でお話していきます。最初にゲストを紹介させてください。まずはスポーツライターの小林信也さんです。私は、小林さんの書かれたものを昔から読ませていただいて若い頃はNumberの記事を読みました。それから高校野球に関する本で触発されてきました。いま、日本で最も信用すべきスポーツライターのおひとりです。小林さん、今日はよろしくお願いします。
小林:そんなふうに言っていただいて、ありがとうございます。
(一同拍手)
山本:もうひとりは、小笠原博毅さん、神戸大学教授でございます。今日はよろしくお願いします。2020年はオリンピックイヤーでしたので、オリンピックの話をこのぽすけんでも多く扱ってきました。「もういいかげんスポーツの話はいいんじゃないか」と言われ始めてます(笑)。「またスポーツをやるのか?」ってお思いでしょう。
(一同笑い)
山本:オリンピックイヤーだからスポーツの話をするということではなくて、いまこそスポーツをきちんと考えたいわけです。これまで僕と小笠原さんは、オリンピック批判をしてきました。だからといって、同じようにスポーツ批判ができるわけではない。湯水と一緒に赤子も流してしまう、というように、オリンピックがダメだからといってスポーツもダメだ、といって済ませるわけにはいかない。確かにダメな部分いっぱいあります。今日は、スポーツについて少し斬新な仮説で迫ってみようと思います。みなさんスポーツって良いものだって思ってるじゃないですか。スポーツが世界をひとつにするというように。世界中の人が同じになる、ひとつになるって、言ってみれば全体主義やファシズムのようなことをメディアは無意識に発信しますよね。そういうことではない、もっと違う角度からスポーツの根源的な可能性を探っていきたい。刺激的な話がでるかもしれません。スポーツよく観てる人たちも、「え、スポーツってそんなふうに考えていいの? メスを入れていいの?」って思うかもしれません。でも、今日は、あたりまえに、いいものだとされてきたスポーツに対して、ちょっと違う角度から踏み込んでみます。そうやって、新しいスポーツの見え方、考え方を提示できればいいと思っています。さて、小笠原さんは甲府、山梨県出身ですよね?
小笠原:大月です。
山本:すいません、大月です。小林さんは越後、私は信州出身。もうお分かりですね。武田信玄と上杉謙信の川中島の戦いです。僕が育ったのは、長野市川中島です。僕の実家近辺で、武田と上杉は5回も戦をしたという歴史があります。
小笠原:その節は。
山本:というわけで、今日は「甲信越」による川中島の合戦ということでお伝えしていきます(笑)。
小笠原:ちなみにreadin’ writin’の店主は甲府です。山梨強いぞ、今日は。
山本:ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ何から話しましょう。どうでしょうか、小笠原さんまずキックオフ、プレイボールということで...。
小笠原:一番激しかったのは川中島の4回目でしたか(真顔)。山本さんが先程、スポーツとはいいものだと思われているとおっしゃいました。例えば勇気や感動を与えるとか、そういうことも含めてですね。そうやってスポーツを礼賛する人がいる一方で、同じくらいの質量と強度でスポーツを嫌う人もいる。それはスポーツが得意不得意とは違うレベルで、例えば非常にマッチョであるとかという理由で。当然スポーツは勝利至上主義という言葉があるように、勝った負けたで人間の能力に優劣をつける。それによってスポーツで体を動かすことが嫌いになっちゃう子供もいる。そうやって劣等感を生み出し人をだめにするんだっていう理由などです。
そういう批判というか非難があると思うんですけど、スポーツというのは人の能力に優劣をつけると。微妙な言い方になりますが、トレーニングして上手くなった人と、天性の素質をそのまま発揮するだけの人、トレーニングによって天性の素質を開花させることのできる人など、いろいろなレイヤーがあるけれど、結局優劣をつけるのは優生思想につながるのだと。より速く、より遠くへ、より高くというのはいわゆる健常者を基準にした形で人間の身体性を考えているのだと。パラスポーツやパラリンピックもあるけれど、それはあくまで後発のものであって、いまでも主流の考え方というのは健常者の身体を基準にしている。などなどいろんな言説がありますよ。
とみに最近激しいのは勝利至上主義批判です。気をつけたいのは、勝利主義でなく勝利至上主義だということです。勝つためには手段を選ばないということです。メディア報道のわかりやすい例は、2年前関学と日大のアメフトの試合で起きたタックルの問題でしょうが、勝ち負けをつけるということと、どんなに犠牲をはらってでも勝つことが真理なんだっていう勝利至上主義というのは違うのかそうじゃないのかということが曖昧なままです。だって勝ち負けがつかなかったら遊べないこともあるわけでしょう。鬼ごっこだって捕まったら負けですからね。
遊びがスポーツの起源の一つだとしたら、遊びの中にもうすでに勝ち負けというのがあって、それがルール化されたのが近代スポーツで、さらにそれがプロ化されたり報奨金や賞罰みたいなものが強調されると、何がなんでも勝ちゃあいいんだみたいな価値が蔓延してくる。だからだめなんだと。この、だからだめなんだという言い方には、先程申し上げた勝ち負けを決めるという遊びの要素と、どんな手段を使っても勝てという勝利至上主義とがごっちゃになっている気がする。
山本:小笠原さんがいまおっしゃったことは、いまでもスポーツを根源的に考えるときの入口だと思います。勝ち負けを決めないほうがいいという風潮、手をつないでみんなでかけっこゴールしましょう。それってどうなの? って思うわけです。スポーツをより楽しむために勝ち負けを決めるっていう、それはスポーツがもってる楽しみを膨らませるための仕掛けのひとつです。ただ、この仕掛けがどんどん肥大化してナショナリズムとか、いろんなものがそこにくっついて勝利至上主義というのがデフォルトになっていく。だからと言って、勝ち負けを決めることと勝利至上主義は同じではないということが重要ですね。その辺含めてスポーツを考えたい。小林さんは長岡高校のエースで、その後、慶應義塾へ進まれますね。エースピッチャーとして野球をやられていたわけですが...。
小林:大学では野球部の合宿所を一週間で2回逃げました。一度は励まされて戻ったのですが、二度目は逃げ切りました。
山本:どうでしょうか、小林さんの経験含めて...。
小林:二人のお話を聴いている間にいろんな思いが浮かびました。まず『スポーツ基本法』にも「スポーツはいいものだ」と書いてるわけですね。でも、スポーツはやり方を間違えると大変なことになる。身体も心も蝕む危険があるという認識を共有することが抜け落ちている。全体主義について言えば、スポーツってひとりひとりの心に浮かぶひらめきや喜びを触発してくれるから楽しい、素晴らしい。でもそれを最大公約数的に「スポーツはこうだよね」って押し付けられた時に変質してしまう。とくに、誰かがスポーツを利用しようとするとき、例えば学校の先生がスポーツを利用して生徒を管理する、政治家が政治のために利用する場合です。あとは商業利用ですよね。そういう時は、利用する側が勝手に「スポーツってこうだ」と最大公約数的なところで決めつけて、知らずしらず私たちはその認識を押し付けられる。僕は、自分だけの感覚だと思ったスポーツの楽しみや感動を、実は知らない誰かも同じように感じていたと知ったとき、「俺も同じ!」とか、そういう会話に出会えたらまた興奮する。それ以上喋らなくても通じ合う、心がつながるみたいな、そういう共有感がスポーツの原点にあるのがいいと感じている。商品化された共有感みたいなものが蔓延しているのは、すごく居心地が悪いです。
山本:僕、今のお話とても納得できました。ひとりひとりのスポーツ経験。一度しか経験できなかったあの日のあのプレー。それを一生おぼえている。しばしばスポーツ経験の記憶とはそういうものです。その特異な経験をもった人が、同じような経験がある誰かと話をする。それはもう、お酒が進むとか盛り上がるとか。仰るとおり多様なひとりひとりには、多様なスポーツの楽しみ方があるはず。でも、その1回限りの経験がパッケージングされて、それがだれかに利用される。まさにスポーツが秘めた危ない部分ですよね。それだけ魅力的だからこそスポーツが利用される。資本主義、国家、学校教育、親もそうですよね。小林さんは、長く野球されていましたけど、そういうことって何かありますか?
小林:新潟県という当時は高校野球のレベルが低いところでそれなりにやっていました。ときどき県外の甲子園に出るような学校と試合をしたとき、信じられないレベルの選手に出会うことがあった。僕はアンダースローの投手だったんですが、相手打者の雰囲気で、どう投げたら抑えられるかだいたい感じられた。その通りに投げたらまず打たれない。ところが、よし抑えた、と思った次の瞬間、突然バットが出て痛打されることがある。打たれてショックなはずだけど、僕は感動した。すごい打者がいるもんだって。
小笠原&山本:え~~!!
小林:球威はなかったんですけど、バッターを翻弄する感覚が楽しかった。でも自分の発想のレベルを超える相手に出会ったら、驚くし、興奮しました。
山本:打たれて逆に?
小林:すごいやつがいるんだなって。自分が想像していなかった次元に出会ったときの感動。でも、それをチームメイトに話すと、「打たれて喜ぶって馬鹿じゃないの」って、あまり理解してもらえなかった。あんまりうれしくて、その選手に手紙を書いたこともあります。
山本:打たれた相手に?
小林:どこに出していいかわからなくて、結局机の中に仕舞っておいたら、遊びに来た友達に見つかって笑われましたけど。僕にとっての野球の喜びって、そういうものでした。
小笠原:まるで恋ですね(笑)。前回ここで関西学院大の阿部潔さんをお呼びしたときに、彼まったく同じ話してたんですよ。彼は陸上部で長距離をやっていたんですが、すげーやつがいると。5000m走って周回遅れにされてしまうんですが、追い越される時の足音、熱量や風、そういうのを感じてこいつすげーなってなって、かなわないやつがいるんだなって。そういうやつがいてそういうやつと一緒のトラックを走っているのが喜びなんです。彼の思い出がそうなんですよ。彼がなにか達成したんじゃなくて、叶わなかったことを覚えているんです。
小林:今度は違う話です。《42.195kmリレーマラソン》ってのを考えたことがあって、やり方も名前も僕が考えたんです。最初は国営公園から「24時間耐久レース」ができないかと相談された。いろいろ調べたり考えたりしたけど、24時間も走りたいのは一握りの人だ。それより「もっと大勢が楽しめる、走るきっかけがなくて普段はためらっている人たちも参加できるレースにしたい」と考えて思いついたのが、2kmのコースを4人から10人で21周リレーして、最後の195メートルは全員で緒に走ってゴールする、というレースでした。
山本:めっちゃ楽しそう。
小林:その時、招待選手に来てもらおうと、当時のオリンピック候補選手にも来てもらったんです。高橋尚子さんが金メダルを獲ったあと、イベントに招待されている光景をよくテレビで見ましたよね。だいたい、ゴール前で選手が待っていて、笑顔で一緒にゴールするみたいな和やかなやり方なんだけど、僕は「それは違う」と思っているんです。実は強烈な思い出あって。
長嶋監督が解任されて浪人しているとき(1982年)、札幌の少年野球の指導に同行取材したときのことです。長嶋といっても、少年たちはもう選手・長嶋を知らない。感激しているのは親だけ。ところが、長嶋がサードで守備の手本を見せ始めたとき、少年たちの目が輝き始めた。ノックを受けて長嶋がものすごい勢いでダッシュして投げるんです。僕も、プロのダッシュって半端じゃない、勢いが全然違うと驚いた。でも、少年たちは、ダッシュを見ているんじゃない。見るとみんな、一塁方向に顔を向けているんです。それに気づいたのか、長嶋がわき目も振らず叫びました。
「気にするな、暴投なんか気にするな。ダッシュだ、捕ったらすぐ投げろ!」
そう言って繰り返し、まだダッシュと送球を繰り返す。その送球がことごとく暴投なんです。でも長嶋は気にしない。その迫力がすごかった。
(一同笑い)
小林:もう子どもたちは、自分もやってみたくてうずうずする。その後の守備練習が活気づいたのは言うまでもありません。その衝撃があったから、スター選手が甘いおもてなしをするんじゃなくて、来たからには本気で走ってもらいたかった。だから招待選手に、「周りを気にせず、とにかく2kmのコースを自分のペースで走ってほしい」と頼んだら、「いつもの練習どおりに走らせてもらいます」って。そうすると、一般の参加者がまだ1kmも行かないうちに2周めに入った選手に抜かれる。追い越されるときの感覚、「うわ、すごいスピード、みたいな。一流選手の風を感じるって素晴らしいでしょ。そういうレースをやったこともあります。イベントになるとみんな仲良くやりましょうみたいな盛り上げ方が多い。それも最大公約数的というか、最低限満足を提供するための保険みたいな、そんなんじゃスポーツの本当の昂奮や感激は味わえない。僕はそう思っているけど、そういう挑戦的なというか、本気でスポーツを感じてもらう目的で計画されるイベントは少ない気がします。それで、やればやるほどかえってスポーツの本質から違う方に行ってしまう傾向がある。
山本:先週、文化人類学者の今福龍太さんと別のイベントで話したんです。そのときも長嶋さんの話がでてきました。サードゴロを広岡の前で奪うように掬い上げて。なんとそこでプレーが終わるというのです。一塁にボールを投げてないのに守備の選手たちがもうアウトだと思い込んで、というかその一連の長嶋の動きに選手たちが魅了されて、もう一塁に投げたと思って帰って行ったという伝説があるらしいんですね。やっぱり長嶋という人がもっている何かがあるんですね。とにかく無尽蔵に自分の体を使って自分の表現をやる。それはファーストミットにボールが投げられようが、投げられまいが、長嶋の中で起きている押さえきれない何かなんですよね。それを他の選手も、観客もその表現に巻き込まれていく。
小林:勝利至上主義では「勝つこと」が目的になりますよね。すると、守りの要素が強くなるじゃないですか。これはやっちゃいけないとか、こうした方が確率は高いとか、どうしても規制される方向に行く。
でも、なんで長嶋さんがみんなから愛されたかと言うと「エネルギーを発散していたから」なんですよね。僕の記憶の中の長嶋は、ゲッツー打のほうが多いですからね。長嶋さんにどれだけがっかりさせられたか。でも、がっかりを共有した末に打ってくれるから、感激はすごい大きい。勝利至上主義や商業主義のいけないところは、がっかりすることを恐れるというか、がっかりを共有する機会が少ないことのように思います。
山本:なるほどー。
小林:東日本大震災で日本が悲しみを共有したとき、なでしこジャパンの女子W杯サッカー優勝がありました。東北楽天の優勝も、特別な感慨をともなって響いた。そこにスポーツが果たせる役割があることを僕らは感じたと思います。スポーツビジネスが作りだそうとする感動や興奮は、それとは違う。人々の生活や実感とはどこか違うところに感動のパッケージを作って、無理やり共有する興奮は本物じゃない。
山本:小笠原さんはイギリスでの生活が長かったわけですけど、「がっかりする」についてどう思います? サッカーには、この「がっかり」の共有がありますよね。特に労働者階級の人にとって。「がっかりする」っていうことの重力がイギリスの人たちにとって結構重たいじゃないですか。このがっかりするっていうことを受け入れる、受け入れないっていうことをまるごと含めてサッカーの記憶として堆積していくでしょ。
小笠原:なんか、スポーツの意味を一方向に見つけようっていう動きがどうも日本社会は強いというか。さっき小林さんがおっしゃった共鳴っていうのは、ピピってくるって話でしょう。平面でベタッと共有されるんじゃなくて、点と点がピピッとなって線のつながりができるってことでしょう。共鳴と言えば、例えばイギリスではサッカー・スタジアムのスタンドの応援で誰も音頭を取らない。鳴り物もないし、いまJリーグも鳴り物だめですけど、野球の応援団からの流れかもしれないけれど、音頭取る人いるでしょう。コールリーダー。いないですよ、そんなの。このタイミングでは何を歌うか、このタイミングで誰の名を叫ぶか、なんとなく同じようにやって大きな波になる。期待したプレイができないときはあーってがっかりして、はってやってあーってなる。それを別にウェーブやろうって言ってやってるわけじゃないですよ。でもそれを鳥の目線から見ると面白い。
ゴール近づいてるぞっていったらなんとなくこう立ち上がって同じ方を向く。ミスるとはーってがっかりする。何万人がそれをやるわけでしょ。そこにリーダーがいるわけじゃないから、それをファシズムって言うのは間違ってるし、同時にそのがっかりがあまり長続きしないんですよ。すぐ入れ替わる、すぐ転換するっていうペースがある。ドライって言えばドライだと思います。
小林さんが長島はゲッツーばっかりっていうのと似ていて、僕は王貞治は三振ばっかりしてる、三振かフォアボールばっかりで、ホームラン打ってる記憶は少ない。すごいポジティブな、陰と陽で言ったら陽、成功か失敗で言ったら成功ばかりがもてはやされるけど、我々自分で経験した記憶は失望したり失敗したりしたことのほうが残ってるのはあたりまえで、スポーツって100回やったら99回は思ったようにいかないんですよ。それが重要。そこをきちんと書いたり伝えたり共鳴させあったり記録したり、もっと言ったらスポーツの現場で取材をしたりしてる記事を書いてる人は、なんというかそっちの失敗で生まれる葛藤や、そこで選手はどう考えているのか、観てる人はどう観てるのか、それを考えてくれないから一面的なベタな、誰が書いても同じようなスポーツ・ライティングになっちゃうっていうことではないですか。と、スポーツライターの前で言っちゃうんですけど(笑)。
山本:日本にスポーツ批評というのがあるのか、それともないのか。そのあたりを話したいですね。どうしてこんなにスポーツに対する批評が成立しないのか。
小林:今のスポーツには、批評がきちんと存在しにくいですよね。例えば、野村監督の下でチームが優勝しました。ファンは感動しました、視聴率があがりました、すると野村監督を誰も悪く言えないんです。勝ったことに文句が言えない、買って盛り上がっている商材にみんなが乗っかろうとする。
あるいは、野村さんが評論家時代に話題となった9分割の「野村スコープ」とか。それが現役時代、キャッチャー・野村のリードの核心だったかとうかはわからない。あれは見て楽しむとき、打者とバッテリーの勝負の綾がわかりやすい。でも実際に打者を抑える要素は別にあるとしても、ファンはもうそれが野村のリードの核心だと思い込んでしまう。例えば僕みたいな書き手が、「本当は違うんですよ」なんて言ったら水を差すことになるから、そういう指摘や原稿は歓迎されない。自ずと、自由な批判や発展性を阻害する方向でメディアは動いている。
400勝投手の金田正一さんがロッテの監督だったとき、弟の金田留広さんがトレードにロッテに入った。そこにやはりトレードで入った野村捕手がいた。これは留広さんから聞いた話ですが、「野村さんが相手だと投げにくいなあ、理詰めの投球は性に合わない」と心配していた。そしたら初めてバッテリーを組む試合前、野村さんが、「トメ、ど真ん中でいいから、ガンガン来いや」と声をかけてくれた。それですごくテンションがあがった、「なんだ、やっぱり野村さんも勝負の土俵では理屈ばっかりじゃないんだな」って。9分割の配球だとか野村IDというのはメディアの話題になりやすい。けれど勝負の核心とは限らない。商業主義が優先すると、その違いさえも一般には伝わらず、ひとり歩きしてしまうわけです。
小笠原:小林さんのことを初めて知ったのは「スポーツ・グラフィック・ナンバー」っていう雑誌でしたが、いつの日からか「ナンバー」を買わなくなってしまいました。その理由はいろいろあるんですけど、昔の「ナンバー」に載っている記事のほうが端的に言っておもしろかったと思います。ずっとスポーツを観てきた人だけじゃなくて、いろんな分野の人が書いたり、ライターも入れ替わりがあったり、同じライターでもボクシングとかサッカーだけとかじゃなくて横断的に書いていた。それにもっと理屈っぽかったですよ。それがいつの間にか褒めるんだったら褒めるばっかりになってしまった。怪我を克服したとか、あと大嫌いなんだけど、内助の功とか家族の助けがどうしたとかね。そりゃあそういうことはあるでしょう。あるけどそこなのかっていう。事実はどうした、プレーはどうした、このプレーについての視点や研究やその蓄積はっていうものが相対的に減った。
小林:創刊1年目から4年目までお世話になっていました、編集部のメンバーは月刊文芸春秋とか、オール読物などの小説誌にいた社員が多かった。あの頃は、この原稿を誰に書いてもらおうかって話し合うとき、最初に挙がるのは井上ひさしさんとか、いわゆる作家の方々。当初のナンバーは、「スポーツ文春」「オール読物スポーツ」といったイメージ。スポーツの深みを文学的に表現できないかという共通の野心を持って誕生したのだと思います。
もちろんそれに加えてビジュアル。それも、スポーツ新聞で主流になっている「決定的な場面」とか「証拠写真」みたいな平板なものではなくて、心情や機微を浮き上がらせる芸術性のあるスポーツ写真の文化を日本に定着させたいという野心があった。だけど、その路線では、たまにうまく話題になるけどあまり売れないことが多かった。なかなか商業的に成功しない。そこにJリーグが誕生して、ブームが起こった。サッカーの熱狂とナンバーがうまくかみ合う流れに乗って、商業的に成功した。ナンバーをビジネスにするパターンが生まれたというか。ところがそのころから、小笠原さんが言うように、つまらないと思う人が増えてきたのかもしれません。最初の文学性や芸術性といった野心より、もっとダイレクトな興味や興奮とつながったからでしょう。
山本:スポーツって、今おっしゃったように一人ひとりの心のなかに色んな経験としてあるんだけど、さきほど小笠原さんが言ったように、スポーツの場面って、二度と同じことが起きない。同じひとつの身体なのに、同じことが再現できない。1回1回の経験ってのが、それぞれ特異であり、厳密に再現できないのがスポーツの難しさや困難でもある。それって、じつは商品になりにくいんじゃないですかね?
小林:最近、ゴルフの倉本昌弘さんの新刊『倉本昌弘の自由奔放ゴルフ』(マガジンランド, 2020)のお手伝いをしたんです。これは倉本さんが週刊新潮に連載していた《冒険ゴルフ》というエッセイをまとめた本です。この本には、倉本さんならではの考え方、勝ち方が書かれていてすごく面白い。例えば、スポーツ選手はよく「好調時にビデオで見直す」って言うけど、倉本さんは絶対しない。「なぜなら、ゴルフでは、以前と同じショットが2度はない。同じようなショットでも、距離が違う、風が違う、ライが違う。だから過去のデータは役に立たない。過去の経験を応用力という感覚に変えていくならいいけれど、「あの時と同じ打ち方でとか、過去を思い出しても意味がない」というのです。かのスポーツでも、あのシュート決まったからとかホームラン見直すとかあまり意味がない。ところが、スポーツを商売に利用したい企業や広告代理店は、「ビデオは技術の習得に有効だ」という。それでビデオを普及させたい、買わせたいわけだから。商業主義の問題というのは、スポーツの本質を曲げられちゃって、それに誰も異論を挟めない構造ができてしまうこと。スポーツをテーマに発信する人間としては、やっぱりそれには屈しないように取り組みたいと思います。
小笠原:今小林さんは、我々が思ってる商業主義と真逆のことを教えてくれた。スポーツにはもともとメディア・コンテンツになって売れる要素が内在してるから飛びつくんだって思いがちだけど、実はそうじゃないんですね。商品になるようにスポーツ自体が管理され、制御されている。
山本:なるほど。おもしろいですね。トロブリアンド・クリケットを想起させられます。大英帝国が作り出したクリケットという身体文化が、植民地主義のなかでトロブリアンド諸島に伝播していく。でもやがて島民たちは、支配者に教えられたクリケットとは全く違うルールとフォームと独自の意味をつくりあげていくんです。ぜんぜん違うクリケットを独自につくりあげていってしまったという歴史があります。だからスポーツはいかに失敗を運命づけられているかということですよね。こういうふうにやれと言われたけど、必ずそれと同じものにはならずに、ズレてしまう。そのズレがスポーツのなかではちゃんと評価されないし、言葉にされてこなかった。むしろスポーツの本質は、失敗にあるかもしれない、習ったとおりにできないということにあるとしたら、それは新しいスポーツの見方になるかもしれません。スポーツが持っている偶発性や不確実性こそ、スポーツの本質かもしれないと考えてみるとどうでしょう。正しいスポーツはこうですよ、という鋳型を想定すると、スポーツの魅力が狭く狭くなってしまう。ひとりひとり模倣してズレていく。コピーを失敗して、新しいものを生み出してしまう。それって厳密な意味で、スポーツの本質だと思います。みんな長嶋のように大胆な表現をする可能性があるわけじゃないですか。だけど正しいフォーム、正しいサッカーの仕方、野球の仕方、正しい投げ方に身体を制御していってしまう。小林さんがアンダースローだったということをお聞きして、今の話に説得力が増しますよね。小林さん、かなりフィジカルがあるから、オーバースローの本格派なのかなって勝手に思い込んでいました。
小笠原:ソフトバンクの高橋だっけ。彼190cmくらいあるよね(注:実際は188cm)。
小林:僕はアンダースローになってすごくよかったのは、上から投げていたら球威で勝負するというのが基本にありますけど、アンダースローというのは間合いなんですよ。これはつい最近「週刊新潮」にも書いたんですけど、伊良部が157kmを清原に打たれました。日本一速い球投げても打たれちゃう。どうしたらいいんだと。そこから始まるんですけど、そこで彼がたどり着いたのは、さっきの9分割をアテにして野球しちゃだめだってことなんです。だって、こんだけ離れているところに、タバコの箱1つくらいの、あれを外すなんて無理だっていうことなんです。そうすると何ならできるかって言ったら、スピードの変化なら、自分で意図的にできるっていうこと。奥行きを使うということなんですよ。僕はアンダースローで何やったかっていうと、ゴムでピュッと離したり、そうするとバッターがおぉってなるし、それは相手の軸をずらすというかですね、それはやっぱり伊良部もわかってから、抑えられるようになった。それでスピード板なんかができたりすると、数字が良ければ良いほど、強いみたいになっているけれど、それを最初にそんなんじゃだめだって言い出したのが伊良部だったわけですね。
小笠原:スピードガンって、小学5年生くらいのときに出てきたと思うんですが、初速と終速って出て、10kmも違うんだとかわかるわけ。このリリースのときとベースを通る時の速度の違いですね。確かにあれがいろんなことを狂わしたかも。
山本:今の若い人にはわかんないと思うけど、YouTubeなどで昔の映像みると、スピードが2つ表示されるんですよ。
小笠原:江川はほとんど違わなかったとか、ホップしてるとか。物理的に原理的に、ホップすることってないんですよね。
山本:それは最近の科学のなかでは、厳密に言えばホップすることはないといわれてますよね。
小笠原:18.44mの中間ぐらいでは膝下に見えたのがベース上に来たら目の高さだったって話があったり。
小林:そう見えるんですね。
小笠原:1個いいですか、アンダースローの間合いの話。里中がね...。
山本:あ、これは新潟が生んだ偉大な漫画家、水島新司先生の傑作。高校野球マンがの最高峰『ドカベン』の登場人物です。
小笠原:小さな巨人・里中智がね、明訓高校のエースの。新潟明訓とは違うけれど、モデルですよね。野球部の人たちにだまってゴルフのキャディーのバイトをするんです。里中は母子家庭で生活が苦しくてバイトをしなければけない。彼がキャディーしながら何してたかというと、パッティングするときにゴルファーの目線とホールまでの距離をずっと見てた、間合いを測ってたんです。知ってるでしょ?
山本:知ってますよ。
小笠原:アンダースロー、決め球はシンカーですか?
小林:カーブです。
小笠原:里中は親指を突き指して、人差し指と中指に乗せて投げなきゃいけない。だから極端なシンカーを投げられた。それをさとるボールって言うんですけど。
山本:それをいったら店主と小笠原さんの山梨が生んだ巨人のエース堀内恒夫の指も面白いです。
小笠原:まあ甲府だから、彼は。
山本:甲府商業ですよね。
小笠原:だから中指で押してやんなきゃいけないから、堀内のカーブってこう、手の甲をバッターに向けるように投げるんですよ。昔あれドロップって言ってた。話を戻そう、失礼しました。
山本:どこに戻すの?
(一同笑い)
小林:宮崎・日南学園の寺原ってピッチャーが話題になったとき、たまたま甲子園のスタンドで見ていました。僕は寺原の投球や、彼のマウンドでの一挙一動をジッと見ていたのですが、スタンドのファンは違う。寺原が投げ終わるとすぐ、みんな一斉にスコアボードを見るんです。スピード表示の数字を確かめたくてね。それがすごく気持ちが悪いというか、僕は不思議な感じがしました。目の前で見た、寺原のボールに感動しているんじゃない。スコアボードで数字を確認してから、どよめいたり、落胆したり。寺原の投球がすごいかどうか、見て感じればいいのに、ボールより表示を見るわけです。
山本:こういう話が、本来、スポーツ批評だと思うんですよ。こういうものがじゃあ巷で読めるかって言うとないですよね。だから満足できるものがないから自分たちでやってるところがあるんですよね。
小笠原:批評的なことが言えなくなるのは何が怖いかというと、2つある。1つは眼力の低下。眼力でいいのかな。すぐ数字に頼ったり、自分では計算したり作り出したものでないデータを後付けでプレーに当てはめてしまう。身体活動の不安定さや不確実性といったものがネガティブなカテゴリーにしか入らなくなってしまう。もう1つは批評という体裁でエリートスポーツのすごい人達ばかりが基準になってスポーツが語られるようになってしまう。ぶっちゃけ、その、それほどのレベルじゃなかった人たちや書いてるだけの人たちもいていいでしょう。嫌いな言葉なんですが、「現場を知らない」とかすぐ言う人いるでしょう。現場を知ってるのはごく一握りでしょう。小説家はごく一握りだけど文芸批評家はたくさんいるかもしれない。そこから逆に作家になったり、作家をしながら批評を生業にしてる人もいるでしょう。音楽もそうでしょう。プロじゃないけど素晴らしい音楽批評する人がいる。それと同じ。「現場を知らない」っていうのが、一流の技術と高いレベルになっていないと言葉を使って批評してはいけないみたいな分断を強めてしまうのではないでしょうか。
小林:僕の取材経験から言って残念なのは、スポーツを表現する言葉が「平均点」に収束しがちなところです。スポーツの技術にしろ、勝負を分けたポイントにしても、ひと握りの勝利者だけが感じた本当のポイントを話しても万人には理解できない。それでチャンピオンたちも本当の実感は喋らない、ある程度のところでとどめる習性みたいなものが当たり前になっている。それを聞いて報道する側も、当然、チャンピオンだけが知る感性や領域は体験もないし、聞いても理解できないので、自分が理解できる範囲で表現してしまう。すると、本当にチャンピオンたちが踏み込んだ特別な領域、いわば120点や150点の世界を語るのでなく、誰もが理解できる平均点70点くらいの表現にとどまってしまう。そういうもったいなさがあると感じています。それにスポーツが好きな人ほど、「オレがいちばんわかっている」「オレに語らせろ」みたいな意識が強いので、それ以上の表現が歓迎されない感じもある。
小笠原:俺もそういう所あるな。でも一番イヤなのは、「誰々と飯食った」とか「誰々ならよく知ってる」みたいな、特定の選手との親密性を「現場」と取り違えている連中です。そういうのとは、ちょっと、いや、だいぶ違う。
(一同笑い)
小林:若いころ何度か知らされて残念に思ったのは、かつての金メダリストたちが大事なことをほとんど喋らないという事実です。レジェンドたちが本当に感じたことを喋ると、「おかしいんじゃないか?」みたいな感覚もあるらしいのです。どこか神がかったような感覚もあるし、一般の常識では理解できない領域にも踏み込んでいる。もしそれを喋ってしまうと、逆に変人扱いされたり、非難されたりする心配がある。実際、そういう思いを経験した人もいて、やがて話すことをしなくなる。
実際に、世界一になった人は、普通の人からしたら「非科学的」なことを言う場合があります。それは非科学的なわけじゃなくて、科学が解明できている以上のレベルを身体で実践してしまっている。なにかしら僕らの知らない世界に突入しているからこその快挙なのに、そこへのリスペクトがない。勝利至上主義というなら、勝った人にもっと真摯に耳を傾けるべきなのに、一般常識を基準にして、それをしない傾向もありますね。例えば長嶋の現役時代にはみんな手放しで賞賛し、敬愛していたのに、「長嶋も監督としてはダメだね」と平気で上から目線になる。僕は『長嶋茂雄語録』(河出文庫, 2013)という本も書かせてもらっています。確かに、面白おかしい、ちょっと理解不能な言葉もあるんですが、意外と真理を衝いているんです。「ボールは必ずここに来ます」とかね。普通に言ったら、投手のボールはどこに来るかわからないんだけれど、打者・長嶋が打つ時、ボールは必ずある一点に来る、そこに来たら打つという感覚だったのでしょう。そこには、科学的な表現では言い表せない打撃の極意があったりする。スポーツの高い次元はそういう感覚でなければ表せないと思うけれど、多くの人がそういう覚悟を持っていない。70%くらいのところで、みんなが理解できる表現にしたほうが視聴率も上がるといった事情で、スポーツ表現の発達が抑えられているのは残念です。わかるわかる、あるある、みたいなところで商売が成り立つから。そうすると「突き抜けたこと」は語りにくくなる。
山本:最大公約数に落ち着いていく。そこはマーケット的には落ち着いてくるエリアなんですね。
小林:スポーツが持つ宿命というか現実があります。例えば高校野球にしても、最後まで負けないのは4000校近い参加チームの中で1校しない。オリンピックでもそう。金メダリストは、すべての競技者の中の1人か1チームだけ。すごく低い確率です。つまり超少数派なんです。少数派の考えは、多くの人が理解できないから、商売になりづらいみたいな図式があるわけです。だから残念ながら、圧倒的多数の、勝てない考え、負ける考えの方が多数派になって、世論を形成してしまう。大勢の人が信じる「負ける発想」が、「勝てる発想」にすり替わって幅を利かせてしまう。
山本:だからトップアスリートの飛び抜けたりする身体の世界、説明不可能な世界、あるいは翻訳不可能をどうやって最大公約数的なものにするかってときに、スキャンダルをまじえて話題にするというような商品化の仕組みがあったりするんですよね。スター選手は、スキャンダルまみれにされて消費されていく。マラドーナがどんな視野や世界のなかでサッカーをやっていたのか、そういう部分が僕らには見えてこない。彼の問題については確かにいろいろ知ってる。でも、スポーツ特有の体験や経験という翻訳不可能なものは、スキャンダルのようなものによって商品化されて、テレビのなかで消費されるという構図がある。そうしないと、結局スポーツの消費が成り立たないという。
小笠原:普通のレイヤーに閉じ込められてしまうということ。
小林:なかなか共有できないと言ったけど、実はそれを共有しやすいのが日本人なんじゃないかという期待も持っています。日本には、第六勘みたいな感覚や、火事場の馬鹿力みたいな尋常でない潜在能力を認識する文化もある。ムシの報せのような経験も多くの人が共有している。科学が前提の世の中ではそれがなかなか一般化できないところがあるけれど、僕が勉強してきた武術ではそれが体系化されているんです。武術もある時代から分断されてほとんどいま本質が伝わっていないのですが。僕が出会った師匠が体現する武術の世界には、科学では説明できないけれど、人間が本来は誰もが持っている心技体が生み出す力の発露がはっきりとあります。かつては日本人が当たり前のように共有していた心身の力や感性が、明治そして戦後を経て、意図的に分断されてきた。そして、欧米の考え方のほうが遥かに素晴らしいといった間違った啓蒙によって、日本の身体文化は衰退した。いまは日本の伝統的な身体文化は廃れて、完全に欧米的な考えに支配されていますよね。
小笠原:合理化されたってことですよね。
小林:全員がそうだとは言いませんが、天才と呼ばれる選手たちの多くは、何を手がかりにその領域に到達したかはわかりませんが、日本人が元々持っていた身体感覚、武術的な発想を自分の技術として磨き上げているように感じます。
山本:型があるってことは、つまり共有を目指してるわけですよね。
小笠原:ただ型もみんなに平等に伝承されるわけじゃないですよね。
小林:呼吸と姿勢。僕は武術の入り口を学んだにすぎませんが、それでも、武術の型が教える姿勢を取ると、それだけで身体に芯がとおり、重心が重くなるといった明らかな変化が起こります。それを学んで試したスポーツ選手が鮮やかに変わるところも何度も見ています。
山本:スポーツにはユニバーサルな型ってないじゃないですか。先ほども話題になったように、必ず失敗するものだから厳密に型というのはない。イギリス人のエリート男性のなんらかのエートスは、各地域で誤読して違うものになったり、違うサッカーになったりする。これが多様性や差異となって様々なサッカースタイルができたり、テニスにしても多様なフォームがあったり。差異の肯定や多様性が、スポーツが世界にひろがるための魅力だったかもしれないけど。これは武道の発展の仕方とスポーツの世界的な広がりという比較をすると、どうなんでしょう? もちろん、どっちがいいとか悪いとかってことではないですが。
小林:武術的なアプローチを持ってスポーツに取り組むと、勝ち負けだけじゃなくなる。勝負を超えた、極める世界が目標になるから、素晴らしいなと感じました。しかも、体系化された武術を手がかりにすると、毎日の取り組みがスポーツの枠を超えて、日常の生活にも活かせる人間力につながる。例えば「漢字の書き順」ってありますよね。あれ、なぜ大切なのか、多くの子どもはわからないし、その意味までは教えられていない。武術的には、人間の潜在能力を発揮するための手順があることを教えられ、実感させられる。だから、漢字の書き順の大切さも自然と理解できる。基本があるから、楷書を徐々に崩して、行書や草書に変わり得る。発展性があるんです。これは野球にも通じる。バッターボックスに入るときの所作も、いまの野球界ではただ自由というか、まったく基礎がないけれど、漢字の書き順と同じく、本当は最も打つ準備のできる手順がある。そういう大事なことはまったく共有されていなくて、もしいきなり僕がそんな話をすると「精神論だ」と非難されそうだけれど、基礎も教えずに打てと期待する方がよほど精神論だと、武術を学ぶと感じるようになります。
小笠原:型とか、他の文化にもあるんじゃないですかね。フェンシングとかね。何回か前のポス研でもやったけど、パンクラチオンっていう古代ギリシャのレスリングの原型になってるものも型が抽象化された形で伝えられていくんですよね。そういうのって世界のどこかしらにあったと思うんですよね。それを武術は体系化する努力をわりときちんとやってきた。しかしパンクラチオンは別のスタイルに発展して、フェンシングは特権階級のものになってしまいましけれど、なんか最近スポーツ人類学の本が出たらしいけどその本には書いてないけどね、こういうこと。批判だよこれ。ある意味、部族スポーツや儀礼のなかには、たぶん世界中でそういう型という概念があると思うんです。
山本:”sameness”にむかっていくのか、それとも小笠原さんが『セルティック・ファンダム』っという名著を書かれましたが、そこで論じているような”changing same”(変化する同じもの)っていう概念で考えていくべきか。字義矛盾しているこの「同じようなものだけど変化していく」というサッカーの変容し続けるスタイルをどう考えていくか。これは型なのか、それとも、型であるが同時にそれは変化していくという「変化する同じもの」として考えていくべきか。
小笠原:その変化は...、ここが難しいんだけど、内面から自発的に変化するのか、社会からの影響を受けて変化させざるをえないのか。前提として、スポーツが社会から孤立しちゃってるっていうことへの反応としては、型と社会の間に断絶があるということですね。スポーツとは社会的なものだっていうところにたどりついたとき、それは社会の波も受けるし、スポーツが何かしたらそれが社会に影響を与えるしという関係性さえ作れなくなっているのかもしれない。
小林:いまのスポーツの価値観では、勝ったらいいんですよ。それがオウンゴールでも入って勝てばいい。ところが、勝つことが基準になると、次の進展の道が拓けない。反省のしようがない。基準があれば、例え勝ってもあまり意味がなかったとか、負けても次につながるとか、明確に分析できるし自覚でき、共有できる。勝っても奢ることも戒められるでしょう。仮に勝っても、「これはスポーツというルールの中で勝っただけで、次元は高くない」といった理解ができるからです。本当はそういう基準や手がかりをスポーツ界がもつことが、スポーツを日常の人間力づくりにもつなげられるために大事なんだけど、いまは勝利至上主義が全盛で、勝利が基準ですから、厳しいですね。
山本:ちょっと話をズラしていきたいのですが、例えばそういう道徳と近くなっていくところがあるじゃないですか。スポーツフィールドから離れたところにも、スポーツの規範的なメンタリティが転用されていくみたいな。それはスポーツがもつ1つの社会性だと思うけど。近年の、スポーツ選手に対する社会からの道徳の押し付け、スポーツ選手に対してのコンプライアンスの厳しさ、これが僕はすごく気になっています。武道みたいな型で考えることも大事かもしれないんだけど、今のスポーツ選手ってすごく縛られている、厳しい道徳に晒されている。カジノなんて、まあやっちゃいけないんだろうけど、すぐ怒られるじゃないですか。
小笠原:やっちゃいけないの?
(一同笑い)
山本:いや本当にスポーツ選手を取り巻く環境が道徳的に枠づけられて苦しくなっている。それこそ僕らは子どものころに野原でサッカーやろうが野球やろうが誰にも怒られなくて、むしろ「よく頑張ってるなお前たち」って近隣の人に言われたけど、いま言われない。そんなとこでバット振り回すな、サッカーやるなって怒られる。スポーツが窮屈になって、道徳的にちゃんとしてない人はスポーツ選手じゃないみたいなそういうしつけが凄く強くなってきているなかで、スポーツ選手が、またここでマラドーナに頼ってはいけないけど、ああいう人がスポーツ選手から出なくなってきている。とにかくスポーツ環境が息苦しくなってきている。
今回トークの主題はスポーツが社会からちょっと冷ややかに見られているというか、かつて僕らが、昭和のころ野球やってると自然とまわりが応援してくれたような空気感がないというか。だって運動会の準備していると近所から怒られる。部活やってると、これは大学でもそうなんだけど近隣からうるさいって怒られる。だんだん社会とスポーツの関係性が変わってきている。どうでしょう、そのへんの議論をしてみたいと思うんですが。その前に、ここで一端休憩しましょう。それではハーフタイムということで。
(5分休憩)
山本:それでは後半戦いきます。前半の最後に武道の話が出ましたけど、これちょっと誤解を招くとよくないので補足します。武道、これは近代にできあがった、いわゆる想像された伝統ですよね。さっき小林さんがおっしゃっていたのは近代化される以前、いわゆる「武術」と呼ばれているものということで補足させてください。
小林:「野球道」という言い方を嫌う人もいるんですけど、それは誤解だと思います。野球を通して道をきわめようとするのは、むしろスポーツの本質です。それなのに嫌悪されるのは、指導者側が「野球道」を標榜して、教える側の論理を押し付ける、自分の指導に服従させる方便に使われがちだからでしょう。
道を極める、という生き方は、あくまで自分の意志でするものであって、誰かに強制されるものではありません。自分の意思で、主体的に取り組むことが大前提です。いまの日本で、○○道という生き方が、誰かに強いられてやるものの代名詞みたいになっている。だから嫌がられる。それは大変な間違いです。むしろ道をきわめる生き方にこそ、スポーツの本質につながる道筋があると僕は感じています。
山本:素晴らしいご指摘です。もう今日はこれで終わりでいいんじゃないかっていう(笑)。
小笠原:スポーツは解放だってラグビー元日本代表の平尾剛さんが言ってたんだけど、走る、パスする、パスの道が見えるとか、考えられないようなパスが通るとか、ボールがすっと手に収まるとか、そのときになにか解放された気分になると。その解放性っていうのは人に強いられたりがんじがらめにされたり、ああやれこうやれって指示されたとおりに動くのでは得られない。アメフトでは選手が解放感味わえるのはパスが通った時のクォーターバックやパスを受けるランニングバックやワイドレシーバーだけだと思いきや、実はそうじゃないらしいんだけどね(笑)。ディフェンスで止めた時に解放感を得られるらしい、試合中一度もボールに触らなくても。クォーターバックに投げさせないように、タッチダウンさせないようにぐしゃぐしゃやったっていうときにも、あるらしい。それは別のお話しかもしれないですけど約束されたものじゃないですからね、こうすればこういう答えが出るっていうことではないはず。
前半の話に戻るけど、そこの答えが決められていないという過程には挫折があるわけで、何かが湧き上がってくるけどだめだっていう、失敗したと。ただそこでやめるんじゃなくて、なんで挫折したんだろう、どうすればもう1歩先に行けるんだろう、違う扉が見えるんだろうって繰り返しやっていくことに面白さや喜びが湧き上がってくるはずで、それを阻止しているものは何かって考えざるをえない。
小林:高校野球は負けたらだめじゃないですか。甲子園に行けなかったチームは全部だめなんです。負け、イコール挫折ですよね。僕は大学時代にフリスビーに出会って、のめりこんだ。ひとりでアメリカにフリスビーを学びに行った。当時アメリカでは、「フリスビー・ローズボウル」という世界選手権があって、本当に6万人の大観衆が集まるすごい大会だった。でも、アメリカのフリスビー・プレーヤーにとっては、それがすべてじゃないんです。勝つ負けるじゃなくて、自分自身の解放感、エンジョイしてハイになる感覚を味わうことが最高の喜び。公園でもビーチでも、ハイになれたら最高、それさえあればローズボウルでなくても構わない。チャンピオンになるならないが最大の目標でも価値観でもない。そういう仲間と出会い、そういう世界を経験したとき、日本の高校野球の封建的で勝負にばかりこだわる価値観がちっぽけに思えた。アメリカっていいなと思った。でもたぶん、野球にもそれはあったはずなのに、高校野球の仕組みがそれを許さなかったというか、僕自身も感じていた野球の喜びとか自分だけのひそかな楽しみは二の次にされて、「甲子園が唯一絶対の価値」みたいな日々を送るしかなかった。
山本:スポーツ論のなかに、なんとか経験を言葉にしようっていう動きこれまであったんですよね。例えば、「ゾーン」って言葉がありますよね。これは、アメリカのマイケル・マーフィーが70年代くらいにすでに提起していた概念です。でも、やがてゾーンという言葉自体が一人歩きしはじめるんですよ。言葉に分節化できない経験を概念としてあてはめようとすると、ゾーンっていう概念によって当の体験が縛られていく。チクセントミハイの「フロー経験」とかも同じような響きですが、これは結局ビジネス用語に転用されていきます。どうやってビジネスマンが短時間で効率的に集中してクリエイティヴな仕事をするかっていうところにパッケージングされる。ひとりひとりが種別的に、興奮とか解放とか、そういうものに関わる分節化を僕らもっと大事につくっていかなければならないと思います。それをゾーンとかフローとかってまとめあげちゃうのもなんかスポーツの魅力なんだろうけど、なにか大切なものを削いでしまうというか、それこそ型にはめてしまうというか。
小笠原:中立的な言葉じゃないはずなんですよ、本来。でも日本のスポーツライティングの世界では、明るい方へ、いい方へ、ポジティブな方へ強引に導こうとする。本当はフローもゾーンも両義的なはずです。
小林:ずっとスポーツ表現に携わってきて、ある時、「フレーズ主義」みたいなものがスポーツ報道の主流になり始めていると感じました。「谷でも金、ママでも金」みたいな。気の利いた、見出しになりやすいフレーズを口にする選手が持て囃される。有森裕子さんの「自分で自分を褒めてあげたい」は、レースの後、ごく自然に出た言葉だったと思うけど、そのあたりから、メディアの喜ぶメッセージを出せる選手が重宝されるようになった。パッケージ化とおっしゃった。まさにそう。でも スポーツって同じことを何千回、何万回もやるものじゃないですか。その積み重ねの中で、深まっていくと新しい発見や喜びがある。そういうことへの注目がすごく小さい。だから、「ゾーンってあるんだよ」「知ってる知ってる」ってことが大事なんじゃなくて、ゾーンがあるは前提で、その深さを語り合う、「おれはこんな経験をした」「今度はもっとこんな経験をした」って会話ができると、豊かだと思うんです。
山本:先ほどの最大公約数の話もそうですし、小笠原さんが指摘した中立という問題もそうですが、スポーツって絶えず「中立な場所」に置かれるべきだという考えに支配されている。多くのアスリートが、はみ出た経験をスポーツのなかでしているはずなんだけど、なんか居心地のいい、口当たりのいいような「中立な場所」に戻されていく。今度、IOCのバッハ会長が来日しますよね。最近『ガーディアン』になんだか中途半端なインタビューが掲載されていましたけど、バッハ会長はそこであくまでスポーツは政治的に中立でなければならないといまなお主張している。IOC会長自らスポーツをつまらないものにしていくような制御、管理の働きを加えていく。そういうものがスポーツを息苦しくてつまらないものにしていくっていうことにIOC会長は全く気づいてない。
小笠原:道徳的にいいことが中立ってことじゃない。いまだにマス・メディアの不偏不党とか、中立公正とか平気で言う人がいるけど、そのなかで中立であるっていうことが作り出す誤解や間違った認識っていうものをそれこそスポーツライターの人たちには書いてもらいたいです。
小林:そういう書き手は少ないと思います。
山本:それで、あ、そうだ、反省の話に戻したいんですけど。スポーツが道徳的でなければならないとか、弾け飛んでしまう経験を削いでしまうことで息苦しくなる、そういうことと並行するかのように、最近スポーツを楽しむ環境がどんどんなくなってきています。スポーツはどこの空間に移動したのか。漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼は、ボールを蹴りながら学校いくじゃないですか。いまそんなことしたらすぐに怒られる。サッカーボールによってトラックにはねられた体が守られた。だからボールはともだち。それが翼のサッカーとの出会いですよね。そういう経験があるから、そりゃ学校までドリブルしますよね。公園でバット振っちゃいけないとか、まあとにかく社会の中からスポーツがどんどん場所を失いはじめている。みんながスポーツに向けていたあたたかい眼差しが弱まっていく一方で、でもオリンピックみたいなイベントで画面に登場する選手をスターとして扱う。すごく、スポーツが分断されている。身近なところにあるスポーツには覚めた目線を向けて、画面のなかの消費物としてのスポーツはどんどん価値を高めていく。
小笠原:最近っておっしゃいましたけど。
山本:最近って、いつのことって話ってことですよね?
小笠原:やっぱり日本社会はスポーツを馬鹿にして、アスリートに社会的価値と承認というものを与えたくないのではないか。長嶋さんにようにエンターテイナーとして確立できた地位の人は一生安泰でしょう。でも色々大変そうじゃないですか、家族が。長男があれだし。だからそういうことを考えていくと。
山本:カットできないからね、いまの(笑)。
小笠原:失礼しました。スポーツに対して蓄積してきたマイナスな目線が如実に現れていると思うんです。だから金メダリストや上げ潮の時のアスリートはちやほやするけど、その代償として瀬戸大也みたいにああいうこともあるわけだし。なんでこんなにスポーツの価値はこの国では低いのか、アスリートへの目線と通底してる気がする。社会的承認の密度の低さというか。どうなんですかね、それは。
小林:イメージとしては動物園の檻の中に閉じ込められているスポーツ選手みたいな。スポーツをしているときは素晴らしいけれど、檻から出したら大変なことになるみたいな。スポーツで本当に常識を超えたパフォーマンスのできる人の感情やひらめきみたいなものを、どこかで怖いと思ってるのかもしれない。スポーツヒーローが真剣に政治の分野にまで進出して、人々を引き付けるメッセージを発した時には、ものすごい影響力を持つ存在になる可能性がある。既存の政治家は、そういう警戒心に敏感でしょう。だから、自分たちの傘下に押し込もうとするのかもしれない。いまの政界にもスポーツ界出身の人材はいるけれど、見事に牙を抜かれていますね。
そういうことに対して僕らはもっと応援するというか、その選手が世界一になるときに発揮したひらめきや心のエネルギーを、政治やビジネスや、他の分野でも発揮したらきっと素晴らしい社会貢献ができる。そういう方向でスポーツ選手も応援され、選手自身も使命感を持って取り組んだらいいと僕は願っています。
ちなみに僕が文章を書く思いははっきりしています。文章で読む人の考えを変えようとか、影響を与えようという思いはありません。僕の文章に接した読者が、読んでピュアになること。その人本来のピュアな感覚になって、ああ自分はこれをやりたい、この道を進みたい、と。具体的には何か僕にはわからないけど、とにかく読んだ人がピュアな気持ちで、元気に行動する背中を押せたらいいなと、それが僕の願いです。1億2千万人が、それぞれピュアになったら、きっと素敵なことが始まるという願いを常に思っています。スポーツって、ピュアな心でやればやるほど面白いものだと思う。でも、みんながピュアになると困る人達もいて、世の中はいまそのせめぎ合いなのかな。
山本:制御しないといけないっていう働きがでてくる。
小林:僕はまあ呑気に人を信じすぎているかもしれないけど、人はピュアになったら変なことはしないと思っている。だけど商業主義や勝利至上主義日本に毒されている人は、勝つこと儲かることが善だから、ピュアとは違う次元に進んでしまいます。僕は小学生のころ、家の近くに友だちがいなかったので、学校から帰るとずっと、家の塀を相手にボール投げをしていた。ストライクゾーンとか、ヒット、凡打とかの的を決めて、仮想のゲームを楽しんでいた。誰にも束縛されない、楽しい遊びでした。
山本:あんな楽しい時間ないですよ。
小林:対戦する高校のメンバー表まで自分で作っていました。
山本:それで社会的地位の話ね。例えば押川春浪みたいに明治・大正あたりまで遡ると、要するにスポーツ選手というのは、当時はエリートですよ。エリートたちがスポーツやる。質実剛健、知性と肉体が両方備わった人が素晴らしい人間のモデルとして提示されていたけど、スポーツがどこかでエンターテイメントになったり大学の宣伝の道具になったりとか分業していくと、精神と肉体が分離していくようになる。推薦入学で大学に入るスポーツ選手は、つねに知性の反対側に置かれる存在になる。「あの人たち勉強してないじゃん、体ばっかり使って」という。これは心身二元論のように、知性が大事で身体はアンコントローラブルなものだと。人種差別もそうかもしれないけど、そういう知性と肉体の二分法にとらわれていて、スポーツやってる人は勉強してない、社会のことを知らないっていう扱いで眼差される。要するに、日本ではスポーツ選手へのリスペクトがないんですよ。だけどそんな選手たちがオリンピックなんかで活躍すると号泣したり、急に愛しはじめたりする。でもそのもてはやし方は危険で、すぐさまスキャンダルの対象にされたりもする。こういうことがスポーツの構造としてずっと続いてるなっていう。学校の教育現場の体育教員の社会的位置取りなんかも同様ですよね。
小笠原:俺は嫌いだったけどね。
山本:嫌いだけど体育教員はどういう役割なのっていうところまで紐解いていくと、知性の反対に置かれたまま。そこで無意識にスポーツを尊敬しないっていう風潮がいまもこの瞬間もずっとつくられているのかなっていうふうに思います。このあたりに、小笠原さんが先ほど、アスリートの社会的地位が気になるっていうところの、根本的な問題があるんじゃないかな。
小笠原:単に優劣や2つに分かれてるってだけじゃなくて、知性だの教養だのという側が、基準をこちら側が作ってるってことですよね。その基準を最初に作ってしまったから、別の次元、社会の別のあり方を作って来られなかったんじゃないか。身体に関しては軍国主義や軍隊の問題もいろいろあると思うんですけど、今はもう21世紀ですから。何か違う言葉、言語、ボキャブラリー、原則みたいなものを打ち立てないと、なんというのかな、エンターテイナーとしてみんながその瞬間は承認してあげられるアスリートはいいけれど、下手くそでも続けたいんだけどやらしてもらえなくなるような二極分化が進むんじゃないか。じゃあ上に行ったら安泰かっていったらそうじゃない。1つのスキャンダルで人生を棒に振る。全てを投げ売ってスポーツ演る人がいなくなるんじゃないかっていうくらい離れてるっていうこともそうだし、この社会にいたって安心して好きなことに打ち込めないっていうことになる。そういうのはほとんど病理って言ってもいいかもしれない。それに棒に振った後、挫折した後、諦めた後も受け入れてくれる素地が薄いでしょう。
小林:なんでかなあって。そのあたりはスポーツの重大な課題だと思うけど、でも社会はどうなんだというと、社会の方ももっと同じ問題を抱えている。スポーツでは自由な発想で活躍できた人が、社会ではその発想やひらめきを生かせるシステムや構造になっていないという面もある。中田英寿選手は誰もが認める天才的な選手だったけど、いまの彼は旅人です。日本酒だとか、日本文化の啓蒙に情熱を注いでいるけど、その分野に関しては僕も少し関わっているから、彼がサッカー選手として発揮したレベルでその活動に携わっているかというと、どこか受け売り的だったり、誰かに利用されているように感じる場面も少なからずあります。結局あのスーパースターが引退後はスケールが小さくなって、見かけは自由だけれど、企業や何かに利用される存在だとしたら、こんな日本社会ってどんだけ情けないか。僕は勝手に、彼の能力はそんなもんじゃない、もっとすごいはずだと思っているから、忸怩たる思いです。スポーツ選手が現役時代の天才性をそのまま社会で発揮できたら、選手はもっと大きな人生の目標ができる。スポーツ界は、野球とか、ラグビーとか、サッカーとか、よくまああんなルールで新しい文化を作ったなあと感心するのですが、社会の中にも新しい種目というか、スポーツ選手が現役後に活躍できる舞台や仕組みを作れたらいいなあと。今はその場がまだありませんよね。
小笠原:女性アスリートなんてもっとないですよ。出産して育児すると女性だけがいろいろ負担しなきゃいけない仕組みになってるし、その中でも谷亮子みたいな例外が「ママで金」とか言って褒めそやされる。結局彼女も自民党ですから。基準がこっち側で作られててあっち側に当てはめられるからうまくいくわけない。格差というのはエリートとグラスルーツの格差だけじゃなくて、男女差でこそ大きいのではないか。現役時代の格差がセカンドキャリアを探すときに、一つの世界から足を洗って違う人生を送るときにさらに広がる。それを底上げするのがスポーツ庁長官の役目だったはずだけど、彼は千葉県知事にもなれないし。
小林:だいぶ調子に乗って喋ってますけど。
山本:ゾーン? ですね。
小林:元選手たちが、立場を得たり守ったりするために、ある政党の言いなりになったり、「バランス感覚があるよねえ」と言われて重用されるとか。それが本当に社会やスポーツ界の発展に貢献につながるのか? そういう大人の社会の枠に入れない人は落ちこぼれみたいになって、まったく活かされていない。そういう場を、作っていけたらいいんでしょうけど。
勝利至上主義の中で、指導者の評価にしても、日本選手権で何人優勝させたとか、オリンピックで金メダルを獲らせたとか、それで名指導者と言われる。でもいまはそういう指導者が突然、パワハラで糾弾される。もっと、この指導者は「こんな人材を輩出した」「スポーツを引退後、このような分野で大活躍している」など、そういう意味での人材をどれだけ輩出したかが指導者の評価になるような側面も大切だと思います。いまとくに高校野球を見ていると、強豪校で活躍した選手の多くは、残念ながら、監督の命令を忠実に遂行できる歯車のようなタイプです。監督の命令系統を離れてしまうと、自分ではそれほど創造性もないし、自発的な行動力もない、組織の一員としては信頼できるけど、人としてはあんまり魅力がないね、みたいな人も少なくない。そういう重大な欠陥に、高校野球の指導者は気づかなきゃいけないと思うけど、なかなか変わりません。
山本:補足で。さっき知性と肉体の文法、例えば東大とスポーツ選手っていう二分法だけじゃなくて、小笠原さんが言ったようにジェンダーにも二分法は働いている。セリーナ・ウィリアムズがラケット叩きつけるた時のメディアの反応。「ほら女だから」「精神をコントロールできない」「ヒステリーだ」と言われる。でもマッケンローなんて何本もラケット叩き壊してるでしょ。
小笠原:体育の軟式テニスで真似したもんね。
山本:あれは1つのキャラクターとして受け止められるんだけど、黒人女性アスリートとが同じことをやるとバッシングされる。
小林:東大の野球部の応援をした時期があるんだけど、何年か。東大の学生は頭がいいはずなのに、ことスポーツに取り組むときは頭がよくないんですよ。そのギャップに驚きました。
小笠原:本当は頭よくないんじゃないんですか、あの人たち。
小林:さっきの二元論は全くそのとおりだと思います。悲しい問題ですよね。それによって知らず識らずスポーツの好感度が下がっている。応援しようという気持ちが薄れていることにスポーツ選手も気づいてない。
少年野球のコーチをやってたとき、近所の住人から苦情が寄せられた。「休日の朝からうるさい」と。でもよく調べてみると、子どもの声や野球の音が不愉快だってわけじゃない。大人のコーチたちが、子どもに罵声を浴びせて、時には殴ったり蹴ったりするのが耐えられないと。それは理解できますよね。
小笠原:新しい。
小林:そういう積み重ねで、「野球なんか子どもにやらせても意味がない」とか。そう考える大人たちが増えてきた。そのことに、僕自身も気づいていませんでした。自分がそういう経験をして初めて気がついたんです。自分たちは楽しいと思い込んでいるので、客観的に見ることをしない。でも、そうやって、野球自体のイメージが悪化している。野球の社会的な信頼や好感度がどんどん下がって来たんだと思います。
小笠原:なんで思い込めるんでしょうかね。体罰はよくないとか言われるけど、高圧的で封建的な指導でも結果が出ちゃう、全国行けちゃう、優勝しちゃう。そして教わっている人たちがなんだかんだあの先生の言ってること聴いてれば勝てるって説明されるんだけど、本当にそうなんでしょうか。
小林:僕は文章を書く人間です。本当はドラマを書きたい。でもスポーツのドラマを書くとなるとすごく大きなハードルがあるんです。みんなで努力して、苦しいこともあったけど乗り越えて勝利した。多くの人がそういうドラマに感動する現実がある。それがいまならパワハラ的な指導であっても、やっぱり美化されたら泣いちゃう。許すというか、受け入れる感覚が日本人にはまだあるんです。うっかりするとね、本当は泣いちゃいけないパワハラドラマで、僕も泣いちゃいそうになる。そんなところで泣いちゃだめっていうね。
小笠原:情動だね。
小林:パワハラを美化する感覚、勝つためなら仕方がないという思い込み、それを指導者だけでなくスポーツファンも含めて心底リセットしないと、変わりません。安易なセンチメンタルで心を動かさない訓練をしないとね。もっと言えば、僕の仕事はそれを訓練させると言うより、これは泣いていいというか、スポーツの本当にピュアなドラマを提供することかなあ。テレビドラマでも、心を揺さぶる音楽が流れてきたら瞬時に胸が震えるってありますよね。スポーツにもそういう瞬間がある。
小笠原:実際の現場にはBGMはないですからね。
山本:感動型の資本主義じゃないけど、感動とスポーツっていうのがあまりにもセットになってる。スポーツってつねに感動しないといけないことになっている。怒り狂ったりとか、いろんな経験があるのに必ず感動することになってるでしょう。これも本当に安易だし、スポーツやればみんな仲良くなれるとか、ひとつになれるっていうのとか、復興できるとかっていうのも本当に安易だし。安易なものにスポーツが支配されて、その間に分業化や分断も進んでいて。例えば、親がオリンピック選手じゃないと子供も一流になれなくなるという構造も見えてきている。スポーツ選手も2世という形が生まれてきているように思います。
小笠原:そこでなにが欠けてるんですか? なぜそういう変な血統主義みたいなものが復活しているように見えるのか。なぜ二世じゃないとエリートになれないのか。国会議員と一緒じゃん。
山本:効率化と合理化ですよね。確実に結果を出せた方がいい。特定のスポーツ種目で効率よく結果を出すためには、幼い頃から認知や反射のレベルを鍛えなければならない。コーチや指導者ではなく、家庭のなかで親がガチっと神経回路を作っちゃう。地域のおじさんに野球を教えてもらうとか、ようわからん先生にバスケを教えてもらうんじゃなくて、親に守られながら徹底的に無駄なく仕上げられていく。もう不良になるチャンスなんてないし、友達に誘われて誘惑にかられるチャンスもない。スポーツが家庭環境のなかに閉じ込められて、エリート化していく。それが失敗のリスクを軽減できて、効率よく結果を出せる選手を作る合理的な仕組みになっている。もう歯止めがかからない。
小笠原:スポーツの世界に多様性の可能性がない。
山本:潜在性はあると思うけど、可能性は限りなく抑圧されていますよね。普通の若者がボクシングの世界チャンピオンになれるかっていうと、昔のように10代後半、20代から競技をはじめても、もうなれない。亀田兄弟、井上尚哉もそうですよね。卓球やバドミントンのような個人種目で如実に現れている。脳神経や反射といった生物学的次元で刷り込んでいくわけでしょ。才能の家庭による独占がはじまっていくと、選手は家族のなかでスポーツの身体というものをガチっと作っていくことになる。
小笠原:でもそれは『巨人の星』とどう違うの?
山本:そうですよね。まあ、巨人の星の親子関係は瓦解してますよね。どうして矢吹ジョーの方がみんなに長く愛されてるかっていうと、ジョーはどこからきたかわからないディアスポラだからです。ジョーには最初から家庭がない。彼を支えていたのは山谷のコミュニティだった。
小笠原:そこに開かれた世界があった。よど号んときの赤軍もそうだったかもしれないけど。今日問題発言多いかな。人種や民族やセクシャリティやという多様性っていう文脈で公式見解では言われるけど、肉体と知性の関係の取結び方の関係性ももっと多様であっていいと思う。
イギリスのサッカー嫌いなこともいっぱいあるけど、好きなのはフットボールブレインって言葉があるんですよ。80年代から90年代にかけてポール・ガスコインって選手がいたんだけど、悪童でどうしようもないんだけど、ピッチに立つとすごいプレーする。ピークで活躍したのは7~8年しかありません。その間に強烈な印象を残した。プロフェッショナルのフェローにも評価が高い。特にリネカーはガスコイン大好きだから。個人のライフコースの中で本当に7~8年しか輝いてないんです。残りは幼少時代の貧困、結婚してからのDVや離婚騒動、人種差別的発言とか。差別と言えばこんなことがありました。引退してから行った講演会の一つで、会場のセキュリティガードが陰に立ってたんです。黒人の若者でした。ガスコインは話を冗談から始めようとして、「そこにいたら見えねよ」って言ったんです。そうしたら人種差別って非難された。
でも彼を評価するときには、「フットボール・インテリジェンス」って言葉が使われるんです。それは例えばケンブリッジの物理やら理学やらでなになにこういう計算したとか、なんとか賞を獲ったみたいなものと同じくらいの価値で書かれる。政治や経済や社会を書くような記者がガスコインを振り返る記事を書く。実際会ったら大変な人だと思いますよ、めんどくさい人だと思います。面白いと思いますけど。でも彼がそういう言葉で形容されることによって世の中に残るじゃないですか。
山本:長嶋さんのインテリジェンスって言わないじゃいですか。カンピューターとか野生の勘って言われます。
小林:僕らがそれをしっかり表現できなかった。かなり一般の常識とかけ離れていますから大変だけど、きちんと通訳すればちゃんと伝わるはずですよ。まだそれが十分にできていない。イチロー選手は独特な発想や技術をかなり評価されている。落合博満さんも長嶋さんとは違って、独特の高い次元を持っているんだと理解されている。
山本:選手やスポーツの歴史だったり、選手が語ったことの内容の濃さというか、イギリスだと『ガーディアン』などはかなり分厚く記事にするじゃないですか。先日、日本では長嶋さんが引退した日をメディアがまったく触れない。何も触らなかった。最も偉大で最も愛されてきた野球選手の引退日をメディアは振り返りもしない。小林さんはそのあたりについてSNSなどで少し発言されてましたが...。
小林:野球がそれだけいまの社会で縮小したってことでしょう。昔は優勝が決まったら、野球ファンでなくても優勝セールだとか大騒ぎしていました。今はそこまでの社会現象になっていませんね。
山本:野球がエンターテインメント全体に占めていた比重が縮小しているんですよね。韓ドラや『鬼滅の刃』と同じようにジャイアンツもいっぱいあるエンタメのうちのひとつ。ちゃんと意味や歴史を重厚に作り、共有していかないとスポーツは、どんどん『鬼滅の刃』に斬られていきますよ(笑)。
小笠原:あいつら人間相手に戦ってないからそれは強いよ。
(一同笑い)
小笠原:どうしたらいいんですか。
山本:やっぱりでも最初に戻れば、スポーツ批評をどうやってつくっていくのかっていうことですよね。それは批評の空間でもいいし、批評の言葉でもいいし、それこそ批評の身振りでもいいと思うけど。BLMのうねりのなかで、大坂なおみさんはそれこそ体をはった批評を創案し、実際に批評の身ぶりと空間を作り出した。BLMのなかで「黒人の命」が言われるようになったけど、「黒人の命」っていうときの「黒人」だって十把一絡げにまとめられて語られる。大坂なおみさんは、黒人たちにも1人1人名前があるって主張したわけです。だからマスクに亡くなった人の名前を書いたでしょう。あれは、大坂さんは確かにBLMに共鳴するけど、そういう運動に対しての批評もさらに加えるわけですよね。そんなすごいことを彼女はやっている。でもスポーツについて伝えたり、書く人たちは大坂さんのパフォーマンスとしての批評をもっと理解して掴んでほしい。
小笠原:日本のスポーツライターは彼女をちゃんと把握できてないと思う。彼女自身でtwitterで発信するし、それを外国の記者は全員とは言わないけどきちんと拾って文脈をつけて配信してるもん。深く掘り下げた日本語の記事はほぼゼロ。少しいいなと思っても、外国人記者の書いたことの受け売りだったり解説だったりする程度。単なる翻訳で、自分で取材して考えて掘り下げてない。責任取りたくないから。ジャーナリズムじゃないんです。厳しいこと言いますけど 本当は「ナンバー」とかがしなくちゃいけないと思うんですけど、きちんと取材して粘り強く張り付いて。
小林:日本では商業的なメディアでスポーツフィロソフィーみたいなものとか、あるいはスポーツの心ですね、心技体でいう心、みたいなものはテーマから外れているんですよ。たとえばゴルフも、スコア100を切るにはどうしたらいいかとか、今週もあの選手が勝ったから、あの選手の何って言って、毎週毎週打ち方が違ったり、だからこう、ないんですよね。
山本:まぁそこはだからこそ、今日は3人で批評を実際にここでやってみるっていうね。
小林:なんだかんだいって僕らも生活があるので商業主義に負けているところがある。書きたいことが書かせてもらえないっていう言い訳がある。本当に書きたいことがあるなら、YouTubeで発信してもいいのになぜやらないの? ということも含めて、行動が足りていないのかなという反省があります。
小笠原:僕らは言論で生きているというか、じゃあお前大坂なおみと同じことしろよって言われてもできないし、マラドーナと同じことはできないですし、言論で言葉を使ってやっていくしかない。その立場なのでやっぱり言葉を大事にしたい。
小林:僕はちょっと違って、スポーツは身体でやるものなので、やはり僕は行動が基本だと思っているんです。文章を書くことが僕の主な仕事ですけど、同時に何らかの行動があって初めて両輪になる。そういう意味で、中学硬式野球の監督をやったり、地域のスポーツ新聞を作ったり、イベントをプロデュースしたり、野球のアンダーシャツの開発をしたり、いろいろな形でスポーツを改革する、一石を投じるチャレンジをしてきました。実際にスポーツ界に新しい波を起こす実践は、これからも分相応な範囲でやっていきたいと思います。
山本:今日はあえてスポーツに対してメスを深めに入れましたけれども。膿がでてきたからといって、どういう治療があるのかわかってないですが...。さて、本来打ち合わせでは小林さんにもっとスポーツのローカルな話、武蔵野市と子供の野球といった話題を伺う予定だったんですけど、時間がここでなくなってしまいました。ぜひまた別の機会に伺いたいと思います。
小笠原:え、もう時間? あ、ほんとだ。決してこう、ハッピーエンドがいいとは思わないタイプでして、「まじか、ずーん」って感じで落ち込んで終わるのもありだと思ってるんですけど、実は最近いいことがあって。 スポーツを表現したり語るっていう意味でですけど。東京在住の一人の大学生に、Jリーグにおける人種差別について卒論書きたいのでインタビューさせてくださいって言われて、zoom越しだったんですけど、インタビューしてもらったんですよ。そのときに、ところで君なんでこのテーマにしたのって、Jリーグの人種差別なのって聞いたんです。
そしたらある記事を読んで思うところがあったという。それはコンサドーレ札幌の鈴木武蔵選手が、自分でtwitterでね、話したことがあったんですよね。お父さんがジャマイカでお母さん日本人。幼い頃からのことや今のことまで、差別を受けた経験や周りの反応について。それをFootballistaっていうネット配信のジャーナルの記事で読んだことがきっかけだと言うんです。鈴木選手はtwitterで反論すると同時に、プレーでも頑張ってきた。けれど差別されてきたりしたことを、それをピッチの上でのね、プレーで返すってどういうことなんだろうって。ピッチの上のことはピッチの上で返せっていうことに対して疑問を投げかけた。サッカー選手なんだから悔しかったらサッカーで返せってね。それは一理あるかもしれないけど、差別は社会の問題じゃないかと。
この記事が出たときに、まず日本にも人種差別があるということを知り、鈴木選手はそれとずっと戦ってきたと、選手になってもそうだと、そういう事実を知った。そしてサッカーというのはあくまで社会の一部で、そこに人種差別があるということは社会に人種差別があるってことだってことが記事に書いてあって、そこで共鳴したと。
その記事を書いたのはあるスポーツ新聞のまだ若い記者なんですけど、彼はがんばっていて、自分が働いている新聞社じゃあ書けないようなことも外でちゃんと書いて発表している。そういう言葉たちがこの学生を触発して、そのテーマできちんとものを考えるというサイクルを1つ作り上げたということを知って、本当に小さな風穴かもしれないけど、いいじゃん頑張ろうよって思ったことがありまして。いいかな? このくらいのこと言っといて。あんまりゾーンって感じじゃないけど。このくらいのことを日々考えて発信していかないといけないんじゃないか。
小林:今日お話させていただいたようなことを、普段から当たり前のようにスポーツに関わる人、応援する人が語り合う環境や習慣があれば、自然といろんな改革が始まるだろうと感じました。今日はひとつのスタートです。ありがとうございました。
山本:私たちも本当に話せてよかったです。それから視聴されているかたからも内容の濃いコメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。延長線をという声もコメントにありますけれど。コメントありがとうございます本当に。はい。視聴者のテッドさんはいつも励ましてくれて。「山本さんや小笠原さんは、教室や本の中でもスポーツしてるもん」と褒めてくれてるわけですね(笑)。あと小林さんのからだを張った批評、これはいいというコメントがありますね。
小笠原:いつも中身の濃いコメントありがとうございます。今日だけじゃないですよ。
山本:延長戦っていう可能性もありますけど、もうきっちり2時間話しましたね。またなにか別の機会をつくってやりたいと思います。今日はありがとうございました。
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、ルールは勝ち負けを決めるためにではなく、次もあるという「希望」のためにある。そこでの鍵は、消費主義とグローバリゼーションと帝国主義の歴史でしょうが、スポーツの伝播とそれらは切り離せませんね。どうやって、それらを分節化していくのか、それができないと、世の中のスポーツ嫌いの人は説得できないと思います。
本橋哲也さんのコメント:
長嶋は千葉県が生んだ唯一の偉人/異人だ! イギリスにおけるスポーツと階級、あるいは地方共同体との深いつながり。しかし同時にそれを、「普遍化・植民地化」するためにパブリックスクールによるスポーツの領有が行われてきた歴史をも批判的にみる必要がある。 なるほど、スポーツの魅力は失敗の記憶の共有か。
本橋哲也さんのコメント:
「批評」の基本が自己批判と他者意識だとすると、それが欠如しているスポーツには、そのような自律への姿勢を排除する何かがある…それは何ですか? 集団性への過剰な思い込み?
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、一回性の出来事がデータになってしまうということですね。
視聴者コメント:
日本の勝利至上主義からくる批評のなさにはがっかりしています。
かつてブンデスリーガでオットー・レーハーゲル監督に率いられたカイザースラウテルンが1部昇格から1年目で優勝しましたが、ドイツでは「カイザースラウテルンのサポーター以外は退屈な、創造性のない下らないサッカー」と酷評されたと聞きました。
日本にはそれがない。
思い出すのは2006年の浦和レッズのJ1初優勝。戦術はワシントンというつまらんサッカーやった(←ガンバ大阪サポーターのひがみ) スポーツの本質や魅力が論じられず、浦和レッズが「芸能タレント化」して称賛されていることに、当時違和感があったことを言いたかったのです。失礼しました。
本橋哲也さんのコメント:
つまり「感動」するのは了解可能な「パッケージ」やステレオタイプに対してであって、本当にすごいスポーツの演技には感動などできない、震撼することはできても。本来のスポーツにはそうした神秘的、宗教的な側面があるはず。勝利至上主義と感動至上主義の隠微な結託!
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、「批評」の責務は優劣をつけるのではなく、共通性を全く異なった主体同士の間に見つけることですね。 なりほど…スポーツに対する尊敬と感謝ーーそれが他者への信頼を育む。 マラドーナやアリのことを考えると、議論していただきたいのは、スポーツと社会正義との関わりですね。例えば今だったら、BLM運動とエリートスポーツとの関わりをどう評価されますか?
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、武術とスポーツとの関わり…それが精神主義に領有されてしまった不幸があるわけでしょうか?
視聴者コメント:
【商業主義について】
フットボール・ジャンキーです。
ちなみにJリーグはガンバ大阪、欧州はデポルティーボ・ラコルーニャ(現在スペイン3部)が好きなチーム。
何ですが、だんだんとサッカーのニュースにワクワクできなくなってきました。
つねに欧州サッカーは常に金金金。誰がどれだけの移籍金で移籍したか、年俸がどれだけなのか。
僕が1990年代後半から2000年代初頭のデポルを好きになったのは、1+1=が3にも4にも5にもなるチームスポーツの魅力でした。
ですがデポル黄金期と同時にレアル・マドリードの銀河系軍団が誕生していく。
そうなると、サッカーの本質としてのプレーの素晴らしさなどが語られなくなってしまったようになったと思います。
ビッグ・クラブしか優勝できないという資本主義、資本蓄積の問題と同時に、新自由主義的商業至上主義はプレー次元の面白さが語られなくなってきたように思います。
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、スポーツと社会との関係は、パンデミックと社会との関係とパラレルなのですね。社会変容がスポーツ/パンデミックを生み、スポーツ/パンデミックが社会を変えてきた。 そうだそうだ、なんでスポーツ選手が不倫してはいけないのだ!? そうだそうだ、演劇やスポーツは社会にとって絶対必要な遊びであり、溜めなのだ!!
Takezaki Kazumaさんのコメント:
再開までもう少々お待ちください。
本橋哲也さんのコメント:
なるほど、挫折と反省があるから、スポーツは人生と共通性があるのですね。
視聴者コメント:
「公園でサッカーができない」等のスポーツの社会からの孤立は複合的要因(新自由主義政策による社会の断片化、原子化など)があると思いますが、身体管理によるスポーツエリートと大衆との分断があるのではないでしょうか。
アスリートが権力や資本によって、トレーニングを介することで身体が管理される。これによりアスリートが権力に従順になる。アスリートは能力が開花されエリートとなるが、大衆と分断されていく。アスリートの権力への従順さ、そして権力に支配されている大衆という関係が「スポーツの社会からの孤立」を生んでいるのではないか。
しかし身体によって、身体表現によって権力を脱構築する可能性もある。スポーツとスポーツ批評が社会批判として有意義にかみ合う可能性が、ここにあるのではないでしょうか。
うまく表現できていませんが。
本橋哲也さんのコメント:
たしかに、社会や文化に対する批評と、スポーツやアートに対する批評とが、切り離されてしまっているのが、日本語圏の現状ですね。その意味でも、CLRジェームズの精神を引き継いでおられる今日のお三方の道を、これから多くの人に歩んでいただきたいと思います。
視聴者コメント:
立花兄弟の駅でのパス練習!!! 橘だったか???
本橋哲也さんのコメント:
『愛の不時着』のジョンヒョクも、平壌のホテルでサッカーボールからセリを守りますね!
本橋哲也さんのコメント:
江戸時代における演劇とスポーツの権力による囲い込みの歴史を見ると、そこには演劇やスポーツがもっていた解放の可能性に対する権力側の恐怖があったに違いない。それを明治以降の歴史は抑え込み、領有することで、近代国民国家が教育制度ともに成立してきた。 そうか、スポーツの本質は「ピュアネス」、つまり何ものも恐れない「テロリズム」にあるということですか!
本橋哲也さんのコメント:
そうですね、スポーツのゲットー化が教育制度によって進められてきたわけですね。 知性を社会と切り離してしまうから、反知性主義が一般化してしまう。日本学術会議も、エリートスポーツも、一般社会から切り離されてしまっている。
視聴者コメント:
中田英寿はサニーサイドアップと金子達仁によって、新自由主義と資本主義に取り込まれてしまった、ナルシストだと思うんですよね。
昔は無茶苦茶大好きでしたが。
本橋哲也さんのコメント:
なるほどスポーツ選手にとって、社会で活躍する場がないから、なおさら、オリンピックに対して反対の声も上げられないわけですね。 円谷幸吉の不幸を思い出します。 その意味でも、大阪なおみさんは、あらゆる意味で希望の星だ!
視聴者コメント:
本当に21:00で終了するのでしょうか。あまりに楽しいので、延長戦を希望します。特にオンラインですので。
本橋哲也さんのコメント:
スポーツと演劇と韓国ドラマのない世界は生きるに値しません。
視聴者コメント:
どのスポーツを選ぶのか?どの人生を選ぶのかという、人生契機のまえに選ばされるという事ですね。
本橋哲也さんのコメント:
ジョーは、しかし、どんな時代でも顕れて来る、と信じたい。 なぜなら、山谷はどの世界にあるし、それどころか、新自由主義の席巻の下で、山谷やスラムは遍在化しているから。
本橋哲也さんのコメント:
「体を張った批評」! いいこと言うなあ!! かりに大阪なおみさんが、「純粋日本人」だったら、どうなりましたか…? ただ取り込まれて終わる…? もっと「女性」ジェンダーのスポーツ批評が出てほしいですね。 そんなことないと思います、山本さんや小笠原さんは、教室や本の中でもスポーツしてるもん。
視聴者コメント:
延長戦を!!!
本橋哲也さんのコメント:
たしかに「肌の色」の可視化という点では、この国のスポーツも進化しているとはかろうじて言えるのでは? 「暴言」や「暴力」は大事です、相手が人でなく、銅像や社会であれば。
視聴者コメント:
👏
Takezaki Kazumaさんのコメント:
https://peatix.com/event/1693105/view
視聴者コメント:
このようなアメリカ研究者のお話は貴重だと思います。
テレビで出てくるアメリカ製紙評論家はだいたい共和党でバイトしていた人たちですから。
Takezaki Kazumaさんのコメント:
チケットはこちらから↑
記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。
