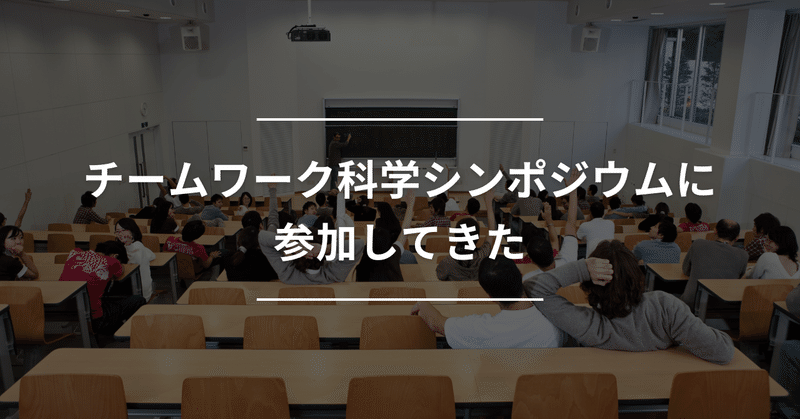
「チームワーク科学シンポジウム」に参加してきた
5月12日(日)、スクフェス新潟の翌日でそれなりに疲れていた中ですが、朝07:24新潟発東京行きの新幹線に乗って東京に戻り、「チームワーク科学シンポジウム」に参加してきました。色々頭の中に浮かぶことがあったので備忘録としてnote更新。
今回のシンポジウム参加の目的はキース・ソーヤ教授のお話を聞くこと。
「学習」と「コラボレーション」を同時に語った第一人者で、下記の著書が有名な方です。
ノースカロライナ大学チャペルヒル校教授。創造性・学習・コラボレーションの研究に関する世界的な第一人者。1982年マサチューセッツ工科大学卒業後、アタリに入社し「フードファイト」「ネオン」「マジシャン」などのゲームデザインを手掛ける。1984年よりシティコープ、AT&T、US Westなど多くの企業で経営コンサルタントを務める。1990年よりシカゴ大学で心理学を専攻し、ミハイ・チクセントミハイ博士(『フロー体験:喜びの現象学』著者)のもとで創造性に関する研究により博士号を取得。研究成果はCNN、Fox News、公共放送サービスPBSの各テレビ局、公共ラジオ局NPR、『タイム』誌、『ニューヨーク・タイムズ』紙など、多くのメディアで紹介された。会社や団体向けの講演も精力的に行い、近年は世界経済フォーラムの年次総会、ダボス会議に招待された。これまでに12冊の本を執筆・編集し、80本を超える科学論文を発表。邦訳された編著作に『クリエイティブ・クラスルーム――「即興」と「計画」で深い学びを引き出す授業法』(英治出版、2021年)、『凡才の集団は孤高の天才に勝る:「グループ・ジーニアス」が生み出すものすごいアイデア』(ダイヤモンド社、2009年)、『学習科学ハンドブック[第二版]』(北大路書房、2018年)がある。また、シカゴの即興劇団でピアノ演奏を行うなど、40年以上にわたってジャズピアニストとしても活躍している。
個人的にポイントなのは「40年以上にわたってジャズピアニストとしても活躍している」という点。
学術的な観点だけでなく、自身の即興演奏体験からのインスピレーションも多分に盛り込まれた「学習」と「コラボレーション」を掛け合わせた研究は、やっぱり例示として挙げられるケースもジャズが入ってて、わかりやすかったです。
キーノートスピーチ:「コラボレーションと学習」
古くから「学習」という概念は、個人の認知の問題として研究されるところからスタートし、どのように個人が知識や技術を習得体得していくのかを研究されててきたようです。そこから徐々に環境やチームの課題としても取り込む「コラボレーション」の概念との掛け合わせることをキース・ソーヤ氏が始め、「集団でどのように学習するのか」の研究を始めたよう。
個人的に印象に残っていたのは「創造性に対する神話」。
かなり意訳、個人のメモが入っているけれどそのまま🔗
創発の神話
その1:個人の洞察にキモがあり、そこからチームの創発が生まれる?→NO
集団によるクリエイティビティは、個人の洞察では説明できない
チームにスーパーマンが一人来ても、それがチームのせいか・創発につながるとは限らない?
個人のすばらしいひらめきにグループの創造性の出発点があったり、素晴らしいクリエイターがいることで素晴らしいグループができているはずだと思いがち。しかしこれは違う。
ジャズ演奏:例えば著名なジャズ演奏家ジョンコルトレーンがいるセッションは、ジョンががすごいんだ!となりがち。みんなジョンコルトレーンに従っているのだと。しかしそれは違う。
その2:何もないところから生まれる?→NO
発想→実行→クリエイティブな結果が生まれる…というのが普通の考え方
しかし、クリエイティブのプロセスは
小さな直感、何かのきっかけがスタートになければいけない
まっさらなところからは生まれない。逆に大きなアクションもいらない。
元々発送していたものと違う帰結になるということもある
その3:新規性があることこそが創造性が生まれる?→NO
構造や安定性を軽視して、目新しいことを頑張ろう!というのは間違い
ストラクチャーは軽視してはいけない
基本、基礎は徹底したほうがいい
ジョンコルトレーンの楽譜も4回同じ構造が繰り返されている。基本構造がある。
即興はストラクチャーがある
ストラクチャーと即興の間にどんなバランスがあるのかを見極め、研究しているのがキース・ソーヤ。
純粋、100%な即興というものはない。
今回のシンポジウムでは、この基調講演の後に
多様性はビジネスの企画に生きるのか
ハイブリットワークで信頼は醸成可能なのか
知識創造活動における対話音声データの分析
などなど、いろいろな研究報告を聞くことができて、人事施策やコミュニケーション施策を考えている人にとっては業務に直結しすぎて心拍数あがっちゃうお話ばかりでしたよ。
感想
色々聞きながら思ったことを。
採用選考における個人を審査するという考え方の矛盾
個人の双発現象の結果が組織を形作っているのであれば、組織がメンバーを増やす時、つまり人材採用において、個人を個人として採用選考することにどこまで有効性があるのか疑わしいなと思った。
意味がないとは思わないが、面接が万能でないというのはこういった理由だろうなと。個々人のアクションにより創発するのがチームならば、採用基準はそこを盛り込んだ基準にすべき。改めて「この人がいい人か」ではなく、「創発する要素としてこの人はプラスかどうか」という視点で採用基準が必要そう。
Backlogは創発現象を加速させられるのではないか?
チームの誰かが発するきっかけ、ひらめき、アクションが創発を生むのであれば、Backlogで共有されている「Backlogがなかったら可視化されなかった情報」がチームの創発の種になるのではないか?チームの創造性を引き出すことにつながるのでは?
大袈裟に言えば、コラボレーションツールがあれば「天才一人に凡人の集団が勝てる」のではないか。
逆を言えば「情報を自分の中で遮断しておく」ことは創発を生み出さない。なんかそれは、実感がある。
コラボレーションツールは使っていない人に説明すると、よく
「管理」のためのものですよね?
導入されると息苦しいですよね?
と聞かれることがある。「そんなことないのだけど」と思っても、うまく説明できない気持ちだった。よくBacklogは「プロジェクト管理ツール」と説明してるが、この時使っている漢字の「管理」という言葉は、日本語と英語で全く異なるイメージがあるから厄介。日本語の「管理」は、英語の「マネジメント」よりは「監視」のニュアンスを感じる人も多い。
しかし、当たり前のルーチン業務も含め、コツコツと、ある程度の型に沿って積み上げるBacklogは創発の種の土壌なんだと思う。結晶を積み上げることで成果になる。個人の小さなアイデアやきっかけを積み上げることでプロジェクトになる。
今後は、Backlogはチームの創発をサポートするツールだと堂々と言いたい。
参考図書
今回の参加にあたって読んだり、後から買ったりした本を紹介しておしまい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
