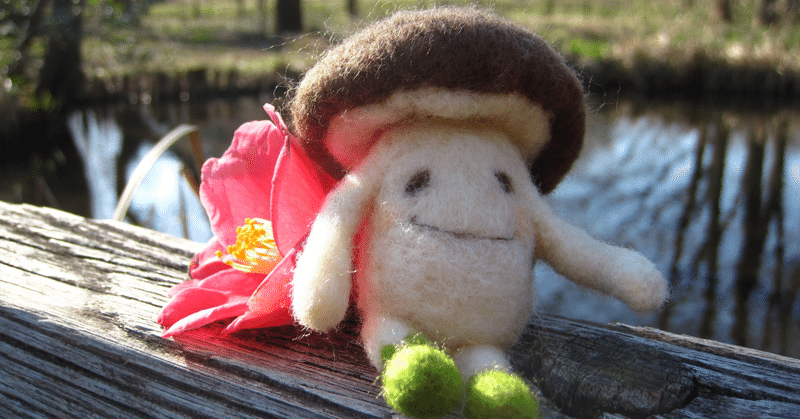
きのこについて
きのこについて
何できのこと呼ばれているの?
倒木や切り株などに良く生えることから「木の子」と言われるようになったという説があります。
きのこを知ろう!!きのこは何からできている?
私たちが「きのこ」と呼んでいるのは、植物では果実や花に相当する器官です。ここでは、植物の種子にあたる胞子が作られ、それらが、飛散して子孫を残します。では、きのこは何からできているのでしょうか?
答えは「菌糸(きんし)」です。
きのこは、微生物の真菌類がつくる糸状の菌糸が集まって塊状になったもので、例えばシイタケの柄を縦に裂いて、それを顕微鏡で見ると、長い菌糸がぎっしりと並んでいる様子を見ることができます。かさの部分も同様で、シイタケは全部「菌糸」でできているのです。また、きのこの下には菌糸の集合体である「菌糸体」があり、土や樹木、落ち葉の中に拡がり、栄養や水を得ながら生活しています。
「子嚢(しのう)菌類」と「担子(たんし)菌類」
きのこをつくるのは、たいていの場合「子嚢(しのう)菌類」と「担子(たんし)菌類」という2つのグループで、これらは、胞子(有性胞子)のつくり方が異なります。子嚢菌類は、子嚢と呼ばれる袋状の器官の内部に胞子をつくる菌類で、トリュフやアミガサタケなどの食用きのこはこのグループに属します。また、担子菌類は、担子器と呼ばれる構造の外側に胞子をつくる菌類で、マツタケやシイタケなどの食用きのこはこのグループに属します。
きのこはどうやって増える?
きのこで作られた胞子が、風などにより飛散して、倒木や落ち葉などの上に落ちて、条件が良ければ発芽します。そして、胞子から菌糸が伸び、養分を吸収して拡がり、菌糸体となります。その後、栄養条件や温度、湿度などの環境条件に応じて、まず、菌糸体の一部で菌糸が密に集合して、きのこの元になる原基が形成され、これが発達して柄と傘ができ、きのことなります。
不思議!落雷でキノコの収穫量が増加?
埼玉・宮代町にある日本工業大学。ここでは日本に古くから伝わる「雷が落ちるとキノコが育つ」という言い伝えを検証し、雷をシイタケ栽培に活用するための研究を行っています。
シイタケは通常発芽から収穫まで1週間かかりますが、人工的な雷を発生させた場所にあるシイタケの菌を打ち込んだ原木では、3~4日にまで短縮されました。さらに収穫量も2倍になりました。
日本工業大学の平栗健史教授は「雷が落ちたときの音の衝撃波が、シイタケの菌糸に刺激をあたえて生えてくるのではないか」と仮説をたてました。
そこで、1日3回、数秒間落雷に近い115デシベルの音をあてると、人工の雷を使った実験と同じ結果が得られました。
きのこは分解/共生して生きている
きのこは、栄養の取り方によって、大きく「腐生菌(ふせいきん)」と「菌根菌(きんこんきん)」に分かれます。
・腐生菌とは
落ち葉や倒木、切り株などに生える菌で、セルロースやリグニンなどの植物体を構成する有機物素材を分解し、栄養分として利用します。腐生菌の生育によって分解された倒木や落ち葉は朽ちて、土へ還っていきます。腐生菌きのこの例として木の幹や枝などを分解する「木材腐朽(ふきゅう)菌」のシイタケやナメコ、落ち葉などを分解する「落葉分解菌」のマッシュルーム(ツクリタケ)などがあります。
・菌根菌とは
生きた植物と共生関係を築いて生活している菌で、菌糸を土の中に張り巡らせ、植物の細根部に共生して菌根をつくります。菌類(きのこ)はチッ素やリン、カリウムなどの無機養分や水を吸収し、自ら利用するとともに菌根(植物の根と菌類が作る共生体)を介して植物にもそれらを届けます。一方、植物は光合成でつくった糖類などを菌類に与えます。菌根菌のきのこの例としてマツタケやホンシメジ、トリュフなどがあります。
きのこは凄いぞ!自然界でのきのこの役割
・分解
腐生菌は、分解者としても生態系における循環システムの維持に役立っています。植物や動物の遺体などの有機物を分解して無機物へ還元し、植物の栄養として土へ戻す役割を果たしています。他の菌類や微生物が分解できない難分解性の物質であるリグニンを含む樹木の幹や枝なども分解することができます。森林が枯れ木や落葉で埋め尽くされないのは“森の掃除屋”と呼ばれる腐生菌のリグニン分解パワーのおかげといえるでしょう。
・共生
菌根菌は、土壌中で植物の根よりも広範囲に拡がり、さまざまな物質を分解する酵素の分泌により、植物の水や無機養分の吸収を促進します。植物は単独で生きるよりも、菌根性のきのこと共生することで、より多くの水や栄養を吸収することができます。また、細根部が菌糸に覆われることで、乾燥や病害に対する抵抗性が高まります。
以上です。
