
国税庁が10月に修正案を発表。「副業300万以下が雑所得に」という改正案はなぜ作られたのか?
2022年8月1日、フリーランスや副業をしている方にとって衝撃的なニュースが飛び込んできました。それは「所得税基本通達の制定」について「副業の収入金額が300万円以下の場合、特別な理由がない限り雑所得として取り扱う」という改正案が出されたというものでした。
これには大きな反響があり、国税庁が募ったパブリックコメントには8月の1ヶ月間で7059件もの意見が寄せられる事態に。これを受けて、国税庁は10月7日に修正案を発表しました。
今回は改正案にいたった背景と内容について、さらに来年2023年10月から開始されるインボイス制度との関連などについてまとめています。
8月の改正案に至った背景

国税庁が問題視しているのは、シェアリングエコノミーなどの「新しいビジネススタイル」や「副業にかかわる所得」の所得区分があいまいで判定することが難しい、という点です。
「適性に申告がなされているのか」という課題は以前からありましたが、副業に関する勢いが加速される今、この課題がより浮き彫りになったとのこと。それが8月の改正案に繋がったようです。
重要なのは「主たる所得ではない収入金額が300万円以下の場合、特別な理由がない限り雑所得と取り扱う」という箇所です。
「事業所得」と「雑所得」
そもそも継続的な収入がある場合は「事業所得」ではないの?と思う方も多いでしょうが、収入が「事業所得」か「雑所得」かはしっかりと区分が決められています。
「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる方の、その事業による所得が該当します。
「雑所得」とは9種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得が該当します。
確定申告の際に事業所得と認められず修正を求められるケースも多く、主な収入が給与所得のサラリーマンである場合は基本的に「副業=雑所得」として扱われると考えておいた方が良いでしょう。
「雑所得」の種別
国税庁のホームページには“業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの”と記載されています。
先ほどもご説明したように、サラリーマンの副業は基本的に「その他雑所得」となり、営利目的として継続した収入は「業務に係る雑所得」に該当します。具体的にはデジタルコンテンツの販売による所得などがこれにあたります。
例えば、暗号資産(仮想通貨)取引は基本的に雑所得となります。しかし、暗号資産の収入によって生計を立てていることが「客観的に明らかである場合」は事業所得になるとのことです。つまり、暗号資産取引で損失があり、給与所得などと相殺(損益通算)している場合は、事業所得と認められることは難しいようです。
影響
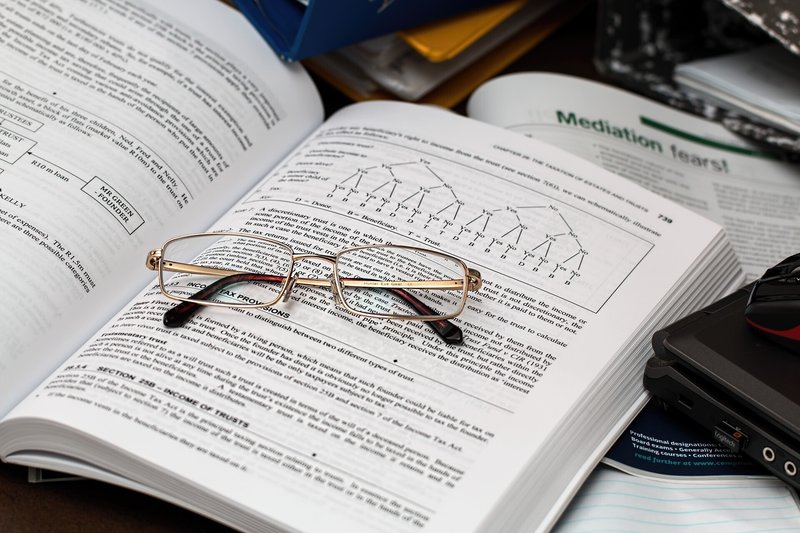
8月に発表された改正内容では、本来の収入はもとより、節税対策として収入金額を調整していた方も節税対策ができなくなります。そのため、「実質的な増税では?」という声も多く見られました。
副業収入を事業所得として申告しづらくなることを不満として多くの方々が声をあげた結果、修正案は300万円以下という金額での線引きではなく、「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」という帳簿の有無で線引きされる内容へと変更されました。
10月に出された修正案では「本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得と認められる」とされています。金額の線引きについては実質的になくなったと見てよいでしょう。
とは言え、今後も多くの改正が行われる可能性もあるので、事業所得として扱われていた所得が雑所得になることで出るさまざまな影響について考えておきましょう。
青色申告特別控除が使えない
青色申告特別控除では、事業所得に限り10万円、55万円、65万円のいずれか分を差し引くことができます。しかし雑所得に関してはこのような取り扱いが無いので、所得が増えることになります。
所得が赤字になっても損益通算ができない
事業所得が赤字になった場合に給与所得と相殺する(所得総額を減らす)ことができます。しかし、雑所得の場合は他の所得との損益通算ができないため所得が増えることになります。
例えば給与所得と事業所得があり、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺(損益通算)をして所得総額を減らすことができます。
赤字分の繰り越し控除が使えない
こちらは青色申告をしている場合のケースに限ります。事業所得が赤字で損益通算しても赤字であるとき、3年間繰り越して翌年以降の所得と損益通算することができます。雑所得だとこの制度が使えません。
少額減価償却資産の特例が適用されない
青色申告をしている場合は、1つ30万円未満の減価償却資産を一度に費用処理することができます。減価償却資産とは、事業用の資産で購入価額が10万円以上の耐久性のある資産、例えば建物、車、機械、備品のことです。こちらも雑所得だとこの制度が使えません。
8月の改正案が出された理由は納税者側にもあった?

一般的な税の仕組みは「累進課税」と言われるものです。こちらは所得の増加に伴って税率も増加するというもの。その一方で「逆進課税」というものもあります。こちらは所得が一定を下回ると税負担が増える、というものです。
「逆進課税」は所得の格差拡大を助長してしまうため避けなければならないにも関わらず、8月の改正は「逆進課税」にあたるのではないかとして問題になりました。また、「働き方改革」として副業への門戸を開いたかと思いきや、このタイミングで実質的に副業を規制する施策を開始したのは矛盾ではないか、という意見も多く見られました。
そもそも、年間300万円以上をクリアするためには「月25万円」の収入が必要となりますが、これをクリアできる副業サラリーマンは多くないでしょう。
結果的に金額の線引きは10月の修正案によってなくなりましたが、8月の改正案が出された理由には、以前から税法の隙をついた手法が推奨されるなど、納税者側の問題も関係していたようです。
法の抜け穴
税法の隙をついた手法とはどのようなものなのでしょうか。
例えば「副業で赤字をつくって節税」などがそれにあたります。中にはこの手法を推奨していたコンサルタントもいたようです。税理士の中にはこの危険性に警鐘を鳴らしていた方も。
このような「税法の抜け穴」ともいえる手法が世間に広まり、国税庁としても見逃すわけにはいかずに8月の改正に至ったと言われています。例えば、事業所得なのか個人の生活費なのか、といった境界線は非常にあいまいで、それを完璧に判別することは難しいのです。
今回の件に限らずこのような事案は過去にも起こっており、その都度法律改正が行われてきたという経緯があります。8月の改正案は「副業での経費を公私混同していた」方に対する規制とも考えられます。
例えばプライベートの遊興費を「必要経費」として落としたことはありませんか?そのような納税に対するルーズな感覚が今回の法改正に繋がったと言えるのではないでしょうか。
300万円以下の線引きはなくなったけど……?

今後注意すべき「インボイス制度」
「主たる所得ではない収入金額が300万円以下の場合、特別な理由がない限り雑所得と取り扱う」という改正内容は修正され、金額の線引きはなくなったため、フリーランスや副業の方々もとりあえずは一安心、というところでしょうか。
ただし、フリーランスや副業をしている方が注意しておきたい制度が2023年10月から始まりますよね。以前も解説した「インボイス制度」です。
インボイス制度は所得の形態に関わらず、取引先から「インボイスを発行して欲しい」と依頼があれば発行する必要がでてきます。
確定申告の際に整理しておかねばならない事項が増えることになりますので、しっかり対応しておきましょう。
まとめ

8月に発表された改正案はひとまず修正されたため、所得金額によってさまざまな控除や特例が適用されない、ということはなくなりましたが、2023年10月以降からはインボイス制度が始まります。
インボイスに関しては賛否両論あるため施行までに変更がある場合も考えられますが、さまざまな問題が指摘されているインボイス制度は8月の改正案と同じく「政府が副業を推進したいのか抑制したいのかよくわからない」といった声も散見されます。中には副業を辞めようかなと考える人も少なからず出てきそうです。
副業に関する法整備は今後も行われると予想されます。しかし正しく事業に向き合っている方であれば、新たな規制が導入されたとしてもほとんど影響を受けることはないと考えられます。「納税は国民の義務」と言われていますが、これからも正しく納税している方たちのための制度であってほしいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
