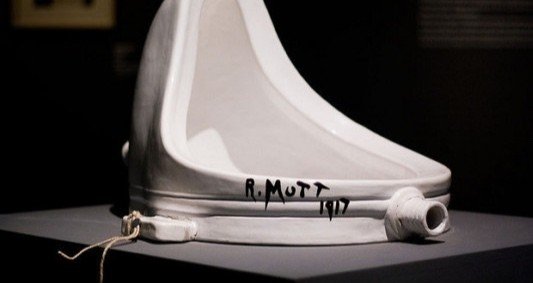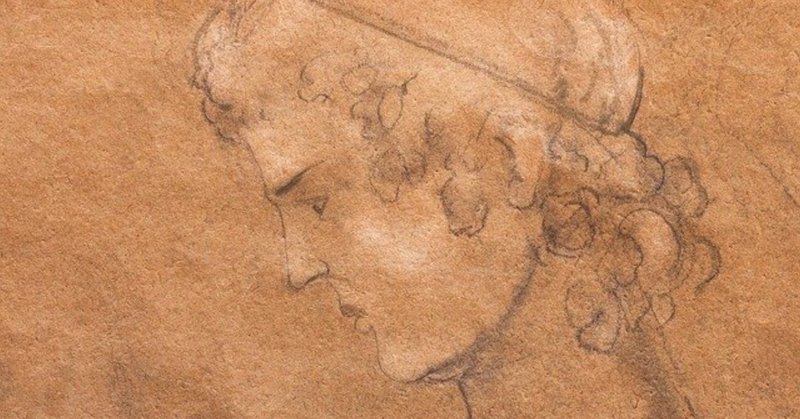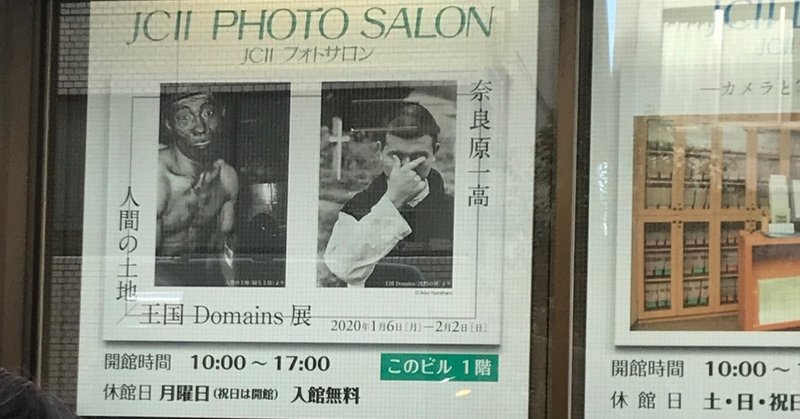2020年2月の記事一覧
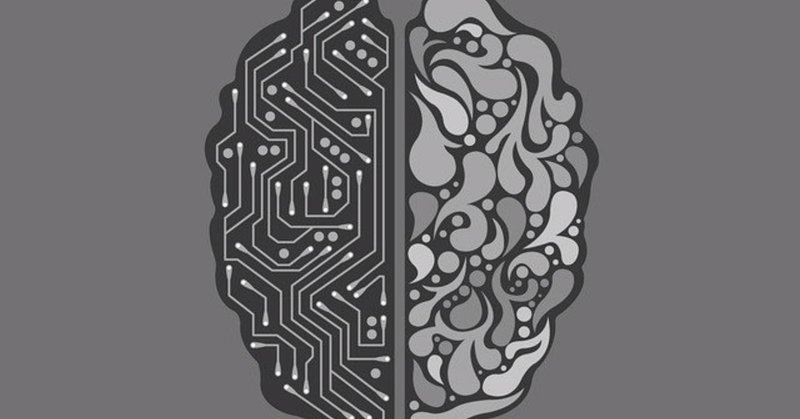
WWFF:対話編 第3回「機械と衣服」人工知能とファッションにおけるコンピューテーショナルな生成力 - パターン / パラメータ / アルゴリズム 聴講メモ
2019年8月の話。渋谷で開催されたセミナーに申し込んだ。 登壇者は次の通り。FBで友達の友達だったりする人も講演している。世の中狭いものだと、常々思う。 岡瑞起: 工学博士、筑波大学システム情報系・准教授。 砂山太一: 建築・美術研究者。京都市立芸術大学専任講師(芸術) 藤嶋陽子: ZOZO テクノロジーズ研究者 川崎和也: (主催者)スペキュラティブ・ファッションデザイナー セミナーは各人からのミニレクチャーを行ったあとで、パネルディスカッションを行うという流れ。フ