
2023年11月にSteamで発売される注目タイトルかもしれないゲーム
今月はSteamで日本時間で21日よりオータムセール(ブラックフライデーセール)が開始されるため主なタイトルも上旬、中旬に集まっているようです。最初にピックアップした時点では15本くらいあってどれを落とすか大分悩みました。今残っているものも正直これは購入確定というものはなくて、良さそうだが小粒の作品そうとか、光るものはあるが万人向けではないな…というのが多かったです。
The Smurf 2: The Prisoner of the Green Stone
11月2日発売
正式リリース
ジャンル: アクション (3Dプラットフォーマー)
日本語あり
以前対戦型ゲームであちこちで起きているスマーフ問題について解説した記事を公開しました。
基本的にはこのスマーフ行為はほとんどのゲームでは歓迎されておらず処罰の対象となることも多いです。しかしこのゲームでは好きなだけスマーフすることができます。というかスマーフ公認ゲームですね。以上です。
Slime 3K: Rise Against Despot
11月3日発売
早期アクセス
ジャンル: アクション (Vampire Survivorsライク)
日本語あり
体験版あり
スライムが主人公のVampire Survivorsライクのゲームです。数種類いるスライムの中から使用キャラを選び、次にプレイするステージを選択するとゲーム開始、一定時間後にボスが登場するのでそれに備えて雑魚、中ボスの敵を倒して強化を進め、最後にボスを倒してクリアなゲームですね。
特徴としては
レベルアップ時に出現する自販機を取るとトークン(資金)が増加し、アップグレードを購入可能
同じアップグレードを3個揃えると強化される(最大3レベルまで)
インベントリサイズの制限があり、それを超過して購入、保持はできない
(不要なアップグレードは売却可能)自販機にはレベルがあり、トークンを消費してレベルを上げると商品の個数が増加、レアリティの高いアップグレードが出やすくなる
アップグレードには「火」「氷」「召喚」などのタグがあり、特定のタグを対象とするパッシブ強化もあります。インベントリサイズは12個(うち8個が実際に使用されるもの、残り4個は保管専用)しかないためレアリティが高いのが出たからと買っていると中途半端になってしまいます。どれか1つまたは2つのタグに特化して取捨選択していけというデザインなのでしょう。
その特化で重要なのがゲーム開始前に行えるデッキ構築です。クリア後に得られる経験値でレベルが上がっていき、新たなアップグレードがアンロックされていくわけですがその全てが自販機に登場するわけではありません。アンロック済みのアップグレードの中から最低15個、最大40個を選んでデッキを構築するとそのデッキに含まれているアップグレードのみがゲーム内で登場します。
あとこのゲームの売りとしてはギャグ要素があります。例えばこちらはゲーム終了後のレベルアップ画面です。

同開発元の過去作もなかなかユニークなイベントがあったりして魅力の1つとなっていました。ただVampire Survivorsライクなゲームでそれがどの程度味わえるかはよくわかりません。
余談ですがこのゲーム、普通のVampire Survivorsライクのゲームと違って必ずしも敵を避ける必要がない気がします。最初から取れる能力の中に周辺の敵にダメージを与えるものがあって、これを集中的に取ると敵のど真ん中で仁王立ちするとどんどん溶けていく、回復アイテムも大量に出て逃げ回るよりもよほど安定するし成長も早い…という印象でした。


Ebenezer and the Invisible World
11月4日発売
正式リリース
ジャンル: アクション (メトロイドヴァニア)
日本語あり
ディケンズのクリスマスキャロルをモチーフとしたメトロイドヴァニアです。ヴィクトリア時代のロンドンで原作の主人公エベネーザ・スクルージが様々な特殊能力を与えてくれる幽霊をお供に、悪しき幽霊を従える実業家のマルサスと戦っていくという物語だそうな。
今年6月のSteam Next Festで体験版が公開されていたらしく、私は見落としていたのですが当時投稿されたプレイ動画を見るとこれといった特徴には欠もののメトロイドヴァニアの基本的な要素は大体そろっていて、クオリティは高そうだなという印象でした。あとは原作のクリスマスキャロルまたはメトロイドヴァニアというジャンルが好き、スクリーンショットやトレイラーを見て雰囲気が気に入ったのであれば、すごい神ゲーという感じはしませんが大きな外れはない気がします。

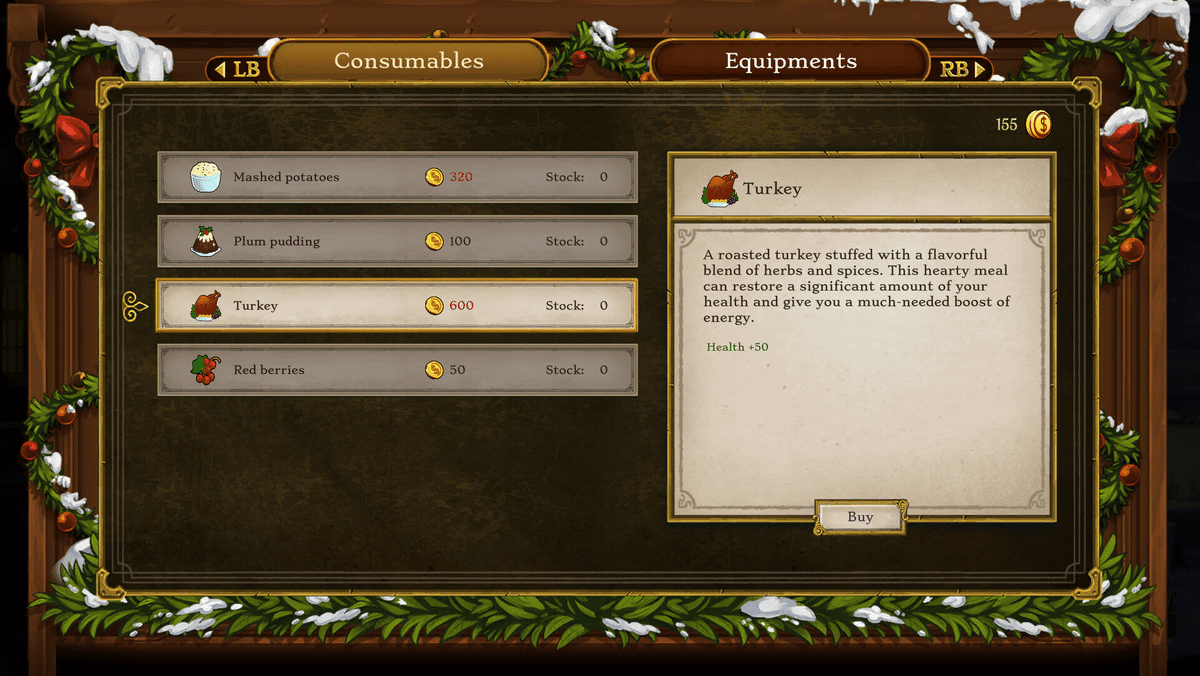
The Invinsible
11月7日発売
正式リリース
ジャンル: アドベンチャー (ウォーキングシミュレーター)
日本語なし
体験版あり
ポーランドの作家スタニスワフ・レムが1964年に発表したSF小説「砂漠の惑星」(デューンではありません)のゲーム化作品です。地球に似た環境を持つ砂漠の惑星レギスIIIで消息を断ったコンドル号の調査のため派遣されたインビンシブル号、その乗組員の1人であるヤスナとなって行方不明となったコンドル号乗員の探索、そして惑星で発生する謎の現象を調査していくナラティブ主導の1人称視点のアドベンチャーゲームですね。
原作ありな作品だけあって雰囲気やストーリーはかなり重厚で魅力的です。悲しいかな日本語がないので英語が読めないと後者については味わえないですが…。ただゲームとしては歩きが遅い、インタラクト可能なポイントの強調表示がなくところによっては指示が不明瞭、不快な視覚、聴覚的なエフェクトが入るなど若干つらいものがあります。こうしたナラティブ主導もののゲームの中でも癖は強めな方で、特にサバイバルものみたいなプレイ感覚を期待していると思うように進められずフラストレーションが溜まってストーリーを楽しめない…ということになるかもしれません。


Gunhead
11月9日発売
正式リリース
ジャンル: アクション (3D、ローグライト)
日本語あり
Risk of Rain 2、Gunfire Reborn、Roboquestと似たローグライトFPSです。ランダム生成された、無人ながら警備システムは作動している宇宙ステーションに侵入、その中枢であるブレインを破壊して有価物を回収して報酬を得て戦力を強化しつつ次のステーションへ…というのを繰り返していきます。

防衛システムの有無、登場する敵の種類、追加目標などが設定されています
1回のサルベージの流れとしてはまずいくつかある候補の中から次に行くステーションを選択、マップを見てどこにどのシステムがあるかを把握して攻略ルートを模索します。ブレインさえ破壊すればクリアなのですが少なくともそれを守っているシールド発生装置も壊す必要があります。時にはシールド発生装置が別のシールド発生装置に守られていたりして、ルート選定が重要です。珍しい点としてはステーション内部を移動する以外に一度外に出て、敵やトラップといった脅威が存在しない宇宙空間を通ってショートカットができます。この手のローグライトFPSではランダムに選ばれた脅威に正面から立ち向かい、対処していく必要があるわけですがこのゲームでは進め方によっては一部無視、迂回することも可能なわけです。

先に自動砲塔や修理装置を停止させて
じっくりと攻めるか…

機体相当のメカスーツが何種類かあって
初期武装や耐久力が異なるようです

次のステーション以降でランダムに登場するようになります。
購入直後に1回だけ、出撃時に確定で拾えるようです

FPSとしての特徴としてはテンポは早め、完全な飛行は無理なもののチャージは高速なジェットパックを使った三次元戦闘が要求されます。耐久力は初期スーツで8、雑魚の攻撃でも1発で1ダメージと脆く、また自然回復もなくてステーション内で回復アイテムを拾うことでしか回復ができません。1つのミッションを終えても減った耐久力はそのまま引き継がれます。武器の弾薬についても同様で、最初は結構な量がありますが撃ち尽くしたら終了、お気に入りの武器でもずっと使い続けることはできません。
戦闘バランス的には好き嫌いは分かれるタイプかと思います。ジェットパックの使用が重要で頻繁に上下移動、視点回転を繰り返すので3D酔いの問題もあるかもしれません。攻略ルートの自由度が高いことは似たタイプのゲームの中では珍しい特徴で、コンテンツ量、生成されるパターンの幅が豊富であればなかなか楽しめそうな気はします。体験版だと遊べるのは2ミッションだけ、選べるステーションの種類も限定されているのでそのあたり製品版ではどうなのかは未知数ですが…。
Cuisineer
11月10日発売
正式リリース
ジャンル: アクション、店舗経営
日本語あり
冒険者をしていた主人公のポムにある日実家より連絡があり、戻ってみるとレストランを経営していた両親は旅行に出ていて残された店を任されるというか押し付けられることになってしまいました。ダンジョンで敵と戦い材料を集め、料理をクラフトして店で販売してお金を貯めて店を拡張、町の人からのクエストをクリアしていったりするゲームです。
現在は公開停止となっていますが6月のSteam Next Festで体験版が公開されており、その際にプレイした限りだと題材や雰囲気、キャラは魅力的なもののゲームとしてはかなりライト寄りだなと感じました。戦闘はHadesに近いですが武器の使い分けや駆け引きといったものは弱く、例えるなら三國無双に似たプレイ感覚であまり深く考えずボタン連打で敵をなぎ倒していくゲーム、にも関わらず爽快さは特にない感じでした。レストラン経営もシステムとしては特に面白い、やり込める部分は見当たらないものの、料理のグラフィックは良くておいしそうでした。これは料理を題材とするゲームとしては大事な点だと思います。
純粋にアクション、店舗経営ゲームとして期待すると色々物足りないと思いますが雰囲気やキャラの魅力はよく、ゲーム内容はともかく傾向としては去年8月に発売されたCult of the Lambに近いものを感じました。また日本人受けしそうな作品だとも思います。



Mob Factory
11月10日発売
正式リリース
ジャンル: タワーディフェンス
日本語あり
体験版あり
タワーディフェンスにライトな工場建設ものの要素をあわせたゲームです。通常のタワーディフェンスは敵を撃破すると資金が手に入り、それを使って追加のタワーや障害物を設置していきますがこのゲームの敵は資金を落としません。かわりにその敵の種類に応じた素材を落とします。この素材をクリックして拾ってクラフトしたり、インプの商人と物々交換で新たなタワーや障害物を手に入れることができます。面白い要素としては敵はスポナーから一定間隔で出てくるのですが、このスポナーもクラフトで生産して設置できます。防衛力が十分であればスポナーを追加して敵の数を増やし、得られる素材の量を増やしていくこともできるわけですね。
クラフトできるものの中に銅、銀、金のコインがあり、これを貯めることで隣接する新たな土地を購入することができます。新たな土地では新たな敵が登場し、新たな素材が手に入ります。それを繰り返してどんどん新たなものを作れるようにしていくわけですね。
最初は素材の回収やクラフトを手動でやっていてもいいのですが大規模化していくと大変です。そこでコンベアを使って落ちた素材を工作機まで運び、工作機から出た製品をまたコンベアでアイテムを回収できる本拠地的なところまで運びます。ただしコンベアは敵の進行まで加速させてしまうのでそれも考えて建設していかなければなりません…。高度なクラフトレシピの中には複数の素材を必要とするものもあって、複数の島にまたがる物流網を構築する必要があります。
タワーディフェンス、工場建設それぞれの要素はごくシンプルでそれ単体の作品と比べると深みには欠けますがこの組み合わせならではの楽しさは感じられました。小粒な作品で価格もそれ相応のものになると思います。



Microcivilization
11月13日発売
早期アクセス
ジャンル: クリッカーゲーム
日本語なし
体験版あり
クッキークリッカーなどでお馴染みクリッカーゲーム、文明の興亡を題材としています。
クリックできる位置は画面上に2つあります。建設ボタンを連打して木、石などの資源を増やして風車や製材所を建て、食糧生産ボタンを連打してそれらの施設で働く人口を増やしていきます。厳密には人口には一般人と、一般人の人数が一定値を超える度に増える専門家みたいなものがいます。施設で働けるのは専門家の方で、一般人の数は研究力に影響します。

中間にある星はクエスト報酬みたいなもので
「マンモスとの戦闘に勝利する」などの目標を達成すると
報酬が受け取れます
もう1つやることはプレイヤーが発展させていく国の外に他の街や森、山があってそこを開拓していくことができます。地形タイプごとに選択肢が2つあり、それぞれ報酬と何らかのリスクが存在します。どちらかの選択肢を4回選ぶと別地形に変化してより大きな報酬が手に入ります。例えば村では宥和を選ぶと専門家が1人増えますが、徴税を4回行うと怒って蛮族の村に変化します。蛮族の村はさらに4回討伐すると農地になり食料のパッシブ生産量増加、4回教化すると専門家が1人増えるといった具合です。

この手の一時的な収入増が結構あるため
一見プラス収入に見えて一時的な効果が切れると
バランスが崩れたり衰退しはじめたりするのも
放置が難しい原因となっています
主にこの開拓では危機と呼ばれるイベントが発生しますがこれは槍兵、弓兵などの軍事ユニットで対処します。危機が発生してから時間が経過するごとに家が消失、人口減少といった悪い結果が出るので、その前に生産しておいた軍事ユニットを使用して危機の耐久力を削り切って乗り越えます。

使用した軍事ユニットは無くなってしまうので再生産が必要です。
レベルの高い危機は貯めておいた軍事ユニットでは足りず
危機発生中にクリック連打で新たに生産しては使用と
なかなか忙しいことになります
あとは装備可能なヒーローがいて、これも開拓や「人口1000人に到達」等のクエスト達成で得られます。文化、指導などいくつかのスロットがあり、そこにランダムに手に入れたヒーローをセットして資源生産量を増やしたり軍事ユニットを強化したり、プレイヤーにかわってクリックしてくれる所謂オートクリック機能が使えるようになります。

ある程度進めてからリセットすると序盤は大分楽になります。
不要なヒーローは売却したり複数消費して上位レアリティに変換、
引き直しなどができます
体験版では最後の技術を研究するとバベルの塔が建設可能になり、これを建てるとリセットして最初からやり直し、周回が可能になります。その回のプレイで研究した技術、クリアしたクエストの数などに応じてポイントが与えられ、それを使用してボーナスを購入することで次回以降のプレイが楽になるとともにより先まで進めるようになるでしょう。


体験版を何周かしてみたうえでの感想としては…とにかく忙しいです。忙しいのはクリックすることではなく研究する技術、クエスト、次に建てるものの選択、ヒーローのスロットへのセットなどの操作をずっと求められ続けます。クリックゲーは進めた段階によってプレイ感覚が変わってきたりもしますから最初の時代しかプレイできない体験版では製品版がどうなのか判断することはできませんが、とりあえず放置系ゲームを求めている人にはあわないでしょう。
The Last Faith
11月16日発売
正式リリース
ジャンル: アクションRPG (ソウルライク)
日本語あり
体験版あり
トレイラーやストアページ上のアニメGIFを見るとハイテンポなメトロイドヴァニア、ダークな雰囲気でBlasphemousみたいなゲームかな?と思いましたが実際にプレイしてみるとシステム、バランスはソウルライクでした。高速で走り回りながらざくざく斬りつけるのではなくて、敵の攻撃パターンを見て回避してから何発か入れてまた距離を取る…といった感じですね。
ソウルライクとしての作りとしては
スタミナなし
回復効果付きのパリィあり、ただしタイミングがかなりシビア
回避(ローリング)はすり抜け可能、使用回数制限もなく高性能
基本的に接触によるダメージはない(?)
回復薬はセーブポイントで自動補充はされない
(所持制限の超過分は倉庫に送られて、そこからは補充される)武器は近接2種、遠隔2種を装備可能
能力値あり、武器の種類により影響を受ける能力値が違う
(筋力A 敏捷Cとかのお馴染みのシステム)近接武器はそれぞれ戦技的なものもあり
こんなところですね。
メトロイドヴァニアとして見ると戦闘バランスや操作の気持ちよさとかの面ではひっかかるものがあると思いますが、ソウルライクとして見れば悪くはないと思います。ただ防御面についてはガードなしでパリィはタイミングがシビアなのはちょっと行き過ぎ、これだと位置取りとローリングだけで身を守るのが安定になってしまう気がしますね。パリィはアビリティの一種っぽいので製品版では他にガード的な性能のものもあって付け替えできたりするのかもしれません。
なお体験版を起動すると表示される操作説明およびその次のクラス選択がいきなり文字化けしてますが、ゲーム本編はほぼ日本語で正常に表示されます(一度メインメニューに戻ればそこも日本語になります)。また体験版中はレベルアップ、能力の割り振りはできません。



Worldless
11月21日発売
正式リリース
ジャンル: プラットフォーマー (2D)
日本語あり
体験版あり
雰囲気重視のプラットフォーマーです。特徴としては戦闘はターン制で、敵と遭遇すると自分と敵以外の時間は停止してどちらか片方が倒れるまでそれぞれが持ち時間を使って攻撃を行います。


攻撃ターンの持ち時間を延長できます
攻撃は物理と魔法(雷)、あとチュートリアルで説明がないので見落としがちですが魔法(氷)の3種類があり、自分が攻撃するときは相手の弱点となるものを選んで攻撃し続けることで敵が脆弱な状態になります。敵の体力を0にする以外に画面右下のメーターを線の部分まで溜めることで吸収、平たく言えばQTEによるとどめ攻撃が行なえます。

キーが半分くらいしか見えません。
当てずっぽうでもクリアは可能です

その前に体力が尽きて死んでしまう敵もいます

青とオレンジの2つのスキルポイントがあって
吸収でこれらを得て新スキルの取得、強化が行なえます
敵の攻撃ターンは最初に攻撃予告が出ます。敵も物理、魔法の2つで攻撃してきて物理攻撃は予告が横線、魔法攻撃が縦線なのでそれを記憶して対応するガードを行っていきます。中には「物理→物理→魔法」みたいな組み合わせた連続攻撃をしてくる敵もいて若干リズムゲームっぽくなってます。ガードは1ターンに使える回数が限られていますがジャストガードを成功させるとその回数を消費せずダメージも軽減ではなく完全無効化、さらに次のプレイヤーの攻撃ターンの持ち時間が少し増えます。

体験版を最後までプレイしてみて気になった点としてはプラットフォーマー部分については途中で入手できるダッシュに微妙なクールダウンがあって連発できなかったり、少しの高度差でも飛び降りると硬直が発生したりで連続動作の滑らかさとそれによる操作の快感が少し損なわれている気がします。敵の攻撃を回避したりシビアなジャンプアクションを要求されるわけではないのでもうちょっと緩い方がいいかなと。
戦闘はジャストガード前提の作りになっていますがガードの発生に少し遅延があり慣れが必要なのと、敵の連続攻撃の中でガードに失敗するとよろめきの動作が入ってそこから次の攻撃をガードしようとしても遅延で間に合わず連続で攻撃をくらいます。一応負けてもすぐ再戦できますし体力は戦闘が終われば全快なので難易度が高いわけではないのですが、フラストレーションを感じる作りではありますね。

白い点には吸収可能な敵がいて
吸収するとそのタイプに応じて青、オレンジの
色がついていきます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
