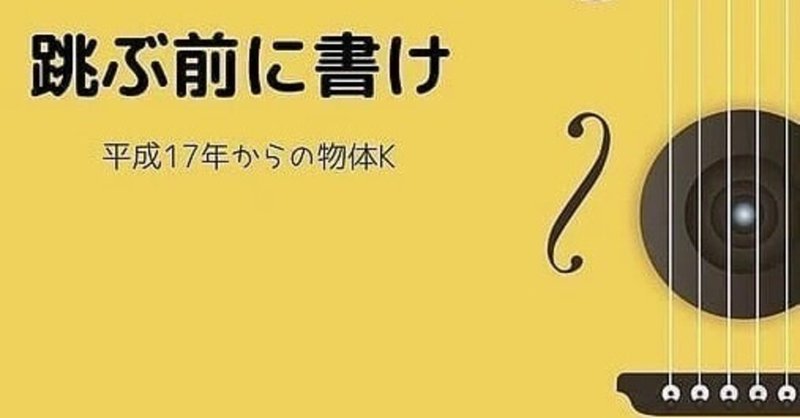
天使よ、故郷を見よ
誰しもが生まれ故郷にはそれなりの思い入れがある。幼き日々に見た街の風景や匂い。方言や慣習なぞは大人になったからとて、どこかにおいていけるようなものでもないのではないだろうか。
しかし、限度はある。どうやら関西人はその点において他の地方出身者とは一線を画しているのではないだろうか、と感じるこの頃でございます。
私自身も兵庫県は尼崎市という、芦屋の次にハイ・ソサエティな街で生まれ育った生粋の関西人でございますが、大学進学で東京へ上京し、卒業後もあわせると、約13年ほど東京で暮らしておりました。その後、家庭の事情で関西へ戻ってきましたが、戻った当初はどうにもこうにも、関西の空気感がとても居心地悪く、なるべく早く他の場所へ移住したいと思いつつ20年以上が経過した次第でございます。
その頃の自分を振り返りますと、同族嫌悪という言葉がございますが、まさにそれだったと思います。
東京に住んでいた頃は、「Englishman in New York」ではないですが、ボヘミアン、もしくは流浪の民のごとく馴染めずに、ただただアイデンティティを探すような心持ちでございました。
そのような東京時代に感じた疎外感は外部からのものではなく、自身が内在する関西人気質からであると気づいたいくつかの事柄について書いてみたいと思います。
その1 喫茶店にて
鳥たちも木々の影から飛び立とうとしないほどの夏の日差しの中、
僕たちはキャンパスをでて太陽に追い立てられるように、喫茶店へ避難した。
友人A「暑いね〜。早く冷たいものでも頼もうよ」
私「こんな日はキューッとチンチンに冷えたビールでもいきたいもんですな」
友人B「チンチン?下ネタ?」
私「ふぁ?いやいやいやチンチンなんて言ってないよ。キンキンだよキンキン。愛川欽也ね」
友人A「そんなダジャレはいいから早く頼もうよ。すいませーん。アイスコーヒーくださいー」
友人B「オレもアイスコーヒーで」
私「わたしも同じでお願いします」
店員「アイスコーヒー3つですね。わかりましたー」
友人B「漱石の日記ではないけど、家ならば素っ裸になりたいほどの暑さだね」
友人A「そうだね。まぁでも四季のある国に生まれたことを愉しみましょうぞ。ははは」
私「おや?あそこの人、なんか店員に怒ってない?」
友人A「ほんとだね。暑さでイライラしてるのかね?」
友人B「しかも関西弁だわ。オレ関西弁苦手」
私「。。。。そうなんだ。。。」
怒っている関西人客「しゃからなんべんも言っとるやんけ。レーコーくれッちゅうとんねん!レーコー!」
店員「あの。。当店は喫茶店でございまして。。。レーコーなるものはおいてはおりません」
怒っている関西人客「なんぬかしとんねん!あそこのお客さん、飲んどるんちゃうんけ!レーコー!」
店員「あちらのお客様がお飲みになられているのは、当店自慢の自家焙煎したコーヒー豆を丁寧にドリップし、冷やして作り上げたアイスコーヒーでございます」
怒っている関西人客「しゃからそれやんけ!レーコー!」
店員「へ?アイスコーヒーでございますか?」
怒っている関西人客「せや!関西ではイキってアイスコーヒープリーズなんか言わへんねん!レーコー言うんや!わかったらもってきてくれ」
店員「かしこまりました。アイスコーヒーお1つ注文承りました」
友人B「ははは。関西ではアイスコーヒーをレーコーって言うんだ。でもそんなの関西以外ではわからないよね」
友人A「そうだね。しかし関西人って我が強いっていうか。。郷に入れば郷に従えってことがわからないんだね」
私「。。。。。。」
私はとてもよく理解ができる。なぜなら関西人だから。そしてその理由も説明できるから。私が子供の頃、関西では、というか私の地元では商店街には必ず「冷やしあめ」と「冷やしコーヒー」が、路面店の惣菜屋などの軒先で1杯30円程度で売られていた。それらはガラスの容器に入れられ、冷たく管理されており、注文のたびにその容器の蛇口からコップに注がれ、その場で皆々が立ち飲みし、少し涼むのが当たり前だった。

「冷やしあめ」とは、水あめをお湯に溶かし、おろしショウガやショウガ汁を加えて冷やしたものである。「冷やしコーヒー」はそのままの意味ではあるが、とても薄く、そして甘いのである。そのような幼き頃からの生活習慣の経緯から、アイスコーヒー=冷やしコーヒー=冷コーヒー=レーコー なのである。なのでアイスーコーヒーを頼む際には関西人はレーコーというのである。
次回もご訪問お待ちしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
