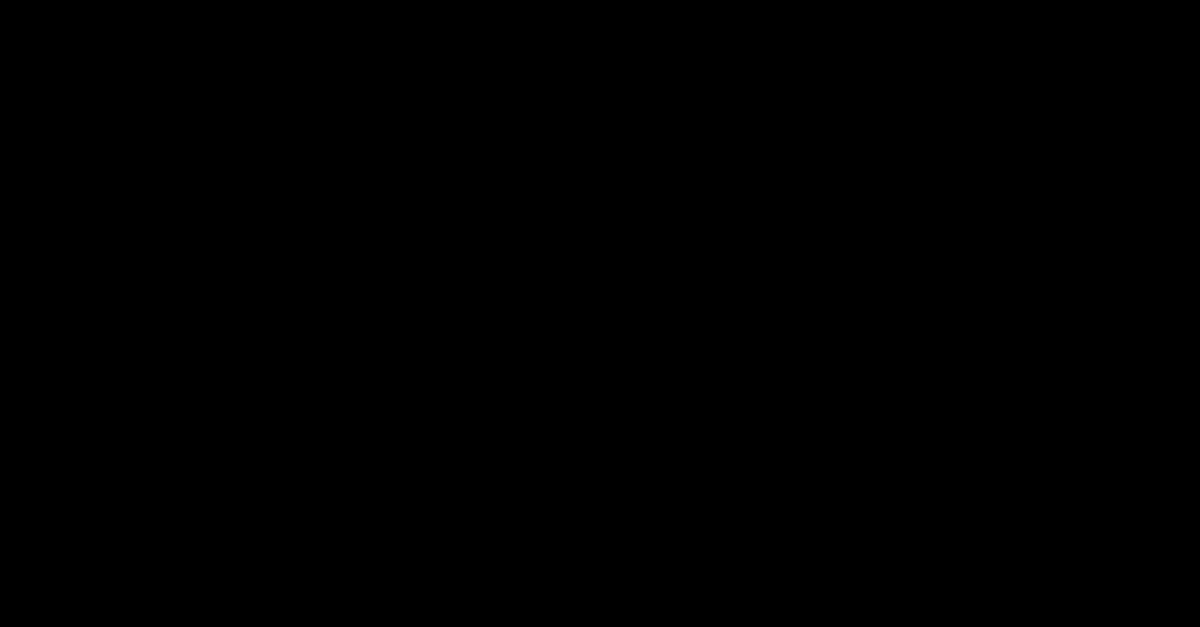
【短編小説シリーズ】 僕等の間抜けたインタビュー 『隣の皿は美味しそう』
柿谷 はじめは25歳の社会人の男。百代 栄香は17歳の高校生の女。二人は共に歩く。
彼等は友人、とは違う、「ありがとう」を言い合う仲。様々な場所に行き、のんびりとした時間を過ごす。話す。話す言葉はお互いに踏み込まず、傷付けない。妙に哲学じみてて馬鹿げてる。そんな日々を切り取って、彼等は笑っている。
柿谷はカキタニ、カキヤ、どっちの呼び方かは本人もあまり分かっていない。呼び方など、どうでも良いのだ。百代は柿谷を認知しているのだから。
百代は柿谷と共に出掛けている事を周りに秘密にしている。理由はない。ただ、刺激が欲しい彼女は自分を騙しているのだ。
二人共、小説に浸っていたからなのか、耽美に陶酔している。愚かにも、この関係を楽しんでいる。
発端
二人の出会いはカフェだった。隣同士席に座り携帯端末をいじっていた。二人がふと隣の端末を横目で悪気なく見ると同じ携帯小説を読んでいた。お互いにその状況に驚き、その驚く相手を見て相手も同様だと理解した。
二人は意気投合し、携帯小説について語り合っていたが、話題が尽きた頃にはお互いの素性が気になっていた。お互いに連絡先を交換し、その後も会うようになった。
二人は会う事をお互いの素性を知る『インタビュー』と呼んだ。今となっては、それもない。ただ『インタビュー』に行こうとお互いに行きたい場所を指定して会っていた。
関係は曖昧を極めていた。彼等は寄り添ってはいるが繋がろうとはせず、お互いにお互いの距離を保っているが、立場を尊重しお互いへの理解を深めている。
二人共、適当に生きていた。余計な気力はなく、ただ二人はお互いの行きたい所に行き、漂流していった。
隣の皿は美味しそう
二人は降りた事のない駅で降り、見知らぬ街を散歩をしていた。ぶり返す寒さに、百代はコートの中の身体を細かく揺らして対抗する。
「えーちゃん、誕生日近いよね」
「ふぇ!?」
柿谷の突然の言葉に驚いた拍子に声が裏返る。
「いや、もうすぐでしょ?3月だよね」
「なんで知ってるの……?ちょっと怖い」
「え、だって話したじゃない最初か次のインタビューかで」
「そうだったかなぁ……てか、なんでその話になったんだっけ」
「誕生石が何とか」
「あー……うっすら」
「どうでもいい話ばっか覚えてるからなぁ僕」
「本当だよ!びっくりしちゃった」
柿谷が鼻をすする。
「その時くらいだよ。敬語やめようみたいな話したのも」
「あ、そっかぁ!思い出してきた」
「えーちゃんに僕がさ、敬語やめない?って言ったらさ、えーちゃんすぐに分かった!って言ったんだよ?」
「そうだっけ〜?」
「そうだよ。僕色んな人に敬語使わなくて良いよみたいな事言っても、分かりましたとか返ってきて結局そんなに敬語は外れないもんだけどさ、えーちゃんは一瞬だったよね」
「うん、なんか、柿谷君年上な感じしなくて」
「お、それは、褒めてるのかな?」
「うん」
「……やけに素直なんだなそこは」
柿谷はペースを崩され頭を掻く。
「お腹すいた」
「えーちゃん何が食べたい?」
「寿司」
「ダメ」
「ダメってなんよダメって」
「お昼から寿司だなんて」
「寿司は夜に食べるものって決まってないでしょ」
「僕の中では寿司は夜を司っているからね」
「なにそれ」
二人の言葉の隙間を枯葉が通る。
「さむー」
「いやもうすぐ春ってのにこの寒さはなぁ」
「柿谷君がすっごい前にさ、あの、初雪の時。手袋貸してくれたでしょ?」
「あー……あれね」
「今その手袋ってないの?」
「父さんにあげた。長年持ってた革手袋がついに壊れたらしくてね」
「そうなんだ」
「あれ編み手袋だからさ、革手袋に慣れてた父さんが違和感が凄いって言ってたよ」
「あったかいよねあの手袋」
「そう。結構お気に入りだったんだ」
「どこで買ったの?」
「母さんが編んでくれたんだ。僕が大学受験する時に」
「良いお母さんだね」
「おしゃべりだけどね」
「じゃあ柿谷君はお母さん似だね」
「それは、違う!」
「ムキになってる〜」
柿谷が遠くに見える看板を指差す。
「あ、あそこのお店はどう?パスタ」
「良いね」
「寿司パスタはないけど、あそこで良い?」
「しょうがない。入ろ?もう寒くて死にそう」
「それは大変だ」
「お洒落な店だね」
「美味しそうだ」
二人はコンクリート打ち付けの壁で造られたレストランへ入っていった。待つ事もなく奥の席へ案内される。店内は茶と白を基調としたシックな造りであり、落ち着いた曲が流れている。
「さて、メニュー見ようか」
「先決めて良いよ」
「あ、本当?どうしよっかな〜」
柿谷が鼻歌を歌いつつメニューをめくっている間、百代は携帯を確認する。
「決めた」
「お、早いね」
「えーちゃんは?」
「もう決めてる」
「いつ見たのメニュー」
「外に出てた看板でビビッと来てた」
「あれ見てたんだ。いつの間に」
百代が店員を呼ぶ。
「お伺いします」
「えっと、じゃあ僕はこの牛肉の粗挽きボロネーゼで」
「私は渡り蟹のクリームソースパスタで」
「かしこまりました。ボロネーゼが一点、渡り蟹のパスタが一点でお間違いないですか?」
「はい」
「かしこまりました。出来上がりまでお時間少々かかりますので、ご了承くださいませ」
「はーいどうもー」
店員が去ると百代が柿谷を指差す。
「上着、脱がないの?」
「あ、悪い悪い」
「忘れんぼさん」
「悪かったな」
しばらく二人は携帯を弄り、互いに干渉しない沈黙を過ごした。
「お待たせしました。こちら、ボロネーゼと、クリームパスタです」
「わーすごーい」
「うまそ」
二人は携帯をしまい、互いの料理を見合った。
「なんかそっちの方が美味しそう」
「僕もそう思った」
「……交換しない?」
「無難に分け合いましょう」
「それ天才!」
柿谷が店員を呼び、取り皿を注文する。
「取り皿です」
「ども」
二人は顔を見合わせる。
「そんじゃ、食べますか」
「いただきます」
「いただきます」
二人の穏やかな食事の様子は外の寒気とは対を成す様だった。
この記事はこれで終わりです。スキを押すと色々なメッセージが表示されます。おみくじ気分で押してみてください。大吉も大凶もありませんが、一口サイズの怪文がひょっこり出てきます。
