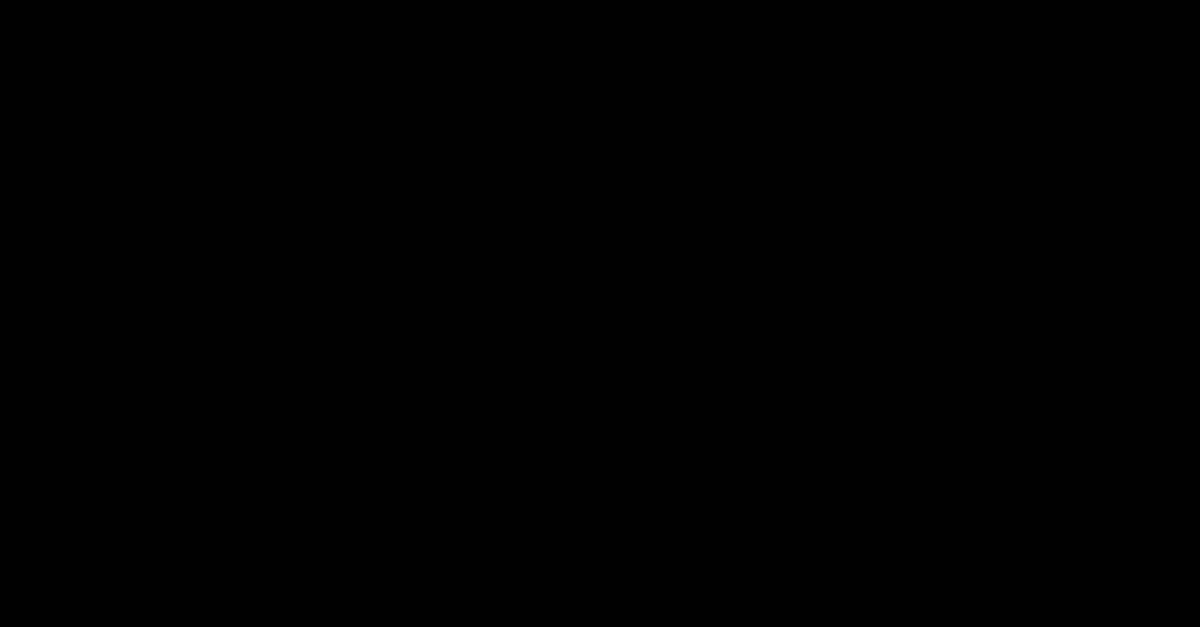
【短編小説シリーズ】 僕等の間抜けたインタビュー 『ぐつぐつと、ぐらぐらと』
柿谷 はじめは25歳の社会人の男。百代 栄香は18歳の大学生の女。二人は共に歩く。
彼等は友人、とは違う、「ありがとう」を言い合う仲。様々な場所に行き、のんびりとした時間を過ごす。話す。話す言葉はお互いに踏み込まず、傷付けない。妙に哲学じみてて馬鹿げてる。そんな日々を切り取って、彼等は笑っている。
柿谷はカキタニ、カキヤ、どっちの呼び方かは本人もあまり分かっていない。呼び方など、どうでも良いのだ。百代は柿谷を認知しているのだから。
百代は柿谷と共に出掛けている事を周りに秘密にしている。理由はない。ただ、刺激が欲しい彼女は自分を騙しているのだ。
二人共、小説に浸っていたからなのか、耽美に陶酔している。愚かにも、この関係を楽しんでいる。
発端
二人の出会いはカフェだった。隣同士席に座り携帯端末をいじっていた。二人がふと隣の端末を横目で悪気なく見ると同じ携帯小説を読んでいた。お互いにその状況に驚き、その驚く相手を見て相手も同様だと理解した。
二人は意気投合し、携帯小説について語り合っていたが、話題が尽きた頃にはお互いの素性が気になっていた。お互いに連絡先を交換し、その後も会うようになった。
二人は会う事をお互いの素性を知る『インタビュー』と呼んだ。今となっては、それもない。ただ『インタビュー』に行こうとお互いに行きたい場所を指定して会っていた。
関係は曖昧を極めていた。彼等は寄り添ってはいるが繋がろうとはせず、お互いにお互いの距離を保っているが、立場を尊重しお互いへの理解を深めている。
二人共、適当に生きていた。余計な気力はなく、ただ二人はお互いの行きたい所に行き、漂流していった。
ぐつぐつと、ぐらぐらと
二人は木造の海鮮系居酒屋で食事をしている。柿谷が生ビールを二杯飲み、仄かに紅潮している。百代はジンジャーエールが半分入った氷の多いグラスに両手を添えている。
「それが、えーちゃんの趣味?」
「そう。絵本って、子供しか読まないものだと思うでしょ?でも、大人が読んでも面白かったりするんだよ」
「へぇー……いやぁ知らなかった」
「柿谷君は小さい頃どんな絵本読んでた?」
「うーんそんなに覚えてないけど、あのネズミ二匹がカステラ?ホットケーキだっけな。それ作る絵本見てあー美味しそうだなぁなんて思った記憶はある」
「多分、ぐりとぐらかな?」
「多分ね」
「にしても、美味しそうって」
百代が手を叩いて笑う。
「なんでぇ?そんなに笑わなくても」
「いやいや、その記憶すっごい子供っぽくて、なんか面白い」
「そうかなぁ」
「ねぇねぇ、頼んでいい?」
「何を?」
「料理」
「あ、どうぞどうぞ。お好きに」
「すいませんなんか」
「奢られる人間はもっとしゃんとしなさい」
「しゃん!」
「よし!それでいい」
背筋を伸ばした百代は髪の毛を耳にかけ、メニューをめくる。
「海鮮お好み焼きとかどう?」
「おーいいね」
「なんか、さっきのカステラじゃないけど」
「カステラは粉ものじゃないと思うけどなぁ」
「え?粉ものでしょ?」
「そうだっけ」
「そうだと思う」
「まぁなんとなーく、似てるかもね」
「似てるから、粉もの繋がりで。じゃあ食べよう!」
「僕ウーロンハイ頼もうかな」
「分かった」
百代が店員を呼び、海鮮お好み焼きひとつとウーロンハイ一杯、海老のアヒージョひとつを注文する。
「あれ?それも?」
「うん。私海老好きなの」
「そうなんだ。僕も好きだよ」
「え!本当に?それはびっくりだ」
「意外にまだ知らない事が多いんだなぁ」
「そうだね」
「アヒージョってあの、炒め物みたいなやつでしょ?」
「そうそう。油に浸ってて、ぐつぐつしてるの。これ」
百代がメニューの中の海老のアヒージョの小さなイメージ画像を指差し、柿谷に見せる。
「あー!これか。なんか鍋みたいのに入ってると思ってた」
「それパエリアじゃない?」
「そうかも!流石えーちゃん。僕の思考が読めるんだね」
「いや読めない読めない」
「じゃあ……今僕は何を考えてるでしょうか!」
「えー?そんな事する人だっけ柿谷君……えー?うーん、なんだろ」
「考えてるよ今。考えてる」
「分かった分かった。じゃあ……さっきの絵本の事!」
「不正解」
「アヒージョ」
「不正解」
「えー分かんない」
「正解は、この食事がおいくらになるのかって事でしたー!」
「うわ思ったより現実的だった」
「残念!えーちゃんアウト!」
「アウトじゃないけど。というかなんかごめん」
「いやいやいや!僕趣味と言える趣味なんてないし、使える時は使います!」
「結構酔ってない?柿谷君」
「まだほろ酔いくらいだと思ってるけど。まぁそろそろ自制しなきゃ」
「私介抱とか嫌だからね」
「分かってるって」
店員が二人の席にウーロンハイを運んでくる。
「こちら、ウーロンハイです」
ウーロンハイは百代の前に置かれる。店員が去ると同時に柿谷がグラスを自分の前に寄せる。
「間違えられてやんの」
「私が大人っぽいって事でしょ?」
「かもね。まぁ僕のビールまだあるし、頼むタイミング間違えちゃったかな」
「柿谷君、お好み焼きとアヒージョどっちが先に来ると思う?」
「え?僕は……アヒージョ」
「私はお好み焼きだと思う」
「その心は?」
百代が考え込む。
「……油料理って時間かかりそうじゃない?」
「えー?鉄板の方が時間かかるよ」
「そうかなぁ……てか、さっきちょっと面白い回答しなきゃいけないのかって迷っちゃった」
「その心は?って聞き方がね、悪かったね」
「柿谷君はアヒージョだと思う心は?」
「まず工程が多いのと、大皿料理だから持ち運ぶのも大変かなって」
「なんか、ちゃんとした理由だね」
「じゃあ僕の勝ちね」
「いや!今、今思い付いた!さっきのもう一回やって?」
「え?」
「その心は?って聞いて」
「その心は?」
「アヒージョは油を売ってるから、遅い!」
柿谷は何も言わず、百代を見つめながらビールを飲み干す。
「油料理だから、油を......ってね?」
百代が足掻きとも思える補足をする。
「うーん、上手くないかな」
「あーダメかぁ……」
「10点中……4点!」
「うわー渋い」
「まぁきっとどっちの料理もえーちゃんの洒落よりは美味いと思うよ」
「ひどーい」
店員が二人の席にやってきた。
「お待たせしました。海老のアヒージョと、海鮮お好み焼きです」
二人の前に湯気の立つ料理が置かれる。
「……同時だったね」
「あぁ」
二人は黙って海鮮お好み焼きを箸で切り分けて自分の取り皿に乗せる。アヒージョの油の呻きだけが席に満ちていた。
この記事はこれで終わりです。スキを押すと色々なメッセージが表示されます。おみくじ気分で押してみてください。大吉も大凶もありませんが、一口サイズの怪文がひょっこり出てきます。
