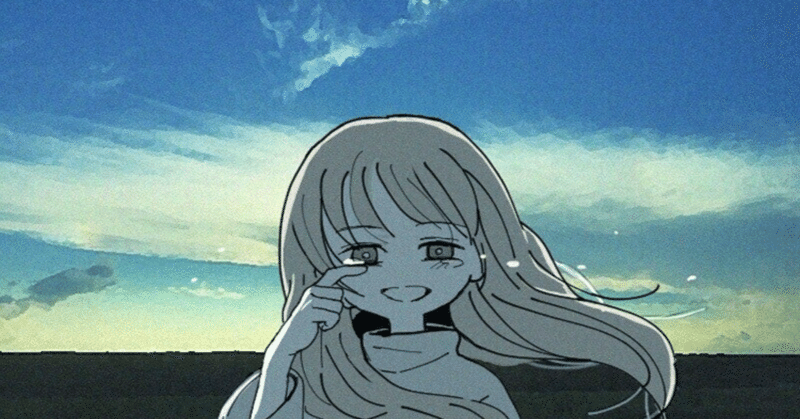
【Love Rescue】血管をなぞるように理解する夜③(2015年)
20代の終わり。俺はまた結婚しようとしていた。
記憶が薄いガキの頃から家族というものに恵まれず、家族のような形だけの環境で育った。
その家族のような「箱」には、愛とか安定とか当たり前とか永遠というものは存在せず、あったのは暴力と絶望と貧困。明日の朝もおはようと言える、明後日もおはようと言える、10年後もきっとおはようと言える、そういう期待を許してくれる「箱」が家族なのだろうとずっと考えて育ってきた。
18歳から夜の世界にいて、22歳の時に普通の大卒のやつらと同じ年で、就職をした。その会社にはお世話になったけれど翌年、退職して起業した。夜の世界ではない。誰に職業を言っても顔が曇らない、「まともな」職種として起業した。俺は、まともな世界が欲しかった。
まともな職業、まともな人間関係、まともな恋愛、そしてまともな結婚。まともじゃない育ちだと思ってきたから、ささやかだけどまともな「箱」が欲しかった。
それでも俺は一度結婚を経験していた。
子供も出来た。
しかし、子供は生まれて数日であっけなく亡くなってしまった。ある夏のことだった。俺はショックを受けて立ち直るのに時間がかかった。
そこから夫婦の関係も上手くいかなくなり、別の道に進むことにした。あっけないものだった。惨めだった。
俺がひとりで起業した仕事はそうたやすくはなかった。
アダルトの仕事ではいくらでも金を稼げた俺だったが、頭が悪くて、人間関係の空気も読めないような脳みそしていたら、まともな世界では仕事なんかうまくいかない。
スタッフに嫌われ、客に嫌われ、取引先にも嫌われ、結果、お金にも嫌わて。生きるのが辛い。そんなありきたりな言葉がしっくりくるほど、ごくごく「まともに」人生がしんどかった。
子供を失ってから、俺はまともじゃない恋愛というか、まともじゃない女性と付き合うのは避けていた。夜の女や、行動がエキセントリックで巨乳の女とかね。俺には馴染みのある世界の女は避けていた。
まともになろうとする恋愛はいつだってうまくいかなかったけれど、それでも俺は新しい出会いを受け入れ続けた。
20代の終わり、付き合っていたのは地元の銀行に勤めている2歳年下のNという女性だった。
Nは短大を卒業してから地方銀行に就職し、支店の窓口の業務をしていた。取引先との飲み会の場で初めて会った。パソコンのメールアドレスを交換したのを覚えている。まだガラケーでメールをする時代ではない。
毎晩、自宅のパソコンでメールを往復させ、たまに電話をしているうちに交際するようになった。
俺には初めてと言っていいほど、まともな職業に就く女性だった。ショートカットの髪が似合っていて、目が大きな可愛らしい女性。性格も良くてね、いつも笑って過ごしていた。銀行の仕事はストレスがものすごいらしく、いつも辞めたいんだと言っていた。結婚したら絶対辞めるってね。
若かったせいもあるかもしれない。いつも深夜まで会って、翌朝6時半にはお互いの携帯電話に電話をかけ、おはようという一言だけを交わした。いつも平和で機嫌のいい女性で。それまで一緒にいた女性のように、突然ブチ切れて暴言を吐いたり、突然連絡が取れなくなるなんてことはなかった。
エキセントリックで感情を振り回す彼女がいる時は、俺はいつもゲンを担いでいた。この前、この道を通った時に彼女がブチ切れて喧嘩になったから、縁起が悪いので違う道を通ろう、とかね。くだらないことだけど、俺みたいな脳みそがいつもバグっていて人生がしんどい人間にはそういう儀式は大切だ。
Nにはそのような脳みその破綻を一切見せなかった。
父親が地元で有名な内科の院長で、裕福に育ったNに対して自分の病気がはずかしかったからだ。
Nとの関係は、俺がずっと欲しがっては叶わなかった、小さな「箱」だった。関係性はとても安定していて、俺は感情的にさせられることもなかった。
俺はNと結婚することを想像していた。もちろん、今思えばまるで育ちも生きている環境も違う二人が結婚するなんて、かなりの困難だったとは思う。でも若かったのでそんなことは俺は考えてなかった。この箱を大切に未来に送り込みたいと、そう思っていた。
そして、失った子供のことをいつかNに話せるときが来るかもしれない。
しかし。
ある日のこと、俺の身体に異変が起こった。高校生に時に発症した発達障害の二次障害が再び襲ってきて、まるで抑えられなくなった。
それまでの人生で経験したことがないほどの強い幻覚と幻聴がやってきた。そして焦燥感と希死念慮。
共感覚もものすごい強さで襲ってきた。自分の足音に色がついて見え、自分が発する言葉はモノトーンで色調変化をした。文字を読むと色がついている。人の言葉にも凹凸が着き、鼓膜が震えるたびに口の中に色々な味覚が広がった。
仕事ではルーティンの作業がこなせなくなり、電話もできず、お金の計算も出来なくなった。自転車操業で資金繰りをしていたので集中力だけが頼りの時期に、突然そんな症状が襲ってきた。幸い、スタッフが優秀な女性だったので不渡りを出することはなかったけれど。
「社長、休んだほうがいいですよ。」とスタッフは何度も俺に言った。でも俺は誰かに追われるように1日中事務所にいて仕事をしようとした。スタッフが我慢の限界であるかのように俺に言う。「社長、その状態で仕事されたら私、迷惑なんです。」
「そうだね、ごめん。」俺は詫びた。
Nとはそれでも毎日のように会っていた。仕事が終わると夜に待ち合わせて食事したり、俺の家に来たり。具合が悪いのは見せないようにしていた。こんなことがバレたらきっとNもいなくなってしまう。そう恐れていた。
でも、Nとは次第に会う回数が減っていった。最初は、俺が仕事で立て続けにミスをするのでその穴埋めに忙殺されて会えない日が増えていたせいだ。同時に、彼女のほうも「何らかの理由」で会えない日が増えていった。
メールの返事も次第に遅れていき、そのうち来なくなった。電話もたまにしか出なくなった。俺が電話料金を払えなくて止められた日が1日だけあって、そのあとから電話がうまく出来なくなった。
俺はその時代、まだ薬を飲む習慣がなかった。
夜のひとりぼっちで自宅で、襲い掛かってくる脳の中のグレーの世界に、じっと耐えるようにして眠っていた。食事の用意がものすごく大変で、まとめ買いしていた味のないクラッカーを粉末のポタージュスープに浸して、流し込むのが精いっぱいだった。やかんでお湯を沸かしたまま気絶してしまい、目が覚めたらやかんが熱で真っ黒になっていたりもした。
それでも自分が食べていくために毎日這うように事務所に行き、天井の模様が野良猫に見えたりして大声を出したり、頑張ってくれているスタッフに「ボーナス」と称して20万円をあげたりした。20万円は集金してきた売上金で、スタッフが「ありがとうございます」と言いながら、会社の口座に戻しておいてくれた。20万円がないだけで即倒産する有様だったので。
俺はずっと、返事の来ないNへのメールを送り続けていた。そこではいつも謝っていた。何を謝ることがあるのか分からなかったけれど、そんな人生でしかない自分を謝っていたんだと思う。もちろん返事はない。電話をかけても出るのはほんの稀で。それも30秒くらいで無言になってしまい、じゃあまた・・・と俺は気まずく電話を切っていた。
自分が生きているのか死んでいるのか分からない意識の薄明かりの中で、ある日、彼女からメールが届いていた。
「好きな人が出来ました。別れたいです。」
すぐに電話をしたが、その電話は解約されていた。メールの返事ももうしなかった。当たり前の帰結だと強く思っていたから。
俺が夢見ていた、安全な箱、ささやかな居場所はまた夢のように霧散したのを考えるのが辛かった。そして彼女に何もできなかった無力な自分に恥じ入った。
好きな人ができた。その言葉を何度も何度も噛み締めた。まるで辛いと分かっている唐辛子を何度も舐めるように。
今となるとNと付き合った前後の記憶が全くない。数年間分。結婚していたことと、子供を亡くしたこと、Nと別れたこと。それだけは覚えている。
きっとひどい状態で生きていたんだと思う。気が付けば頑張ってくれていたスタッフも辞めてしまった。
お詫びに、退職金を払った。無論、借金をして。
「いやだけど、また、エロの仕事をするしかないか・・・」
そう思ってげんなりした。
仕方なくまた始めたエロの仕事は当日からうまくいき、金が勢いよく流れ込むようになった。惨めなことに、俺はエロの世界では天才でしかなかった。
高校生だったなつき(その後、俺の人生に深く関わるようになる)が事務所に出入りするようになり、エキセントリックな女がまた大勢で俺に絡むようになった。
数か月が経って病状が落ち着いたころ、俺は何かまた元のだらしない不良に戻ったような気がした。つまり、派手な女、泡立つ酒とグラス越しに見る夜景、だらしないセックスライフ、飛び交う金。そんな世界に。
いろんなものを諦め、見切ったあとで、また「アキラ」として生きることになった。
追いかけては手に入らない、小さな箱をそれでも追い求めて。
自分の人生が本当にどうにもならない、そんな俺でも毎日をなんとか生き抜こうとして。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
