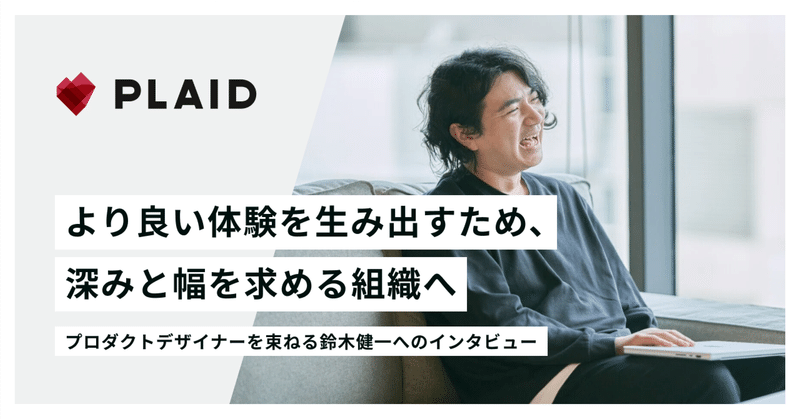
より良い体験を生み出すため、深みと幅を求める組織へ──プロダクトデザイナーを束ねる鈴木健一へのインタビュー
デザイン観点での思考やアウトプットで、多彩なプロダクト価値の最大化に寄与するプロダクトデザイナー。今回は、プロダクトデザイン組織を束ねながら、自身もデザイナーとして働き続ける鈴木健一にインタビュー。
デザイナーたちが集う組織をどのように設計しているのか、プレイドのデザイナーはどのようにプロダクトに向き合うのか、その思想や今後の展望について話を聞きました。
体験の一貫性を担保するための横断組織
──簡単に自己紹介をお願いします
地方のケーキ職人から一転して Web 制作の世界に足を踏み入れ、制作会社で経験を積んだ後にUIデザインを専門とするスタンダードという会社を設立しました。プレイドとは当時のクライアントとして出会い、その後スタンダードの解散と時を同じくしてご縁があって入社しました。
現在は Chief Design Officer として Design Department (以下、Design Dept.) というデザイン組織の責任者を務めながら、プロダクト組織内のプロダクトデザイナーをサポートしています。
──プレイドに入社しようと思った決め手は何でしたか
大きく2つあります。1つは、創業者たちが「やりたい」と語ることが難しくもおもしろいと感じ、デザインでその実現に寄与したいと思ったこと。もう1つは、KARTE というプロダクトの世界観とデザイナーの活動が似ていると感じたことです。
KARTE は「ユーザーの行動をデータで捉え、よい体験を設計できるようにする」ためのプロダクトです。その役割は、デザイナーがユーザーインタビューなどで知った課題を解決するためにデザインするプロセスに似ているなと。
プロダクトを軸にした活動は、1対1で価値提供するクライアントワークに比べ、1つのプロダクトが不特定多数の人に価値提供できるため、世の中のよい体験の絶対量を増やすことができるのではと感じたのも魅力でした。
入社以前は、事業会社に所属することでデザインの対象が固定化してしまうかもしれないという懸念がありました。しかし、KARTE はマーケティングというドメインであらゆる業界・企業の多様な課題にアプローチしているため、活動の幅が狭まることはなかったです。
むしろ今では、マーケティングだけでなくカスタマーサポートなど他の事業領域にもプロダクトのケイパビリティは拡がっています。その分考慮すべき対象や必要な知識が広がり、日々新しい発見が今でもできています。
──デザイナーの組織について教えてください
プレイドではデザイナーの活動領域として「プロダクトデザイン」「コミュニケーションデザイン」という2つの領域が存在しています。
2024年5月現在は組織としてのプロダクトデザイナーが集うチームは置かずに、KARTE をはじめとしたさまざまなプロダクトごとに設けられた開発組織に所属してデザインを担っています。
コミュニケーションデザイン領域はチームとして存在し、プロダクト以外の様々な顧客接点をデザインしています。あり方は異なりますが、それぞれの領域を横断する Design Dept. を設けることで、横のつながりを保って活動をするようにしています。

Design Dept. という横断組織を置いている大きな理由としては”体験一貫性の担保”です。例えば「KARTE」と「KARTE Blocks」は別のプロダクトで開発チームも異なりますが、クライアントから見れば同じ “KARTE” というブランド。もし使い勝手やデザインが大きく違えばプロダクトごとに学習コストがかかってしまいます。
また、ユーザーにとってはプロダクトを利用し始める前に触れるサービスサイトや資料などの接点も、一続きの連続した体験の中で触れる情報。我々のプロダクトを知り使い始めるまでの一連の体験に食い違いや品質のばらつきがないよう、プロダクトを含むさまざまな顧客接点を横断してデザインという軸で連携しやすくするために、組織横断の取り組みを進めています。
具体的には、週1回デザインの共有会や相談会を開催したり、Slack にアウトプット専用のチャネルを設けて投稿できるようにすることで、メンバーがお互いにどんなものをデザインしているかを知り、連携し合う機会につなげています。

表層だけじゃない、プロダクト開発への深い関与
──プロダクト開発におけるデザイナーの役割についてもう少し詳しく教えてください
プロダクト開発への関わり方は大きく2つのパターンがあります。1つは新規プロダクトの立ち上げ、1つは既存プロダクトの磨き込みです。
新規プロダクトの立ち上げでは、実際にUIなどを設計することに限らず、アイデアを発散するワークショップ、見込み顧客へのヒアリング、新機能の企画など「何をつくるか?」という段階から携わります。デザイナーだからといって、その領域に閉じずに関与することが期待されます。
既存プロダクトの磨き込みでは、各プロダクトが実現したい状態を表すプロダクトビジョンをもとに、新たな価値実現のための機能を検討したり、既存クライアントが困っている声に応えて既存画面を改善したりしています。
関わり方は参画するタイミングやスキルセット次第でさまざまですが、デザイナーの仕事としてイメージされる「デザインツールを使って画面を作る」などの手を動かす作業は全体の2~3割くらい。どのようなプロジェクトであっても、前提整理や認識合わせに割く時間のほうが多いです。
プロダクトデザイナーが担う変わった業務だと、開発中の分析機能を自分たちで使ってクライアントのサイトのユーザー行動を分析してデザインの示唆を得たり、本来はコミュニケーションデザインが担当するプロダクトを紹介する Web サイトのコンテンツを、理解度の高さを活かしてライティングすることもあったり、多様なバックグラウンドや強みを持つメンバーが活躍しています。私自身は Head としてメンバーをサポートしつつ、いちデザイナーとしても活動しています。
──メンバーにはどういったバックグラウンドを持つ方が多いのでしょうか
スタートアップを含む事業会社出身のメンバーもいれば、受託の制作会社やデザインコンサルティング会社でクライアントワークを中心にやってきたメンバーもいます。独学でデザインを勉強した人もいますね。
ここまでデザイナーと一括りにしてきましたが、その中にはインターフェースを設計するプロダクトデザイナーと、それを実装するデザインエンジニアがいます。
両者は強みの軸足こそ異なりますが、完全な分業ではなく、デザインエンジニアがプロダクトデザイナーに「こういう見せ方のほうが使いやすいのでは?」と提案することもありますし、協力してプロダクトをつくり上げています。そうすることで試行錯誤のスピードも上がり、良いものに早くたどり着ける。相互に関わることで仕事の面白みも増しているのではないかと思います。
本務から離れた仕事も楽しんで取り組んでくれているメンバーが多い気もします。デザイナー同士のコミュニケーションには割と余白があり、相互作用も起こりやすい。
クライアント向けアワード用のトロフィーをデザインしていたコミュニケーションデザイナーからの相談で、3Dが得意なプロダクトデザイナーがモデリングを担当するなど、一緒に働いているデザイナーが思いがけない仕事をすることが毎日のようにあって、相互に刺激を受け続けられる環境だと思います。
最近だと、自身の出身地域のクライアントのカスタマーサクセスを自身で行うデザイナーや、生成AIを使ってアイデア出しや分析に活用しているメンバーがいて、個人的には自分が一番刺激をもらえているなと思っています。
データを活用し、長く愛されるプロダクトづくりに向き合う
──プレイドでプロダクトデザイナーとして働くうえでの面白みを聞かせてください
プレイドのプロダクトデザインは、いわば便利な道具をつくる活動だと考えています。デザイナーであればデザインツール、大工さんならトンカチなど、職業によって必要な道具があり、道具によって仕事の質もやり方も規定されます。
KARTE はマーケターのためのプロダクトとしてスタートしましたが、徐々に業界や用途を限定しすぎずに使ってもらえるようになってきていて、その先にいる広範なエンドユーザーの多様な接点でよりよい体験を届けることを目指しています。
業界や提供価値が広いゆえの難しさがありますが、影響力が大きな道具を作れる面白さや醍醐味があると思います。
成長という観点では、先ほど話した多様な強みや経験を持ったデザイナーと働けることで、お互いの仕事から学び取れることや、難しいドメインの概念をシンプルにわかりやすく表現するための試行錯誤を通じて、体験から情報設計、インターフェースデザイン力を高められることが挙げられます。
さらに、マーケティングやグロースハックのドメイン知識を深められるということも、大きなメリットだと思っています。
どんなプロダクトを作っても使われなければ意味がなく、使い続けてもらわなければ事業の成長や存続は難しい。そのために何が必要なのか、データからユーザーの特徴や行動を読み解き次の打ち手を考える力は、プロダクトを成長させる術を身に付けたいデザイナーにとって一生の強みとなるものと考えています。
自分自身、データを見る感覚が磨かれている実感があります。プロダクト開発をしていると、この機能が本当にユーザーに役立っているのか不安になることも正直あります。
その点、感覚ではなくデータをもとに確かめられるようになったことで、より良くできるポイントも認識できるようになりますし、作ったものがユーザーに貢献できているという実感できることは何よりも嬉しいと感じます。
環境面では、プレイド自体の見据える領域の広さに面白みを感じます。「データによって人の価値を最大化する」というミッションのもと、特定の業界の「負を解く」ためのソリューション開発をしていたり、事業開発組織「STUDIO ZERO」のようにプロダクト活用を前提にせずにクライアントの事業課題の解決や地方自治体のサポートをしている組織があり、人とプロダクトの両輪で事業展開していることは、道具によって人が成長し、人によって道具が進化する良い循環を作ると考えています。

よい体験を生み出すプロダクトを追求できる組織へ
──プロダクトデザイン領域の今後の展望について教えてください
各自が役割にとらわれすぎず、能動的に動いて色々なことをやっていけるような組織にしたいですね。今以上に、個々人が研究テーマを持って活動するような環境を作りたいです。
個人的にやろうとしているのは、インタビューのログやフィードバック、解約したユーザーの声など、さまざまな定性的なデータを一元管理できるようにすること。デザインを考えながら「これに困っている人はどれくらいいるんだろう」と悩んだときに回答や手がかりを見つけるのに役立ちますし、より良い解決策を考えられるようになり、結果として、よいプロダクトづくりや、ユーザーに提供できる価値の増大へとつながるはずです。
プロダクトデザイン領域として取り組むべき目下の課題は、事業単体での最適化とマルチプロダクト展開する上での全体最適化のバランスをとることです。
例えば同じ操作なのにAとBのプロダクトでボタンの位置や見た目が大きく違うと、余計な学習コストがかかってしまう。とはいえAとBのデザイナーはそれぞれそれぞれのプロダクトにとってのベストを探求してくれているため、理由をヒアリングし、どちらかにあえて寄せたり、より上位の解決策を導く必要があります。
さらにその他のプロダクトにも横展開できれば、全体としての使い勝手がより向上します。コミュニケーションを含む課題解決の難易度は高く、場合によっては開発スピードが落ちるかもしれません。
独立性の高いチームで活動している良さを活かしながらも、プロダクト全体の価値を高められる組織にしたいです。
──そのために、組織にどんな進化が必要でしょうか
2023年に行った組織変更では、それまであったプロダクトデザインチームを開発組織に所属する形に変更し、プロダクトとの接続性を高めました。
それによって各プロダクトの取り組みが推進される一方で横断的な視点が弱まることを防ぐために、Design Dept. 内に Design Program Management というチームを組成し、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザインそれぞれの領域を横断した連携や学習機会を増やすための活動をし始めています。
デザイン組織のバックグラウンドが多様になり、提供できる価値も広がっています。誰かが何かをやると他のメンバーも刺激をうけて「自分も何かやってみようかな」と新たなチャレンジが生まれ、組織間の壁や線を越えた取り組みもしやすくなる。
個人が能動的に動けるようになることが大切だと思いますし、それと同じくらい、個々人の考えや思いを繋ぎ、動きやすくなるためサポートをするような場や活動も必要だと考えています。
コミュニケーション領域についてもこれまではマネジメントの役割を置いていませんでしたが、明示的に組織として切り出しました。そして、そのリードを別のメンバーに担ってもらうことで、施策を横断した意思決定をしやすくして、自分では考え及ばない組織の形を探索することに繋げてほしいと考えています。
プロダクトデザイン領域では、使い勝手やデザインの統一感は大切と話した一方で、事業会社である以上、事業が存続しなければユーザーへの価値提供は終わってしまいます。
デザイナーとしての視点は大切にしながらも、事業を伸ばすためにデザインスキルをどう発揮すればいいのかを考えることも大切。事業やチームの状態、プロダクトの現状を冷静に判断して、戦略的にデザインを活用できる能力が、これまで以上に求められていくと思います。

──最後に、鈴木さんの個人的な目標も聞かせてください
組織の長として、もっと論理と感情を行き来できるようになりたいですね。論理的に「こういう課題があるなら、こう解けばいい」と言うのは簡単ですが、各プロダクトのデザイナー視座では目の前のユーザーに最適なものを届けたいという想いがあります。
みんなが納得感を持ち理想の方向に進むには、どんな伝え方や会話であるべきか。人の感情にも寄り添えるコミュニケーションができるようになるのが目標です。
プレイヤーとしては、「Wicle」という分析系のプロダクトに関わっていますが、データ分析や統計学などの知識不足を感じます。データアナリストほど専門的な知識まではいかずとも、データを見て仮説を出し、打ち手のアイデアを出すところまで一巡できる力があるとデザインももっとスムーズかなと感じています。
最終的には、「自分たちのようなデザイナーが使える道具をつくる」ということをやっていきたいんです。私自身がデザインツールを使うことでデザイナーになれたように、自分がつくったツールで業界に恩を返したいと思っています。
前職で、デザイナー向けに自分のデザインを公開できる Web サービスを開発したのですが、いわばこれがプロダクトデザインに興味をもった原体験でした。自分が手がけたサービスで、自分に近いロールの人が新しいコミュニケーションの機会を得るのを目の当たりにして嬉しかったんですよね。
今プレイヤーとして入っているデータ分析のプロダクトは、マーケターよりはどちらかというとプロダクト開発チーム向けのプロダクトなので、これも将来の目標につながる取り組みになるはずと考えています。プレイドで積めるプロダクトデザイナーの経験は、ほかにはないものだと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
