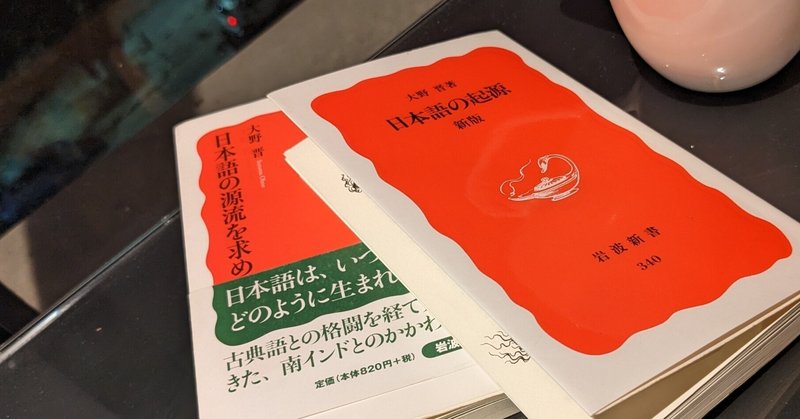#本

「余白」への感受性:インド・チェンナイのアート展覧会への招待『WHITE Emptiness as Limitless Potential』
「日本のグラフィックデザイナーである、原研哉氏の著書『白』に影響を受けたデザイナーがいるから、個展を見に来てほしい」という連絡があった。その方はアート・コレクターの方で、以前別の展覧会でお会いしていた。 原研哉氏に影響を受けたというそのデザイナーさんは、現在14人の若い芸術家のメンターでもあるのだそうだ。 海外で、かつ文化に関わる者として、日本の文化や美学をより深く理解して、それを自らの芸術や精神、哲学として広めようとされている現地の方々の存在は非常に重要である。原研哉氏