
国際標準の日
国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が合同で10月14日に記念日制定した国際デーのひとつ。
標準・・・深く切り込むと、哲学的な話題になる。
私はこの辺りの議論に慣れていないが、これから親しんでいこうと思う。
今日はジョグしてみよう。
まずは時間についてであるが、どんな高級時計でも狂いはある。つまり得られるのは、高次の絶対時間のぼんやりした影でしかない。ニュートンは運動し変化するすべてが普遍的背景のもとに運動し変化すると信じていたが、アインシュタイン以来、そんなことはないことがわかってきているが、アインシュタイン以前にも時間が絶対的ではないことはわかっている。すなわちポアンカレだ。
ポアンカレは「時間の測定」(形而上学・道徳雑誌)の中で、時間を同期するとは、人間が便利のためにした”取り決め”であって、正しいから選ばれるわけではないとしている。時間についての直接的な直感には同時性に対して解決能力はない。だから時間とは規約であって真理ではないのだ。
この同期するという問題に、物理学、哲学、測量学が交差するのである。
距離にしたって同様である。
ポアンカレはそもそも鉱山学の人であった。実際煤だらけの現場で働いてさえもいる。彼は鉱山にて使った機器類(ランプ、昇降機、通風装置)を改善しながら、数学の問題に取り組んでいたのだ。そうした視覚的で直観的な方法がポアンカレに道案内の役目をはたし、さらには非ユークリッド幾何学を用いていた。「星々はかねて定められし矩(のり)をまたがざればなり」という格言のもと微分方程式を始終考え続けた。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
今日は日本では鉄道の日でもある。
実際、鉄道と時間の問題は密接である。
フランスは、イギリスの世界的に優秀な海底ケーブル網で抜きに出ていたのを羨望の眼差しでみていた。天文台は正確でもパリの街路では恐ろしいほど不正確であった。
都市の失敗を嘆きながら、啓蒙時代のメートル法の勝利に酔い、
普遍的合理性を時間のカオス的な領域に拡張していった。
L’heure UTC, les horloges à affichage numérique, etc., représentent des aspects du progrès scientifique et technique, mais cela ne doit pas faire oublier que les fuseaux horaires, notre heure légale, le décompte des 24 heures, nous les devons essentiellement aux chemins de fer.
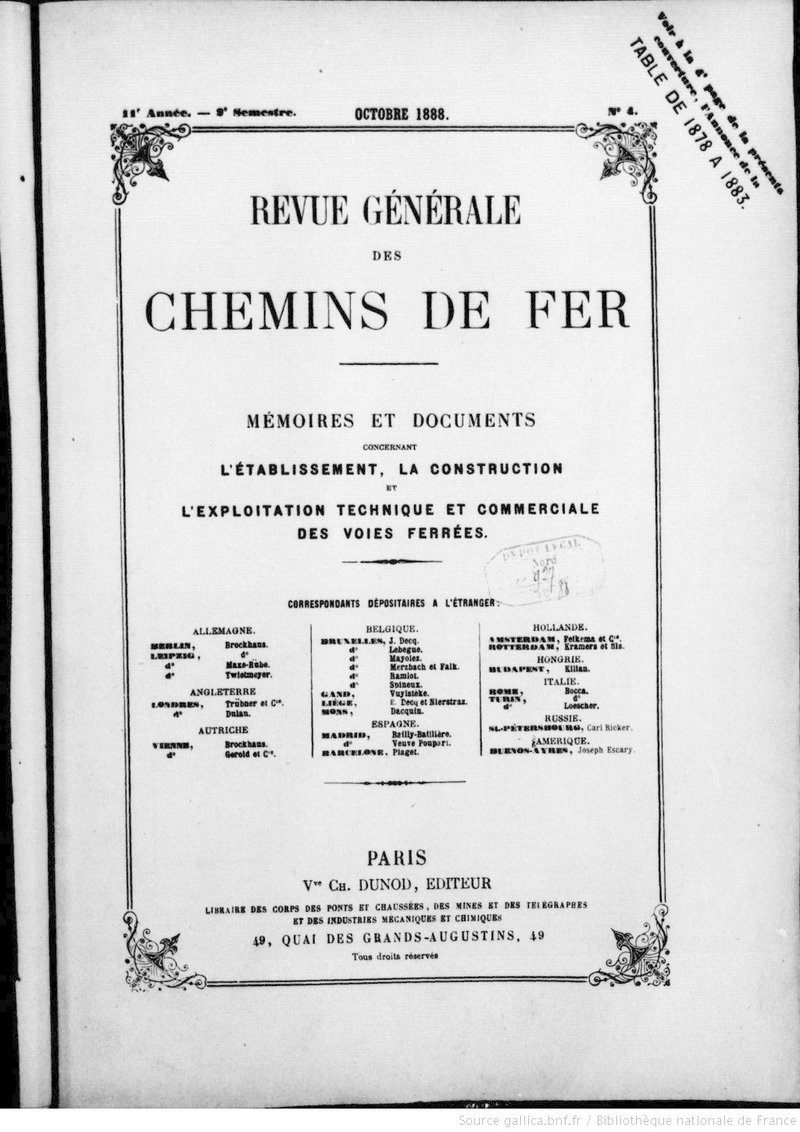
メートル法はフランスの才能の栄光ある創造物のひとつで[...]全面的な勝利を疑う人はいない。[...] ある地域の時間を、どのみち恣意的に選んでほかの地域に課し、そうして標準あるいは全国的時間を生むという思想を広めるためには、鉄道や電信による連絡の速さを必要とした。これが、かつての全国に度量衡が複数あることによる混乱のような、型は同じでも新たな種類の混乱をもたらした。
とはいえ、1884年時点のパリでは、天文台時計は、列車と市の時計を決める主たる存在というわけではまったくなかった。ポアンカレにとって、進歩と技術の目標は経度局というフランス革命以来の啓蒙科学の一大拠点で統一されていた。経度局の主な活動は、電気的に世界地図を作ることであった。
このマッピングは象徴的にも実践的にも空間に対する支配をもたらした。19世紀半ばの大かがりな土地獲得時代においては、位置を確定することは、通商、軍事、鉄道敷設にとって成否を左右することだった。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
また、ポアンカレは、時間の10進法化にも関わっていた。ポアンカレにしてみれば、時を示す1個の中に時間・分・秒という3つの単位があるという不条理を克服したかったのだ。この運動は停滞したが、経度局での彼の仕事は、哲学と物理学における時間と空間の概念を考える糸口なるには十分な議題にとりくんだということだ。
1.絶対的空間はない。認識できるのは相対運動だけである。そしてたいていの場合、力学的事実は参照できる絶対的空間があるかのように立てられている。
2.絶対時間はない。2つの期間が等しいと言うとき、その発言には何の意味もなく、規約によって意味が得られるだけである。
3.われわれは2つの期間が直接的に知る直観を持たないだけでなく、異なる2つの場所で起きる2つの事象の同時性についてさえ、直接的に知る直観も持たない。
4.ユークリッド幾何自体が言語の規約に過ぎない
非ユークリッド幾何もがよく理解できていないが
ポアンカレにとって力学は非ユークリッド幾何学で表せるとのことだ。
であれば、これをぜひとも勉強していこう。
いずれも基準を求めようとして、熟考を重ね、絶対的背景が壊れるに至るが、そこからなんとかして、定義を構築し、積み上げる作業の結果が基準ということになっているのである。
時計合わせの副産物として(副産物というには大きすぎるが)1905年の相対性理論がある。アインシュタインの独創ではあれほどの理論は打ち立てることができず、相対時間、恣意的であるといった概念を論じたポアンカレのような人物の影響を土台にしたり参考にしたりして構築したものであり、逆に、ポアンカレがもう少し長生きしていれば、相対性理論に関する議論に必ず登場した人物に違いない。
直観というものを大事にしたポアンカレ。いわば、数学を極めた人がもつ暗黙知の境地に立脚して、ものごとを考えたのであろう。その境地はいかなるものかぜひとも追体験したいと思う。世界基準は暗黙知をどう扱うのか・・・そのせめぎあいも楽しみであり、ぜひともこのNoteでいつの日か書き上げてみたい。
ポアンカレについては → 参考記事:東京の日
鉄道については → 参考記事:東海道本線開通の日
------------------------------------------------
<来年の宿題>
・ポアンカレ「科学と方法」
・鉄道の日の行事について
------------------------------------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
●見出しの画像
ポアンカレの肖像(画像はお借りした)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
