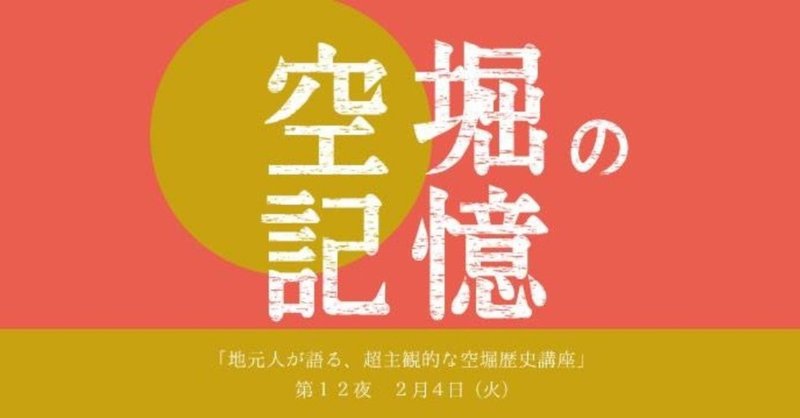
空堀の記憶~みんなの記憶 part1~
(空堀の記憶 2020/2/4 メモ その1)
これまでのまとめの意欲?を買っていただき、私が進行役として関わらせていただき、多くの方からのお話を聞く回となった。話題が尽きないので2回に分けて。
進行役をするに当たり、第11夜までのゲストや内容を振り返ってみたが、どうしても途中、思い出せない。もちろん何回か行っていない…気を取り直して、参加者の方にふせんとペンを配布して、テーブルを囲みながら、色々なお話をしてもらう。
模造紙にこれまでの「空堀の記憶」の内容を簡単に書き、過去のトピックスを頼りに少しずつ話を膨らましていく。

空堀周辺の地形と神社・お寺のお話から
空堀は、生國魂神社と高津宮の氏地が混在している。2つの神社はともに崖の上にあり、今やビルや高速道路が建っているけれど、かつては大阪市中が見渡せたそう。
2つの神社はいずれも別の場所にあったものが豊臣秀吉の命で現在の場所に移転し、今に至っている。それぞれの神社の歴史やなりたち、神社の格の違いなど、複雑な事情があるらしい。
このまちにお嫁にこらえたYさんは「同じまちなのに氏地が高津さんといくたまさん両方あるのが不思議」と仰っていたので、きっと珍しいことなのだろう。
それと、高津宮の前に「黒焼き屋」があった。黒焼き屋は大阪名物だったらしい、薬として使われるイモリの黒焼きなどが売っていたそう。
黒焼き屋の話は、高津宮ホームページの中にもちらっと出てきている
高津宮の鳥居のそばにある「梅の橋」という橋には梅川という川が流れており、道頓堀の方までずーっと流れていた。大阪は、湧水―水脈が豊かだった。地下鉄の建設で湧水が枯れてしまい、今ではごく一部しか水脈は残っていない。(東平地区の花熊さんもまだ出ているようだ)
高津宮は、「高津(たかつ)の宮の~」という歌詞で始まる大阪市歌に出てくるので、大阪のまちの人にとっての親しみある神社だったのだなぁということがわかる。
現在の大阪市歌は大正10年に制定されたもの
最も印象的なのは、やはり戦争の話
空堀の記憶に参加されるゲストの方や色々とお話してくださる方の記憶の中で印象的なのが、やはり戦争の話。
学徒動員で市電で工場に通っていたこと、大阪空襲のこと、焼夷弾の消火の話などなど。
Yさんは大阪空襲の時、間一髪逃れることができた。その後、工場に向かうため、当時暮らしていた寮のある阿倍野(松虫)から市電の通っている大正橋まで歩いたそう。(Googleマップで調べてみると約6km)
Oさんは屋根の上から遠くで光る爆弾を見ていた。
少し市電の話題が出ていたので、「地下鉄は空襲の日はどうなっていたのか?」という質問(戦前から地下鉄は難波~梅田間は通っていた)に対しては、「空襲の日も動いていたのでは?」とのお答え。ちなみに、市電は、線路が無事なところから徐々に復旧していったとのこと。
空襲の後は、ずーっと焼野原で大丸とそごうが残っていたのが見えていたそう。どちらも平成を過ぎて建替えられてしまったけれど、戦災の後に残った象徴だったんだなあと感じる。
当時の風景は私たちには写真やテレビでみたことがあるモノクロにしか見えないけれど、お二人に見える風景はきっと鮮明に残っているんだろう。
遠足の思い出
今回、色々な年代の空堀育ちの方がおられたので、それぞれの思い出とかいろいろとお話してもらった中で、口々にでてきていたのが「(大阪市立)電気科学館のプラネタリウム」の思い出。中之島にある大阪市立科学館の前身で当時は、四ツ橋にあった。日本最初のプラネタリウムがあり、大阪の自慢でもあり、大阪の子はだいたい遠足で行くところ。椅子がフカフカ(フランスベッドの椅子)で倒れていくとだんだん眠くなってくる、とみなさん笑いあっていた。1937(昭和12)年から大阪市立科学館ができる1989(平成元)年まで52年間現役だったので、幅広い年代の方の思い出に残っているようだ。
大阪市科学館のHPより
配給、お金、買い物のこと
遠足といえば、おやつ代が10円だった、100円だった。というところからお金や物価の話題へと…市電は(戦前)6銭だった。違う路線に乗り換えるときは乗り換え切符をもらう(何回乗り換えてもOK)、銭湯子ども2銭で子どものお小遣いも2銭だった。
運動会は学校の運動場が狭かったので、東大阪、花園の競技場まで行っていた(当時の運動会は、まちじゅうのお祭りのようなもの)が、その時35銭入っていた財布を落として悔しかった!
今でも覚えているんだから相当くやしかったにちがいない
配給のお米は1人1日2合7勺だった
いつもホンマに細かいところまでよぉ覚えてはるなぁと関心するけれどOさんにとっては昨日のことのような話なのだろうなといつも思う。
配給は班長が先に並び、班の分を分配する(当番制)で、お米の通帳というのもあった。
昭和24,5年頃ぐらいまで、商店街でパンを買うときは小麦粉を手に入れて、小麦粉と引き換えでパンが買えた。お砂糖はヤミでないと手に入らず、すごく高級だったとYさん。亡くなられたご主人が甘党でY家では比較的よくぜんざいを作っていたそう。「小麦粉はどこから手に入れたの?」という質問には「たぶんヤミやったかなあどうやったかなあ」というお答え。他にも、お寿司屋さんに寿司を買うときも米と引き換えだった、出産するときに産院から1日3合のお米を持ってくるよう言われた、臨海や林間、修学旅行などの宿泊ではお米持参だった、など物々交換や自給自足エピソードは尽きない。

配給のエピソードなんかは「この世界の片隅に」の話を思い出した
つづきはこちら
サポートいただけると大変うれしいです! 空堀のお店に貢献するために使いたいです。
