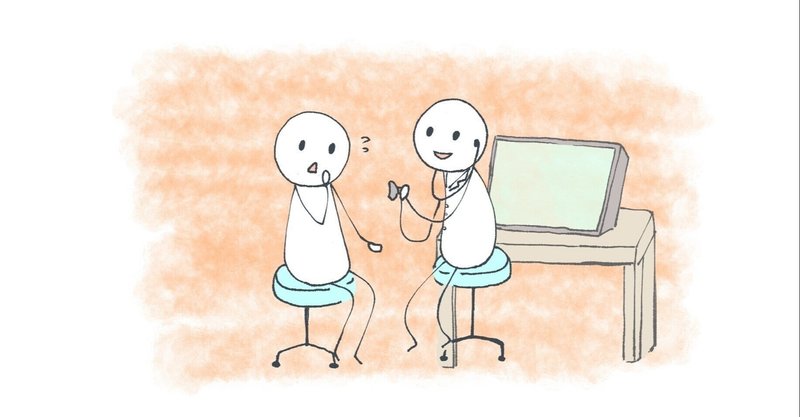
訪問看護ステーションを経験して…~リハ栄養の観点から~
明けましておめでとうございます。去年一年間は変化の年になりました。
私は、リハビリテーション病院で5年半臨床経験を積み、去年訪問看護へ転職しました。
1年間訪看を経験して感じたことは、在宅での食生活の偏りがより顕著に見られ、訪問リハビリだけの介入では生活の質を上げることは難しいと感じました。
前の職場では、NSTという栄養チームを運営し、医師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士とともに患者様の栄養管理に携わってました。低栄養という栄養状態が顕著に低下している人を対象にして行っていました。そのため、対策まで実行に移るのがスムーズでした。
訪看の場合は、ご家族様の理解ももちろんですが、最終的な決定はご本人の意向が大きく関わります。また、主治医やケアマネとの連携も必要不可欠であり、様々な意見も討論しながら実施することもありました。
リハビリテーション病院や訪看でのリハビリどちらも経験しましたが、食事を全量摂取している人の方がリハビリの進み具合が早いと感じています。年齢は関係ないように思えます。5大栄養素の一つであるタンパク質の1日に必要な摂取量は1kgあたり1gですが、高齢者はその1.5倍摂る必要があると推奨されている文献もあります。また、厚生労働省から出されている「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、高齢者のフレイル予防の観点から、総エネルギー量に占めるべきタンパク質由来エネルギー量の割合について、65歳以上の目標量の下限を13%エネルギーから15%エネルギーに引き上げられています。
このことから、リハビリを提供するにあたり身体の栄養素の土台が出来ていることがかなり重要になってくると考えています。
ダイエットで例えるなら、食べないという手段で痩せようと考えている人は必ずリバウンドしますよね?なぜなら、食べないことによりタンパク質量が必要量に満たなくなり筋肉量が低下し、一時的に痩せたように見えます。しかし、代謝量は低下を招き、痩せる前の食事量に戻した途端に体重が増えることが予測できるでしょう。このことから、食べないという選択肢は痩せる手段として正しいのか?という疑問が生まれます。答えはNOであり、身体のレシピを知らないことがこういう結果を招くのです。
最後に、、、
今回は訪看の1年間の経験についてお話しました。私は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のリハビリ業界の人たちに栄養の知識をつけた方がいいと感じています。それに加え、患者様や利用者様、そのご家族様への栄養の教育を行い、栄養の大切さを触れる機会を作ることがこの先大事になってくるのではないかと思っています。
いつも閲覧していただいて、ありがとうございます。 受け取ったものは、すべてnoteでのブログの幅を広げることに活用させていただきます。 皆様と面白いこと、貢献できることを一緒にできる日が楽しみです✨
