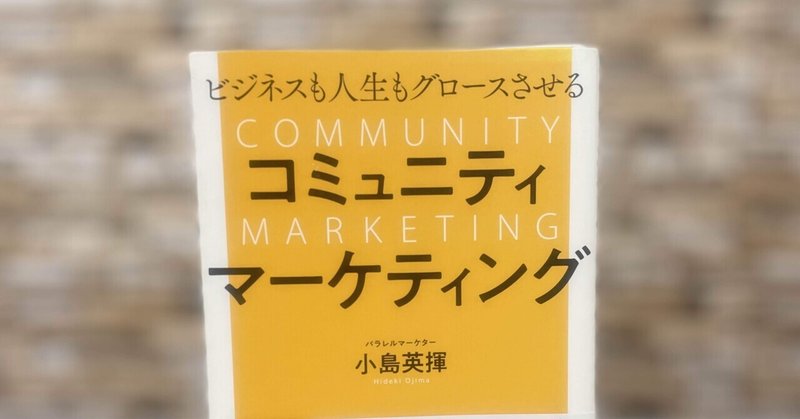
コミュニティマーケティング 小島英揮
商品やサービスのファンを巻き込んだマーケティング戦略を学べる一冊です
従来の顧客満足度アップには限界を感じる中で、顧客自身が自ら情報を発信したくなるようなコミュニティを顧客が中心となって運営までしていきます。マーケッターは巻き込まれすぎずに顧客のリーダーに伴走するようにコミュニティを育てていきます。
そんな顧客満足度アップと新規顧客獲得を達成させるコミュニティマーケティングを著者の小島英揮さんから学びます

コミュニティマーケティング 小島英揮
■第1章コミュニティマーケティングとは何か?
◯コミュニティマーケティングとは
商品やサービスを知っていて、それを気に入っていて、他の人にも広めたいと思っている「ファン」と言える人たちをコミュニティ化することによって、新たな顧客を獲得していく前略
◯マーケティングはリサーチやランキングではない
ランキングとは単なるリサーチであって、マーケティングではない。マーケティングは恋愛と同じ。好きな人がいたらその人のことを考えて、食事に誘ったり、ドライブのコースを考えたりする。相手によってオファーも変わる。これがマーケティングそのものだ
◯Sell Through The Community
人は自分のお気に入りのもの、自分が知見を持っているものについては、誰に言われるまでもなく自分から他の人たちに薦めよう、広げようとする。その人たちを通じて製品の情報が自律的に発信されて拡散していく
いいコミュニティは情報を発信していくことが自分自身のプラスになっていく、というメリットに最初から気づいている人たちが中心になる
ゆえに初期メンバーが極めて重要になる
◯マーケティングにおけるコミュニティ
マーケティングにおけるコミュニティは、集まることが目的ではありません。コンテンツの生成装置となります
⑴発信するためのハードルを下げる
20分の事例紹介+5分のライトニングトーク
⑵懇親会
勉強会後に同じ会場でお酒を飲んだり、居酒屋に行くのが通例。大事なことは、次回の事例紹介のスピーカーを探すことと、コミュニティのファシリテーターが上手な人、コミュニティのリーダー候補を探すこと
⑶情報発信
ミートアップ、勉強会後の熱量が高い状態でハッシュタグをつけて発信してもらう。イベントの終わり際に「Twitterで発信してください」「ぜひブログで書いてください」と促す
コミュニティのメンバーに情報を発信してもらうとき、気をつけていたことは、間違った情報でないかぎりは、訂正にいかないこと
◯ライブ配信で地方ユーザーも巻き込む
初期の頃は勉強会の模様を動画配信サービスの「Ustream」でライブ配信していました。次第に『自分の地元でもやりたい』という声が上がるようになった
地方への拡大、関心軸が多くなってきたら、関心軸ごとの株分けをして、それぞれが自走化するように進めることが重要です
■第2章新しい視点をもたらすコミュニティマーケティング
◯伝える相手、メッセージ、タイミングを最適化
クルマの広告は広告代理店のクリエイティブがキャッチコピーを考えますが決定するのは売り手である自動車会社のマーケティング部や宣伝部の人たちで、買う人ではありません
一方で買う人の言葉『この間、新しいエコカーに試乗したんだけど、オレが思っていたのと違っていた。走りもいいし、びっくりした』という実際のユーザーの同じ視点を持つ人の声の方が人を動かすのです
これは同じ立場の人の話は「自分ゴト」になりやすい。そしてみんなの「いいよ」という声を束ね、その声を聞く人を集める場が、マーケティングにおけるコミュニティなのです
■第3章コミュニティマーケティングを成功させるための鉄則
◯3つのファースト:オフライン・コンテキスト・アウトプット
オフラインファースト:
最初に熱量を伝えて方向づけするのは、やはりリアルな場で対面して行うのが一番だと思います
コンテキストファースト:
文脈とか背景となる事情のことで「関心軸」という。何に共感して集まっているのか、どうしたいと思って集まっているのかが重要なので、それをきちんと設定しておく
人が集まってから方向性を決めようというのはうまくいかない
アウトプットファースト:
メンバーが外の人たちに「こんなにいいものをどうして使わないの?」「これはこんなふうに使うといいよ」というアウトプットしてくれないと熱量が伝播しない。声が外向けに出ないといけない
きちんと「発信してほしい」と具体的に頼まれないと、やってほしいことはわからないもの
例えば、イベントの終了後に「今日はよかったという人、手をあげてください…上げてくれた方はぜひアウトプットしてください」とお願いをする
◯お願いをフレーズ化する
「ブログを書くまでが勉強会」というフレーズをよく使っていた
◯無理やり勧誘は危険なサイン
大切にしたいのは相手の主体的な参加を促すこと。『イベントやりますからお願いですから来てください』とは言わない
重要なことは自分ゴト化して受け止めてもらうこと。『こういう場があると良くないですか?』に対して『そうだね』と賛同してもらったうえで『じゃあ、場をつくります』という流れにする
◯ベンダー側のコミュニティの接点はシンプルに
コミュニティをマネジメントするときの顔は、1人のほうがいい。それをできるだけ固定すること
コミュニティのマネジメントは何人かで分業することもありますが、あくまでインターフェースは1人または少人数にすることが大切です
◯コミュニティマーケティングに必要な3つの要素
⑴マーケッターであること
コミュニティづくりはマーケティングの一環であると理解すること。コミュニティに取り込まれないこと
⑵人に好かれる人であること
たくさんの人とリレーションを持っていく役割には大切な要素
⑶社内営業ができること(要約)
会社に説明したり、必要なリソースを要求したりする交渉力、会社に対して言いたいことが言える力
◯フォロワーがリーダーをつくる
コミュニティはリーダーだけを見つけても仕方なく、どうやったらフォロワーが集まるようになるかが重要
・積極的に人を巻き込みたい人
・いいものがあったらどんどん真似したい人
最初から両方のタイプを探して、それをセットにしてファーストピンを構成すること
◯コミュニティづくりに役立つ「焚き火理論」
コミュニティづくりにおいて数を追いかけると不完全燃焼が起こるり、それでは焚き火は成長しない
種火に点火したら、その次は枯れ枝などの燃えやすいものをいれないといけない
→これを「焚き火理論」と呼ぶ
◯コミュニティのゴールを途中で変えない
最初に決めたコミュニティの目的を変えないこと。他の話をするのであれば、名前や場所を変えてやってもらう
『ここは“そういう場”なのだ』という共通理解をみんなに持ってもらう
◯焚き火理論のピラミッド構成
焚き火理論になぞらえてコミュニティを
リーダー(種火)
フォロワー(枯れ枝)
ワナビーズ(生木)
のピラミッドで示す
この基本形から細分化された(地方展開、他目的展開)によって分かれた小さなピラミッドが4つ、5つと増えたそれぞれが大きくなると、全部を足した時にとても大きくなる
◯コミュニティリーダーは新陳代謝が必要
コミュニティリーダーはできれば3人がいい
ワンオペは避ける
リーダーについて大事なことは新陳代謝です。外的要因で参加できなくなったり、リーダーとしての熱量をずっと持続させるのは、なかなか簡単なことではありません。そこで新しいリーダーにどんどん変わってもらいましょう、という普通の文化のようにしておく
■第4章コミュニティマーケティングの実践ケーススタディ
◯LTVが重要な商材
サプリクションビジネスは長く使ってもらうことでお客様の数が積み上がり、ビジネスがスケールしていく。重要な指標になるのが「チャーンレート(解約率)」をどれくらい低く抑えられるか
ファンが集まるコミュニティを作用させることで「うまく使えている人」の話を聞くことができる。これにより解約を防ぐことができる
◯いいフィードバックグループをつくることができる商材
お客様に商品やサービスを使い続けてもらうためには、改善ポイントをお客様からいただくことです。「こうしてくれたら、もっと使う」と言ってもらえる
フィードバックを聞きたくない、という人や会社にある大きなバイアスの一つは『聞いてしまったらすぐに対応しなければならない』という思い込み
まずはきちんと聞いて、それに対応してコミュニケーションしている姿勢が重要。10の要素が出てきて、2つか3つ対応できただけでも『2つも対応してくれた』となる
■第5章コミュニティマーケティングは人生もグロースさせる
◯パラレルキャリアをどうやって実現したか
私がAWSを辞める時にイメージしていたのは、いわば「流しのCMO」でした。いろいほな会社のマーケティング戦略策定に関わったり、マーケティングチームをマネジメントするイメージ
どの企業にも等しく時間を割き、自分自身が実行者となっていくモデルだと、何社も並行して仕事をするのには無理があります
パラレルキャリア先をセグメントして設定する
・代走 プラン+実行主体
・伴走 プラン+実行管理
・コーチ プラン+実行へのアドバイス
代走する請負う企業は少数に絞り、主に伴走とコーチの割合を増やすことで同時に複数企業と仕事を進められるようになった
◯新しい分野でキャリアを築きたい
AWS時代より年収が下がるというのは選択肢として家庭に対して負荷がかかるが、パラレルキャリアは有利に働ける
1社で同じ給与を払える企業というのは難しい。しかし、複数企業にシェアしてもらう形なら実現の可能性が高くなる
実際、『コミュニティマーケティングについて教えてください』という話がたくさん舞い込んできた
最初はいろんな会社にお話に伺ったが『参考になりました』『勉強になりました』と言われるだけでなく、『言う通りやってまたらこうなりました』というフィードバックが欲しくなった
教える一方=知識を消費するだけの立場から、私自身のインプットにもつながる。そのためにまずは話を聞きたがっている人を束ねてみたらいいのではないか、と思った。コミュニティマーケティングに関心のある人を集めて、コミュニティを作ってしまう。そこで小さなコミュニティが大きくなる様子を全員に体感してもらおうと考えた。実際に体験することで「自分ゴト化」できれば、コミュニティマーケティングをもっと信用して、実践してもらえると思った
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
