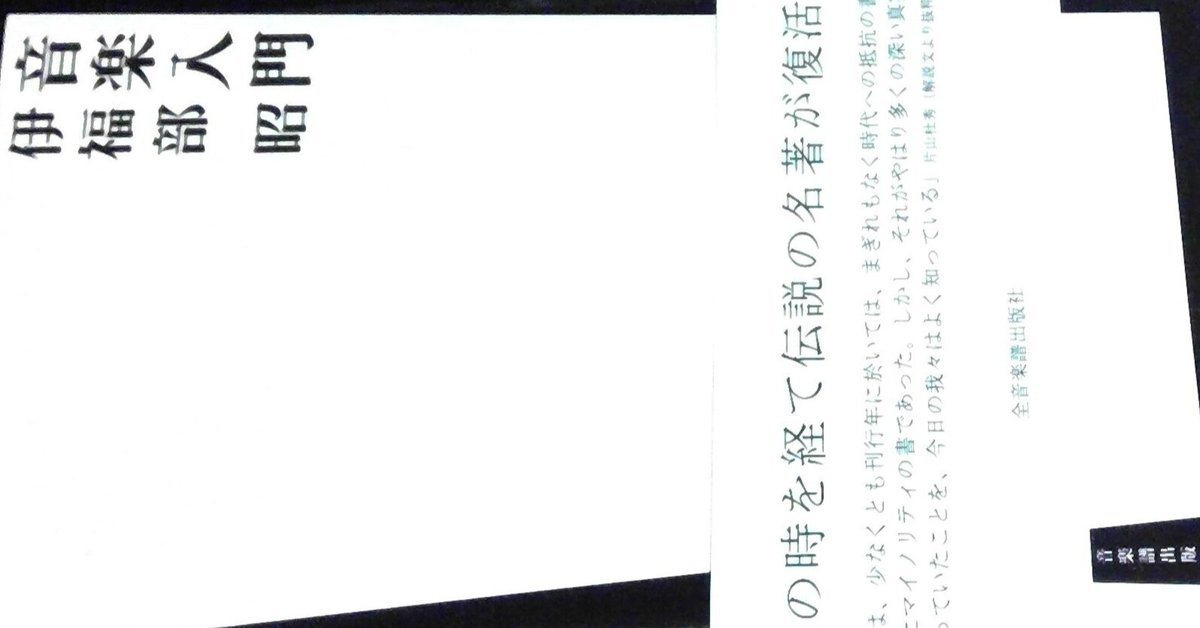
伊福部昭の『音楽入門』を読む
記事の概要
伊福部昭を端的に紹介するとゴジラのあの曲を作曲した人で、クラシックの分野の作曲家です。その伊福部が一般向けに著した『音楽入門』 (1951)という本の内容を紹介しつつ、現代のリスナーとしての立場からいくらか余計なことを付け加えるのがこの記事です(その付け足しについては小見出しに*を付けることで区別しますのでお前の語りに興味はないという人は読み飛ばすことができます)。
*『音楽入門』は何が特殊で面白いか
『音楽入門』は副題に「音楽鑑賞の立場」と記されています。作曲家が音楽作品の方ではなく"鑑賞"に目を向けて論じた本というところが特殊な点の一つです。もう一つは記載されている内容が大変に opinionated であることです。
作曲家が一般向けに著した本としては、例えば伊福部が指導した一人である芥川也寸志の『音楽の基礎』 (1971)という本がありますが、ここに書かれていることはいわゆる楽典的な内容で、数ページに一度くらいは楽譜が登場し、おそらく楽典としては現在でも修正する必要はないような普遍的な内容で、かつ平易に書かれていますが、芥川の思想のようなものはあまり出ていません。
対照的に『音楽入門』には楽譜は一つも出てこず、代わりに伊福部のオピニオンに満ちています。そしてその内容に普遍性があるかというとかなり疑問がある。伊福部は自説を補強するための学術的根拠をいくつも引き、それは彼の博学ぶりを示すものですが、現代から見てそれらの引用にどの程度の学問的強度が残っているかは怪しい。その主張も彼が想定敵とした時代状況に依存していますし、言及している音楽ジャンルについても狭い(彼の関心は「純粋音楽」であって、当時や現代のポピュラー音楽——伊福部の時代の言葉では「軽音楽」——は対象から外れるでしょう)。
しかし伊福部の言葉は読むものに洞察を与えるという点については抜群に秀でており、その点において現代の音楽リスナーにとっても得るものがあります。また、音楽自体が時代とともにが多様化・複雑化するのに対して「純真な、初心な鑑賞者」(序)は新しく生まれ続けるわけなので、その点でも意義を失っていないでしょう。
「はしがき」
はしがきにおいて伊福部は鑑賞において解説・権威・定評に依ることの弊害についてこんな挿話を引いて述べています。
国立博物館が一般に開放されて間もないころのことですが、教師に引率された中学生たちが熱心に見学しておりました。生徒たちは、ちょうど新聞記者のように忙しそうに、陳列品に付されている解説や、先生の説明をノートしておりました。しかし、生徒たちは、誰一人として肝心な陳列品そのものを見つめてはいませんでした。
この出来事は極めて些細なことのようですが、少なくとも次の二つの事柄を含んでいると思います。一つは、何かある作品に接した場合、作品そのものからくる直接的な感動とか、または、印象などよりも、その作品に関する第二義的な、いわば知識といわれるもののほうをより重要だと考えることです。更にいえば、枝葉的な知識とか解説なしには、本当の鑑賞はあり得ないと考えることです。他の一つは、たとえ、自分がある作品から直接に強烈な印象なり感動を受けたとしましても、これを決して最終的な価値判断の尺度とすることはなく、より権威があると考えられる他人の意見、いわば定評に頼ろうとする態度です。
このような態度が無自覚に長く続けられると、終には、一つの思考上の習慣となるのです。
大分長く引用しましたが、伊福部の態度の第一の要点は概ねこのはしがきに含まれています。ただしこれはナイーブな感性至上主義というものでもなく、こうも述べています。
もちろん、正しい思考と、長い訓練によってのみ、はじめて感得し得るような種類の美がありますが、まず、第一に裸になって、自分の尺度を主とするところから始めなくては、決してそのような高い美しさを感得し得るようにはなり得ないということを述べたいのです。
* 音楽と権威と定評
上に引用した事例は展示の鑑賞に関するもので、これは現代の感覚でもよくわかる感じがしますが、音楽についてはどうか?
【第1章】美術館へ行くたびに思うことがある(1/10)
— 新月ゆき (@Shingetsu_yuki) December 20, 2023
「私は作品を見に来たのかな?解説を読みに来たのかな?」#pr pic.twitter.com/hRD9nZOBdG
権威について、巻末解説(片山杜秀)には伊福部と同時代に影響をふるった小林秀雄(『モオツアルト』)の名が出てきますが、現代に小林秀雄級の影響力と権威と文章の巧みさをもった(音楽)評論家はいないでしょう。少し遡ると専門誌の編集長をやっていたような人はまあ権威だったのかもしれないが、特定のジャンルに限っても2023年まで強大な影響力を保ち続けている個人はもういなくなったと思います。加えて、とっつきにくいと見做された音楽についての文章をわざわざ読んでくれる初心者も殆どいないでしょう。
一方で、「定評」に頼り、"音楽そのものというよりは知識を消費している"というような態度が、SNSの発達によりむしろ音楽フリークの間に見られるようになった印象があります。誰が何を聴いているかという情報の横溢により多くの「定評」が容易に、半ば自動的に入るようになり、それにより「あの人もあの人もあれを聴いている」ということを気にし、「よいとされる音楽を広く聴いている」ことに何か義務感を感じ、なるべく早くサブスクの新着に目を通し、年間ベストで答え合わせをするというような。いわば現代の権威は分散された形でSNS上に存在します。こうした音楽鑑賞の態度は「裸になって、自分の尺度を主とする」ところから遠ざかっていくような実感が何となくあるんですよね。
「音楽と連想」
伊福部の思想を伝えるものとして次に重要なのは第二章「音楽と連想」です。ここでは音楽を理解するとはどういうことかについて語っているためです。まず伊福部は音を聴いた時に生ずる印象を「直接的なもの」と「連想」に分けています。
音響というものは、私たちがこれを聴いた場合、私たちの中にある特定の感覚とか心情をよび起こすものですが、この心情には二つの種類があります。一つは、その音響それ自体がもつ直接的なものであり、いま一つは、その音に付随した連想に基づく印象です。このように私たちが一つの音を聴いた時、自分の中に生まれた印象が、直接的なものなのか、また連想によるものか、それとも両者の結合されたものであるのかということを見極めることはかなり困難ですが、このことは音楽を鑑賞する態度の上で重要な因子となるものなのです。
想像はつくと思いますが、伊福部は「連想」を「音楽の実体から逃れ」 (p.32)るものとして退け、「直接的なもの」を重視します。そして「勝手な幻想を持つ態度が真の高級な音楽の鑑賞であるかのよう」に思われていると指摘します。
このことは、現在行われている音楽作品の解説を一見しても、明らかなことです。解説はいかにして多くの連想や幻想を起こさしめる材料を提供するかということに、主眼が置かれているかのようです。
私たちは、しばしば「この音楽はわからない」という言葉に接しますが、その場合ほとんどすべての人は、自分の中に、その音楽にぴったり合うような心象を描き得ないという意味のことを訴えるのです。この心象は、その人によって異なり、哲学、宗教、文学といったものから視覚的なもの、とにかく、音楽ならざる一切のものが含まれております。
もし、そうだとするならば、その人たちが音楽を理解し得たと考えた場合は、実は音楽の本来の鑑賞からは、極めて遠いところにいることになり、理解し得ないと感じた場合、逆説のようではありますが、はじめて真の理解に達し得る立場に立っていることになるのです。
伊福部はそのような表現はしていませんが、彼が批判しているのは大体次のようなスキームを音楽鑑賞と捉える態度であるといえるでしょう。

こう書くと作曲者も作品に題名をつけることがあるではないかと思いますが、それについても伊福部は一つ後の章で釘を刺しています。
作品に付されている題名は、作家が単に自分の霊感の活動を容易にする目的のために選んだ一つの方便に過ぎないのであって、決して素材でもなく、またその題名に関して想像を逞しくしてほしいという意味でもないのです。
伊福部の主張を聞いてもう一つ思うことがあるとすれば、「直接的なもの」は音響でしかないが、それ以外の連想が余計だとしたら、鑑賞者は音楽を聴いた印象をどう言葉にすればいいのか?ということだと思います。
私たちは音楽の印象を述べる場合、適当な表現法が見つからないので、他の連想的な言葉を借用しています。これ以外に今のところ適当な方法がないのです。強弱高低の音響語や、感情語は仕方ないとしても、黄色い声とか明るい音楽というような視覚、甘いという味覚、柔らかいという触覚、冷たいという温度感覚、香り高いという嗅覚などのすべての感覚語を濫用し、それらはあまりに数多く、ほとんど枚挙に暇ないのですが、これらの感覚語のみで表せなくなると、風景とか情景とか、または宗教とか哲学、文学、詩、なんでも引き合いに出してくるのです。
このような表現法にのみ触れているうちに、連想的な鑑賞態度に傾くことになるのではないか、とも思われます。
要するに伊福部は鑑賞の態度については関心があるが、それを言葉にする技芸には比較的冷淡で、連想的な言葉以外に「今のところ適当な方法がない」が、「このような表現方法のみに触れる」のは気をつけろということだけ述べています。言語化したい人にとっての答えはここには書かれていないということになります。
* 連想的に鑑賞することについて
この本での伊福部の関心がクラシックの領域の、特に「純粋音楽」に偏っていることを改めて注意しておきたいと思いますが、私はさほどクラシックの熱心なリスナーでないので、ここではポピュラー音楽の領域で「わからない」と言われがちな双璧として、インプロ系の音楽とアンビエントについて述べようと思います。
ここでインプロ系の音楽というのは楽曲のテーマの間に独奏者の即興演奏が入るものという意味ではなく(それは非常に多くのポピュラー音楽にある)、あらかじめ決まった曲というものがなくて、大抵の場合なんだか訳のわからない音を40分くらい出して終わる、みたいなやつのことです。
伊福部がこれを好みそうかといえば多分違うでしょうが、彼の主張に照らしてみたときに、この種の演奏の良いところは、まず一切題名がついていない点です。少なくとも私はこれ系を聴きに行って「今から『嵐の夜』という演奏をやります」みたいなことを聞いたことはありません。美術系のパフォーマンスアートの人だったら訳の分からないことをやりつつも、うっかりそれに題名をつけてしまい、オーディエンスに題名について考えさせてしまうかもしれないのですが、インプロ系にはそういう慣習がない(録音物になるときは題名がついているかもしれないが)。もう一つはその音響に「連想」の余地が殆どないことです。最大公約数を取ると「なんか☆△🌈っていってた」みたいな感じです。
したがってインプロ系の音楽はある意味良心的です。「わからない」と思ったときに、一旦はその分からない地点に留まらせてくれるためです。「わかんなかったけど解説してもらったら分かった」ということは多分起こらない。
アンビエントミュージックについても音響として「なんか☆△🌈っていってた」なのはある意味変わらないのですが(しかし不思議と面白いのとつまんないのとはちゃんとあるんですよ)少し違う。まず演奏の機会で触れるよりは録音物で触れる機会のほうが多いので何かしら題名がついているという点が違います。ただし、これは大抵後付けで名前を付けただけだろうと思います。もう一つは、これは最近分かったのですが、皆アンビエントを聴きながら結構思い思いに連想をしているらしい。
死後の世界見た
幽霊がいっぱい出てきてすごかった!原理としてではなく、イメージとしての乱反射する音。あるいは木漏れ日のような音。
2001年宇宙の旅 分厚い星雲みたいな音響
溶解しゆらめく幽玄夢幻の音。死者のざわめき。「死は生の対極としてではなく、その一部として存在している」村上春樹のあの有名な小説の一節のように、いずれ直面する身近な「死」の世界を感じた
天国の音を浴びているよう
海なのか空なのか、畝りながら昇る姿が見えた 人魚や龍の鱗が艶々と光っていた
永遠みたいな夕日の光
「戦争」を感じた瞬間があった。
これらは最近私も行ったあるアンビエントのライブのSNS上での感想を検索したら出て来た言葉の一部なんですが、みんなあまりに詩人なので、こんな気の利いたこと言えない自分がちょっと恥ずかしくなってしまった。これらから分かるのは、かなり抽象的な部類の音楽を聴いた場合でもそれを音以外の概念に対応させて形容するのは伊福部の時代からあまり変わってなさそうだということでしょうか。
「現代生活と音楽」
間をかなり飛ばして第十章の内容では、現代でも共感されそうなこと、「レコード、ラジオ、映画、テレビ等によって、強制的に私たちの心境とはなんら関係のない音楽が、暴力的に私たちに朝から晩まで降りかかってくる」 (p.139)ことについて嘆いています。
このように音楽を聴き流すように慣習づけられた私たちが、今度は逆に、何か音楽作品を聴こうとする場合には、反作用として、耳に聞こえてくる音響美の外に、何かいつもとは違った意味を音楽からくみ取ろうとする方向に傾くのです。単に音楽が見事に構成されていると感ずるのみでは鑑賞とは考えられず、哲学的思索とか、文学的連想とかを無理に作り出すことに努力し、終に、さきに述べた音楽の鑑賞から遠のいていく結果を生むのです。
ではどうしたらいいか。
これを救うには、暴論のようではありますが、第一に、あまりに多い音楽から逃れることです。選ばれた作品を時々聴く方が毎日音を聴くよりも音楽について知ることができるかも知れません。老子は既に二千年の昔「五音令人耳聾」(五音ハ耳ヲシテ聾セシム)と述べているのです。
ここにいう五音とは音楽のことで、あまり音楽、音楽とこれに執着、惑溺すると、かえって、真の音楽がわからなくなるという意です。
これはなかなか沁みますね。
* 「家具の音楽」の失敗について
本筋とはやや離れるのですが、この章には挿話としてかの有名なサティの「家具の音楽」の話が出てきます。
かつて、エリック・サティは、音楽があまり人々の注意を惹かずに、ただ何となく聴こえている程度のものであることも面白いという見解から「家具の音楽」という作品を書き、広い室の方々に演奏者が散らばって、室の内の客人がそれぞれの話の興に乗った頃合を見て、ごく目立たないように弱く演奏を始めるという計画を立て、これを実験したことがありますが、この天才の音楽は、どのように弱い音で演奏しても、その結果は、客人の話を止めさせるほどに印象的であったのです。この妙な、彼の計画は完全に失敗したのです。すなわち音楽は飽くまで音楽であって、終に、家具にはなれなかったのでした。
この話はアンビエントリスナーとしてはとても面白い。「アンビエント」という言葉は最近ではビートの希薄な電子音楽全般を指すように使われており(ということにも最近気づいた)、ビートさえ希薄であれば「アンビエントジャズ」「アンビエントR&B」など(個人的にちょっといらいらさせられる)のようにも使われますが、元々はブライアン・イーノが提唱した、環境音楽を指す、かなりコンセプチュアルな言葉です。そして「家具の音楽」のコンセプトは、いまでもアンビエントについての本や雑誌特集が編まれるときにはイーノの言葉とともに書き写され続ける、いわば「アンビエントのドグマ」の一つなんですが、個人的にはどちらも「もういいんじゃない?」と思っていて、何故かというといまアンビエントと分類される音楽を聴くにあたってそれらのコンセプトが鑑賞をガイドするように働くことが全くないように思えるからです。
だから「家具の音楽」がその始まりにおいて失敗していたという話は個人的にちょっと愉快です。惜しむらくは伊福部がこの挿話の出典をきちんと挙げていないことです。
* 結語
『音楽入門』についての雑な紹介と雑な付け足しは以上です。引用のページ番号は全音楽譜出版社の再版によっています。近年になっておそらく『シンゴジラ』の公開に合わせた時期に角川ソフィア文庫にも入っていて、そちらには全音版にはないインタビューも入っているようなので何か面白い話が載っていたら教えてください。
この記事で紹介した部分以外でも伊福部の書くことで面白い部分はいくらもあります。「シュトラウスの作品(引用者註:『ツァラトゥストラはかく語れり』)は題名だけが意味ありげで、内容は口にするのも腹立たしい」 (p.46)とか、「街は、感傷と虚無と肉感しかない流行歌とジャズに支配され」 (p.136)とか。あと「あとがき」の書き出しが面白い。私はあとがきが面白いというきっかけでこの本を知りました。
なおこの記事で伊福部の考えをオピニオンと呼んだのはそれがどんな音楽にも通用する考えだとは思っておらず、異なる音楽は異なる基準で鑑賞される権利があると考えるためです。あしからず。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
