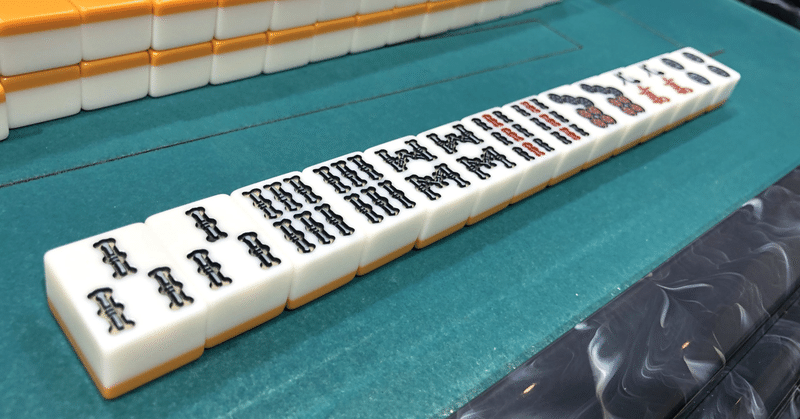
[cakes]麻雀千年紀
cakesに載せていた記事です。大学の寮で自分たちが作った変なルールの麻雀ばかりやっていた頃の話。
(2014年1月1日)
2000年1月1日、新しい千年紀が始まった日、僕は当時住んでいたK大学K寮でいつもと同じように麻雀を打っていた。
当時僕は22歳の大学生で、勉強もしたくないけど就職もしたくないし、将来が全く見えなくて、学校にもろくに行かず寮にひきこもって、現実逃避的に毎日麻雀ばかりしていた。麻雀の卓を囲んでいる時だけは現実の面倒臭いことを全て忘れていられた。
その日も正月だからといって特に新年ぽいことをするでもなく、唯一年末年始を感じさせるのは寮生の多くが実家に帰省してしまって麻雀の面子が集まりにくいということだけで、いつもと同じように、ボロボロに古びたコンクリートの建物の中で隙間風に震えながら、唯一の暖房器具であるこたつに4人で足を突っ込んで、冷たい指先でただひたすらに麻雀牌をかき混ぜていた。
「せっかくミレニアムなんだから、ちょっと別のルールでやらないか」と僕は言った。
他の3人が、こいつは何を言ってるんだ、という顔で僕を見た。
「リーチするときって1000点棒を出すじゃん。それを2000点出してリーチしたら『ミレニアムリーチ』ってことで普通は1飜のリーチが2飜つくことにしようぜ」
みんな普通の麻雀に飽きていたので、やろうやろう、ということでこのミレニアムリーチが導入されることになった。
だけどこのミレニアムリーチ、2000点のコストで役の強さが倍になるというのはちょっと安価で強力過ぎた。必然、みんな普通のリーチをせずに、「ミレリー」ばかりが卓上に飛び交うようになった。
「これゲームバランス悪くないっすか」と後輩のYが言った。「普通のリーチする気がしないっす。クソゲーなのでは」
確かに、と僕は考えこんだ。ミレリーが強力すぎるのならもうちょっと弱めたほうがいい。でも、役の強さを2飜から下げると1飜のノーマルリーチと同じ強さになってしまうから弱めようがないし、コストを上げるなら供託する点数を上げるのが一番簡単だけど、2000点じゃないとミレニアムの意味がなくなってしまう。どうしたものだろうか。
「じゃあこうしよう」と僕は言った。
「ミレリーは今まで通りに2飜。だけど、ミレリーでアガったときは、サイコロを2個振るようにする。それで、ゾロ目が出なかったら普通に点数が貰える。でももしゾロ目が出たら……」
「出たら?」
「コンピュータが『誤作動』してアガった点数を逆に相手に払わなければいけないようにしよう」
「コンピュータって何すか」
「まあそういうものがあるということにしようや」
当時、「2000年問題」でコンピュータが誤作動して世界中でいろんな問題が起こるということがニュースになっていたのだ。
「しかも1のゾロ目か6のゾロ目が出たら『大誤作動』ということで2倍の点数を払わないといけないことにしよう」
サイコロを二つ振ってゾロ目が出る確率は6分の1。1か6のゾロ目が出て「大誤作動」する確率は18分の1。
これでちょうどよくバランスが取れていたのかは分からないけど、「サイコロを振る」という行為はシンプルだけどなかなか盛りあがった。
結果、リスクを顧みずにミレリーに突入する勇者が続出して、
「ミレリー!」
「ロン、サイコロ振ります! うわっ、誤作動した! 飛び!」
などという白熱した闘牌が行われた。
【ミレニアムリーチ】
●千点棒を2本出して「ミレニアム」と発声する。他は普通のリーチと同じ。強さは2飜。
●アガったときはサイコロを二つ振る。ゾロ目が出ると「誤作動」が起こり、アガった点数を相手に払わないといけない。1のゾロ目か6のゾロ目が出たら「大誤作動」ということで2倍の点数を払わないといけない。
「Yは帰省とかしないの?」と配牌を取りながら僕は後輩に聞いた。
「はい、正月は帰らないんですけど、でも成人式があるので来週帰る予定です」
「成人式だと!」とS先輩が顔色を変えた。
「成人式ということは、あの麻雀をやらんといかんじゃないか。こんなミレニアムなんてわけの分からん麻雀をやってる場合じゃない」
「え……なんですか……」
「二十歳の献血というルールを知らんかね」
「知りません……」
「知らないなら教えてあげよう」
【二十歳の献血ルール】
●二十歳になったらもう大人、献血をしてちゃんと社会に貢献しようね、というこじつけから来た超インフレルール。
●麻雀牌には赤い部分がある牌が20種類あるが、これを全部ドラにする(萬子の一から九、索子の一・五・七・九、筒子の一・三・五・六・七・九、あと中)。
●すぐに数え役満になるので、13飜を越えた分からは1飜ごとにチップを一枚貰える。
●もともとは坂本タクマの『ぶんぶんレジデンス』という麻雀漫画に出てきたルール。大学の寮でひたすら麻雀を打ってるという漫画で、二十歳の献血以外にも変なルールが多数登場する。
「おお! それはアツいですね!」とYは乗り気になっている。僕は「二十歳の献血」はちょっと単純なインフレルールすぎてそんなに好きじゃないんだけど、まあたまにはいいかもしれない。
「じゃあやろうか」
「やりましょう」
ジャラジャラジャラ。ひたすら牌をかき混ぜる音だけが人の少ない寮内に響いて行く。 そうやって2000年の正月もいつも通りに更けていった。
* * *
あの頃はそんな風に寮の中で麻雀の変なルールがたくさん生まれては消えていった。あれは今思うと面白い環境だったと思う。
みんな学生で時間に余裕があって、しかも学校をサボる寮生が多くて、やることのないやつが4人集まったらとりあえず麻雀だろ、って感じでみんなひたすら麻雀ばかりしていた。でもそんなに麻雀ばっかりやってるとだんだん普通の麻雀に飽きてきて、それでいろいろと変なルールをひねり出すことになる。
今だったら、昔麻雀をやってたようなゲーム好きは、カタンだとかドミニオンだとかのアナログゲーム、いわゆるボドゲとか、ポーカー(テキサスホールデム)なんかをやってる人も多いのかもしれない。でも2000年くらいの頃はまだそんなにボードゲームは流行ってなくて、多分麻雀が一番メジャーなアナログゲームだった。だからみんなひたすら麻雀ばかりやっていた。
あと麻雀は将棋などのゲームと違って運の要素とかランダムな要素が入るから、新しいルールを雑に付け加えても変更部分がランダムさに吸収されて極端にバランスが崩れにくい。だから新ルールを付け加えるのが他のゲームに比べて比較的楽だ。
実際に麻雀のルールは場所によっていろいろ違いがあるものだし(「麻雀のローカル役 - WiKipedia」などを見てると楽しい)、現在一般的に遊ばれているルールもいろいろ後から付け足されたつぎはぎ感があるものだ。また、極端に変則的な麻雀は麻雀漫画でよく登場したりもする(「アカギ」の「牌がガラス製で透けて見える鷲巣麻雀」とか)。だから麻雀のルールを変えるのは他のゲームよりも馴染みやすいという背景もあったのだろう。
変なルールが誰かの思い付きで誕生しては、すぐに飽きられて「やっぱ普通の麻雀が一番面白いよな」とか言われたりして消えていくこともあれば、「これは面白い」とそのまま遊び続けられて定着することもあった。「ミレニアムリーチ」は一時的には盛りあがったけど、元が時事ネタだということもあってそんなに長くは遊ばれなかった記憶がある。
当時寮生の間に定着して数年以上のスパンで遊ばれているルールとしては、白がオールマイティー牌として使える三人麻雀の「白マイティ」とか、東家が四枚一度にツモって全員が一斉に牌を切る「こってり」という超変則麻雀なんかがあったんだけど、そのへんの説明を書いていたら超長くなった上に麻雀知らない人にはわけがわからないだろうのでこのページの下の方で補足として説明しました。ルールの詳細に興味のある方だけどうぞ。
「時間が余っているゲーム好きの若い人間が一つの場所に集められてひたすら一つのゲームを遊び続ける」という当時の寮の環境は、新しい麻雀のルールを生み出すには最高の環境だった。それが何の役に立つんだって言われると答えにくいけど……。「何か新しいアイデアを産み出すためには過剰で過密なコミュニケーションが必要だ」みたいな話の実証にはなっていたんじゃないかと思う。外界から遮断された環境に人間がたくさん放り込まれて過密なコミュニケーションを続けていくと、その中では他では見られないような独特の文化が発達する。そんな環境から新しいオリジナルなものが生まれてくるというのはよくあることだ。
あと、ゲームって別にお金を出して買わなくても自分たちで新しく作ったりもできるんだ、ということを知ったのも良い経験だった。それはゲームに限ったことではなく、生活に必要なものはわりと何でもちょっとした工夫で作れるし、自分たちでものを作るのは楽しいことだし。
僕があの麻雀漬けの寮生活から学んだのは、「遊び相手とちょっとしたアイデアさえあれば、お金がなくてもいくらでも工夫して楽しめる」ということかもしれない。結局35歳の今でもそんな感じで、インターネットで適当な仲間を集めて知らない人が聞いたら全く意味が分からないような単語でチャットをしながら、毎日うだうだと暮らしている。
* * *
そんな麻雀漬けの生活を送っていた日々も、もう10年以上前の昔のことになるのか。
その後僕は何とか大学を卒業して寮を出た。寮を出るとほとんど麻雀も打たなくなった。最近は2年に1回程度、たまに誘われて打つくらいだろうか。
寮にいた頃の、毎日ふらふらになるまでひたすら麻雀を打ち続けて、夜が白む頃にみんなで連れ立って近所のなか卯に牛丼を食べに行って、おなかがふくれたら倒れこむように眠って、夕方に目が覚ますとまた当然のように麻雀の卓が立っているので参加するという、そんな日々を懐かしく思う。
久しぶりに「白マイティ」や「こってり」を打ってみたい気もするけど、今さらという感じもする。あれをわざわざ雀荘とかに集まって打つというのもなんかちょっと違う。あれはあの時あの雰囲気で、ボロボロの廃墟のような寮で、大学生という社会人から見ると気楽な身分に見えるかもしれないけど主観的には人生をどう進んでいけばいいか全く先行きが見えなくて不安で仕方ない状況で、閉塞感と焦りを抱え込みながら仲間と集まって打っていたからあんなに楽しかったんだろう。
今はたまに麻雀を打っても当時みたいに全てを放り投げて一日中打ち続けたりできない。体力がないのもあるし、もっと他にもすることいろいろあるよな、って思ってしまう。もうあんなに夢中になって一つのゲームに没入することはないんだろうと思うと少し寂しくもある。
(了)
K大学K寮麻雀ローカルルール(2000年当時)
【白マイティ】
当時継続的にずっと遊んでいたのは「白マイティ」と呼ばれる変則ルールだった。これは「白(何も書いてない牌)」が、「何も書いてないんだったら何にでもなれるだろ」という雑な発想で、トランプでいうジョーカーのように何の牌としても使えるオールマイティーの牌として使えるというルールだった。確か半分くらいは僕が考え出したルールだ。
●四人ではなく三人で打つ三麻
・二萬から八萬までは使わない。北は抜きドラ扱い。
●白はオールマイティーとして使える
・白を1枚持ってると「二五索と四七筒の四面待ち」みたいな待ちができる。
・白を2枚以上持ってるとかなり無敵感がある。
●基本的に白を持ってる人が圧倒的に有利。白を使わないでアガると「リアル」と呼ばれて尊敬されて、チップが2枚貰える。他にも一発・赤・裏などでチップが乗る。
●白を手に入れにくいため、小三元は役満扱い、大三元はトリプル役満扱い。
●白を捨て牌として切ると「白フラッシュ」と呼ばれる現象が発生して、白から強烈な光が発生して自分以外の人間は目潰し状態になり、「見えない見えない」と言いながらその後二巡のツモを強制的にツモ切りしなければならない。
・白は手牌として攻めに使うだけでなく振り込まないための守りとしても使えるという意味のルール。
●ただし、白単騎、白シャボで待っている場合はフラッシュとして切られた白をロンすることができる。この場合「フラッシュ返し」と言って得点が倍になる。
●白単騎、白シャボでのテンパイは現物以外は何でも当たれる。というか本当は前のツモの時点でアガっているが、リーチ一発狙いや特定の相手を飛ばすためなどにあえて白で待つことがある。「何でも単騎」略して「でもたん」と呼ばれる。
●他にも「箱リーチ」「付加カン」「鬼将軍」など細かい変則ルールがいろいろある。
普通のルールでも三麻というのは四人麻雀よりも荒っぽくてスピード感があるものだけど、白マイティーだとさらにアガリが速くて点数も高く、まあ要するにインフレルールなのですぐにトビが出て半荘が終わる。白のせいで天和とかダブリーも頻繁に出る。そんな風に大味だけど、派手で楽しいしサクサク遊べて快適だったので、普通の麻雀がかったるくなったときにしょっちゅう「白マイティ」を打っていた。
配牌から白が2枚以上あったときの「この場は俺のものだ、みんなひれ伏せ」という万能感。あと、指でツモ牌を盲牌したときに白のぬるっとした感触を引いた瞬間の、脳内で変な物質がどばっと出る感じ。あれはたまらないものがあった。
【こってり】
K寮で遊ばれていた麻雀で一番変態度が高かったのは「こってり」というルールだろう。主にB3ブロックで遊ばれていた。なんで「こってり」と呼ばれているのかは忘れた。これは四枚一度にツモるところに特徴がある。
●親(東家)が4枚一度にツモって、好きな牌を一枚選んで残りの3枚を南家に渡す。南家は3枚のうちから1枚選んでさらに西家に回す。西家は2枚のうちから一枚を選んで北家に渡す。北家は残った1枚をツモる。そして「せーの」で全員一斉に牌を切る。
●次の順は、南家が4枚ツモ、西家が3枚ツモ、北家が2枚ツモ、東家が1枚ツモになる。4枚ツモの権利は一巡ごとに回っていく。
・下家に何の牌を回したかが分かるので記憶力のいい人が有利。
・4枚ツモの順番をわかりやすくするため捨て牌は4枚ずつ並べる。
●リーチの場合、「せーの」の前に点棒を出して宣言する。
・リーチ宣言牌を捨てるのと同時にロンした場合、「リーチ一発」より速いので「リーチゼロ発」として2飜つく。
●ツモアガリした場合、捨て牌と同時のタイミングでアガリを宣告する。
●捨て牌が4人同時のため、「2人から同時にロンする(ロン&ロン)」とか「ツモアガリすると同時にロンアガリもする(ツモ&ロン)」とか「対面をロンしたけど同時に対面からもロンされた」なども起こりうる。こうした場合全てのアガリは同時に成立するものとする。
・ロンで8000点もらうと同時に振り込みで8000点払ってプラマイ0などの現象も起こる。
●一万点棒(稲妻棒もしくは稲棒と呼ばれる)を出してリーチすることを「イナヅマリーチ(イナリー)」と言って、点数が2倍になる。
・稲棒を複数出すこともできて、その場合一本ごとに点数は倍倍になっていく。
●割れ目が2つ存在する。いわゆる通常のリンシャン牌の「割れ目」と、「移動割れ目」と言ってそのときツモっている山の目の前に座っている人も、アガリと支払いの得点が2倍になる。
●イナリーと割れ目の2倍の効果は全て重複する。理論上の最大値としては、稲棒を二本出して割れ目と移動割れ目が二つともアガリに絡んでいた場合、2の5乗で得点が64倍になる。
・ただし稲棒四本出しを成立させるには他の3人から飛ばさない程度に点棒を奪って稲妻棒を集める必要があるので、すぐに飛びやすいこのルールではなかなか難しい。
・アガリ点が100万点を越えた場合「ミリオン」って呼ばれてた(ごくたまに出る)(使用例:「ミリオンおめでとう」)。
●他にも「白ポッチ」「コスモリーチ」「真似マン」など細かい変則ルールがいろいろある。
やる夫がこってりのルールを説明しているサイトもあった。誰が書いたんだろう。
「こってり」も超インフレでギャンブル性が高いルールなので、すぐに飛びが出て半荘が終わる。けれどインフレ性と同時に「他人に流したツモが分かる」「他人に流すツモをある程度コントロールできる」などの戦略性もあり、派手さと細やかさが両立したなかなか面白いゲームだった。「必要な牌をあえてツモらず下家に流して安全牌と錯覚させる<送り込み>」などのこってり独自のテクニックも発達していった。
======================
ここから先は

曖昧日記(定期購読)
さまざまな雑記や未発表原稿などを、月4~5回くらい更新。購読すると過去の記事も基本的に全部読めます。phaの支援として購読してもらえたらう…
ꘐ
