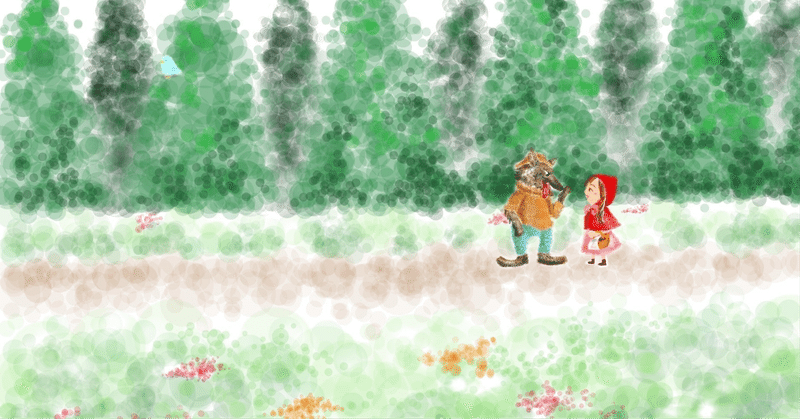
雑記帳28:「赤頭巾ちゃん…」の知性
偏見と言われればそれまでだが、率直に言うと、心理学ってとても人工的で不自然なものではないか。心理学は心というものから一部を切り取って科学的・論理的に取り扱おうとするが、そうすればするほど、生身の「心」からかけ離れたところへ疾走していくように思えるのだ。
それが科学というものだと言うならそうなのかもしれないが、そうだとしても、猛スピードで行き着いた先から人の心が生きる現在地に戻るには、気が遠くなるほどの時間とエネルギーを要する気がする。戻る距離も相当なものだから、(自分なら)間違いなく途中で迷子になるだろう。
知性とは何か----それを諸家の見解を踏まえて論じることなどとてもできない。
ただ、心理臨床家にとっての知性は、クライエントと関わるという「地」に根をおろしたものでなければならないと思うし、その点は絶対に間違っていないと思う。
知性というものは、すごく自由でしなやかで、どこまでもどこまでものびやかに豊かに広がっていくもので、そしてとんだりはねたりふざけたり突進したり立ちどまったり、でも結局はなにか大きな大きなやさしさみたいなもの、そしてそのやさしさを支える限りない強さみたいのものを目指していくものじゃないか(中略)
知性というものは、ただ自分だけではなく他の人たちをも自由にのびやかに豊かにするものだ
だいすきな小説の一つ、そのなかの印象的な一節である。
主人公の語り口はものすごく饒舌(もしくは冗長)で、しかもほとんどが独白であり、そのとめどない発信に圧倒されるほどだ。また、それはきわめて率直で、誠実・真摯であると同時に、前概念的で、安易に結論を導こうとせず、ぐるぐる回るものであるため、いつのまにかこちらの方が摩擦熱をもってしまう。そうした営みの途中で立ち寄られた一つの「考え」が、上の引用だ。これが主人公の歩みを支え続けるものとなった。
私たちの知性も、そのようなイメージに支えられている必要があるのではないか。また、そこに記されているのは、明確な答えではなく、問いのもち方だ。そう、答えよりも、問いによって私たちは自由になれる。答えは時として私たちを不自由にもしてしまうのだ。
もう一つ、付け加えなければならないことがある。それは、この一節が、あるクライエントとの関わり合いの中で、私の記憶の古層から呼び起こされたということである。
クライエントは、大切なことをたくさん知っている。それは、本当は私たちも考えていたはずなのに、何かの「発展」「成長」と引き換えに忘れてしまった、あるいは考えなくなってしまったものである。クライエントは今まさにそれを見つめながら真摯に生きようとしていて、あるいはもがいていて、私たちにもそれを見つめ直すよう求めているのではないか。そうして、私たちがそれに気づき始めるその瞬間に、そして、考えていくその時間に、二人の間で何かが起こるのかもしれない。
心理臨床の知性は、そのようにして脈打つものではないだろうか。(W)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
