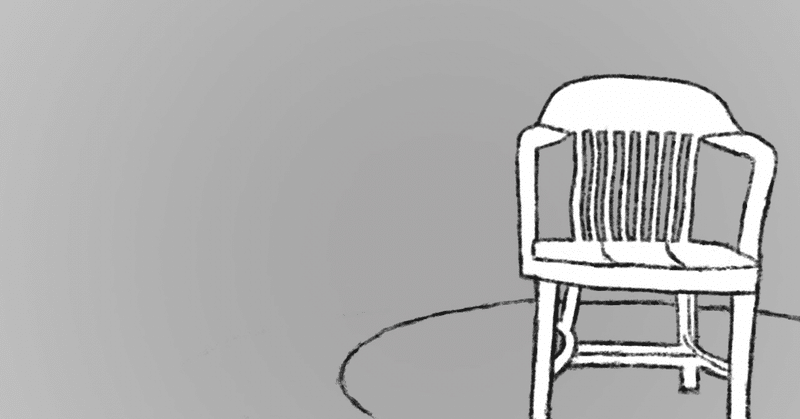
ショートショート その星のいとなみ|ピーター・モリソン
その星のいとなみ
*
生まれつき、舌の形が人と違っていた。
先端が割れていない。胎児のときに二つになるはずだったのが、くっついたままで生まれてきてしまった。
それゆえ、子供の頃から口を開けて笑うことは憚かれた。笑わないので、おのずと人づきあいも苦手になる。ましてやそれが異性にでもなると、さらにひどくなった。
しかし成人し、将来のことを考えるようになったとき、人生を一緒に過ごしてもらえる女性がいてくれたらどんなに幸せだろうと、そう思うようになっていた。
悩みに悩んで、私は結婚志願の登録をしてみることにした。
「……正直言って、それじゃ、見込みは少ないわね」
最初のカウンセリングで、舌の形状を指摘された。
「満足なキスができないでしょ」
真っ先に整形を薦められた。結婚してもらうにはそこまでしなくてはならないのか。何度も逡巡を重ね、結局、私は舌を割る決断をした。
手術は呆気なく終わった。あれほど悩んだのは何だったのだろうと思うほどに……。ただ、術後にはひどい痛みに悩まされ、喋ることも、食べることもままならなかった。傷口を癒着させないよう、舌先を独立して動かす訓練を続けた。
キスというものが、正直どんなものなのかわからない。空想の女性を相手にして、闇雲に舌を動かす。日を追うごとに、舌の自由が効くにようになっていった。さらに練習器で自然な動きを学んだあと、もう一度カウンセリングを受けてみた。
「見せてみて。そう、動かして」
言われるままに舌をさらけ出す。
「……なるほど、綺麗になってる」
すると、物事はすんなりと進み始めた。
口内常在菌を採取され、菌でのパターンマッチが行われた。肉体の相性を見るためだ。
「とりあえず次回のお見合い、参加してみなさい」
暗幕で仕切られた部屋に通された。
簡素な椅子が一つだけ……。目隠しをして座るように指示されていたので、それに従った。
耳を澄ませ待ちわびると、気配がすっと現れた。どんな女性だろうと思う間もなく、その気配は私の頬に手を添え、キスをした。
あっ、と思わず声が漏れる。
初めてのキスに恍惚としたが、されるばかりではと思い直し、稚拙な動きを返してみる。
目隠しのまま、しっとりとしたやり取りがしばし続いたが、急に相手の舌先から熱意が失われた。溜め息と共に唇が離れていく。困惑する私を残し、気配はふっと消え去った。
どうだったのか? だめなのか? いや、そんなはずは。……自問自答を繰り返していると、また気配がやってきて、相手が変わったことに気づかされた。
気持ちを切り替える間もなく舌先を動かすが、その気配もまた、言葉もなく消えていく。
気に入られれば目隠しを取ってもらえる。そのはずだった。……しかし。キス。キス。キス……キス。相手は変わるものの、そんな瞬間はいっこうにやってこなかった。
さっきの気配が、今日最後の女性だったらしい。終わりの合図を耳にして、そのことを理解した。私は自分で目隠しを取り、濡れた唇で吐息を漏らした。
それから数ヶ月の間、数々の女性とお見合いを重ねてみたものの、私が選ばれることはなかった。きっと舌技が未熟なのだ。だから、相手に想いが届かない。
どうすればいいのか、焦りだけがつのる。手術とリハビリで時間を費やしていたため、お見合いにかける時間が足りなかった。契約期限が、目の前に迫っていた。
再びカウンセリングを受けてみても、通り一遍の精神論ばかりで参考にならない。相手を惹きつける何かを身につけようにも、今更小手先でどうなるものでもない。そもそも生まれつき結婚には向いていない身体だった。
私はお見合いをしつつも、どこか諦めの境地に達していた。
これが最後になるかもしれない。私はそう覚悟しつつ、目隠しをして椅子に腰を下ろしてみた。
いつものように気配が現れ、コツコツと靴音を鳴らした。頬に手を添えられる。
……甘い匂いが鼻をくすぐった。果実のような匂いだ。唇が重ねられると、頭がくらくらとした。何かが、今までとははっきりと違っていた。
これが本当のキスなのだと思った。
無我夢中で彼女の動きにあわせた。溶けるような刺激に、思わず感情が漏れる。くすりと微かな笑声がして、吐息ごと掬い取られるようなキスを受ける。やがて、頬にあった彼女の指が動き、はらりと私の目隠しを取り去った。
乏しい照明の中に、彼女が輝いていた。
見た瞬間に、心が掴まれ、息すらまともにできなくなった。それだけ美しく、一瞬で支配された。
「わたしと、結婚したいの?」
彼女の声が降り注いだ。
私は椅子からくずおれ、両膝をついた。
「はい」
そう答えてから、彼女の靴にキスをした。
彼女はしなやかにしゃがみ込み、私の顎をぐっと持ち上げた。
「そうね。……気に入ったわ」
それが妻との出会いだった。

*
私たちは結婚式を挙げると、妻の仕事場近くに雰囲気のいいアパートメントを借りた。
妻は自らの事務所を構え、法律関係の仕事をしていた。私は農業法人に属し、農夫として働いていた。
最近の妻夫の考え方は知らないが、私は結婚して子供をもつのが夢だった。
「子供、欲しいの?」
三年目の記念日に、妻から尋ねられた。
公園で遊ぶ子供たち。そこへ向ける私の視線を読み取っての言葉なのかもしれない。私がその意思を伝えると、妻は耳打ちをした。
「その覚悟があるのなら、今夜、わたしのところに来なさい……」
妻の言葉に怯むことはなかった。生まれもった願いのようなものに、私は突き動かされていた。
その晩、妻の寝室へ行くと、裸の妻がベッドで待っていた。
「もう引き返せなくなるけどいいの?」
立ち尽くす私に、優しく語りかけてくる。頷く私を見て、妻は寂しげに微笑んだ。
「じゃあ、あなたも服を脱いで……」
手を繋ぎ、ベッドの上に招かれる。裸の妻に包まれると夢心地になった。いい匂いが立ち込め、朦朧となる。頭の箍が外れて、もう何も考えられない。
「目を閉じて」
うしろから妻に抱かれつつ、肩に顎を載せられると、皮膚が反応して、私の輪郭が徐々に溶け出した。彼女の胸から腹が縦に開き始め、その谷間にゆっくりと飲み込まれていく。気が遠くなるくらいの快楽が軟らかくなった背骨を伝った。
「すべてをわたしに任せて……」
私たちは溶けあい、一晩をかけて、深く深く交わった。
*
男性は女性と交わると、頭を残して女性に取り込まれ、双頭の一つとなる。
それは当たり前のことで、わざわざ言葉にすることでもない。しかし、実際自分が体験してみると、自然の摂理に畏怖するばかりだ。
今、妻はすぐ隣で眠っている。どちらかが覚醒しているとき、どちらかが眠る、双頭の妻夫だけがもつ特有のサイクルだ。
覚醒は一日交替でやって来る。一日を普通に生活し、夜床について朝を迎えても目覚めず、そのまま丸一日眠り続け、翌々日の朝に目を覚ます。互いの意識が同時に覚醒することはほぼないと言われている。
身体を捧げた私は農業法人を退職し、妻の法律事務所の事務を手伝うことにした。子供をつくる妻夫には公的機関からかなりの補助が出るため、収入の不安はないが、今まで通り何かしらの仕事をしていたかった。
子供をもうけることは大きな喜びを生み出す。その反面、配偶者と直接話すことができなくなるという寂しさを抱えることになる。二人で出かけて、食事をしたり、景色を眺めたりすることも、もうできない。身体は常に一緒だが、妻はいつも眠っているのだ。
日々の申し送りのために交換日記を始めた。朝、妻の文字を眺めてから、一日を始めるのが日課となった。
そこには彼女の様々な意思が詰まっていた。料理のレシピであったり、刹那的なつぶやきであったり、本や音楽の感想があったり。もちろん、私への細かい指示もある。食べ物のことや、つかっている薬とか、されては嫌なこととか。様々なことを私は学び、心に留めた。
双頭の生活にも馴染んだ頃、ようやく妊娠の反応が現れた。気分や食欲が乱れ、寝つきも悪くなる。互いの神経は絡みあっているゆえ、妻の身体の細かな変調は、私のものとして脳へ返ってくる。
おめでとう。喜びを共有しつつ、今後のことについてやり取りをした。ちょうど重要なクライアントを複数抱える時期だったので、妻は仕事に専念し、私が出産の準備を進めることになった。
私は可能な限り、妻の身体を丁重に扱った。清潔さを保ち、髪を整え、好みの化粧をほどこし、季節にあう服装を身につけた。恥をかかないように所作にも気を配った。
日記を交わしながら月日を重ね、とうとう私たちは臨月を迎えた。
どちらが出産してもいいようにと心づもりはしていたが、私の覚醒時に激しい陣痛がやって来て、やはり慌てた。
メモに書き出していた用意をもって病院に向かうと、そのまま分娩室に入れられた。事前の診断で、子宮内には四つの影が確認されていた。
陣痛がうねりのように寄せては返し、激しさを増していく。玉のような汗をだらだらと流し、声を押し殺す。こんなひどい痛み、本当に耐えられるのか。弱気になっていく自分を何度も奮い立たせるが、長時間の激痛と疲労で、しだいに意識が遠のいていく。
「……しっかり」
耳元で発せられたその声に驚き、消えかけた意識がはっと甦る。荒い息を繰り返しながら、視線を横に向けると、妻が目を覚ましていた。
「手を貸すから、一緒に……」
天井を睨み、妻はそう言った。
双頭の同時覚醒で一つの身体を制御することができるのか。二つの指令が交錯すると、うまく身体が反応しないのでは? ……疑心暗鬼になるが、今更そんなことを言ってもいられない。
妻は右手で、私の左手を掴んできた。指を絡め、握り締める。同じ痛みを耐えながら、呼吸をあわせ、力を振り絞った。何度も何度も繰り返す。
やがて、私たちは四つの繭を産み落とした。
「……ありがとう」
妻はそう言い残すと、深い眠りの中へ戻っていった。
私はぐったりと身を横たえたまま、思いがけず現れた妻の余韻を、噛み締めていた。
*
半年後、繭を脱ぎ捨てた子供たちは、健康そのものだった。舌も美しく割れている、私は安堵の息を漏らした。
六人での生活は、目が回るほどの忙しさだった。
子供たちと対等に過ごせる七年間は、スキンシップをとろうと最初から決めていた。性が確定した時点で親子の関係は改められる。もし女の子ならば親元を離れ、寄宿制の学校へ行くことになる。
子供の成長を見るのは楽しかった。話しかけ、笑みを交わし、抱き締める。その繰り返しと共に時間は流れ、やがて四人のうち、二人が女性化した。
娘たちを送り出したあと、私は息子たちと数々のスポーツを楽しんだ。
妻は彼らに規律やマナーを教え込んでいるようだった。確かに息子たちの態度から、妻、私、そして自分達という序列が身についているのが伝わってきた。
妻は最近、日記に詩のようなものをよく書いた。星が綺麗だとか、雨を眺めていたいだとか、そのあとの虹の見事さだとか。それを読むたびに、眠った妻に頭を寄せる。
ずっとこんな生活が続けばいいのにと願いつつ、いずれ終わりが来ることに心を痛めた。気分の浮き沈みに困らされるのはきっと、今が幸せ過ぎるからだろう。
そんな小さな胸騒ぎを抱えていたある日、異変は不意にやってきた。
いつものように交換日記を開くと、そこに妻の文字が見当たらなかった。ページを捲ってみるが、空白しかない。こういうことは前にもあったが、事務所の勤怠記録が抜けているのを見つけて、唇を噛んだ。
取り乱す気持ちを抑えつつ、眠っている妻を鏡に写す。その表情からは何もわからない。ずっと眠ったままだったのか? 息子たちはあいにく不在だったので、昨日の様子はわからなかった。
とにかく病院へ行き、妻の状況を説明した。
「残念ながら……」
医者はゆっくりと首を振った。検査の結果、脳が壊死していると告げられた。
唐突にそう言われても、素直に受け入れ難い。身体はこうして生きているし、その表情は眠っているようにしか見えない。髪も、肌も、唇も、生き生きとすぐ隣にある。
私は妻の艶やかな頬に手を当てた。
「お母様はまだ、こうして生きていらっしゃる。だから、お母様のお身体を大切にしてやって」
あとから病院に駆けつけた長女が、涙を堪えながらそう言った。通例通り、葬式は出さず、私が死んだときに合同ですることになった。
だからというわけではないが、死の実感はあまりない。これまで通り隣には妻があり、妻の身体と共にある。変わったところと言えば、日記が止まったことと、覚醒のタイミングが毎日になったことくらいだ。
私は妻の事務所を畳んだ。息子たちが巣立つ時期と重なったので、アパートメントを引き払い、郊外に小さな家を借り、畑をもった。
優雅さと上品さを忘れず、妻に見合う日々を送った。スキンケアをし、身なりを整える。ときにはレースつきのトーク帽を彼女に被せて、旅先のガーデンでお茶を飲んだ。

*
妻が亡くなって十年が経った。
もう私も若くはない。たまたま受けた検診で病気が見つかった。免疫系の疾患で、回復の見込みはないと告知された。
妻の身体が病魔に蝕まれていたことが、悔しく悲しかった。もちろん、自分事として、死は純粋に恐ろしかった。死ぬ瞬間のことや、そのあとのことがやはり気になる。眠れない日が続き、薬をつかって何とか落ち着かせた。
死を悟ったからだろうか、あれこれと考えるようになった。
死因にもよるが、融合した妻夫は死を共有できるケースが多い。死の間際に同時に目覚め、短く語りあったあと、命を閉じる。それは素直に幸せなことだと思う。しかし、私は妻に先立たれ、一人になってしまった。
死ぬと心は肉体を離れ、旅立つといわれているが、いろんな解釈がある。
私の死をもって、二人の死が完結するなら、妻の心はどこにも旅立ってはいない気がする。それはまだこの身体のどこかにあって、私のことを待ってくれていると信じたかった。
そんな根拠のない論理の繰り返しと、肉体の衰弱が、私に最後の夢を見させてくれたようだった。
その夢は不思議な感覚から始まる……。
身体の隅々に行き渡っていた意識というか、心そのものが、頭の中心へ集まっていくような感じを受けた。ぎゅっと縮まっていく。それは粒子のように小さくなり、居場所を求めるかのごとく、複雑に絡んだ管の中を流れ始めた。
もう元には戻れない、不思議な予感があった。
微細な私の心は自分の領域を外れ、身体の隅々を巡ったあとに、とうとう妻の頭の中へ流れ着いた。妻の匂いが色濃く感じられる。その芳しい匂いに包まれると、私は本来の大きさや形を取り戻していった。それにつれて、周囲の情景が様変わりしていく……。
顔を上げたその先に、ぼんやりと懐かしい扉が見えてきた。辿り着いたその場所は、かつての妻の部屋だった。
「ずっとそこで、立ってるつもり?」
扉が薄く開き、若かりし妻が顔を覗かせた。
「入って」
妻の部屋にはふっくらとしたベッドがあった。妻はその上に座り、膝を抱えた。
目の前に妻がいる。胸が熱くなり、言葉に詰まる。
「どうしたいの? 言ってみて」
見透かすような視線に射抜かれる。
「もう離れたくない……」
敬語も忘れ、私は心のままを訴えた。
妻は唇を緩め、ゆっくりと両手を広げた。
「おいで」
夢中でしがみつくと、妻は私の背中にその手足を絡めてきた。
「わたしも、離れたくない」
妻は私の頬に手を添え、そっとキスをした。
「今までわたしをありがとう……」
その言葉だけで涙が滲み、心の輪郭がほどけていった。様々な苦痛や不安がことごとく消えていく。どろどろと妻の中へ沈み込みながら、私はほっと息を漏らした。
それが人生最後の吐息になればいいと、そう願いながら⋯⋯。
〈了〉
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
もしよければ、「スキ」や「フォロー」をいただけると、創作の励みになります。
よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
