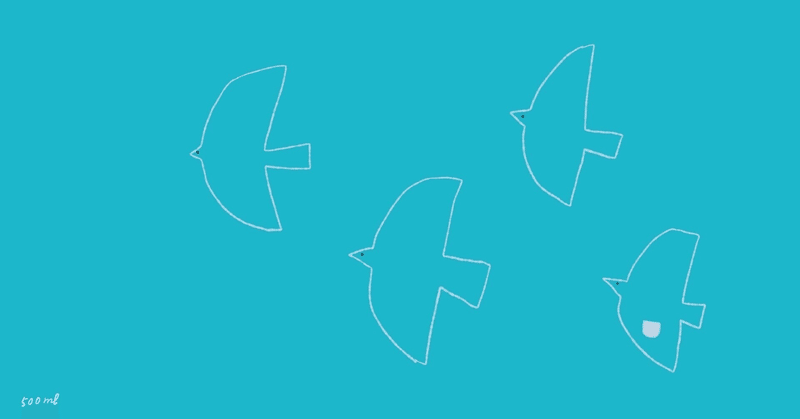
臨書をする時の勉強方法
会の課題のひとつに臨書があるのですが、昨年の11月から今月まで「牛橛造像記」でした。
これがまた苦戦しました。
ペン字で臨書するというのも大変難しく、この特徴的な鋭い角度!その他全部!難しかった…。
思い切っているつもりでも足りない、
その他すべて「?」といちいちなるような、
思い込みがかたいことを思い知らされるような、
とても強刺激な臨書でした。笑
臨書しても、なんだか違う… という思い。
添削されて返ってきたものは、赤で上からなぞるように入っていました。
たとえ1ミリの違いであってもそこじゃないということで確実に違うということ。
頭で理解していても感覚として掴みきれていない。これをどう突破しようか。
ふと、添削されて返ってきた自分の字と、手本に、それぞれ「線」を入れてみました。
「線」というのは、こんな感じで。
あと、三角の箇所なども、どれぐらいの開きがあるかとか。(ここだけではないですが、こんな感じで)
文字の全体を囲って概形をつかむことも大事ですね。

角度、位置もそうですが、より視覚化することができます。
自分の字と手本の両方に線を引くことがポイント。対比がはっきりと見えます。
文字からはみだして少し長めに引くとより分かりやすいです。
たとえば「衆」
上の二本の横線にひいた線の開き具合はどうか。自分の字と手本を見れば(引いた線を見る)一発で違いがわかります。
私の場合は、思い切っているつもりでも角度が浅かった。
しかもどれぐらい浅いのかが目で見て分かったことが収穫でした。
次に書く時に加減がより分かります。
そして、線を引いた手本を見ながら臨書すると「これぐらいの角度なんだな」というふうに、より分かりやすい。
もう少し鋭い角度が必要と分かっていても、正直しっかりと掴みきれない。
この「視覚化する」は大事だなと感じました。
自分に分かりやすいように、細かく見せてあげる。おすすめです。
古典…。
苦戦もしますが奥深く、まだ見ぬ宝がたくさんあるようで、出会えるとワクワクしたり、うれしくなったり、次への活力になったり。
この世界はとてもおもしろい。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
