
錆納戸色と幼稚園生
「熊日」の愛称で親しまれる熊本県の熊本日日新聞には、「きょうは何色」というコーナーでがあります。編集局からそのコーナーで色を覚えた幼稚園生(ぼく)の微笑ましいエピソードが紹介されていました。北海道から熊本に帰省中、お絵かきが好きなぼく。そんなぼくのために、おばあちゃんが記事を毎日切り取ってノートに貼って、文字を書き写していたといいます。去年の夏休みにおばあちゃんの家に帰ったときに、ぼくはそのノートが気になったそうです。「何しているの?」「これは何色?」とおばあちゃんに聞いて色を覚えたそうです。たくさんの色から、ぼくが選んだ好きな色は「錆納戸色(さびなんど色)」だというのです。幼稚園の先生に好きな色を聞かれたら、「錆納戸色」と答えたら驚いていたそうです。それは驚きまかすがな。「好きな色は何かなー」と聞いたら「赤」「黄色」「青」「赤」「黄色」「錆納戸色」となるわけです。
「納戸色」でなくて、「錆納戸色」というのが渋いです。納戸色というのは江戸時代に生まれた色で、青系の色の中で非常によく使われ江戸で流行色になりました。男性の着物の裏地、風呂敷の色などでよく使われました。

納戸色から派生した色として鉄納戸、桔梗納戸、納戸茶、藤納戸など複数の色ができました。派生する色が多く、「錆納戸色」もそのひとつです。

納戸色は青系の色で、やや緑がかかった暗い青。青系の色の特徴ですが、この色見本からもっと青によった色、さらに緑によった色まで広範囲で使われます。広範囲で使われるのに、細かい色名があるのが、江戸の粋というものかもしれません。「これはなぁ、錆納戸っていうんだよ」と名前を付けて自慢していたに違いません。錆納戸の「錆」は色につく接頭語のひとつで、もとの色より灰色かがってくすんで見えたり、暗くなって渋く見える意味を持ちます。
この納戸色の由来は諸説あります。昔は多くの家庭に物置として使う納戸があり、その納戸の暗がりを表現した色ではないかというものです。納戸の中にある暗さ、青暗く見える色。

他にもこの納戸の入り口にかかった暖簾の色、将軍の出納係であった御納戸役の制服の色だったという説もあります。将軍が愛用した着物の色に「御召納戸色」という色があることから、納戸の暗がりという意味ではないのではと思われます。将軍には「暗がり」や物置の色という由来の色は使わないと思うのです。
さて、冒頭の錆納戸色が好きというぼくは、ランドセルは錆納戸色がいいなといっているそうです。なかなか渋いです。納戸色を好む性格のデータがないことと色の好みが変化しやすい幼稚園生ということを考えると、まだまだわかりませんが、保守的ではなく青でも緑でもなく、自由にそのときの気持ちを表現できる前向きな人に成長するのではないかと思います。でも、その渋さは、人としてどこかに持っていて欲しいです。
ちなみに私は子供のころに悪戯をして、母によく物置に閉じ込められました。あの闇の色はこんな美しい色ではありません。暗闇の中に悪い子を今にも襲い掛かりそうになる何かが潜んでいるような怖さがある闇です。でも、懲りないので何度も閉じ込められました。納戸だけに。
ここから先は
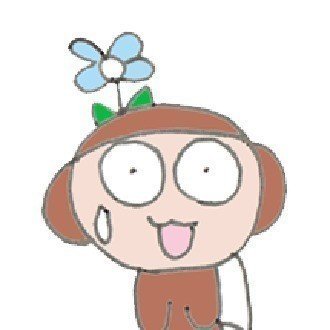
ポーポー色彩研究会
「色を使って問題解決しよう」「色の可能性を広げていこう」をテーマにした色彩心理の研究会です。 マガジンを購読いただくと色彩心理関係のセミ…
いつも応援ありがとうございます。 みなさまからいただいたサポートは研究や調査、そしてコンテンツ開発に活かしていきます。 ミホンザルにはバナナになります。
